焼火神社関係論文
1
隠岐島前、焼火権現の信仰については、すでに昭和十三年の夏この地に採訪した故大島正隆氏が「海上の神火」(文化六、七)において明らかにされたところである。この大島氏の報告にもあるように、焼火の信仰は遠く岩手・宮城などの東北地方にも及んでいるのであって、焼火山が隠岐にあることも知らなかったかもしれないような海民の間にも、日が暮れた頃、削りかけに火を点じてぐるぐる廻しながら
お灯明、お灯明
隠岐の国焼火の権現様にたむけます
よい漁に会わせ、よいアラシ(風)に会わせてくなはれ
千日の上日和
などという唱え言をカシキが叫んで、その火を海上に投ずる習俗が近年まで残っていたのである。
江戸時代にはかなり広くこの習俗が行われたもののようで、広重の「諸国六十三景」などにもその絵のあるのをみても、これが江戸の人士の間にも知れていたことがわかる。
船霊信仰を明らかにするためには、この裏日本における一つの中心地焼火山のことを一応は調べてみる必要があることは永年痛感してきたところであるが、今年九月わずかな余暇をつくることができたので、初めて隠岐を訪れ、極めて短時間ではあったが、焼火神社に詣でて宮司松浦康麿氏の好意で、同社所蔵の資料などをみせてもらうことができた。これは、その船霊信仰からみた焼火信仰の一端である。
2
同社には万治二年(一六五九)の奥書がある漢文の縁起書とともに、年代不詳ではあるがそれを和訳したと伝えられる和文の縁起書が所蔵されている。「常福寺住快穏筆」となっていて、松浦氏の話では寺の過去帳からみて文化の頃のものらしいとのことであった。
それはまず
「そもそも御焼火山大権現と申奉候は昔平城天皇の御宇大同年中当山の麓、曲(地名)の海中昼夜のわかちなく数日鼓動することおびただし。人々怪しみ恐れて其所以を知らす。然るに或日光明四方に輝き風波天を渾して海底より一の*火天外に飛て此山中に入る。山下の村人驚き其跡をしたひ連て山中に至り是を見るに怱ち千丈の岩石目前に突き出たり。村人恐れ神なることを知りて岩火の前に一つの祠を造営して御飛来神と号し奉る」
というところから始まっている。焼火もまた海中出現の神であったわけである。以下、神社の縁起を述べてあるが、この中に漢文の縁起にはない船玉大明神の由来をしるした一節があることは注意すべきであって、単に漢文のものを和訳したのではなく、漢文の縁起をもとにしながらも、当時の信仰状態を考慮に入れて新しく縁起の形に書いたもののようである。
「謹而古伝船玉大明神の由来を尋奉るに人王五十代桓武天皇延暦二十三壬午年七月空海法師入唐の折、筑前の国に下向あり。然るに蒼海風波荒く博多の浦に風待ちして風波を凌がん心に思ひ給ひけるは、夢に諸神現じ給ひ、『万里の海上に風波の難を恐る事なかれ。諸神諸仏力を添えて船中安全を守るべし。末世末代に至るまでこの船玉を信ずる輩は堅護の利益を蒙るべし』と告げ給ひ夢は覚めたり。則枕の元に光明輝きたる玉あり其内透き通りて諸神十二体鮮かに拝れさせ給ふ」
と、空海がこの玉を祀ったのが船の守神を船玉というようになったはじめだということを述べている。諸神十二体とあるところなど、船霊を十二船霊と称する民間信仰を採り入れたもののように思われる。現に、
「此船玉十二尊は十二方の本主として四海を守らせ給ふ御誓い願也」とも誌されている。
「其頃大師紀州高野山に此玉を安置したまひ加持祈祷に奇妙のしるし有事を伝え聞き北国の海辺浦々より海上安全の加持を願ふものおびただし。大師つくづく感じ給ふに、隠岐の国の海中より出現し給ふ大山大権現は御神徳あきらかにして諸人の疫病を助け、就中海上の風波の難を救い闇夜に火を掲げて入津をしらしめ、万人の患を救い給ふことと天下渡海の万人その神徳を蒙らざるものなし。然れば先年夢中に授かりしところの船玉を隠岐の国へ送り大山大権現の御神殿におさめて、いよいよ海上安全御神徳を保護し祀らしめんとて隠岐の国へ送り、天長八年三月祭り給ひしよりひとしほ
権現の御神徳も盛んに北国の海辺悪風逆浪しづまり今において船の往来自由を得たり」
というのが、焼火山に船玉大明神を祀るようになった由来だというのである。その玉かどうかは明らかでないが、焼火神社には船玉石というものが所蔵されている。
「玉の形を長く延れば船の姿となり、丸く縮むれば玉の形となる。亦大船を表より向みる時は則玉の姿なり。しかれば船と玉とは万物同体の宝と知るべし。正月二日船を絵に描いて枕にしけれは初夢の吉事をうるといふも、船には宝珠の心あれば、宝を頭に戴くといふ義なり。その時に唱ふる歌に
なかきよのとおのねふりのみなめざめなみのりふねのおとのよきかな
ここに言歌は廻り歌とも云どちらから読むも同様に読まるるなり。和歌六体の一にて丸く書て読時は右も左もぐるりぐるりと廻られ則玉の形也」
とあるところは、同社で出している宝船の絵の由来を船玉信仰に結びつけてこじつけたものである。
最後の一節は
「如是船玉大明神の御神霊を焼火大権現の御神殿に納め奉れば陰陽和順に水火こもごも用を助けて常々焼火大権現を信心有輩は災難を逃れ冥加叶ひ益々渡海安全福壽無量円満なるへし。然れば焼火大権現の御縁起古伝漢字にして人々見難き故、国字に和らげ梓に写して万人の爲にしらしめんと、是を仰げば弥高起御神徳の広大なるを普く知する一助とも成んと然言
焼火山雲上寺
筆者常福寺住快隠拝書
となっている。全文を写すだけの時間がなかったので、要所だけメモしてきたのであるが、結局焼火権現はもと大山権現と称したもので船霊信仰よりも恐らくはもう一段と古い海民信仰の一つの中心であったところへ、船霊信仰も添加されものではないかというのがわたくしの想像である。なお、大山権現の名
が焼火となったのは、後鳥羽院が
灘ならば藻塩やくやと思ふべし何をたく火の煙なるらん
という御製を詠じられたことから、このたく火を以て神号としたということになっている。今も海士の人たちはオヤマといっている(松浦氏)。
大晦日の夜、海上から飛んできた火が火燈杉にとまってから常夜燈に入るという話は有名である。
3
隠岐が古くから海上交通の重要な地点であったことは明らかである。延喜式にも「比奈麻治姫命神社」の名が出ているが、朝廷から度々この神に位を授けられたのも、やはりここが交通上の要所であったからであろう。北前船ーーつまり松前から関西にいたるまでの日本海の西廻り海運諸船にとっても絶好の風待ちの港だったわけで、この北前船、ベンザイによって焼火の信仰が東北地方にももたらされたことは、すでに大島氏の指摘されたところである。
ところで、海上交通における熊野信仰の大きさについては柳田先生もたびたび述べていられるが、この焼火信仰にもまた熊野の影響があることがあきらかなのである。
焼火神社はもと雲上寺と号していたのであるが、その開山は紀州道玉といって熊野から来たということになっている。現松浦宮司の祖に当たる二代目は薩摩の坊ノ津から来たことが天文年間の勧進帳からわかるということであるが、この開山と二代目との血縁関係はわからない。
焼火と熊野との関係を示す証拠は少なくないのであって、雲上寺で出していた午王の文字も、その筆先は烏になっている。またここのお使は二羽の烏だとされていて、二十四日と二十八日(この方は山神のお祭)には、山神の木にいるという二羽の烏のためにお供えを鍋の蓋の上に載せて供えておくと、いつの間にか烏が食べてしまうといわれている。この烏がいつも二羽で、こどもが生まれるともとの親はどこかへ行ってしまうと伝えていることも、紀州や薩摩の伝承と全く一致しているところである。
この烏のことは漢文で書かれた縁起書にも出ている。
4
船霊信仰から焼火信仰を見る場合に、最も興味をひいたのは、焼火山から「神銭」と称して一文銭を出していることである。徳川時代の玩銭目録「板児録」などにも出ていることであるし、同寺の「年中御札守員数」をしるした天保十三年十二月の日付のある帳面にも
一、銭六百銅
とか
一、銭千弐百枚
などと、かためて江戸へ送った数字が記録されているので、当時のさかんなさまも伺われる。天保十三年には年間〆て七千九百銅というおびただしい「神銭」が授与されているのである。今も出されていて「銭守」と呼ぶものもある。この「神銭」と船霊様の御神体として十二文銭を納めることとの間にはどんな関係があるだろうかというのが、わたしの抱いていた興味の一つでもあった。
ところが隠岐に行ってみた結果、わかったことは、この神銭はお守りとして授与されるものであって必ずしも御神体にするために出されたものではないということであった。隠岐では丸木舟だとハヤヲのところに船霊様をまつるのであって、この点牡鹿半島の丸木舟などと同様であるが、ここにもお札をはるくらいだそうで、御神体らしいものはないのである。大きな舟ーーカンコ以上になると帆柱の下に船霊様をまつるが、女の髪毛、銭、賽二個などで、この銭には神銭を入れるものもないではないが、むしろ神銭はお守りのようにして肌につけるものなのだそうである。
隠岐では猫が人を化かすといわれているが、そんな場合とか船幽霊に逢うた場合などにはこの神銭の穴を通してみると、はっきりわかるというのである。また、神銭を肌につけておれば、たとえ遭難しても死体の揚がらないようなことがないともいわれている。網がひっかかってひくことができないので、この神銭を紐に通して下したところ、すぐに網を揚げることができたという話も伝えられている。
もちろん神銭を授与する風習がそれほど古いものでないことは明らかであるが、とにかく御神体に銭を納めることは一応は関係がないものとみなければなるまい。神銭の由来については、頂上に近いから鐘地蔵のあたりで何かが光を放っているのをいぶかってそれを探してゆくと、壷があって神銭が湧出していたのを漁師が持っていったのが始まりだと伝えられている。
5
焼火山の神銭が、船霊様の御神体として十二文銭を納めていることとは無関係だといったが、実は考え方によっては大いに関係のあることかもしれないのである。
焼火の神銭が魔除けに使われていることは述べたが、船霊様の御神体としての銭も、あるいは魔除けとか、船が遭難した場合に海の神に捧げるために、海民が船旅に携行したものが、いつか御神体として考えられるようになったのかもしれないのである。賽にしても、それが魔除けのためだという説が「卯花園漫録」などにはあるし、嵐に逢って船路を見失ったような場合、船霊様の賽をとり出して振り、行くべき方向をきめるという伝承もある。人形も、かならずしも船霊様の姿をうつしたものでなく、遭難の際に身代わりとして海神に捧げるヒトガタだったかもしれない。御神体の中で、もっとも古いものと考えられるのは髪の毛であって、沖縄のヲナリ神信仰との関係は明らかであるが、「山原の土俗」には、難船した際、船頭が自分の毛髪かカコの毛髪を切って海に投げ込んで無事を祈るということがでているが、本土にも同様の習俗があったことは「擁書漫筆」「雨窓閑話」などにも出ているところである。つまり、弟橘媛が日本武尊のために海に身を投じられたように、海神に捧げるためか或いは嵐の神をしずめるための用意として、姉妹がその髪を船旅に出る兄弟のために与えたのがはじまりであるとみられぬこともないのである。
もちろん船霊信仰が御神体を必要とするようになったのはかなり近い時代のことで、廻船によって諸国にひろまったのではないかという桜田氏の意見にも同感である。その一つ以前には、枕箱のようなものの中に、いわば非常用としての携行した信仰のためのいろいろな品が御神体として考えられるようになったという想像もできないではない。そうすれば、その一つに焼火の神銭があったということも、考えられないことではないのである。
近頃わたくしは船霊様という特殊の神が元来あるのではなく、家の神が船旅の守護として祀られた場合に、船霊様とよばれたものではないかと考えるようになった。その証拠は沖縄のヲナリ神信仰およびそれを今に伝えたとみられる船主の妻や娘の髪を御神体とする風に残っていると思うのであるが、焼火の神銭が魔除けやお守りとして授けられたという事実もそのヒントの一つになっている。(二九・一〇・二五)
こては昨年十一月、民俗学研究所における談話会で行った研究発表の原稿であるが、当の焼火神社松浦宮司をはじめ、山陰の同学諸兄に叱正を仰ぎたいために「山陰民俗」の貴重な誌上をお借りしたわけである。
(民俗学研究所代議員)
牧田茂 山陰民俗五号(昭和二十九年十月二十五日)
焼火信仰について研究され、そして発表されたものは、故大島正隆氏「海上の神火」(文化6の7)、牧田茂氏「焼火信仰と船玉信仰」(山陰民俗5)二宮正彦氏「隠岐の神社について-焼火神社」(隠岐関大島大共同調査会刊)があり、そして最も新しく発表されたものに北見俊夫氏の「海上の信仰」がある。このように中央の専門の方が研究の対象となさる程に「焼火信仰」は単に隠岐島民のみのものでなく広い信仰圏と種々の信仰内容を持つ、所謂「霊験あらたか」といわれる大神であった。このすべてを資料にもとづいて記述することは膨大なものとなるので(これはいづれ一本にあとめる予定)ここには北見氏の「海上の信仰」より抄出して焼火信仰の一端を紹介することにした。北見氏に対し心より御礼を申し述べる次第である。猶、焼火信仰を考える時、熊野信仰との関連をのべるべきであるが、ここでは一切こうした私見はのべないことにする。本論考の題目は「海上の信仰」であるが、仮に私が表題の様にして紹介することにした。(焼火神社宮司、松浦康麿)。(一)日の入りのお燈明
「オド-ミヨ-の薪は、削りかけを三本棒に結わえたもので、先ず燧石を三度チョンチョンチョンとうち然る後に火をつける。それを右手に高く捧げトモのカジ柱の所に立って大声で次の様に唱える。--お燈明、お燈明、お燈明、オキノ国タクシ権現様にたむけます。よい漁に会はせ、よいアラシに会はせなはれ千日の上日和。かく唱へ終るとその火を三回頭上に大きく振り回して海中に投ずる。これはカシキの行ふもので其の間船頭始め乗組全員舷に立って祈念をこらすのである。(話者船渡勘治氏、79才」。「日の入りのお燈明」献燈に際しての唱えごとは、岩手県気仙郡綾里村砂子浜(現在三陸村)で「その昔(昭和14年現在)といえども、オキのタクシ権現なるものが何処の如何なる神様であるかは、全く知らず、単に古来からの伝えのままに唱えられてきている」そうである。宮城県桃生郡宮戸村室浜(現在鳴瀬町)での唱えごとの神様の名前には、隠岐の都万目の顎無地蔵の名まで出てくる。これらの伝承を大島正隆氏に語った白髪赤顔の漁師の翁は、かって少年の日、カシキの役に当っていた。また三陸海岸ベンザイ乗に従事し同様の献燈儀礼を行っていた船乗りたちも、ともに酒田以南の海路を知らず、ましてや隠岐の島山をまだ見ぬ人たちであった。さらに、当時すでに伝承者になっていたかれらは「タクシ(焼火)の権現とは昔から船方の神様であるから、是非とも念じなければならぬ。その神様のお社の下を通るときにはどんなアラシ(凪といふ意)のよい時でも帆をセミモトまで引かせ、米一升のオサングを海に撒くものだ」と付け加えて語っていた。(二)タクヒといふ珍しい神の名
この珍しい神の名が、津軽南部の海にまで運ばれた事実や、以下追々述べる文献所収の記録などから1)焼火山の霊験がいつ頃から説かれる様になったのか、2)どのくらいの信仰圏の広がりを持っているのか、3)どの様な霊験内容が語られてきたものか。したがってこの神の性格機能はどうか。4)どの様に伝承が薄れてきたものかなどを考察してみよう。「六国史」類でこの神のことが記されているもので古いのは、桓武天皇延暦18年(799)の記事であろう。遣渤海使帰途にさいし「帰郷之曰、海中夜暗、東西メメ曳、不識所著、干時遠有火光、尋遂其光、メメ到嶋浜、訪之是隠岐国智夫郡、其処無有人居、或日奈麻治比売神常有霊験、商賈之輩、漂宕海中。必揚火光、頼之得全者、不可勝数、神之祐助、良可嘉報、伏望奉預幣例許之。と記載されている。ついで承和5年(838)冬10月この神に従五位下を授け、貞観十三年(871)閏八月二十九日任申、夜流星があり神々に位を授けたとき、この神に正五位下を授けたさらに元慶二年(878)正五位上を授けている。平安初期から都の人々にも知られていたことはこれだけの記事からでも伺えるが、「栄華物語」巻第三六には「根あはせ」の条に「恨みわび干さぬ袖だにある物を恋に朽なん名こそ惜しけれ」をうけて右近少将源経俊朝臣の歌として「下もゆる嘆きをだにも知らせばや焼火神(たくひのかみ)のしるしばかりに」いとをかしくて過ぎぬ」と出ている。焼火神について、「和訓栞」の註では「隠岐国の海中の神火也焼火権現と称す、海部郡島前にまします」と記されている。中世になると、承久の変後、後鳥羽院が島に渡られた日、風波漂白の海上、雲間はるかに例の火が現出した時、院が-灘ならば藻塩やくやと思ふべし何をたく火の煙りなるらん-という御製を詠じたことから、たく火をもって神号とするに到ったというのが一般の説になっているが、「栄華物語」の例でもわかるように、すくなくとも平安末期には焼火権現の名で呼ばれていたのではないかと考えられる。近世になると前述の「日の入りのお燈明」行事に隠岐のタクヒを唱えることが広く行われ、葛飾北斎の「北斎漫画七編」の中に、又安藤広重の「六十余州名所図会」にも「焚火ノ社」としてその絵が画かれており、海民のみならず、江戸人士の間にも知られていたことがわかる。それよりさき、まづ隠岐島前焼火権現社に伝わる同社の縁起は万治二年(1659)の奥書のある漢文体のものと、年代は不詳(筆者常福寺住快穏は文化年間の人につきこの頃と推定)であるが、これをもとにして当時の信仰を折込んだものとがある。それによってみると、平城天皇の御代、大同年中に奇端があり、海中出現の神として祀られたのに始まることになっている。そして焼火山に船玉大明神を祀るようになった由来については、空海法師入唐の折博多の浦で風待ちし、夢の告げをうけ、夢さめて枕元に光明輝きたる玉が出現したとしている。その玉が一度高野山に安置されて後、隠岐国の海中より出現し給うた大山大権現の御神殿に天長八年(831)より納められることになりいよいよ海上安全の御神徳を現わすことになったと記されている。寛文七年(1667)の「隠州視聴合紀」所収の焼火山縁起は、これらとちがって、一条院の御宇(986~1011)海中より出現の火光飛んで山に入りしを以て此社の始めと説き多少相違がみられる。この外貞享五年(1688)の「増補隠州記」寛保三年(1743)の「諸国里人談」天明七年(1789)「紅毛雑話」上田秋成集」などに焼火権現信仰の記事が見えている。明治以降については網羅的に調べ上げたわけではないが、ラフカディオヘルンの「知られざる日本」に紹介されているのは有名である。(3)焼火権現神火の奇瑞
焼火権現に関し、どのような奇瑞が文献や伝承を通じて伝えられているであろうか。ただ漠然と船方にとって、きわめてあらたかな神様であるということ以外に、以上の資料から、具体的につぎのような内容に分類することが出来る。イ)難破しそうになった時祈願をこめる。するといかなる嵐のなかでも三すじの火光がありありと示され、船をその中央の火に向けさえすれば、かならず安全に港をとることが出来る。されば、ロ)平穏無事のときでも前述のごとく、カシキ演ずる処の「日の入りのお燈明」行事にさいし、-隠岐国の焼火権現、早よう港をとらせ給え-と念ずるのであった。漁船は唱え言葉のなかに-オキの国のタクシの権現にたむけます。よい漁に合わせ、よいアラシに会わせてくなはれ千日の上日和-などの文句が含まれる。また、ハ)この社から授与される「銭マモリ」は魔除けとして船乗りにとって護符の役割を果たし骰子とともにこれを船玉さんの御神体として納めている廻船もあった。江戸時代の玩銭日録「板児録」にも記載され、同寺の「年中御札守員数」を記した天保十三年十二月の日付のある帳面にも年間〆めて七千九百銅をいうおびただしい「神銭」が授けられていた。その神銭の由来については「嶺に巨岩在り、其半腹に穴あり是に宮殿を作れり(中畧)鐘楼在り、宝蔵あり。山上へ行道在て到れば、神銭湧出る一壷在り、人壱銭を得る時は水難をまぬがれ疫病をさける(中畧)神徳を記て説に不逞神火を施して闇夜の漂船を助け給ふ凡そ秋津州は不及言に高麗に至っても神火を請時は出すと云事なし」とある。もう一つ重要な要素は、ニ)竜燈神事である。「隠州視聴合記」の著者斎藤勘助の「焼火山縁起」に「(前略)有神燈毎歳除夜見之。海中其始出也、一点如星炬如篝、耿々而明、徐々而立。如見漁火於波涛渺茫之中如有物伝火来焉、漸而近未及山里許対神祠而止。自山而隔一海湾而有村日千振。自千振観之、燈不止於海中遂達於山羊。相伝海神献之焼火之神。雖陰晴風雨年々不同、然必以夕見此燈也。若其燈数年有多少。土人以漁為業者以是為卜。故見燈数多則隣里相慶、以為多漁之兆。此夕土人遠近来観焉。其数千百、年々加盛。自古今尚多矣。」これは、竜燈神事について、近世初期の状況を描写したものである。近くは明治25年ラフカディオヘルンが隠岐に渡ったときの紀行文のなかに、「(前略)焼火山には伝説がある。自分はそれを友から聴いた。その頂上には権現様の古い社殿がある。十二月三十一日夜、霊火が三つ海から現れ出て社殿の処へ昇り、社殿の前の石灯篭の中に入り、燈のやうに燃えて居るといふことである。その光は一度に海から現れるのでは無く、別々に現れて、一つ一つ峰の頂上へ上がってゆくのである。みんな其光が水から昇るのを見に小舟に乗って来るが、心の清浄な者だけに見えて、よこしまな考えや願を有って居る者はその霊火を見ようと待って居ても駄目である(後略)」と記している。以上あげた焼火権現信仰の内容のうち、ロ)についてはすでに検討したが、ハ)に関しては牧田茂氏が「焼火信仰と船玉信仰」といふ論考で船玉信仰上、裏日本に於ける一つの中心地と認め、船玉信仰の性格を究明するなかで「船霊」様という特殊の神が元来あるのでななく、家の神が船旅の守護として祀られた場合に船霊様と呼ばれたものではないかと」いう考へを提出した。その論拠として焼火権現発行の銭守りと其の効能からヒントを得たとし、またそれに沖縄のオナリ神信仰やそれを今に伝えたとみられる船玉の妻や娘の髪を御神体とする風の残っていることなどあげている。これだけでは仮設としてなら受取れるが、まだ論拠不充分なように思われる。(四)竜燈と祖霊信仰
イ)に述べた神火の信仰こそ、古くからの海中出現の神として尊敬をうけて来た焼火山信仰の中核をなすものであり、ニ)は其の後、いつからこの様な神事の形になったものか明かでない。そこで竜燈信仰について海上関係のものに限定せず、もっと視野をひろげて全国的展望に立って考えてみよう。そうした意味では、焼火山の竜燈神事が大晦日の晩におこなわれる点に注目したい。竜燈信仰については、はやく柳田先生が「神樹篇」のなかで柱松の神事から説き起こされ、盆の燈竜や祭の折に柱を立てることも柱松の行事と系紋を同じくするもので、竜燈という漢語は語はもと水辺の恠火を意味し筑紫の不知火(しらぬい)河内の姥が火などがこれに該当し常に一定の松杉の上に懸るという点がわが国の特色といえるのであって燈を献じたという類の口碑はむしろ後に発生したものであろうと説かれた。各地の竜燈信仰のなかで、竜燈が一年のうち一定の時期に発現する例をとらえてみるに徳島県の津峯権現、舎身山竜寺の両所はいづれも除夜の晩に山の頂上へ竜燈が上った。石川県の最勝寿住吉神社は一名竜燈社とも呼ばれ、毎年一二月晦日の晩に竜燈の奇事があったもでこの名がある。(畧)大晦日に竜燈の上がるこれらの例に対し新潟県八海山の頂上にある八海明神の例は七月晦日である麓の里に住む人々は毎年この夜は登山参拝して一宿する習である。此夜山から麓の方を下し臨めば数十の火が燈のごとく連り、連綿として山中に飛来るをみる。(畧)結局、一年のきまった期日をそれらの期日は神霊を送る季節であった事を考へ合はせると、焼火権現の場合も明らかに其の例にもれず、祖霊信仰と関連するのではないだろうか。八海明神の例には祖霊との関係が一層深いように思われる。さらに焼火権現の場合には年占の要素が習合している。(五)竜燈の種々相
竜燈はもと一種の天然現象であったろうと思うのであるが、その名のつけられたのは五山の学僧などの命名でなかったかと柳田先生は推論された「諸国里人談」火光部にいくつかの竜燈信仰の事例を記載している。不知火について「豊後国宮古郡甲浦の後の森より桃灯のごとき火、初夏のころより出る。又松山よりひとつの火いでて空中にて行合、戦ふごとくして海中へ颯と落る。(畧)四五月八九月にかならずあり。これつくしのしらぬい火といふなり。」とありこれも一種の竜燈であろう。橋立竜燈については「丹後国与謝郡天橋立に毎月十六日夜半のころ丑寅の沖より竜燈現じ、文殊堂の方にうかみよる。堂の前に一樹の松あり。これを竜燈の松といふ」と記しまた津軽岩木山に関し「(前略)御祠には、かねのみかたしろ三ならび、その中にまじりて、石のみかたしろのあるは守山の神とか。赤倉のかたに神場(おにば)にて処を見やり、いと静かな夜には、竜燈、天灯のささぐるを見-」とあるのは意味深長に感じられる。(畧)いづれにせよ、近世にはすでに一般的にその名が普及していたようである。これを要するに、竜燈は、信仰のある人々にとって暗夜の道しるべであった。竜燈が発現する時期は、焼火権現その他大晦日の例、八海明神の七月晦日の例などから考えて、それらは祖霊を迎え送る日でなかったか。すなわち竜燈信仰に、種々なる要素が習合したなかで、海上の信仰に関する部分は重要なものとして伝承されてきた。そして海上で夜を迎える廻船や漁船が行う「日の入りのお燈明」行事は、海中より竜神が捧げる燈火をカシキが代行する形をとったと解することはできないであろうか。(6)焼火、篝火、燈台、竜燈
海上での神火の発現は、どこまでが神秘でどこからが現実生活なのか区分しがたい面をもっている。海上航行上、港や岬によって暗でも目印になる何かがあった。燈台以前の昔の生活を考えてみれば思いあたる点が多い。これまでにも述べてきた処であるが、焼火権現に感応する”みちびきの火光”に似た神火が各地に伝承されている。同じ隠岐島後の五箇村久見(くみ)では、その沖合いを通って難破しそうになると、一心に内宮さん(久見の伊勢命神社)を拝んで、オヒカリを上げて下さいと念ずると久見の波止(はと)にオヒカリがあがって目印になるといわれている。新潟県西蒲原郡間瀬村での伝承では、野積との村境に祀っている榎坂の地蔵様が、シケのときに火がついて知らせてくれると信じられている。この種の伝承に対して、現実的な目当てとして、夜間の燈台以前の常夜燈、燈明台などで火をともしていたこと、発生的には篝火をたいていた処を考慮してみる必要があろう。神秘的な神火の出現をすべてこのような篝を焚いたところに此定することは必ずしも当らないかもしれないが、何かしら相関関係があってのことではなかろうか。(畧)航路標識として、最も原始的な焼火(たきび)、篝火が近代的な燈台設置まではもっとも普通のものであったことを示すであろう。能登の三崎も重要な目当てになる場所であったが、三崎の権現様の奥宮が山伏山の頂上に祀られ、そこで篝火を焚いたことが伝えられている。そうした意味から隠岐の焼火権現の焼火も、篝火を焚いたタクヒからその名がtけられたのではないかと考えられ、またこの山の竜燈神事で述べた如く「有神燈毎歳除夜見之。海中其始出也。一点如星如炬篝--」「社殿の処へ昇り、社前石灯篭の中にいり、燈のやうに燃えて居る--」と伝えられる。竜燈とび来たって灯篭の中に入る伝承は、焼火権現だけの伝承ではない。以上の点を勘案してみるとき、竜燈と灯篭との媒介から、暗夜の道しるべ、目当てに焚いたもっとも素朴な篝火との対応関係に注目してみたいと思う。信心ある人にとって、体験的なある現実が、神秘的なひらめきをもって、心のなかに竜燈などの火光を現ぜしめるのではなかろうか。(7)海上信仰の伝承
「諸国里人談」の著者は「焚火」の項に「隠岐国の海中に夜火海上に現ず。是焼火権現の神霊なり。此神は風波を鎮給ふなり。いづれの国にても難風にあひたる船、夜中方角わかたざるに、此神に立願し、神号を唱ふれば、海上に神火現じて難をのがるる事うたがいなし」と述べついで後鳥羽院隠岐遠島の故事にふれ、焼火権現の来歴について一条院の御宇に海中より出現し給う由緒を引用しているところをみると、文献から得た知識も相当含まれていることは確かであるが、当時のいわゆる里人談を紹介した点も疑いえないであろう。18世紀中葉における、その里人談の内容をなかに置いて、昭和10年代の故老からの伝承と、文献を遡って、本稿で前述した「日本後紀」所収の延暦18年、遣渤海使帰途にさいしての記事と、これら三者の間にいくばくの差異があるであろうか。このような事情から推して遣渤海使の筆にとめられた信仰内容は、それ以前の悠久のいにしえからのものであろうことを、今にして想うのである。その継承の古さと根強さを痛感するものである。一方天明7年(1787)記するころの「紅毛雑話」では「洋中にて難船の時、舳先の方の海面に神火の現ずるを見る時は、其船かならず恙なし、蛮人「フレ-ヒュ-ル」と号く「ウヲ-ルデンブ-ク(書名)」にも説あり、一昨年来りし「カピタン(役名)」「ロンベルゲ(人名)」印帝亜(いんでや)の海上にて難船の時、彼神火を見たるよしを語りしと、家兄の物語なり。吾邦焚火山の神火と同日の談なり」とあり焼火権現信仰の広がりと内容の斉一性に驚く。この信仰は、時間的経過の深さと空間的広さという点において考えさせられるものをもっている。
『隠岐(島前)の文化財一号』
(2)御伊勢参宮講前書。それ伊勢両皇太神宮は天下の宗廟にして百王鎮護の至尊神仏聖の惣本地なり。御恵の新たなる事は座に述べがたし。あしたの日の山の端に出、夕べの月の海づらに浮かび至らぬ隅もなきは皆是神明の余光なり。天地の間に生を受け月氏晨旦といえどもいづれの輩か神恩に洩れ奉んや。就中、吾神国に生るるものは大神の懐子なり。上天子より下庶民に至まで一日片時も神恩を忘れてはあるべからず。恩を得て恩を忘るは畜獣にもおとれり。往昔元禄年中牛鳥神明に詣で翅を刷ひ頭をたれ神明の徳を尊び不信の輩の耳目をおどろかせり。浅間しき禽獣なおかくのごとし。況や五常を備え有情に冠たる人間誰か信仰し奉らんや。億劫にも受けがたき人身を受、幸に有難き吾神国に生まれ、何ぞいたづらに時日を過ごし空しく年月を送らんや。ここを以て男女参拾人参宮講を結び、二季の懸銭を集め一度神明へ歩を運び宮川の流れに身を清め至誠心に「あまてらすすめおほむかみ」を唱奉り、神前を拝し能く神恩を報し奉らんと欲す。一度の参宮の功徳は万善万行にすぐれ、一遍の神名号には無量の重罪を滅し八百万神はもとより、閻摩王三世の仏菩薩も恭敬礼拝し給ふこと疑いなし。功徳利生更にはかるべからず。猶まめやかなることは旧記に散在せり繁をいとふて爰にはぶきぬ。唯其の一、二を記すのみ。興行誠に速やかに参宮成就せば、現世安穏家内豊楽子孫繁栄豊貴自在にして、浮世又高天原無為の都に至らん事、何ぞ瞬息を待んやと云に。倭姫尊の宣く。此神名号は大道を悟る勤めゆへ、死人月水穢火其外忌服などあるとても少しもはばかりなく、神名号を唱へぬれば、其功徳にて有るほどの穢忽にはらわれ、其所其身も清浄に成るのよし、しるし置き給へる上は道行の内婦人は月の障等もこれ有る可く候へ共、信心の誠候へば、神明納受遊され参宮空しかるまじく候。熊野権現の御歌に、もとよりも、塵にまじはる、神なれば、月のさわりは、何のくるしき。惣して男女貴賎僧俗を論ぜず日本に生るるものは、大神の氏族なり。然るにその元たる神道を忘れ異国の法を第一とするは先異端なり。たとえば僕あり家主人につかへずして、能く他の主人に仕え、又子ありて其父母を捨てて他の父母に孝せば豈人悪さらんや。此趣きをよく弁へ先神明を尊び、猶余力あらばいづれの異道をも勤め神道の翼とすべし。弘法大師の歌に、あるといふ、あるが中にもとりわけて、神道ならぬ、成仏はなし。神道引導の歌に。生まれこぬ、さきも生まれて、住める世も、死るも神の、ふところのうち。定。1)御講定日は霜月十一日早朝行水垢離身を清め欠無く出席仕り、大神宮を勧請奉り、御神酒幣帛を捧げ、異口同音に神名号を唱え奉り、意願成就子孫繁栄を祈り奉り、喧嘩口論一切不浄なる誥開仕間敷候事。
2)懸銭は一年四百文に相定め四月十一日、十一月十一日両度異変無く急度相立申す可く候。勿論懸銭は御初穂同然の儀に御座候間、たとえ仲ヶ間中に勘定合これ有候共、指引次やり一切自分勝手なる算用仕間敷候事。
3)人数参拾人を四に分、四人の組頭を定め懸銭万端世話仕る可く候。組下懸銭不埒は、組頭の不世話に御座候間、組下の内至て不如意なる者又は不精なる者は前度より尋合、正銭を以て出来申さず候はば、麦大小豆日雇手間其の人の勝手次第に立てられ講破り申さざる様に、四人の組頭工面仕り、組子を励まし講終迄、退屈無く仲能く成就仕る可く候事。
4)懸銭は集まり次第四人の組頭預かり利満仕り、又茶木綿等相懸のもの調置き利廻しに相成様に才覚仕り、少にても懸銭の足しに相成様に仕る可く候事。
5)参宮仕候儀は、前年より三人宛鬮入、鬮落のもの一人前に懸銭の内四貫文相渡申す可く候事。
6)参宮の序に西国順礼又は大和廻り仕り度者これ有り候はば、遠慮無く順達仕る可く候。諸神諸仏も皆天照宮の御身分にてこれ有間参り候事少しも苦しからず候。併し参宮第一と念願仕り、外は次第廻りと相心得申す可事。
7)船中乗合道中懸連は男女打込にこれ有候間、婬事妬毒一切不浄なる事申し懸け間敷候。遥々参宮仕り候ても、婬欲等不浄これ有候はば、男女共に邪婬の罰のがれ難く候。一生多病無福の身となり子孫も繁昌仕らず候。第一戒たくべく候事。
8)出船より道中帰帆迄、殺生並誑惑仕間敷候。平生は渡世にこれ有の間、是非に及ばず候。参宮の間は堅く相慎み申す可く候。天照宮は慈悲第一の大神にてましませば、殺生誑惑は御嫌い遊され候。既に以て宮川阿漕ヶ浦其外神領の内は殺生禁断放生の地に御座候。人畜異といへども殺生は死相なり。誑惑は盗人の端なり。君子猶以て慎まざれば、神明何ぞ納受これ有るべき。何分急度相慎み申す可く候事。右条々堅相守興行速に参宮成就仕り、神恩に報奉可く候。尤も拾年余を経候事に御座候へば、各退屈にこれ有て可く候共、何れも心法仕り、四人の組頭は組子を諌め組子は組合を励まし退屈無く御講成就仕り、内外共清浄に参宮仕り、宮川の水に身を清め御神前に於て神名号を唱奉り丹誠に抽で村里静謐家内安全子孫繁栄意願成就を祈奉る可きもの也。依而願状如件。明和五年戌子正月十一日。橋村講中。茂八組合、伝兵衛、源四郎、久五郎、儀右ヱ門、喜兵衛、きん、きさ、萬右衛門組合、宇左ヱ門、勘助(以下氏名略)。
(3)以上がその全文である。これは快栄が起草したもので、橋村(今の波止)の藤森家(面屋)に保存されているものと、私の方にも控えが残っている。快栄自身、僧籍にありもっぱらこの様な主意書を書いたということは、当時の社僧というものの在り方の一端を伺う上で参考になろう。さて、この文書の橋村(波止)は焼火山麓にあり、現在約五十戸位の集落であるが、当時は三十戸で、文中「同士男女三十人」という事は全戸に当るわけである。この外私蔵の資料「弘化三年伊勢二人別覚帳、大津村」という横帳の一冊があるが、これは六十八人で講をなしており、これも当時の大津の全戸数であった。この外にも二、三見たことがあるがいづれも集落全戸を単位として組織されていた。大体島前には百戸を越すような集落は少ないので、集落全戸を以て講をつくるのが普通のようである。次に、講日であるが、波止の場合は四月と十一月の十一日と定めているが、他の場合は記録も伝承もないので島前全体については詳にしない。次は講当日の行事についてである。これは他の講も大体同じで、神供として神酒、粢一重~三重、塩水等を供え、各自拝礼をした後で、路銀の懸銭を集める事と、二人~三人の代参者を鬮によって選び出すこれが主なる事であった。これはすべての代参講に取られる方法であり、又この鬮に当ったものを代参者ということは各地の例と変りない。
(4)この様にして決められた処の代参人は大方が四月から六月の頃を見計らって参宮に旅立ったものの様である。講の資料として橋村の様な定書等の残されているのは、当地では珍しい例で、大方の資料は講銭の出納が記されている程度である。一例として、一人宛の割当額と代参人一人宛の路銀について、橋村の場合と大津村の場合をあげてみると、前者は一人割四百文で、代参者には四貫文が出されており、後者は一人割三百四十八文で代参者には十一貫文をあたえている。又講銭の年出法も両社異っていたこの事については次で述べることにする。
(5)講銭の捻出方については前記橋村の如く、四百文を年二回四月と十一月に正銭を以て各自が納める方法と、次に示すような、区の共有林を共同で伐採してこれを売却して参宮の諸経費に充てる方法とがあった。弘化三年伊勢二人別覚帳、大津村中。村中申合之儀は木切りだし壱ヶ年に弐人宛参詣仕候事、一人に銭拾壱貫文づつ渡可申こと。と規定し午六月(註、弘化三年、1846)。拾壱貫文、平八。拾壱貫文、菊五郎。外に壱貫七百文、酒壱斗。これは牛六月伊勢講相談の時の御神酒、〆弐拾参貫七百文、是を六十八人割三百四十八文六分づつと記され、壱〆五束(註2、壱〆五束、薪「一〆」は木の長さ一尺八寸~二尺のものを、高さ二尺五寸巾三尺に積んだもの。束は長さ五尺の縄を二回まわしてしばった木の数量(西ノ島、美田の例)三百五十七文、長尾、八文余り。同、三百五十七文日当八文余り。壱〆四束、三百三十文、中瀬、十九文不足。壱〆四束半、三百四十二文、吉右衛門六文不足(以下略)と以下六十八人それぞれの薪雑木の伐採量とこれが価格並に一人割三百四十八文八分に対する過不足が記されている。然して規定した如く年に二人宛参宮しても三十四年間もかかる事になるので、中断された時もあったらしく、明治十七年に講員の元帳を書改めているが、其の時まだ二十人も残っている。この元帳には面屋の如く参宮を済ました者にはそれぞれエトによって参宮の年が記されているので、結局大津村の場合は、弘化三年に始まった伊勢講が明治二十六年になってやっと全部の者が参宮を終えた事になっている。
(6)さて次は、隠岐島よりの参宮についてであるが、これは今の処他の資料がないので、快栄の「参宮道中日記」によって考察をすすめてみる。先ず、経路であるが、ここにあげるのは一例であって島からの参宮には必ずしもこの経路をたどったとというわけのものでもないが、明治時代に参宮したという故老の話を聞いても、大方が先ず大山寺に詣り、四十曲峠を越えて山陽道に出たとの事であるので、参考にはなると思う。「道中日記」によると四月二十日に出立して、帰島したのは六月二十五日この間六十五日を要している。(地図参照のこと)この時の一行は五人、内二人は女連れであったので、日数は多くかかったものと思う。日記といっても綿密なものでもなく、経路、宿屋名、発着時刻、宿料、買物代等々いわば毎日の金銭の出納が主でそれに前記の様な事が記されている程度である。始めの方を記してみると、「四月、二十日出達千ブリ郡に出、浮二日逗留、同、三日四ツ時出(註4)、七ツ三保関着(註5)。安来屋久平方宿ス。四月二十二日、銭二十四文、四人、三保殿(註6)ヘ上ガル、神酒五合代、八十文、四人、同百文、三保関ノ宿ヘ出ス、四人、同二十三日朝伯州サカイ行、直ニ安来行。銭二百八十文、かさ代二つ代、同百二十文、かさ二つ、銭壱貫二百二十文、木綿壱疋(下略)といった塩梅のものである。経路は、出雲美保関を二十二日に出発して次の日は安来泊り。翌日は清水寺詣り、米子在の今在家泊り。赤松越をして大山寺詣。因備線の根雨に下り坂井原、美甘を経て備中神代着は二十七日。勝山、勝央、三日月を経て、姫路に着いたのが五月三日、此間十一日を要している。途中には宿屋あり、中食の茶屋もあって、これも堂々たる街道であったわけである。それより須磨、西宮、大阪、伊丹を通って京都着が五月十一日、大津、水口、松坂と歩いて伊勢着五月十六日。隠岐を出立より二十七日目に目的地山田に着いたわけである。毎日の出発は大体五ツ時(午前八時)宿着時を七ツ時(午後四時)一日八時間を歩いている。伊勢での宿は山田守屋金大夫方宿となっている。この項を抄出すると、七ツ過守屋金大夫宿ス、同十七日、雨天、守宿逗留、金百疋御初穂上ル、宮廻り両度、銀弐匁六分五厘かへる、金壱、代壱貫五百六十四文、と、いとも簡単に記されているので参宮の様子など知るよすがもない。翌十八日は六両の中を朝熊山に詣で此の日は小俣に宿している。帰途は高野山参拝の為、八太、新田、初瀬、宇野を経て二十四日高野山着。ゆっくり順拝して、翌日午後に下山して慈尊院泊り。法隆寺、奈良、宇治を経て再び京に着いたのは六月一日であった。京で一週間滞在、八日出立、それより須知福知山、河守(大江)宮津、久美浜を通り城崎着は十四日、三日間入湯の後キリハマ(竹野町)より舟をやといモロイソに出、ここから隠岐島後の船権現丸というのに便乗、風待ちの後二十日に出帆西郷着が二十三日。帰りはゆっくりした旅をしているので、往きの時より日数を要して、六十五日目に帰山したわけであるが、途中京の滞在、城崎の入湯の約十日間を差し引いても五十五日を要した事になる。いづれにしても隠岐島よりの参宮という事になると早くても四十日~五十日を要したものと思われる。
(7)それでは参宮に要する経費は一体どれ程であったろうか。前に引用の橋村の場合は明和から安永にかけての参宮で一人宛四貫文、大津村の場合は弘化から明治にかけてであるが十一貫文の路銀を渡していR。今道中日記によって宿の木賃、米代価、酒代等を抄出し、これを元として大体の諸経費を考えてみることにする。左に主なる宿泊地と木賃、米代を一覧にして示すと、(地名、米1升代、木賃)今在家、90文、35文。神代、76文、40文。勝山、90文、45文。勝央、86文、40文。姫路、77文、32文。石山、100文、40文。水口、100文、松坂、()、32文。小俣、116文、30文。八太、110文、35文。初瀬、106文、30文。神戸、95文、35文。京都、112文、55文。奈良、100文、55文。久見浜、93文、35文。となる。又当時の酒一合代金は大体十六文から十八文位。これで見ると当時(天明四)仮に一日百文としても約六十日で六貫文は入用になる。橋村の場合は明和五年より始めていて、四貫文宛渡している。この頃の米価(註8)は一升五十文前後、木賃二十四、五文という事であるので仮に一日八十文として五十日位の経費はあった。大津村の場合はこの時代より約六十年後の事であるので比較にはならないと思うが十一貫文宛渡すから大体の経費はあったであろうが、橋村に比較すると物価も相当上がっていた事と思われる。以上大まかではあるが、資料に基づいて一通りの考察を試みたわけだが、講費の捻出も苦労する百姓衆にとっては参宮はなかなかの思い立ちであり、さればこそ一生一度の参宮は一入の感激であり、又念願であったわけである。さきにも述べた如く伊勢講は殆どが当時の村(今の区)単位に組織されていたから代参が全部終了するのは大津村の如く明治の中頃までかかった様な例は珍しくなく、うたわれる民謡に伊勢音頭があるが、この節まわしは本場のものとは随分違ったものになってしまって、今ではまるで別な民謡の様に思える程変化している。この事は伊勢講としての記録はなくてもある時代に島の伊勢参りも相当盛んであったという一つの証左にならないものであろうか。
(8)伊勢講を考える時、伊勢の御師(オシ)について是非ふれなければならないが、これも古い記録は今の処見あたらない。最近発見された資料で浦郷村の庄屋であった渡辺家に「諸国配札配当帳」という一冊がある。これは伊勢のみでなく、近くは大社、日御崎、遠くは高野山、京都愛宕山等々から来島の御師から神札をうけ、それを浦郷、赤之江、珍崎、三度の各区に頒布し、そして御初穂を納入したものの控えで、嘉永元年から明治四年までの間の記載がある。所謂御師が持って来る神札は当時は庄屋が責任を以て頒布したものである。参考までに初めの方をあげると、諸国配札配当帳、嘉永元年申六月十七日、高向二頭大夫様御使者渡部正兵衛殿知夫里村より四ツ下刻御出、同日美田村へ御越被成候、一つ、箱御祓、三拾二。一つ、見先御祓、百拾枚。一つ、はし、百七拾弐ぜん。(畧)一つ、箱御祓、一。一つ、萬金丹、壱。一つ、扇子、二本。一つ、風呂敷。一つ、箸、壱袋。〆二百文。庄屋所、〆三貫六百五十八文、右者大庄屋所に而御使者渡部正兵衛殿へ直に相渡申上候、六月二十一日(下畧)すこしく説明を加えると、高向ニ頭大夫というのが、伊勢の御師職で、この御師というのはそれぞれの縄張が厳重であって、隠岐の場合は二頭大夫の管轄であった。(因に伊勢から廻って来る大大神楽の大夫とは無関係)先ず来島すると各村々の庄屋所を訪ねて恒例の通り配札を依頼し、村送りで次の村へ出立して行く、なかなか権威のあるものであった。箱、見先(剣先)御祓は神札の種類、それに箸をつけたものである。萬金丹、扇子、風呂敷、ここにはないが伊勢暦等は庄屋所への手土産として持参したもの。数量は浦郷村全体の配布数である。又、私蔵のものに、記、一金三百疋也、右者此度主家大口付御寄付御頼申上候処格別之思召を以御寄付被成下恭頂戴仕候何れ帰国之上無相違収納可仕候為後日仮請二候仍如件。高向ニ頭大夫、渡部正兵衛印、嘉永五壬子年七月、雲上寺様。又、西郷町高梨氏所蔵の「伊勢講打入銭並差引帳」(嘉永七年)に卯三月二十三日、壱貫七百文、金壱分、此分伊勢大夫渡辺正兵衛様へ宿大仲より御案内被下候節中間より進上物に成申候、同四月二十一日、参貫四百文、金弐分、此分右同人様帰国之節中間より進上物ニ成申候(下略)。右の記載がある処からして隠岐全島二頭大夫の管轄であった事がわかる。橋村の如く地元に先達のいる場合は、それが中心となって「講」を組織する事も出来るが、そうでない地域では、こうして毎年廻国して来る伊勢の御師の配下の者が講をつくる事を勧めたのではないか。
(結)本稿の初めに「山内の一角に伊勢山を見立て内宮、外宮の碑を設け云々」と書いたが、この碑のかたえに、天明三癸卯六月吉日、奉詣両皇太神宮御宝前、と記された碑があり下方に快栄外参宮者の名七名が記されている。もう一基天明六年五月の記名のある右同様の碑がありこれには八名の名が記載されている。参宮の記念碑まで建てるという事は、今の感覚では想像も出来ないが、昔の旅には出立に当って水盃までして旅立ったといわれ、それだけに一生一度の念願かなって参宮も恙く終えて帰った時の喜びは感慨一入であり記念碑まで建てる気になったものであろう。
(註1)天明三年の参宮記念碑に、宇賀村八百次、伊平太、別府村□□、美田村平兵衛、安右エ門、快栄、おとら、とある。天明六年の碑、美田村みそや祐七の外、大津おくり、浦郷村、清八、同、大江およし、おせん、雲上寺快栄、覚善、宥海、美田村安立常右エ門とある。
(註2)壱〆五束、薪「一〆」は木の長さ一尺八寸~二尺のものを、高さ二尺五寸巾三尺に積んだもの。束は長さ五尺の縄を二回まわしてしばった木の数量(西ノ島、美田の例)
(註3)「参宮道中日記」は年記の奥書はないが、「辰六月十五日」とあり、他の資料も参考にして「天明四年辰年」と推定した。
(註4)4ツ時(午前四時と午前十時とある)
(註5)七ツ時(午後四時)知夫里発午前十時とすると六時間で美保関に着いた事になるので一寸早すぎる様だ。しかし順風にのるとこの時間でも行けたものだという。この場合何れか不明。
(註6)美保殿=美保神社の事。
(註7)モロイソ、現在の住吉(旧芝山港)か諸寄か不明、ただしキリハマより舟を雇ったとあるから、さすれば諸寄の方が妥当かもしれぬ。加露当りでないかという考え方もある。
本稿は昭和35年、神宮司庁刊「瑞垣」(47、48)に掲載したものの改稿である。前稿における誤を訂正し、新たに、御師関係資料を加えた。(52、4、4)(隠岐島前文化財専門委員)
『隠岐(島前)の文化財七号』
その制度の初期から享保ごろまでは政治視察の上で幕府にとっても効果をあげたといわれているが、寛文ごろからは殊に海辺浦々の巡見が重視されたという。焼火神社の御社参記録には、寛永十年の巡見以来の記録がその都度認められ、和巻手記にある先触れから知夫一泊翌日社参、一泊のこともあり、休息の後出発の場合もあった。ここには、その一つをあげて大体のことを知っていただく事にしたい。
淳信院様御代替え翌年。延享三年寅六月御巡見御参詣之記。大巡見。小幡又十郎様、御知行千五百石。板橋民部様、同千七百石。伊奈兵庫様、同千石。延享三年寅四月二十八日雲州三保関より知夫里湊江夜五ツ時に御着船翌二十九日四ツ時橋浦より御登山、御迎住持宥賢伴僧清水寺、有光寺恵光、精進川土橋之前に而御待受申上、小幡又十郎様御用人関仲右衛門殿三張常助殿御先へ登山、直に神前へ御参詣済、寺へ御入り候而、又十郎様より住待へ御口上之趣並御初穂白木台ニ而御持参取次、同宿春山、次に又重郎様御乗物五丁程跡より参、伴僧壱人ツ、御案内路次門迄参り夫より御座敷江之御案内春山。次板橋民部様右同断、次伊奈兵庫様右同断。御座敷江御着座巳後、住持御目見御挨拶申上、次御引渡三宝、次御盃御吸物次御酒次御肴等。一、御行水之支度仕候得共、御行水は不被遊候。神前へ御参詣御案内春山、祖寛、拝殿に御待請ハ清水寺恵光、住持御殿之高蘭之内ニ着座、御三殿之膝付迄御登り御排相済、拝殿へ御帰座之上、御神酒御洗米差上寺へ御着座。一、御用人衆御家老衆六人屋舗、御家老衆四人上ケ炬燵ノ間、士衆二十四人客殿ニ而是迄御吸物本膳御上候同断、但客殿光之間へは二之膳出し不申候。一、家来衆七於余人是亦こたつ之間、囲爐裏間ニ而三しきりに膳部差出相済候。外ニ雲州より渡海之御船手等大勢入込杯之外膳部余計出し候、殊ニ御船手等勝手迄入込大混雑ニ御座候。一、雲州より御馳走方三人御料理方御茶道、是ハ新六畳之間。一、医師衆三人、是ハいろり之間上ニ着座此外、御供人数十人斗は隠居ニ客着座、是も二しきりに膳相済。一、雲州より之御船頭衆三人此外、中間等拾四五人は座敷無之ニ付直に橋へ下山。一、当島御郡代御代官目付元吟味方、是ハ朝五ツ半時知夫里より登山膳相済夫より西之蔵ニ着座、其外下役人衆勝手廻りニ被居候。一、当山ヲ九ツ半時御、下向橋浦へ、御下山夫より美田へ御通り御船ニ而、別府泊り御見送り住持、伴僧若党ニ而精進川土橋罷出候。一、先達而、雲州より両度之御巡見御渡海海上安全御祈祷被迎遣候、御初尾白銀一枚神献御座候。則前方を護摩キ行御巡見御登山之節座敷ニ而右雲州より御祈祷御頼ミ被露仕御礼差上申候。
一、翌晦日別府御本陣迄御影神銭等持参、昨日御社参之御礼ニ住持罷出候、伴僧長福寺春山、若党伊八、外ニ二人召連。一、同日海士村へ御渡海御泊。一、五月朔日島後都万村へ御渡海、同日西郷へ御越し二夜泊同月三日島後御出船三保関へ御着船。
夘月晦日之献立。御引渡、三宝、御吸物、御酒、御肴、三種。御本膳。生盛。夏大根、すまし、志ゃうが。御酢和会。きくらげ、御汁、小志いたけ、めうが竹、ふき、ゆず、山椒。御煮物。むかこ、水こんにゃく、御飯、路くぢやう、引而、香之物。二之膳。平皿。ちくわとうふ、くわい、竹の子、かんぴょう、つけ松たけ、御汁。とろろ、あおのり、包こしょう、猪口。こまとうがらし、うこぎ、すりわさび煮。御麩皿。麩。いり酒、生こんにゃく、指末、海そうめん、けん青梅、かんてん、れんこん、河たけ。
御地紙折。山のいもちりめん焼、あけこんぶ、やきしいたけ山枡みそ付。御酒、御肴。ふりけし、ひたし物。御肴御吸物。みそ、御吸もの、御肴。此方見合。後段。御茶、御菓子、御餅。すまし御吸物、へきいも、しいたけ、しほで。御酒御肴いろいろ。
御次之献立。皿、すあへ、夏大根、こんにゃく、青みちさ。汁、あられとうふ、ふき。煮物、香之物、おわり大根、むかご、氷こんにゃく。飯。平皿、引而、山いも、わらび、かんぴょう、あげとうふ、こんふ。指味、からしかけ酢、とさか、かんてん、ちさ。あへもの、ひじき、白あへ。酒、肴、いろいろ。
後段、茶。料理人、水野善兵衛。手伝、崎村観音寺。美田重左衛門。別府次郎左衛門。座敷給仕等配役覚。知々井春源、同宿恵光。同宿、春山。一、御座敷、規寛、小座敷、美田新九郎。同、伝之進。先炬燵之間、海士村建興寺。美田甚兵衛。客殿、有光寺。美田甚助。度した炬燵之間、大山教運。美田次郎右衛門。同儀右衛門。囲爐裏間、美田儀右ヱ門。同八之丞。はし伴助。新座敷、別府千福寺。同松之助。座敷惣見役、美田長福寺。勝手見繕、浦之郷。七兵衛。勝手繕場見繕、知夫里伊八郎。酒方、文太夫。四郎兵衛。行水場役、二人。勝手働、男女二十三人。料理方、四人。〆五拾四人。一、橋村より御登山之節床御小休所迄御茶持参役。新九郎、千太郎。松之助、作左衛門。此節毎度ニ遣候人足四拾参人、是ハ西鳥居より内道橋掃除等ニ遣候御社参当日人足遣候。右何レも橋村之者共。一、御札守役、宇野大和。是ハ護摩堂ニ而出ス御影六百枚程用意仕置、是ハ沢山也。神銭三千程拵置候得共七百、程不足ニ付翌日相成別府へ持参仕候、壱枚縁起等余程入用也。一、当寺之寺号山号並住持之名同宿之名迄書出候様被仰候ニ付則左之通書出候。覚。一、焼火山雲上寺住、兵部郷法邦宥賢。同宿、春山。恵光。視寛。一、当山境内並寺内間数書出候様。被仰出左之通書出候。覚。一、隠岐国嶋前知夫里郡美田村焼火山雲上寺。寺内間数梁行五間半桁行十五間。境内麓寄り絶頂迄拾丁余東西拾二三町。右当山之儀断崖絶壁樹木深欝故巨細ニ難斗候故大既書上申候。延享三年寅年四月二十九日別当兵部卿法印。宥賢印。如此三通相認別府(翌日御礼ニ罷出候節差出申候。御初穂之覚。一、金弐百匹、小幡又十郎様より。青銅三百文、銅御用人衆中より。一、同弐百匹、板橋民部様より。青銅三百文、同御用人衆中より。一、同弐百匹、伊奈兵庫様より。青銅三百文、同御用人衆中より。以上である
一回の御社参記は終っているが、大方の場合、この大一行は焼火山の苦心も大変なものであったことであったにちがいない。和巻手記の方では、島前村方の方の苦労がわかるが、焼火山が中心になって、当時の島前各寺々の僧を集めて、その応接にあたっていることがわかる。こんな大仕かけな仕事を仰遣わされ、それをみごろに果たしてきた当時の焼火山雲上寺の実力は想像以上であって、後年の焼火信仰の普及と経営に大きく作用したと考えられる。いまは、島民から忘れ去られているけれども、巡見使の来島と、焼火社参りの例外のなかった史実について、もっと考えてみたいと思うのである。それにしても巡見使が必ず最初に着岸し、そこで、一泊した知夫の地に、なぜその伝えがのこらなかったか不思議思はれる。筆者が島後の古文書で調べたところではその当時の知夫の宿割りの明記したものも残っているので、知夫には伝えだけでものこってよい筈である。何かわりきれない感じがする。
巡見使社参。
1、寛氷十年、大巡見、市橋伊豆守。村越七郎右衛門。拓植平右衛門。
2、寛文七年、大巡見、稲葉清左衛門。大巡見。市橋伊豆守・村越七郎右衛門・拓殖平右衛門。大巡見。稲葉清左衛門・市橋三四郎・徳永頼母市橋三四郎。徳永頼母。
3、延宝九年、大巡見、高木忠右衛門。服部久右衛門。佐橋甚兵衛。
4、元禄四年、御料巡見、秋田三郎左衛門。宝七郎左衛門。鈴木弥市郎。
5、宝氷7年、大巡見、黒川与兵衛。岩瀬吉左衛門。森川六左衛門。正徳二年、御料巡見、大巡見。高木忠右衛門・服部久右衛門・佐橋甚兵衛御料巡見。秋田三郎左衛門・宝七郎左衛門・鈴木弥市郎。大巡見。黒川与兵衛・岩瀬吉左衛門・森川六左衛門。森山勘四郎。三橋勘左衛門。湊五右衛門。
7、正徳六年、大巡見、鈴木藤助。小池岡右衛門。石川浅右衛門。
8、享保二年、大巡見、松平与左衛門。落合源右衛門。近藤源五郎。
9、延享三年、大巡見、小幡又十郎。伊奈兵庫。板橋民部。
10、延享三年、御料巡見、佐久間吉左衛門。野呂吉十郎。山田幸右衛門。
11、宝暦十一年、大巡見、阿部内記。弓気多源七郎。杉原七十郎。
12、同年、御料巡見、永田藤七郎。高野与一左衛門。児島平右衛門。
13、寛政元年、大巡見、石尾七兵衛。御料巡見。佐久間吉左衛門・野呂吉十郎・山田幸右衛門大巡見。阿部内記・弓気多源七郎・杉原七十郎御料巡見。永田藤七郎・高野与一左衛門・児島平右衛門大巡見。石尾七兵衛・花房作五郎・小浜平太夫・花房作五郎。小浜平太夫。
14、同年、御料巡見、清水利兵衛。池田八郎左衛門。村尾源左衛門。
15、天保九年、大巡見、諏訪縫殿助。竹中彦八郎。石川大膳。
16、同年、御料巡見、高橋。八木岡。山本。天保九年の大巡見は、松江藩人
数を入れ
御料巡見。清水利兵衛・池田八郎左衛門・村尾源左衛門
御料巡見。高橋・八木岡・山本
て総渡海人数は四百十三人といった大がかりのものであった。近世の焼火信仰。早くから航海安全の神として崇められていた焼火権現が、西廻航路の航程のなかに隠岐が入ってから航海業者や船乗りの参詣が多くなったこととあわせて、この数度ににわたる巡見使の参詣が慣例になって、地元の篤い信仰とともに、焼火信仰は全国に拡がり普及していったことはまちがいない事実である。補。知夫里村、大江、渡辺喜代一氏の所蔵古文書のなかに、(襖の下張にしたものをはぎとったもの)巡見使の人馬先触の断片があったので、それをかかげて参考に供したい。前文紙切れてなし。宝暦十一年巳三月十。但馬宿中。○人足弐人馬二疋従江戸播磨但馬備中備後美作石見丹後隠岐国迄上下並於彼御用中幾度も可出之、是者右国為巡見御用御徒目附児島平左衛間罷越ニ付而相渡之者也。宝暦十一年己三月、但馬宿中。○永田藤七郎、高野与一左衛門持参之巡見御用書物長持壱棹。従江戸丹後但馬石見隠岐播磨美作備中備後国々迄御用中幾度も急度可持候者也。巳三月、但馬宿中。覚。御朱印一、人足弐人。同断。一、馬三疋。内弐疋ハ人足四人ニ代ル。御リ文。一、御用長持壱棹持人足。永田藤七郎分。御証文。一、人足弐人。同断。一、馬三疋。沙汰文。一、人足弐人。一、馬一疋。これは、筆者が現在までに知夫で見た唯一の巡見使関係古文書である。
『隠岐(島前)の文化財一号』
西ノ島町誌
- 日常の食事
- 主食
- 米飯
- 麦飯
- イモ
- その他
- 粥
- 混ぜ飯
- 蕎麦
- 幼児の補食
- 焼餅
- 携帯食
- 間食
- コジャ
- 主食調査
- 副食
- 魚介類・海藻
- 肉
- 汁
- おひたし
- たきもの
- 調味料
- 味噌
- 醤油
- 酢
- ダシ
- お茶
- 四季のメニュー
- 久見の場合
- 浦郷保育所の場合
- 晴れの食事
- 赤飯
- 巻き酢
- 粥
- 餅
- ダンゴ・マキ
- 祝儀、不祝儀の食物
- 本膳
- 嗜好品
- 酒
- 甘酒
- 焼酎
- ビール・麦酒
- 焼火山の巡遣使への献立
- 食生活の変容
日常の食事
日常の生活の中で、最も変化に境界線の引きにくい分野は、衣食住の領域であろう。西ノ島においても昭和三〇年代を堺に急激に変化していったのが、この部分ではあったが、また、その記録をとどめていないのも衣食住であった。文献にとどめてある記録から、我々の食事の変化の粗筋を述べてみたい。
主食
明治二九年「隠岐国概況取調書」という行政の調査書によると「・・島後地方は米麦をもって常食とし、島前地方は米・麦・甘藷を常食とす。しこうして沿岸地方は山村より幾分の上等飲食をなし飲酒等もしたがって多し。その常食物の歩合は左の如し。島後は米七分・麦三分。島前は米四分・麦三分・甘藷三分・・」とある様に、島前ではイモも主食に入っていたのである。明治末期の米の生産量は西ノ島で一人当たり五勺程度であり、その量ではとても日常の食事に具することはとても不可能であったろう。
つまり米はハレの日(盆・正月・祭・祝い・不祝儀などの日)の特別な主食としてあった。その辺の事情を「隠岐島の民俗」(昭和四八年現在)から引用紹介する。
米飯
「米はわずかしか作らず、しかも一部落にある田圃全部が某家一戸の所有田であったという所もあり、そのようなところでは、小作をするか、あるいは消費する米すべてを購入する必要があった。かつては半農半漁(現在では二農八漁)といわれた豊田でも、半年分は米が 、あったが、あとは安来米を購入したという。従って、大ダンナと呼ばれるほどの家は別として、ほとんどの家が米皆無の麦めし、やや米に恵まれた家で、米一割入りの麦めしといった日常の食生活で、いわば米はハレ用の食料であった。・・米をわずかしか消費しなかった頃は、麦、イモをもっぱら常食していて、米を食べるのは正月、三、五、九の節句、二十三夜、大山さん、氏神祭のときぐらいであった。(仁夫)。米を病人に食べさせると、薬になるともいわれた(宇賀)いったいにイモで腹の下 ごしらえをして、麦で押えるという主食の食べ方をしたのだが、村で唯一のダンナと呼ばれる家は、そのような時代でも全部米の飯であった(崎)。また、船に乗ったときは、三食とも米が多く入った御飯を食べた。仕事がえらいので、そうしないと力がでないという(多沢)」
麦飯
「麦はたくさん作った。大麦と小麦とがあり、前者は麦めしに、後者は粉にしたり、麹に作ってエンソ(味噌・醤油)に仕立てるのに使う。他に小量ではあるが餅麦がある。これは外観は紫色で粉は白色。ひいてオロシでふるって、こねてゆがくと、餅のように粘りのある団子ができた(三度
)。大麦は収穫してから、まずカラ竿で叩いて、オロシでおろしたものを、唐臼で搗く。三回搗かねばならぬなど、かなりの力仕事なので、おもに嫁が搗き、すわっていてイレボウでかき混ぜるのは年寄りの役であった(薄毛)・・大麦を一ぺん火にくぐらせて、ソウキに打ちあけて汁をとり、新しく再び水を入れて、一升の麦に米二合くらいを入れて煮る。ソウキに取った汁は、もったいないので畑仕事のときかぶる手拭いやユカタの糊に利用する(物井)。家によっては麦だけの家もあり、さらに麦だけではもったいないといって稗を混ぜる家もあった(仁夫)」
普段の日は、この様に麦もしくはイモ(甘藷)が主食の大半を占めた。
イモ(甘藷)
「島で単にイモといえば、甘薯のことで、麦作の前にイモを作る。以前はどこの家でもたくさん作って一年中食べた。収穫後は生のまま貯蔵するほか、イモカンピョウに加工してたくわえた。生のイモを収納するイモグラは、昔はイロリの近くの床下に、スクモ(籾殻)を敷いて、そこに置く方法をとったが、その後、戸外に横穴(入口は四〇~五〇cmくらいの角形にし、奥は広く掘る)を作り、中に藁を敷き、イモを置いてから籾殻でおおう。イモグラはすべて個人持ちであった(全域)イモカンピョウはイモカンペイとも、単にカンピョウと
もいう。洗ってから薄い輪切りに切って、その一枚一枚をブリキで作った穴アカシで穴をあけ、紐を通して三~四日干す。ゆでてから以上のようにすると、とりわけ甘味がでる(物井)・・丸のまま洗って、羽釜にコザキや板に穴をあけたものを伏せて、その上に甑を載せ、この中に入れて蒸すか、五升釜に水とイモを入れてゆでるかして食べる(全域)カンペイ団子も作る。ナマのイモを春のきつい光で干して、唐臼で粉にし、水でこねて沸騰した湯に投じて
、引き上げたものを黄粉をまぶして食べる(物井)手間がかかるのでたまにしか作らなかったが、シェー団子もあった。ブリキ板にプスプスと穴をあけた、大きなおろしようのものを自家製で用意し、これでイモをすって、水で洗い上げ、でん粉をこして取り、かわかして粉にしたも
のを、蒸したイモと練り混ぜ、団子にしてウマガタリの葉を両面につけて蒸して食べる(三度)
」
イモに関しては前述の「隠岐国概況取調書」に次の様な伝承が記述されている。「・・知夫里島多沢の里に往時大空藤助と云うものあり諸国を回歴したる際薩摩より甘薯の種子を得て帰るこれ隠岐国に甘薯あるの始なりと云う現今の戸主を大空甚八という。藤助五代の孫なり今尚藤助の遺物負ひ櫃叩き鐘及び富士山の石竹生島弁天の像等を蔵せり。」つまりイモは島前から始まったとされているのである。それと現在でも島前では「芋代官の碑」というのが多く見受けられる。これは大森代官井戸平左衛門が薩摩から種を持ち帰り皆に植えさせたという史実を元にしている。いずれにせよ、島前でのイモは主食として重宝がられたことがわかる。
昭和二六年の調査においても米飯が中心となっているわけではない。
「高齢者調査表集計表」昭和二六年(一九五一)黒木村
(表1挿入)
「黒木村長寿研究」第二報 昭和三十二年(一九五七)(六〇才以上)
(表2挿入)
米飯がほとんどを占めるのは昭和三〇年代中頃からの事と思われる。
その他
粥
ふだん食べる粥は、麦めしの水分を多くしたていの麦の粥もあったが、たいていは他になにか混ぜ入れて作った。小麦の団子や蕎麦を切って入れたり(崎)、シイラをコゴメといって、これの粉の団子も入れた(物井)。イリコを水に入れて、煮立ったらイモや和布を入れて、お 粥にしても食べた(薄毛)
混ぜ飯
米を多く食べるようになってからも、いろいろのものを加えてたいた。自生するコゴネをとってきてたき込んだり、和布を刻んで、御飯の蒸し上がる前に入れ、塩を振ってからむらして掻き混ぜた、和布御飯もよく作った(豊田)。加える具がよいものになると、御馳走と しての混ぜ御飯となり、来客の折やモノビ(特別の日)にセンタ、サザエ、鮑などを熱湯をかけてはがし、米と混ぜて炊き上げたり、人参、大根、野焼き、椎茸、昆布などを細かく刻んで、だし汁、醤油とともに入れてたくものもある(豊田、宇賀)加える具は他に干し大根、揚げ、カマボコなど 任意に入れる。
蕎麦
メイタとメン棒を作っておき、平生もよく打って食べた。ネギや胡麻、海苔などをかけて、ダシ汁で食べる。(崎)蕎麦粉を練ってのし、切って塩味で煮たのをニゴミといって、小麦粉でも作った。大根を千切りにして醤油味の汁にして、蕎麦を切って入れたものをデエコ
、ソバといった。蕎麦粉を熱湯で練った蕎麦のネリコもよく作った。( 仁夫)。ネリコを形つくって、中に黒砂糖をアンに入れて、アブリコで焼くヤキモチ
は、夜食用にした(物井)。
赤児の捕食
米の粉をいって、篩(フルイ)でふるって、沸騰した湯を入れて、砂糖で味付けしてさましたものを与えた(物井)
焼餅
焼餅は明治、大正の頃から戦前まではよく焼餅を作ったが、粟、稗、麦、などで作るもののうち粟で作ったのが一番いいという(多沢)
携帯食
山などに行くときには、コウリやミツに麦飯を入れて、味噌漬やコジョウユを添えて携帯した(仁夫)。ヤキメシといって、握り飯にコジョウユをつけて焼き、サンショウの葉や和布の芯をつけたものはおいしい携帯食として好まれた(豊田)。麦飯をツクネ(ムスビ) にして、手拭の端に包んで行くこともあった(薄毛)。学校の弁当には、親の使っている手拭に蒸したイモを入れて行ったり、昭和の時代に入って、米をいくらか多く食べるようになると、麦と混炊する米の、たき上がりを混ぜないで、米のところをすくって持って行った(薄毛、豊田)
間食「コジャ」
きつい仕事をする頃には、三度の食事の他にコジャといって軽食をとる。朝飯(あさはん)の前にひと仕事をするので、仕事を始める前にチャノコをとり、朝飯と昼飯(ちゅうはん)の間にアサコジャ、昼飯と夕飯(ゆうはん)の間に晩コジャと三回食べる。このほか仕事が夜遅くまで及ぶ時には夜食を食べる。下記は昭和の初め頃の某家の献立である。(崎)
(表3挿入)
「黒木村長寿研究」第二報 昭和三十二年(一九五七)(六〇才以上)
間食
(表4挿入)
副食
魚介類「海藻」
昔は海苔は自由にとってよかった。今はスを立てるのでおのずととってよい場所が決ってくる。海苔はまずソウタテ(スを仕掛ける)をしておき、そこに付く海苔を、コサゲといって、海苔をこそげ取る道具で掻き取る。これを家に持ってきて、細かく切って海水で洗い、海苔ブネに水を張って、型に海苔簀を付けたものに海苔を薄く広げてつけ、干す。以前は今の市販のものよりは大きかった。これを一〇枚単位位にしてオヤカタに上げたりした(物井)別に玉海苔も作るが、これは塩っぱい。採取した海苔を丸めてから平たくし、真中に藁を通 して軒下に下に下げて干し、使うときは水に入れて柔らかくする。正月の雑煮には欠かせぬものとされている(全域)
肉
昔はなんの肉でも、肉のことをウシといった。牛が針をのんだり、崖から墜死したりしたのは、肉が新しくてよいといった。鶏や鴨もスキヤキにして食べた(崎、豊田)
「汁」
味噌汁は寒いときのほかは、ふだんあんまり作らなかった。味噌汁はイリコを煮出した汁に、汁味噌をといて入れ、海藻や野菜をその時々に応じて入れる。一二月頃に長くなったソゾを採って汁の実にする。火の止めぎわに入れて食べるが、おいしいので食べすぎぬようにしないと、油が多くて頭が痛くなるという。保存があまりきかず、二日ともたない。水に浮かして置かぬとすぐ焼けてしまう(物井)ゴジルもちょっと御馳走を食べようか、というときに作るが、手間がかかるのであまり作らない。味噌汁の中に小麦粉を練ってちぎって入れた汁団 子も、寒いときに捕食としてよく作った。山芋をカガツですって、ダシでのばすトロロもたまに作った。和布蕪のトロロもあって、これはかぶを細かく包丁で刻んで湯をかけ、醤油で味をつけて食べる。干したメカブを叩いても作る(物井)
おかず
「おひたし」
菜、野性の芹をゆでて醤油をつけて食べたり、イヌビユをヒの葉といって、お盆の仏前に供えるものとしていたし、平生もゆでておひたしに食べたが、最近は食べなくなった。(仁夫)なお、和布、岩海苔、カジメ、サザエ、ニナなどをたいて抜いたものの酢味噌あえや、茗荷の茎を刻んで酢味噌であえ、シイラなどの魚と混ぜあえたものなどを作る(薄毛)
「たきもの」
野菜をイリコのだしでたき、味噌で味付けしたものは昔も今も変らず作る。例えば大根と昆布を煮たり、荒目の干したものを水に戻してたき、水に煮だして渋味を取り、刻 んで油でいためてからたく。夏には南瓜もたいた(物井)ハバといって、海苔のようにオカに生えているのを取って、ダシを入れてたいたり、焼もする(仁夫)
調味料
納屋の横のエンソ(塩気のあるもの・味噌・醤油など)小屋を作って、味噌、醤油、漬物などを貯蔵しておく(崎)
「味噌」
味噌にはなめ味噌と汁味噌とがあり、後者は辛味噌ともいう。汁味噌は前は三年味噌がおいしいといったが、この頃は白味噌がよいといって、半年ごとに作る家が多くなった。麹も昔は麦だけであったが、今は米のみを使う。汁味噌はまず麦でハナ(麹)を作る一方、大豆をかしてたく。このとき煮汁が多い目になるようにし、豆を搗くときこの汁を差していく。ボロボロの味噌にならぬように。麹とたいた大豆と塩とを合わせて唐臼で搗く。こ れを大きなバンドに入れて貯蔵する。バンドには一斗、三斗、四斗と各種あった。湯に味噌をとかして牛にも与えるので、大量必要であったため、四斗バンドを三本くらい作った(仁夫)
醤油
醤油を作るには、まずハナ(麹)をねかす。大豆をホ-ロクでいってひき割って、すでにいってあるからさっと蒸し、これを綺麗なむしろに広げて、その上を「雨降り」と呼ぶ木の葉(ネバの木)でおおっておく。ねる時期によい八月初旬ごろであると、一晩もすると真っ青になるので、ハナ一升に塩五合、水一升の割りに混ぜ合わせて、醤油桶に計って入れておく。翌年の同じ頃に簀を立て、ひしゃくで汲んでたき、ひと煮立ちさせたものを瓶に入れておいて使う。こし糟は灰をまぶして肥料にし、麦蒔きの下に敷く(薄毛)
酢
大麦でハナを作り、ハナ三升に水三升、ハナと同種の麦五合とをハンドに入れてねかし、暑いときには一週間、他のときには二週間もすれば酢になるので、晒でしぼって容器にとって使う(崎)。橙を切って晒布に包んで手でしぼって作ったり(物井)、酢酸を買っても使った。
ダシ
鰹以外の魚を使っていても、ダシ用に加工するのをカツオにするという(崎)アゴ、鰺、鰯をさっとゆがいて、天日に当てて干したものをイリコといい、ダシに使う(全域)
飲み物の事
現在の情況はよく解らないが、昭和三二年には次のような面白い調査があった。
以下の表は黒木村が長寿の村として脚光をあびた時に行った様々な食生活の調査の一部であり、六〇才以上にアンケートを行った。
「黒木村長寿研究」第二報(一九五七年)
(表5挿入)
四季のメニュー
久見の場合
以下のメニューは大正の終わりから昭和一〇年代にかけて隠岐島(島後の久見)で作られていたものである。これを直ぐに西ノ島にあてはめる訳にはいかないが、少なくとも一般的家庭の片鱗はうかがえると思われるのでここに揚げておく。しかしこのメニューでさえも久見では上の階層に属する家なので、その辺もある程度割り引いて考えなければならない。『島根の食事』から(表6挿入)
浦郷保育所の場合
さて、これを現代と比較するために「一九九一平成三年一一月 西ノ島町学校給食」をあげると
(表7挿入)
自給自足体制が崩れると、それまでは労働に依存していたものが、貨幣に依存することに変わり、食品も商店もしくは移入物に依存する様になる。そこで商店の依存度が高くなってくるのであった。
食事の原料も自給物から商品に変わり、それに連れて加工品が多くなってくる。広い範囲から集められた食事の商品は季節の物さえ忘れさせてくれるほど広範囲になる。おかずのメニューは必然的に多くなり、今までのものは、和食というよりも郷土食として位置付けられる事になる。日常は和食・洋食・中華の混合であり、それが普通とされているのが現在であろう。それに連れて調味料も、味噌・醤油・塩だけであったものからソース・胡椒・マヨネーズ・ケチャップなど多種にわたってきた。最も変化したのが主食であろう。隠岐島特に島前では一般的には米・麦・甘藷が主であったが、ほとんどが米食を中心とすることになり、朝食などはパン(小麦)場合も珍しくなくなってきた。しかし、昭和三十年代中ごろまでは混食(米と麦の混合)が一般的であった。食事は何よりも腹いっぱい食べられるのがよしとされていたのが、栄養のバランスを中心に献立を考える様になってきた。この傾向は特に学校給食に顕著である。
わが国でパンが製造販売されたのは明治三五年といわれるが、あんパンのような菓子パンが主流であり、食事として考える者は少なかったといわれる。そのせいか菓子パンは食べても食パンは普及しなかった。そのパンが主食として食卓にあがるのは戦後からである。食パンの先鞭を付けたのは学校給食であった。給食でお馴染みとなったコッペパンは進駐軍の放出メリケン粉で作られ、全国の児童に配給されたのがはじまりである。以来学校給食には欠かせないのがパンであった。西ノ島では昭和二四・五年頃からパン製造は行われているがやはり菓子パンが中心で、食事として普及するのは給食の開始された昭和三九年以降のことと思われる。パン食に欠かせないバターやチーズも、老人の間では牛くさいと毛嫌いする者もいたようであるが、日常の食事に調味料として利用されるようになると次第に慣れていったようである。しかし、肉体労働には不向きでパン食では力が出ないという者も多い。また、近年では島内の喫茶店でも朝はモーニング(パン定食)が一般化するようになった。店頭に並ぶ数多くの種類、売れ行きをみても、パンは日常の食事には欠かせないものとなっているようである。喫茶店でモーニングと命名された主食をパンとした洋風定食は、一般家庭の食卓形態をも物語っている。つまり、朝の食事であるということ、飲み物はコーヒーか紅茶であることなどが特徴である。主食としてのパンが普及したといっても、現段階では昼食・夕食までもパンが主流になったわけではない。
昭和三三年にはインスタントラーメンが発売された。これがすぐに西ノ島に普及したのではないが、以後徐々に、商店から手に入れてすぐに口に入る食品の代名詞としてインスタントラーメンはあった。昭和四〇年代には各家庭に冷蔵庫が広まるにともなって、生鮮食料品の長期保存が可能になる。それはレトルト食品・冷凍食品の発売と相まって現在ではそれをファーストフード(手間をかけずに、短時間で食べられる食品)と呼ぶ。短い家事時間を効率よく切り盛りする必需品として、特にご婦人方には重宝がられている。
家庭の食事ともいいがたく、また晴れの食事とも確定しがたいものが、旅館・食堂・レストラン・寿司屋などの外食である。元は観光客に対応する必要から徐々に普及したのであろうが、地元の人にとっても利用されているのがこの方面の食事であった。旅館などでは晴れの食事を出す場所として観光シーズン以外にも賑わうが、食堂・レストランは主に日常の家庭料理の息抜きの場所として親しまれている。この外食は和食・洋食・中華と明確にメニューの区別があり、それが家庭料理のモデルとして一層メニューを豊富にする役目を果たしていると思われる。
晴れの食事
今までは日常の食事であったが、晴れの日(祝儀・不祝儀・祭の日)はご馳走の出る日という以上に特別であった。その種の資料に乏しいのではあるが、民間資料からある程度はうかがう事も可能である。『隠岐島の民俗』から、そのメニューを引用する。
コワメシ(赤飯)
モノビ(特別の日)にたくという。三度では氏神さんの祭りには、その年に生まれた子のいる家で、麦の甘酒と赤飯をたいて近隣や親戚に配る。他に盆、節句、トシイワイなどにたく。 「鮓」 押し鮓、鮓めしを型で抜き、モロブタに並べて、一つ一つの上に卵焼き、デンブ、ショウガなどを載せて飾る。昔は春菊の葉も載せた(仁夫、物井)
巻き鮓
芯に椎茸、卵焼き、デンブなどを入れて海苔で巻く。イカで巻くこともある(崎)
バラズシ
モロブタよりこまい桶に、野菜や貝などを煮たものを混ぜた鮓飯を入れ、イサキ、鯵などの魚を三枚におろして酢に漬けたものを上に張った(豊田)
粥
ふだんの麦の粥などと違って、ハレの機会には上等の(タダ米の混合率の高い)粥を御馳走の一つとして食べた。三度ではシモツキ粥といって、米に小豆を入れた粥に蕎麦を切って入れた粥(ネゴミ)を作り、霜月の家の大将(戸主)の干支の日に、大きな鉢やハンボウに入れて親 戚に配る。また、正月と五月一六日には、トキガユといって、タダ米ばかりの粥を作って仏様に上げ、人々も食べる(仁夫、崎)。仁夫では男女が寄って粥を煮て会食した。亥の子の日にダイコ粥といって、大根を細かく切って入れた粥を作り、餅を入れて食べた(多沢)
餅
正月をはじめ、三月、九月、氏神祭、田植のとき、四二才、六一才、八八才、のトシイワイのときなどに餅を搗く。ボタモチは刈り上げのときつくる(物井)。他に祝儀、不祝儀の機会にも餅を搗く。これらのうち、正月の準備のため、暮れに一番大量に搗く。糯米ばかりの餅のほか、各種の餅を、二~三斗は搗く。イレテと搗き手の二人で搗くが、米を蒸す者、餅を形づくる者など人手を要するので、親戚や近隣で仲間で搗くこともある(物井)。糯米にタダ米(粳米)を混ぜて搗くと、タダ米が粒のまざった餅ができ、これをアラカネ餅という。フキモ チは糯米、粳米半々ずつを粉にしてから蒸して搗くので、リキがない。 大豆をひき割って混ぜるとこうばしいといわれた。また、大豆を粉にして、蒸すとき入れると柔らかな餅ができるという。ズイキ芋も搗き混ぜると柔らかくなってよいといった。甘味がでてよいといってイモも入れる。黍はひいて団子にもするが、臼で搗きもする。粟はモチアワイを使う。バクモチといって、小麦粉、糯米の粉、蓮を混ぜて搗く餅もあり、これには蕎麦粉を入れることもある。これらの餅を全部で一俵くらい搗くとして、そのうち米のものは二斗、粟、稗、黍、バクモチの類のものが二斗の割りくらいに搗いた。正月の餅はイリコでダシを取り、餅を 入れた椀に注ぎ、上から丸海苔をかける(全域)。餅を小豆で煮たものをニナガシという(仁夫)。三月三日の節句には、米、粟、蓮を入れて搗き、のし餅にしてから四すみを切ってシノギ(菱形)に切る。これを屋内の神々や仏に供え、また三枚をオヤモト(嫁の実家)の神に供える(三度)
団子およびマキ
小麦を石臼でひいて、粉おろし(篩)でおろした(ふるった)粉で作る小麦団子は、日常補食として作るが、節句や盆などに作る団子類は米の粉も加えて作る。五月五日の節句にはマキを作る。糯米とタダ米を混ぜて粉にして、水でこねて団子にし、カタリの葉に包んでから蒸す。葉の色が変色したら蒸れたと判断する。五月の節句の場合はオマキも萱の葉を何枚か合わせて包み、藺でぐるぐる巻いた萱マキにする(物井)。あるいはカタリの葉一枚で巻いてから、萱の葉二枚で包む(三度)。餡を入れるものも入れぬものもある。田植や盆に はカタリの葉二枚を団子の両面につけたオマキにする(物井)ホオカムリとよぶ(多沢)。盆にはネジリ団子も作った。昔は小麦粉で、現在は糯米四にタダ米六の割合の粉をコネバチに水を差してこね、ネジリの形にして鍋でゆでて、とり出して黄粉をつけて食す(物井)。二〇年く らい前までは、モチ麦の粉でもマキを作った。萱に包んで五個、七個ぐらいづつにたばねてたく(仁夫)
祝儀、不祝儀の食物
地下に祝儀や不祝儀が生じると、地下の女達が集まって膳のしたくをする。普通は正月に一度使うくらいのカドの大クドも、このときは使って、豆腐を作ったり、餅搗きの用意をしたりする。豆腐はたくさん作って、袋に入れて井戸に吊しておく(薄毛)。
本膳
これは高膳で、御祝儀や氏神講のときなどに用意される献立は、次のとおりである。膳の右手前はオツケ椀で、豆腐、ネギの入った味噌汁に上から岩海苔をかける。左手前は御飯を入れた椀、二合半くらいの量を高盛りにする。真ん中はツボでゴボウ、人参、カンピョウ、豆 腐、センタなどを采の目に切り、油でいためてから醤油で味付けをし、海苔や胡麻をふりかける。右奥はムコウツケ、漬物やナマスを盛る。左奥はフィラ(ヒラ-平皿)、ワラビ、大根、人参、ゴボウ、豆腐、コンニャク、昆布を大きく切って煮しめて、器に盛つけるときは、大きい長方形の豆腐を上からおおうように載せる。 煮物の具の品数が多いほど豪華とみられ、また奇数になるようにした(全域)。膳のフィラには手をつけずに、添えてある竹皮に包んで各自持ち帰ることになっていた。現在はフィラには魚や果実を型どった砂糖や菓子を盛るので、紙に包んで持ち帰る(全域)。本膳が出る前に、餅 入りの吸物、刺身、海の肴の盛り合わせがでるので、取り皿に取っては食べる。六〇年前に某女が嫁に入ったときは、行ったヨ-サに御飯、ニコミ、汁、ナマスが出て、翌朝は汁とコウコと残り御飯、昼飯もありあわせを食べ、夕飯にツボ、フラ・オツユ、酢のもの、刺身が出て、豆腐を油で揚げて、その下に昆布を二つ盛り込んだものが出た(崎)
嗜好品
酒
米の酒も少しは作ったが、米の少ないところなので、失敗を恐れてあまり作らなかった。米の酒はまず御飯を蒸し、買った麹と混ぜて、こまい壷に入れて一週間もすると沸いてくるので、その中へ蒸した米をさまして混ぜ、米と同量の割合の水を混ぜ、蓋をしてさらに 一週間たったらふたたび沸く。これを三回繰り返す。一回ではイジ(辛味)が出ない。そのうち上のほうが澄んでくるので、竹の輪の簀を入れて汲み出す(物井)ドブ酒は戦前は作ったが、戦後このかた作らなかった(多沢)
甘酒(アマガユ)
現在でも、正月に作る。正月にはヤク落しといって、家族に四二、六一才の者がいると、皆が祝って来るので、このときは二斗ぐらい作ってふるまう(薄毛、三度)。甘酒を作る機会が、ちょうど寒い時期なので、しろうとでは麹がうまくいかないので、麹は 麹屋から購入する。餅を柔らかく煮て麹と混ぜてモロブタに入れておくとすぐできるが、糯米、麹半々の割では甘すぎるので、麹と米と一:二くらいにする(豊田)
焼酎
麦、甘薯、南瓜などで作った。作り方は皆同じである。このうち南瓜の焼酎の作り方を示す。麦のハナ(麹)を作り、南瓜はおかずにする程度の大きさに切ってゆでる。水を多い目に入れ、ゆで汁ごと(ここが肝腎)ハナと混ぜて三日ほど置いておくと沸いてくる。これをこして飲む。こしかすをオリという(崎)
ビール酒、麦酒
麦酒ともいう。ビール麦(大麦)を唐臼で二~三度搗いて白くし、洗って蒸してモロブタに入れて、ほやほやするくらいの温度にしておくと、二~三日から三~五日くらいで白いもやがつくので、手返しをする。熱が強いと真っ黒になってしまう。これでハナが でき上がり、麦を二升くらい蒸してこのハナと混ぜる。ハナが余分に入ったほうがおいしくできる。ハンドにこれらと水を混ぜて入れ、時々かき回しておくと沸いてくる。できのよいのはさらっと澄んでくる。中へ簀を入れてかい出して飲む(豊田、三度)
巡遣使の食事
島民の晴れの食事ではないが、幕府の高官が隠岐を巡視するに当たって、総勢四百人以上を引き連れて来島した時の資料があるので、ここに紹介したい。但し、このメニューは巡見使の一行の中に料理人十人とあることから、地元の住民が料理をしたのではなく、御付きの専門料理人がこれにあたった。
(表8挿入)
(表9挿入)
(表10挿入)
食生活の変容
少なくとも昭和三十年代くらいまでの島前の祭・祝い・法事などの日には、どの様な食事をしていたのかはある程度推測できるかと思われる。江戸時代から完全なる自給自足体制であった訳ではなかったが、ほぼそういう形ですべてのものが賄われていた。
「ご馳走」とは、盆・正月・祭など少なくとも戦前において飽食と多数のメニューと米飯の事をいったものであろう。それは、ハレの日の食事であった。盆歌の口説きに「盆が来たらこそ麦に米混ぜて、中に小豆をチラパラと・・」という文句も理解できよう。ハレの食事は日常の食事のほどは激変はしなかった。というのは、日常の食事の向上が目指していたのがハレの食事だったからである。そういう意味では食事においては毎日が祭・正月になったのである。日常の食事と異なることは、儀式の食事が現在でも「吸物をどうぞ」という口上に見られる様にハレの食事は大なり小なり一定の順序に従って献立が出されることになっていることであり、煮しめ・マキ・ツボ・寿司・ボタモチ・餅・団子などは依然としてハレの日のものとして意識されている。
巡見使の料理で見た様に、それは高膳に盛られてある。次に酒宴となり、いわゆる食事は本膳と呼ばれる。現在は住宅の変化と共に自宅での儀礼・宴会は少なくなり場所は旅館に任される傾向にあるが、昔ほどには格式ばって無いとしても、形式の片鱗だけはうかがえるのである。そして、食事だけでなく、衣装、住宅の飾り付けなどの伝統的な演出によって晴れがましい心持ちが醸し出されたのであった。
- 幕末の頃
- 明治から昭和三〇年代
- 住居の変化
- 材の変化
- 家具の変化
- 間取りの変化
- 建物構造の変化
幕末の頃
現在、西ノ島では一戸建て住宅としては十坪というのはありそうもないが、百七十年ほど前には、村の中でも広い部類に入り、どちらかというと金持ちの家であった。一般住宅の歴史的資料というのはほとんどないが、文政九年(一八二六)には船越から小向にかけて大火が起こり、その時に代官所が調査を行ったらしく、その調査書が現在残されている。その調査書は幕末の西ノ島の住居に関して参考になるので一部引用してみる。(表1挿入) 船越・小向全体で六一戸。住居の面積(坪数)の統計は表の通りとなり、さらに単純化すると七坪以上が二三%・六坪以下の住居は全体の七七%を占めている。因みに雪隠(便所)はすべての住居に付帯しているが、土蔵や納屋は七坪以上の住居にしか付属していない。すなわち六坪以下が当時の一般的住居の規模とみて差し支えなかろう。家族数も調査項目に記してあるので、これも平均をとってみると、なるほど小さい住居になると平均人数も少なくはなってくるが、三坪住居でも五人もいる処もある。端的に言うと当時は一人が一坪の住居空間を占め、しかも八割近くが六坪以下の住居に住んでいたことになる。この頃の住居の間取りや、家具に関する記述が無いのでさらに詳しい事情はわからないが、少なくとも明治が始まる四二年前までは西ノ島ではこの様なものであった。
明治から昭和三〇年代まで
現在、極端な例では、アパート形式の住居であるが、我々の住まいは昭和に入ってから驚くほどに変化した。それは生活の変化に付随する大きな環境変化であった。
戦前までの西ノ島の民家は驚くほどに似通った田の字型の母屋とそれに付随した納屋、その周りには畑があったり、カドと呼ばれる野外作業場に囲まれていた。別棟には風呂や便所、外流し、まであったのである。戦前までの生活はほとんどが半農半漁であり、また出稼ぎで本土に出掛けるという状態がこの当時から始まってもいた。
さて図の建物の母屋から説明すると
(図面1挿入)(表2挿入)
母屋の前にはカドがある。
(表3挿入)
また母屋の横にある納屋はひとつの職場でもあった。
(表4挿入)
その他には便所や風呂が母屋とは別棟で建てられていた。
(表5挿入)
西ノ島における民家は、大体において以上の様なものであったが、昭和二〇年代後半から現在にかけて暫時改造が行われたり、新築にされたりして、現今に至っている。
(図面2挿入)
建築の構造的に顕著な変化が起こったのは、昭和四〇年代の町営アパートの普及であった。このアパート建設の発端は、各船団から要望があり、先ず浦郷に漁民住宅が建った事であった。それから次第に一般住宅としてのアパートが増大していく。鉄筋コンクリート建て住宅や木造平屋・木造モルタル造りが主で、旧来の民家と対極をなすのが鉄筋コンクリート建ての四階である。
(図面3挿入)
(表6挿入)
住居の変化
旧来の民家から現在の改修・新築・アパートへの変化を、機能の面から見ていくと、
一)納屋は牧畜の衰退と共にダヤが無くなり、倉庫専用の部屋として使用されるか、もしくは、解体されて倉庫専用棟として建てられている場合が多い。
二)野外作業場としてのカドは庭木を植えて庭園にしたり、広場として駐車場にするケースがみられる。
三)ナカイにあったハンドは、水道の普及と共に台所から消えていった。
四)洗面は民家の時代にはナガシ・外ナガシ・風呂場・井戸・川など特定の場所ではなかったが、現在の住居では必ず専用の洗面所が付設されている。
五)石油・ガスの普及と共にイロリが無くなる事によって、そこで決められていた、家族の地位を表す座(ヨコザ・キャクザなどの)も消滅した。これは、大家族から核家族への変化にも連動する。
六)食事をする場所を食堂とするならば、その場所はあまり変わってはいないが、ただ、箱膳から飯台へ飯台からスリッパ履きでテーブルへと変化することによってナカエは台所やキッチンと呼ばれることになった。
七)元々、室内は裸足というのが一般であったが、スリッパの使用は台所だけでなく、廊下や応接間・便所にもおよんだ。
八)水道の完備は各戸に風呂場の常設化を促し、燃料が薪から石油・ガスに代わることによって、風呂はボイラーが一般的になっている。
九)明治一四年の清潔指導法によって、実施された大掃除は、役場・警察などの監視の中で行われたが、昭和三〇年代に廃止されると共に忘れられた。(大掃除とは、現在年末に行われる掃除とは異なり、春・秋の天候の良い一定期間に部屋中の畳を上げて、外に立て掛け、棒でたたいて、埃をとり、畳の下の座板には石灰やDDTを散布した。また、家の周りの溝の掃除もその時に行った)
材の変化
一)屋根が杉皮葺きから瓦葺きに変わった。
二)木材は地元から切り出していたものから、外から規格化された部分材(プレハブ)を導入するようになる。そして、新建材と呼ばれる材が一般的になってきた。
三)屋根や壁に大量に使用されていた土は段々みられなくなり、代わりに断熱材・耐火ボードになる。
四)中の間とオモテ・茶の間とヘヤを仕切っていた中戸(なかど)は襖に変わった。
家具の変化
一)煮炊はイロリで行っていたが、ガスコンロの出現によって消滅し、それに伴って、イロリの上に櫓(やぐら)をかけて炬燵にしていたが、それは電気炬燵にとって変わった。
二)食事をする段になると、ナカイでは箱膳を出してそれに盛り付けていたものが、丸い折たたみみ式の座る机である飯台(はんだい)に代わり、ついには、テーブルに椅子の食堂となった。
三)照明は電力の向上によって行灯・カンテラ・ランプから電灯・蛍光灯に変わった。
四)暖房の面では炬燵・火鉢から電気炬燵・ストーブへ。寝る時の暖房は猫炬燵・湯タンポ・アンカから部屋暖房をする石油・ガスストーブ、電気ストーブへ、電気コタツ・電気毛布へと変わりつつある。
五)夏の過ごし方も変わった。団扇で扇ぐ事だけが涼しいとされていたが、扇風機が普及して機械的風を起こしはじめ、夜は蚊帳を吊って過ごし、蚊取り線香をたいたのが網戸へと変わり、今ではクーラーによって部屋自体を涼しく方法に移行している段階に入っている。部屋の洋間化は寝室にも及び、布団からベッドとなる。
六)情報機器としては、ラジオ・テレビがまるで家庭の劇場であるかの如く垂幕付きで、居間に鎮座していたのが、今では極端な場合には各部屋に設置される様な状況になった。
七)電話も家庭に一台であったのが、ホームテレフォンとして、各部屋に分割され、ここ四・五年でコードレス・ホーンも普及して野外でも送受信が可能になった。
間取りの変化
一)屋内の作業場でもあり、日常の出入口でもあったニワは作業場は取り払われて玄関となり、中の間にあった儀礼用の玄関は消滅する事になった。つまり屋内の作業と儀礼(結婚式・葬式など)が必要とされなくなったとみるべきであろう。結婚式は代わりに旅館・ホテルで行われ、アパートなどでは葬式は親元で執行されるケースをみると、いづれにせよ自宅での儀礼・宴会は少なくなり、外に施設を求める風潮に移り変わってきた。
二)今までは専用にされていなかった子供部屋が、必要とされるようにもなってきた。
建物構造の変化
一)旧来の民家は大黒柱を中心としたほとんどが平屋であったが、数寄屋造りを基本とした、二階立てになり、洋風建築も増えている。
二)建築の基礎は軒下にジロイシと呼ばれる硬い土台の石を置き、その上に床を支える柱が縦に木で建てられている開放型から、コンクリートで固められた密閉型に代わる。
三)窓の少ない家から、ガラスを多用した窓に変わってサッシと呼ばれる建具が大勢を占めることになる。
四)障子や襖からサッシやドアに代わることは、部屋自体を密閉し、いよいよ暖冷房に適したものになった。しかし、暖と冷が均等になったわけではない。現在の建物は暖に適してはいるが、冷には向きが悪くなっている。外光を室内にふんだんに取り入れた結果、室内の温度が上がり、また壁の土からボードになることによって外気の遮断率が少なくなる。また土のボード化は屋根の工法にも適用されるとなると、室内の温度はいよいよ高くならざるを得なくなってしまったのである。この効果は一階よりも二階に顕著に現れて来た。
五)住宅の少なくとも一室は洋室があり、台所・便所などは今や和風をみることの方が稀である。
六)風呂は別棟で外にあったものが、内風呂に変わり、五衛門風呂からユニット風呂へと変化して、燃料も薪からボイラーに移る趨勢にある。
七)便所も風呂と同じく外から内にかわり、以前には肥料として使用されたものが、現在では汲取によって処理されると、呼び名も金肥(きんぴ)から屎尿へと変わった。
八)ナカイは台所もしくはキッチンと呼ばれるようになると、クドではなく電気釜・ガス釜を使用し薪は不要になる。薪が不要になると、今までは煙を逃すための煙突も不要になり部屋には天井が張られるようになる。
九)主要燃料が薪や木炭から電気・石油・ガスになると、当然の如く木小屋は消滅していかざるを得なくなった。
一〇)ナカエの屋根にあった空窓(そらまど)は無くなって、天井が張られる事になる。
十一)食器などを収納する戸棚は、水屋などに変わり今では見る事が少なくなった。
変化はすべて、期を一にして行われた訳ではなく、長期間に渡るものであり、現在の住居がすべて、この様に変化している訳でもないが、少なくともこの様な傾向に流れているという指標として記述した。
以上の変化は、生活の都市化・文明化だけでなく、家業や家族構成の変化の結果とも言えよう。家業は半農半漁の自給自足生活からサラリーマンを中心とする貨幣生活への変化であり、生活の場と職場の分離でもあり、家族構成は、四世代、三世代の大家族から二世代もしくは一世代の核家族化にいたる。出稼ぎと核家族の関係も相俟って独居所帯・老人ホームへの居住が増大している。現代は、ほとんどの住宅が改築・新築されており、昭和三〇年代以前の民家は廃屋に、その名残があるに過ぎない。
参考文献
「文政九年隠岐国美田村火災と流人の住居空間」
共同の井戸
井戸というのは地面を掘って揚水する設備をいうのではなく、流れや川の水をせき止めた水使いの場のことを指している。 その内、水を集めたり地面を掘り広げる方法が考えられるようになり、井戸が掘られるようになった。わが国では六・七世紀頃大陸から技術が入ったといわれるが、初めは四角い浅井戸であった。技術の発達と共に掘削が少なくてすむ円形に変わり、やがて深井戸も掘ることが出来るようになった。江戸時代後期には三〇メートル以上の掘削に成功したといわれている。近代になってからは機械掘が行われるようになり何百メートル下の地下水も汲み上げることが可能になり現在に至っている。
ところで島前では井戸のことを「カワ」という。こうした呼び方をするのは流れの少ない地方に多いらしいが、たしかに島前には常時水を湛えて流れる川というのは少ない。生活用水のある場所が「カワ」となり、その「カワ」は各集落毎に掘られ、共同井戸として利用された。島前の古井戸については『隠岐の文化財』に詳しく紹介されているので、ここでは西ノ島内の部分のみを引用する。上がわ・地下がわ(物井)
飯田小路がわ・尾ノ代がわ・川崎がわ・千福寺がわ(別府)
犬屋がわ・上小路がわ(美田尻)
水壽(大山)
龍沢寺がわ・あちだんがわ・そうのがわ(大津)
抜井がわ(小向)
清水がわ(船越)
専念寺がわ・中がわ(浦郷)
清水がわ(赤ノ江)
隠居がわ・学校井戸(昭和六年発掘)(珍崎)
右記の一九カ所が現在報告されている西ノ島古井戸である。
島民はだいたい共同の井戸を利用して生活していたが、そのうち個人の家庭でも井戸が掘られるようになった。しかし、どこでも良質、豊富な水が出るとは限らない。その点、昔からあるカワというのは水質、水量とも優れていたようである。
昭和三十年代になって簡易水道が普及するようになると、共同井戸の利用は少なくなり家庭用井戸はすたれていったが、生活文化向上とともに水の使用料が増加すると水道用の水源は枯渇していった。そこで再び家庭・共同のカワが利用されるようになった。ボーリングがもっとも盛んに行われたのは昭和四十年代。島中が水不足に悩み、町でも家庭でも生活用水の確保に奔走した。
昭和五十年代、美田、大山のダムが建設されてから水資源も安定し、井戸の利用は少なくなったが、それでも旱魃等でダムの水源があやしくなると井戸が復活する。美田尻の上小路のカワなどは、かつて酒の醸造に使われた名水。いかなる旱魃にも枯れることなく今でも集落の貴重な共同井戸として活用されている。
釣瓶のある風景
「朝顔に釣瓶取られて貰い水」
井戸といえば釣瓶のある光景が思い出される。昔は手桶に縄、竿などを縛りつけ井戸水を汲んだ。深い井戸には滑車もつけられていた。バケツが普及するようになってから、ブリキ製の釣瓶が一般的なものとなり、次に手押しポンプがつけられるようになった。動力ポンプが家庭で普及するのはボーリングが盛んになった昭和四十年代である。最近では釣瓶も手押しポンプも見かけなくなった。
井戸端会議といわれように昔の井戸は主婦達の溜まり場。たしかにコミュニケーションの場ではあったろうが、それは都市の長屋の光景である。農家の主婦が油を売っている時間はなかったようである。また水汲みはもっぱら子ども達の仕事でもあった。飲用水は一日でハンド(台所の水瓶)一杯。おおよそタゴ(水汲み用の桶)四・五杯で一杯になった。
井戸の信仰
水は貴重なものであるし、それだけに井戸は大切にした。正月が来るとカワには注連飾りをつけ、元日の朝暗いうちに若水を汲みにでかけた。水を汲むときには米を持参、井戸の淵に置かれた三方に備えて拝礼、井戸の神様に感謝をささげながら汲んだ。若水汲みは全国どこでも行われている一般的な正月行事ではあるが、最近ではその若水汲みも少なくなってきた。しかし、井戸を埋めなければならなくなった時などに、米や塩を捧げたりする処をみると、頭の中から記憶が完全に消え去ったというわけでもなさそうである。
『隠岐の文化財』
『国民百科事典』
『隠岐島の民俗』
薪と同様に木炭も、日常生活には欠かせない燃料であった。
正倉院に伝わる火鉢の中には当時の木炭が残されているといわれるが、このように相当古くから用いられていたようである。
木炭は薪と違って煙が出たり炎が上ったりすることがない。火力が強く火持ちがよいことが重宝がられ薪と並ぶ燃料として定着した。
木炭に用いられる木は、クヌギ、ナラ、カシ、ブナ等のクロキであるが、松炭も焼かれた。西ノ島では資源の豊富な焼火山を中心とし、旧美田村一体の集落で生産が行なわれている。戦前の状況は不明であるが昭和三十一年の資料によると、窯数四十三のうち、半数は大山地区に集まっている。
そのようにこの地区では木炭製造を専業としている者が多かった。
島で生産された木炭は島内需要だけでなく島外にも移出された。移出物としては海産物に次いで重要な地位を占めたといわれ、鳥取、京都、大阪、富山方面にまで移出されている。当時、木炭流通に関わった人の話によると
「昭和三十年ごろは、米子から要請が有って炭の移出をしました。炭の質は大山、波止の炭が良かったようです。というのも、材質の優れたカシ、ツバキの炭が多かったからでしょう。ツバキ等は五十俵のうち五俵もないほど貴重な物でした。(浦郷、池田 談)」
このように、需要、生産ともに盛んであった木炭も昭和三十五年頃から次第に減少していった。七輪はガス、電気コンロに、火鉢はストーブにかわり、木炭の需要は掘りごたつくらい。それも昭和四十年代になると電気こたつが普及し、一般家庭で木炭を使うことはほとんどなくなった。
木炭生産の移り変りは別記のとおり。現在は鍛冶などの工業用のほか、調理などの燃料として使用されるのみとなっている。
炭火の時代
七輪にたきつけ(紙、木片)を入れて消し炭を乗せて火を付ける。消し炭に火がつくと木炭を乗せ火が起きるのを待つ。その間数分、火が起きるのを見計らってれヤカンを乗せる。炭火の時代はお茶を一杯沸かすのにもそれだけの手間がかかった。当時はそれが普通であり別に不便とも何とも思わなかったが、ガスコンロが登場すると、七輪の不便を痛感するようになった。
また暖房も同様である。火鉢では火力は限られるし薪は煙たくて汚い。ストーブが普及しはじめると囲炉裏、火鉢は姿を消した。
七輪、火鉢、囲炉裏は過去のものとなり現在一般の家庭ではほとんど見かけなくなっている。千年以上続いた炭火文化も利便性を求める近代生活にはついていけなかったようであるが、しかし根強い人気があるのは事実、ことに調理の面では炭火ならではのものがある。昔はよく囲炉裏の炭火の上にアブッコ(足のついた金網)を架け、魚を焼いて食べたものであるがその味覚は格段に優れていた。魚に限らず肉、餅、焼きおにぎりなど炭火にかなうものがないという。現在でも旅館、料理店はもちろん、一般家庭の野外パーティなどで利用されている。
参考
風俗辞典(東京堂)
西ノ島町勢要覧(昭和三十三年)
隠岐の産業
島根県統計書
平成六年現在、西ノ島町の山々は紅葉と見紛うほどに松が赤く染まり、また部分的には赤い松葉も落葉して幹だけが目立つ寂しい景観である。かつては隠岐汽船からだんだんと島に近づくにつれて、薄紫から濃い緑に代わり最後には黒松や杉の色が島の色と思うほどに緑の島であった。
だが、その景観さえも大正時代以降のものであり、それ以前には、現在山林であった場所は牧畑であった。牧畑の島は、夏ともなれば麦で黄色に染っていた。明治二十五年に隠岐島を訪れた小泉八雲は牧畑こそ言及してはいないが、船からみた知夫里の光景をこう述べている。「山裾の白ちゃけた裸岩から、山は傾斜をなしてのぼり、その上は低い草や木の生えた寂しい荒地になっている・・中略・・十軒ばかりの人家が互いに軒を重ねながら、山の窪地をはいのぼっているのが見え、その上には、荒地のまんなかを耕した段々畑が少しばかりある。それだけである。・・後略」
一般に隠岐島の植林といえば布施村であり、そこでは享保四年(一七一九)に藤野孫一が杉の植林を始め、以後、隠岐の杉といえば布施とまでいわれるようになった。しかし、西ノ島でも、それより八〇年以前寛永一八年(一六四一)には焼火山で杉の植林を始め、安永六年(一七七七)には一〇万本の杉を植えたと記されている(焼火山近世年表)。元々、島の材木が重宝されたのは、北前船の風待港として利用された事に起因する。本土で鉄道や車道が完備されるまでは、船が大量輸送の中心であり、即ち陸地輸送よりも低コストで運搬できたのである。
当時、一般的に植林が当時そんなに普及したとも思えないが、島前の入会地のある焼火山という特殊な場所では木材利用を意識しての事業は行なわれていた。具体的には、労働力は雑木を地下(里)人に与え、その代わりに植付けの手間を出してもらうことなどを指示している。雑木が燃料源であった時代、また雑木のあった場所だからこそ可能な事業であったかも知れない。
明治一〇年の地租改正は、旧来の物税から金税に変わり、それと共にスライド方式の税金から固定方式の税金へとも変った。隠岐ではその折りに現金を産み出さない牧畑から地目変更を行なって森林にした形跡がある。これは商品としての木材を、より意識させることにもなる。
西ノ島では基本的に土地は牧畑として利用されていた。『隠岐牧畑の歴史的研究』の資料によると、西ノ島の場合には大正から昭和初期にかけて、牧畑内の畑地の割合は減少の一途をたどり、それに反比例して牧畑内の林地の割合は三七~七六%と逆に増大している。黒木村は昭和二四年段階で既に牧畑内での耕作面積は二%に過ぎなかった。牧畑の消滅と共に山林開発もあり、次第に植林地や牧場へと変っていった。
黒木村議会決議書を見ると、大正一〇年には村有林を中心にして、村民に労働供出させて植林を行なったり、下刈りをさせているのがわかる。それも後には労働の代わりに金納になったようである(黒木村議会決議書)。さらに下がって、昭和一〇年の黒木村と浦郷村の経済更正計画の林業欄をみると、黒木村は七,〇四九円、浦郷村は二,三二二円。さらに昭和一五年には黒木村二六,五二〇円、浦郷村は一,〇〇〇円となっている。これは各村の地形もさることながら、各行政の政策方針の相違でもある。
経済更正計画の比較(くろぎ・由良から)
この傾向は西ノ島町に合併されるまで続き、現在にも至っている。
昭和三五年(一九六〇)新町建設計画基礎調査書(分析編)P一九〇
人工的に植えられた黒松などは、現在一〇〇年以上の物は少なく、植林が一般的に普及したのは大正以降、しかも黒木村を中心に流行したと見た方が妥当かと思われる。だが、それが全て植林したものでも無く、牧畑を放置した結果、自然と黒松が育成した場合も多かったであろう。町内には昭和二〇年半ばには苗木を売る所も出て来ているくらいである。
特に戦後は乱伐の時代でもあった。昭和二五~二九年には用材の高騰により、荒っぽく言えば、木なら何でもよいというような時代であった。戦後の建築ブーム(敗戦のために家の需要が大きくなり)と、パルプや杭木のために、特に松が重宝された。パルプには建築材のように木材の形態・色などは問題ではなく、容量だけが重宝がられた。杭木はある程度細いものが要求された。それに対して、杉は建築材木としてのみ利用され、また植生区域が限定されるので、松ほど一般的には普及しなかったと思われる。
しかし、本土の鉄道と車道の整備により、隠岐の材木は徐々に価値が低くなって昭和四〇年代には植林事業も衰退していった。
町の「松喰い虫対策」は昭和五九年くらいから開始され、被害を受けた松の伐採、消毒の空中散布など懸命に対応したが、成果は芳しくない。これは西ノ島町特有の現象ではなく、「松喰い虫」の被害に遭った地域はいづれも同じ運命を辿っている様にみえる。
昔、どこの家庭でも木小屋があって、薪が堆く積まれていた。
日常の炊飯、あるいは暖房、あるいは風呂に薪は欠かせない。
「むかし、むかしお爺さんは山に柴かりに・・」桃太郎の昔話ではないが 農作業の合間にはよく樵(薪取り)に出掛けたものである。
薪にはクロキと呼ばれる広葉樹のほか、松、杉などの枯れ枝が用いられた。
昔は、島のほとんどが牧畑である。島民の燃料は焼火山一体で確保していた が牧畑の山林化が進むようになると、近くの持ち山やジゲ山(共有林)に出掛 けて取るようになった。持ち山も共有林もない者は購入しなければならなかっ たが、枯れ枝、杉の葉、松葉などは持ち主の許可をもらって、取っていたよう である。
また、山林伐採が行なわれたときは、先を競って枝葉を貰いに出掛けた。現 在、古い農家を見かけなくなったが、昔は大きな竃と囲炉裏が何処の家庭にも あった。いわゆる薪オンリーの生活である。薪は台所の竃には杉、松の枝な ど、囲炉裏には火持ちの良いクロキが用いられたが、一斉に焚くと部屋中は煙 だららけになる。梁や柱は真っ黒け、風の強いときなど屋根裏に貯まった煤が よく落ちたものであった。
薪は山で乾燥させてから自宅に持って帰るが、道路のないところがほとんど である。木負いといって背中に背負って搬出した。木負いの用具はニカ(物を 背負うときの縄)とセナアテ(藁等でつくったクッション)、カルイ(背負い の専用用具)が用いられた。
戦前の小学校には、勤倹、勉学の鑑として二宮金次郎少年の銅像が立てられ ていたが、薪を背負って本を読んでいる。木負いの仕事は大体女性か子どもが 分担していたようであるが、結構きつい労働で木負いをしながら本を読むなど 考えられなかった。山で樵っておいた薪は雪の積もらないうちに搬出して正月 を迎えたようである。
昔の人は木小屋に木がなくなることをもっとも嫌ったという。食糧と同様に 燃料を常時確保しておくことは、農家にとっての常識であった。
戦後、竃の改良によって小量の薪で炊飯出来るようになり、また囲炉裏で木 を焚くことも少なくなり、薪も製材等の端切れが用いられるようになった。
昭和三十年になると石油コンロが登場、燃料の主力はプロパンガスへと変わ り、薪は風呂焚きくらいにしか用いられなくなったが、近年は石油ボイラーの 普及によって、薪の需要はますます少なくなりつつある。
薪を輸出
江戸時代西ノ島では焼火山周辺が薪の産地で、島前各村の燃料が賄われてい た。松江藩では「御用薪」調達場所として焼火山を指定、美田村でも薪確保を ジゲで請負って松江藩に薪を移出している。また石見銀山でも隠岐の薪を欲し がっていたといわれるからかなり人気があったようだ。
寛文年間(一六七〇)まで、隠岐の移出物の大半は材木、薪によって占めら れていたといわれるが、北前船が寄港するようになると、境、松江はもちろん 遠くは長崎、若狭方面にまで移出されるようになった。移出が過ぎたのか幕末 にはとうとう少なくなって、貴重なものになってしまったといわれている。
海に囲まれた島では搬出が手軽で船による大量輸送が可能である。そんなと ころから島の特産物として、移出が促進されたのかも知れない。
新しいメディアとしてのラジオは、大正十四年に東京で始まったが、島根県では「島根県に放送電波が行きわたるようになったのは、昭和七年三月、全国で一七番目の日本放送協会松江放送局が開設されてからであるが、開局当初のラジオ聴取者数はわずか一四三六人に過ぎなかった。」「山陰放送(昭和二九年七月ラジオ放送開始)からの放送も島根県をエリアとしていきわたっている。」と島根県大百科事典には記述されている。以下はラジオ契約者推移(島根県)を示したものである。
一方、西ノ島では、「ラジオ購入は、昭和二年に浦郷では三沢屋(沢野光一)宅に始まり昭和七年現在は、三沢屋・徳中・警察・中原・学校の五軒」(由良より)
因みに「たちあがる隠岐」から当時の隠岐島のラジオ普及状況を拾ってみると、
ラジオ普及率
昭和二四年九・二%
昭和二五年一二・一%
昭和二九年二五%
昭和三一年三二%(全国平均六八%)
昭和三二年NHKはFM放送開始
昭和三三年(全国平均八二パーセント)これを境に下降する
昭和三一年六月調査 黒木村は八七五戸中二八八戸=三三パーセント
浦郷町は七三二戸中二二三戸=三十パーセント
となり、全国平均の約半分くらいの普及率であった事が理解できる。
しかし、この普及率は当時の電気状況を考慮に入れると、一概に全国平均と比較することは出来ない。と、いうのは昭和三一年当時の西ノ島町(黒木村と浦郷村)は中の島と一緒で百四十キロくらいしか配給されてなく、一日に四時間(午後七時から十一時まで)程しか送電されてなかった。そういう状況でラジオの普及率が三十パーセント以上というのは家電製品としてはずばぬけている、というより、それ以外の電気製品は使用出来なかったという方が正確な言い方かも知れない。もし、それ以上の家電製品を使用すれば、家のヒューズか電柱のヒューズがが飛び、近所一帯が停電にみまわれ、ついには電力会社が調査に来て違反(これを盗電と呼んでいた)がばれてしまうことになる。
当時の西ノ島町の家庭の電力状況から見て、(各家に20Wの電球一つという制限)ラジオが十分に使用できるという様なものでは無かったが、ラジオの電圧を上げる為に内部のコイルを巻き直したり、補助電力としてバッテリーを利用するという様な事もあったらしい。
西ノ島ラジオ普及状況(昭和32年10月1日現在)西ノ島町勢要覧/「新町建設計画」昭和35年
西ノ島町全体ではこの間に57%から七五%に普及率が上がっており、この年をピークとしてラジオは全国的に数値としては下降してゆくようになる。しかし、それは後に見るようにラジオが少なくなっていった事を物語るのではなく、一家に一台の時代から個人に一台の時代に入っていった。後でみるように、これと連動した動きはテレビに現れている。昭和三四年のNHK松江放送局のテレビ放送開始によって、ラジオ放送の人気は急激に下降線を辿り、ついに昭和四三年には受信料廃止が決定された。
そんな状況で聴いていた番組は、次の様なものであった。
日本でテレビ放送が開始されたのは昭和二八年(一九五三)、日本放送協会(NHK)と民間では日本テレビ放送(NTV)であった。東京地区という限られた場所での開局であったが、新しいメディアの登場として話題を呼んだ。NHK開局時(二月一日)の受像器は、わずかに八六六台、NTV開局時(八月二八日)には約三五〇〇台であった。だが、その人気は各所に設置された街頭テレビのおかげで大群衆が押し寄せたほど鰻登りとなった。日本テレビは関東一円の駅前広場などに二二〇台の街頭テレビを設置して、広告効果をあげるとともに受信機の普及促進をはかった。スタート時の放送時間はNHKが四時間、日本テレビが六時間であったといわれる。
広告収入によって運営される民間テレビ局は、とても採算が合わないと世間では見られていた。開局当時のテレビ台数では誰もそうとしか思えなかったのは当然といえよう。当時のテレビ受像器は二十三万円、中堅サラリーマンの一年分の給料でもとても購入でき無かった。しかし、開局七カ月で早くも黒字経営に転じたのには驚いた。時代は既に熟していたようである。
テレビ放送スタート当初の番組表は、スポーツや演劇の中継番組が大きな比重を占めた。特にスポーツ中継は人気が高く、NHKを例に取れば昭和二十八年度における合計二七七件の中継番組のうち一四四件をスポーツ番組が占め、その中心は大相撲(六十二件)と野球中継(四十六件)だった。民放はスポーツ中継にプロボクシングとプロレスを加えて、世はスポーツ時代を感じさせるまでに到った。
昭和三十二年(一九五七)田中角栄郵政大臣は民放テレビ三十四社に予備免許を与えた。これを期に各地方では一気にテレビ局が増大することになる。昭和三十四年十二月には民放テレビは三八社、受信契約数三四六万に達し、広告収入はテレビはこの年にラジオを上回る。それによって徐々に民放各社はラジオ局名からテレビ局名へと社名変更が相次いだ。
昭和三十四年(一九五九)には松江にもNHK松江放送局(十月二十八日)でテレビ放送が可能になり、同じ年に一斉に民間放送局(山陰放送(BSS)(十二月十五日)・日本海テレビ(三月十一日)(NKT))も開局された。この松江放送局でのテレビ放送を期に、西ノ島町ではテレビが普及した。その当時の状況を浦郷の間瀬氏に聞くと「私が電器屋を開業したのは、昭和三四年四月十日の現天皇御成婚日と記憶している。その時は、今の前田屋あたりの街頭で御成婚式典の中継をテレビで放映した。それを広告の目玉として間瀬電器の貼紙をした覚えがある。それまでは、浦郷に二軒テレビがあり、岡山放送の電波を受けていた。場所によっては、十円の視聴料金をとっている所もあった。開店当時にテレビをつけたのは、先ず散髪屋で、それから急激に普及していった。当時はテレビ受像機がなかなか入荷しにくく常に品物が少なかった。昭和三五年の浦郷のテレビ設置者は、升谷・調府・田中(別府)・渡・真野(なかばら)・朝山・竹中・熊沢・岡田(満月)・岸本・寺下・一畑バス事務所・山本医院(美田)・日高(保健所)・山木鉄工所・家中である。」
当時のテレビは、色はモノクロ、ブラウン管の角は丸くなっていて、画面は使わない時には小さい緞帳の様な幕がかけてあり、画面を大きく見せる為の拡大鏡の様なフィルターなどがオプションで付設されてあった。電波は本土から直接受信していたので、少し天候が悪いと画面が雪が降るようにチラつき、五メートル以上も離れないと絵を結ばないような電波状況の時もあった。
映画の放映も少なく、大人も子供も「テレビ・テレビ」とテレビのある場所や家に群がり、大げさに云えば私設映画館の様相を呈していた。そんな中で変わったケースでは、波止区が個人に先駆けて、分校にテレビを購入したという事もあった。
昭和三十五年(一九六〇)テレビのカラー放送が東京と大阪で開始され、日本は世界で第二番目のカラー放送国となる。当時の受像器は一七インチ型で四十二万円、二一インチ型で五十二万円。大卒の初任給が一万五千円の時代でもあったので、とても庶民には手の出せる受像器ではなかった。しかし、昭和三十六年(一九六一)にはモノクロテレビ受像器が一千万台を突破までに至った。
西ノ島町では昭和四十年に焼火山頂にNHKのテレビ中継所が完成してから電波状況も良好になり、後には民放三局(日本海放送・山陰放送・山陰中央テレビ)も中継所を設置することになる。
昭和四十四年(一九六九)テレビ受像器は二一八八万台、家庭への普及率は九〇%を突破し、島根県では山陰中央テレビ(TSK)も開局された。
昭和四十六年(一九七一)NHKと日本テレビが全番組をカラー化し、カラー受信契約数一千万突破。モノクロテレビからカラーテレビへの移行は目覚ましいものであった。
昭和四十七年(一九七二)島根県・鳥取県の両県は全国でも有数の過疎地帯で、経営的に一県複数民放局の開設が無理なための特例措置として、両県の民放が、互いに中継局を設けて相互に放送できる体制をスタートさせた。島根県は島根放送(現山陰中央テレビ)、鳥取県は日本海テレビと山陰放送であった。
平成元年(一九八九)衛星放送が本格化。衛星にアンテナを向けさえすれば、全国どこからでも映像送信ができ、従来五・六段階の中継地点が必要だった山岳地帯や離島といった場所からの中継も可能になった。この時、テレビ史上初めてNHKがCMを流した。
現在は民放三局とNHK総合、教育、衛星放送などチャンネルの半分は埋まるまでに至った。
『現代用語の基礎知識』一九九四年版別冊付録
島に文化の灯が点る
わが国で最初に電灯がともったのは明治十一年(一八七八)といわれる。その五年後の明治一六年に東京電灯会社が設立され電気の供給事業が開始され全国に普及していった。島根県では明治二七年(一八九四)松江電灯、隠岐では明治四四年九月(一九一一)に隠岐電灯(西郷)が開業している。
島前で電気事業をはじめようと動き出したのは大正の半ばごろ。別府の安藤猪太郎氏の発案によって、黒木村長中西松次郎・浦郷村長今崎半太郎・美田は竹田才吉・安達和太郎各氏の協力を得て大正九年二月島前電気株式会社を設立した。美田尻に火力発電所を建設、大正一〇年五月頃から送電を行ったといわれるが、実際に事業が開始されたのは大正十一年十二月であった。しかし全島に電灯がともるまでは時を要し、三度は昭和四年、珍崎は昭和五年五月になってようやく送電されている。電灯がついたといっても発電能力は二十キロである。だいたい十燭光くらいの電灯が各家庭に一灯、夕方から十一時頃までしか送電されずランプやカンテラに依存しなければならなかったが、島民にとっては近代生活を体験する文明の灯であった。
昭和十八年、島前電気は中国配電(のちに中国電力)に統合、発電所はそのまま中国配電黒木発電所として送電事業をが行われることになった。しかし、電力施設が増強されるのは戦後になってからである。
黒木発電所は昭和二十四年に八十キロ、昭和二十六年には百二十キロに増設し、一家に一灯、一ラジオの時代が到来する。しかしまだ夜間だけの送電。時折停電するなど不便な状況は続いた。
待望の昼夜二十四時間送電が開始されるのは昭和三十二年七月。一般家庭では定額電灯制度で電力使用が制限されてはいたが、早朝からラジオが聴けるようになったことは喜びであった。この年は西ノ島町が発足した年であったが、新町発足にふさわしい明るい話題であった。
各家庭に使用料メーターが設置され、自由に使われるようになったのは昭和三十九年からである。ようやく本土並になり、これを契機に家電製品急速に普及していった。黒木発電所の現在の出力は七千キロワット。昭和五十八年には島前島後間、昭和六十三年には海士・知夫間も海底ケーブルで結ばれ、隠岐島全体を結ぶ送電網が整備されている。
情報通信の手段として方法としては、現在は書簡・狼煙・郵便・電信・電報・電話・ラジオ・テレビ・ファックス・パソコン通信などがあるが、その中で現在消えてしまったメディアは狼煙だけであろう。特に急場の通信手段としては明治の電信を待たねばならなかった。しかし、天平の昔に緊急手段として、隠岐と出雲間において狼煙を使用した形跡がある。『新修島根県史・通史篇』から、関係項目を拾いだしてみると
天平六年(七三四) 隠岐国と出雲国の間に烽火を使用して通信せよ(出雲国計会 帳)
天平六年(七三四)
烽火の期日を決めて、試しに烽火を実験せよ(出雲国計会帳)
寛平六年(八九四)
延暦年間に内外が無事だったので停止されていた、烽火を再び復活する事を要請して、認可される。(類聚三代格)
以上の記事がみえる。
いつから始まったかは、定かではないが、少なくとも、今から一二〇〇年前には隠岐と出雲の間で、烽火(ノロシ・トブヒともいう)が用いられていたらしい。通常の伝達は、行政の書簡で済ませていたが、賊が国境を侵す様な緊急の場合は賊の数によって烽数を変えて通報していたらしい。昼は煙を上げ、夜は火を燃やすような施設であった。
この時代の隠岐での急場とは、新羅・渤海人の侵入、漂着が考えられる。桓武天皇の延暦十一年(七九二)には辺要の地以外の兵士を廃止し、「健児の制」を定めた。その数は、
出雲国
百人
石見国 三十人
隠岐国 三十人
但馬国 五十人
因幡国 五十人
伯耆国
五十人
であって、出雲は山陰では最も多く、山陽の備中五十人や、長門五十人などより多く、百人以上の国は近江・伊勢・美濃や北陸、東国のみであることと合わせて注目される。そこで、出雲風土記では、
暑垣烽(意宇郡)
布自枳美烽(島根郡)
馬見烽(出雲郡)
多夫志烽(出雲郡)
土椋烽(神門郡)
に烽火が設置された事が明記されている。
この緊急事態を日本の流れの中で見てみると
七三四
隠岐国と出雲国の間に烽火を使用して通信せよ(出雲国計会帳)
七三四 烽火の期日を決めて、試しに烽火を実験せよ(出雲国計会帳)
七五九
新羅征討のため、北陸・山陰・山陽・南海諸道に、船五〇〇隻を造らす
七六二 新羅征討のため、伊勢大神宮以下の諸社に奉幣する
七九九
渤海使帰国
八一三 新羅人一一〇人、肥前小値賀島に来着し、島民と戦う
八三五
壱岐島に徭人三三〇人を置き、警護に当たらせる
八六六 山陰道諸国・太宰府に新羅来襲に備えさせる
八六九
新羅海賊、博多津の豊前国貢調船を掠奪する
八九〇 隠岐国、新羅人来着を報告
八九三 新羅の賊、肥前肥後国を襲う
八九四
新羅の賊、対馬を襲う
八九四 延暦年間に内外が無事だったので停止されていた烽火を再び復活する事を要請して認可される。(類聚三代格)
以上のように、八世紀から十世紀にかけて、日本と新羅は二〇〇年にわたって戦闘状態にあり、その脅威が狼煙を復活させたものと思われる。これに前後して隠岐の諸神社が延喜式神明帳に列挙されてくる。現実的な防御法としては軍隊の増員。それに加えて神の加護を目的として西ノ島では、比奈麻治比売神社(宇賀・倉ノ谷)、真気命神社(物井)、海神社(別府)、大山神社(大津・市部)、由良姫神社(浦郷)が列挙されている。
時代は下がって狼煙の記述が見えるのは、巡遣使が隠岐に巡回の折りに、知夫里島から焼火山へ、また焼火山から別府への連絡として狼煙が使用されたという記述がみえる。
(註)
延喜式神名帳(えんぎしきじんみょうちょう)
延喜年間(九〇一~九二二)に編纂され九二七年に完成された法律書(延喜式)。その内全国の神社が列挙されているのが『神名帳』である。ここに列挙されている神社は、全国で三千三百三十二社。少なくとも千年以上前に上記の神社が西ノ島には存在した事が証明できることになる。
現在われわれが電信を使って遠隔地と情報交換するメディアとしては、電話・無線・ファクシミリ・パソコン通信など多種多様にわたっている。その発達目覚ましいものがあるが、これらの機器が島民の日常生活の中でさほど珍いものでなくなったのは、むしろ戦後になってからである。普段の生活に欠くことの出来ない電話でさえも、この島で一般家庭に普及してから三十年にも達してい。テレビの普及以上に急速に普及したようである。ことに隠岐のような離島の場合、島の近代化に大きく貢献したことはいうまでもないが、その発達の過程を振り返ってみると、国、地方を問わず通信システムの充実に力を注いできたことをうかがうことが出来る。
電報
明治政府は情報を重視して郵便制度よりも早く、明治二年(一八六九)に官営で電信事業に着手することを閣議で決定し、官用通信を開始した。「通信」の始まりは電報であった。翌年には東京・横浜間に公衆電報の取扱を開始。明治四年には大北電信会社が長崎・上海間の海底線を完成させ、わが国最初の国際電報を始めた。明治五年、政府は私設電信の禁止を閣議決定し、以後電信は政府専用事業になり、電電公社まで引き継がれることになる。
明治十一年には新橋・横浜間の各停車場で一般電報の取扱をはじめ、十八年には電報料金の国内均一制を実施し一〇字までを一〇銭、市内はその半額、壱岐・対馬は別料金となった。
一方島根県では明治十三年に松江電信分局より米子を経て鳥取まで電信線の架設完了し、鳥取・米子電信分局も開始された。『新修島根県史』年表には「明治十五年に内務省から県当局に山陰新聞発行停止命令が電報で到着した」とあるから、当時本土の行政では電報も珍しいというほどの事もなかったかと思われる。島根の県会では十八年に隠岐国本土間海底電線の国費架設建議を内務卿に提出したが、実現は明治三十一年まで待たねばならなかった。
明治二〇年(一八八七)には郵便局に合わせて電信局にも等級がしかれ、全国に東京・大阪・京都・横浜・長崎・函館・新潟など八局の一等通信局が設けられた。これは明治二六年には一等郵便局と合併し一等郵便通信局と改称されることになる。
明治四〇年(一九〇七)、別府郵便局では電信取扱開始、四三年には美田郵便局もこれに次ぎ、これによって西ノ島での電報は全員が利用できるようになった。昭和に入ると十一年(一九三六)には慶弔電報も開始された。この頃から電話と電報は併用され、電話で電文を伝える形式が普通になったので、文字を間違えない様にアイウエオや数字を音読する書式があった。
電文の音読表(表挿入)
昭和三九年(一九六四)、美田の電報配達業務は浦郷に統合された。
平成二年(一九九〇)、浦郷局の電報配達業務廃止され、民間に委託することになる。
現在、電報のほとんどは慶弔電報であり、日常の情報は電話によって伝えられている。
明治二十三年(一八九〇)政府は「電話交換規則を制定し、電話線と電話機の設置」維持費は逓信省負担、加入者は使用料と電話料金を納付することにして電話事業を創業した。そして東京横浜間に電話交換業務開始した。当時の東京市内の電話機使用料は年額四十円であったという。
明治三十一年、八束郡千酌(ちくみ)村から海士村の太井を経て西郷へ海底電線が敷設された。知夫線は崎村から来居へ、西島線は同じく海士村木戸より黒木村大山の礫(つぶて)へと開通した。
この年は呉鎮守府所属海軍望楼台が西郷に設置されたり、乃木将軍が島内を視察に来たり、隠岐が軍事的に重要な位置を占めることを暗示している。翌々年には浦郷郵便局が松江西郷電信回線に接続局として音響通信が開始される。思い起こせば千年前も、国境に危機が感じられる時に隠岐と出雲の間でノロシが設置された。日露戦争も日本海を舞台として展開されたことといい、通信環境の整備とは決して無関係ではかったようである。
日露戦争が始まった明治三七年(一九〇四)には、全国の電話加入数が三万五千を越えた。三八年、日本海海戦に先だっていち早くバルチック艦隊を発見、哨艦「信濃丸」が無電で報告してたことは有名である。クロギヅタは、この時にバルチック艦隊が紅海を通過した時に付着した胞子が元だというもっともらしい説も生まれた。
大正六年(一九一七)四月一日、西ノ島初の公衆電話が浦郷・別府郵便局同時に、また美田局は三年遅く大正九年に設置され、これによってようやく地元で電話が使用されることになった。
昭和元年(一九二六)わが国初の自動交換式電話を東京の京橋電話局で使用された。この年は青森・函館間の電話開通により本州・北海道間の電話連絡が可能になった年でもある。
昭和九年(一九三四)日本最初の外地通話として東京・台北間に無線電話が開通し、翌年には東京・ロンドン・ベルリン間にも通話は拡張された。
西ノ島で郵便局以外で電話を所有できた年、電話元年は昭和十二年であった。十月十五日、浦郷局では市内公衆電話ができ、当時の加入者数は八人と数えられている。翌年十一月二十四日には別府局にも設置された。
戦後になると電気通信省は廃止され、昭和二十七年八月一日に日本電信電話公社が設立され、翌年にはお馴染みの赤電話が東京に設置された。この年は船舶電話も開始。昭和三十年(一九五五)に入ると電話による天気予報と時報サービスがはじまり、翌三十一年に初めて東京都心から近郊都市にのダイヤル即時通話が開始された。次の年には近鉄の特急に公衆電話設置。
昭和三十四年(一九五九)西ノ島の電話加入者は浦郷局九二・別府局五六合計一四八。翌年には町議において浦郷局に別府局を統合する事を可決し、三十七年に実施された。統合化によって別府と浦郷は同市内となり、旧来、別府一番という言い方から浦郷五百番代に番号が変わり、市外料金を払わなくてもよくなったのである。
当時の料金体系は市内なら基本料金だけでよく、市外のみ基本料金以外に市外料金を支払わなければならなかった。その市外通話も回線数が少ないので二時間三時間待たされることはざらであった。浦郷局では市外線が四本(松江線・西郷線・菱浦線・知夫線)しかなく、順番待ちになるのはいたしかたなかった。そこで急ぐ場合は「急報」「特急」という言い方で順番を優先させてもらい、それだけに通話料金も割高となったのである。
さて、電話局が統合されたといっても、別府局が電話交換業務をやめたわけではない。別府局の電話業務は浦郷局と同じく、昭和四十五年の統合まで浦郷局として引き続けられた。また、局の統合がすぐさま個人に電話を普及したというわけでもなく、また、それを許さない事情があった。浦郷局には交換機が三台あり、一台に対して六十回線使用できたので、全回線を使用したとしても最大限百八十回線である。そこで公共団体・商業・サービス業・通信運輸業・漁業など素早い情報が重視される業種に限って使用権を許可した。
では、個人が電話を使用する場合にはどの様にしたのだろうか。先ず、各郵便局には公衆電話が設置されており、郵便局に近い地区はそれを利用した。郵便局のない地区は「集落電話」と称して各集落で公衆電話を使用したのである。逆に外から電話がかかった場合、区の有線放送で電話呼び出しの放送をしたり、呼びにいったり、その辺の事情は各集落によって多少異なった。この様な公共性のある「集落電話」の基本料金は、役場が納めていた。
現在では民具室でしか見られない電話機は四角いロボットの顔の様な形をしていた。両目玉は呼び鈴、口は送話器、右耳は受話器、左耳は局を呼び出すダイヤル(ダイヤルといっても番号があるわけではなく、ハンドルをグルグルと回すだけのもの)であった。この電話機は三尺四方の小部屋に設置してあり、そこに入って左手で受話器を耳に当て、右手でダイヤルをグルグルと回し、局がでると「浦郷○○番お願いします」(もしくは「役場お願いします」と言っても通用した)とロボットの口に向かって大声で叫ぶ様に話す。厳密な意味でプライベートな会話が守れない様な電話風景は昭和四十年近くまで続いた。
昭和四十年(一九六五)東京都区内と道府県県庁所在地間がダイヤル即時になり、四三年にはプッシュホンとポケットベルが登場した。
昭和四五年(一九七〇)二月一五日、島前の電話局はすべて電電公社海士営業所に統合され、郵便局と電話事業の関係はこれで幕を閉じることとなった。統合と共に電話もダイヤル化され、電話をとりつけたい希望者は自由に取付られた。この年、島前の電話普及台数は一気に千百二十台に増大し、五十二年には三千台を越えてほぼ一〇〇%の普及率となった。
一方、全国的には自動ダイヤル化が、この島とほぼ同時期に行われたわけではなく、完遂されたのは昭和五四年三月一四日であった。
昭和六一年(一九八六)電信電話公社は民営化されNTTとなり、その後、第二電電も登場して、電信産業は一気に開花した。
現在は電話機も軽量化・デザイン化され単純に会話するだけでなく留守番録音、番号短縮、割り込み機能など多機能なものに変化している。また、コードレスホンと呼ばれる短距離無線電話も開発され家から一〇〇メートル以内なら持ち運びさえ可能となった。本格的な携帯電話は、船舶電話・自動車電話など無線でどこへでもかけられるものも登場し、都市部では普及している。
電話回線を使用したメディア
ファクシミリ
昭和四八年(一九七八)電電公社は公衆電話回線を一般に開放することによって、画像を送受信する機器であるファクシミリが最も普及した。電話が耳を通した音通信とするなら、ファクシミリは目を通した画像通信である。一般的には画像というよりも文書などの文字を転送している場合が多い。これは郵送に比べて簡単で安くて、速いという長所がある。しかし、発売当時は機器自体が高価で、とても一般には買えないコストであったが、十年もたつと隠岐島にも入ってくるほど安価な家電製品となった。昭和六二年には隠岐の価格で二十万円だったのが、現在では五・六万でも買えるほどになった。ワープロの普及と連動して事務所には欠かせないオフィス機器である。
キャプテン
文字図形情報ネットワークの商品名で、電話網を利用して情報検索・計算処理・郵便貯金口座の電信振替などのサービスをモニタ(テレビ)に映し出すシステムである。テレビモニタと電話回線をつなぐ同様の機器にファミコン通信というのもあり、それによって手軽に株・競馬などの情報が得られる。
パソコン通信
電話通信網を使用するメディアとしてはパソコン通信(ワープロでも可能)もあげられる。右のキャプテンと異なる処は、両方向通信であること、ここからは松江につながりさえすれば世界につながるのと同様にネットワークに連結されることである。メニューには次の様なものがある。
一、メール交換=情報を手紙の様に送ったり受けたりする機能
二、シグ(フォーラム)=同好の趣味や同種の仕事などの人達が集まって作る、情報交換の掲示板
三、PDS=個人がボランティアで無料や少額で配布するソフト
四、チャット=通信内でリアルタイムに文字会話(筆談)できる機能
五、データベース=知りたい情報を、有料で調べる事が可能な情報ボックス
六、通信販売=パソコン通信での通信販売
七、掲示板=天気予報・観光ガイド・スポーツ情報などの便利掲示板
八、ゲタウェイ=他の通信ネットに接続する機能
右記の様なメニューで、通信メディアとしては非常に汎用性に富むが、ただ、使い勝手が電話やファクシミリほど手軽ではないので、日本のユーザは現在百万人程度。西ノ島では現在七、八人のマニアがこれを使用しているに過ぎない。
参考文献
『日本史分類年表』
『黒木村誌』
『新修島根県史』
『新町建設計画基礎調査』
『隠岐島誌』
『郵便創業一二〇年の歴史』
『離島振興三十年史』
島内各村々に存在していたことは明らかであるが資料として見られるのは近世以降である。江戸時代には島民信仰の場として、また、宗門帳を預かるなど幕藩行政の一端を担っていたが、明治元年の排仏によってほとんどの寺院は打ち壊しに遭い消滅してしまった。明治十年以降になってようやく再興の道を歩むことになったが、その道程は険しかったといわれる。
西ノ島の場合、排仏の影響は比較的少なかったといわれるが、それでも別府、地福寺のように焼棄された寺もある。そのような経緯の中で、足跡の全容を明らかにすることは難しいが現存する資料を基にその概要を述べて見ることにしたい。
『隠州視聴合紀』寛文七年(一六六七)によると、「国中寺院」知夫郡として左の寺院があげられている(所在地は筆者註)
真言
性徳寺
真言 長福寺 (美田)
浄土 専念寺 (浦郷)
真言 足利寺 (別府)
真言 飯田寺 (別府)
真言
香鴨寺
(物井・知当?)
また本文、浦郷の中に城福寺(真言)がある。右の内「性徳寺」は知夫村の中にも見えないし所在地も不明である。当時西ノ島内には七ヶ寺があった。ところが『増補隠州記』貞享五年(一六八八)になると次のとおり
城福寺 真言 浦郷(本郷)
有光寺 真言 浦郷(本郷)
専念寺 浄土 浦郷(本郷)
長福寺 真言 美田(小向)
円蔵寺
真言 美田(市部)
小山寺 真言 美田(大津)
道場寺 真言(時宗か?) 美田(大津)
飯田寺 浄土 別府
千福寺 真言
別府
願成寺 真言 宇賀(物井)
観音寺 浄土
宇賀(宇賀)
(所在地は旧村名( )内は区名)
わずか二十年ほどの間に性徳寺・香鴨寺・足利寺の三ヶ寺はなくなり、七ヶ寺が多くなったことになる。殊に飯田寺には大破と註されており、宗旨も浄土とかわっている。
さて、煩瑣のきらいはあるが現在に最も近い「隠岐古記集 文政六年(一八二三)」によると
城福寺・有光寺・専念寺(以上浦郷)
長福寺・円蔵寺・小山寺・道場寺(以上美田)
飯田寺・千福寺(以上別府)
香鴨寺・願成寺・観音寺(以上宇賀)
となって(内飯田寺・香鴨寺は大破とあり)貞享からすると百五十年を経ているが、ほとんど変わっていない。前記の「隠州記」には記載がないが、この外に大津には龍沢寺・薬師寺。別府には飯田寺に替わって地福寺(浄土)ができており、又、大山には海前寺(現在行者堂という)があった。これらにはいずれも住職(または堂守)がいたものである。又、美田地区の「堂」には、船越堂は万福寺、小向堂は正楽寺、市部堂は成仏寺、波止堂は地福寺と寺名はついているがいづれも堂守がいないので寺とは認めなかったようである。(この寺名も明治以前から付けられていた。波止堂にある「双盤」に天明三年地福寺という銘が入っている。)
以上が西ノ島にあった寺院である。また、その集落に寺院の有無にかかわらず「堂」が必ずあり、各種の仏様が祀られている。波止堂の例を挙げると、本尊は観音菩薩であるが、地蔵尊・弘法大師像・釈迦如来・賓頭廬尊者(俗に撫仏)と色々である。(釈迦ビンズルは元焼火山雲上寺のもの)この堂は普段は老人の憩いの場にしたり、十夜法要にはお寺から住職が出向いてお勤めや説教をしたり、お寺の出張所の役割をする。また葬儀の折にはここで葬列の持ち物を作ったり、区には無くてはならない存在である。
ところが、明治元年に「神仏判然令」が達示された。これは寺院を廃止せよというものではなく、神仏混淆の寺院、神社(焼火権現は、焼火神を祀ると共に本地仏として地蔵・薬師尊等を合わせまつり、ここに奉仕する者を社僧といった)に対して神社、寺院のいずれかに決めよ、というものであるが、これを隠岐では廃仏(排仏)と解して、明治十年以降に再興をみるまで隠岐の寺院は全部消滅したのである。これに関しては、『隠岐寺院史・前編』に詳しいので、ここでは触れないでおく。
長福寺 山号高田山 美田・大津
本尊 大日如来(胎蔵界)(本尊は現在、大日如来となっているが、由緒にいう「千手」も祀られている)
脇士 聖観音菩薩・勢至菩薩
宗派 真言宗東寺派
本寺 教王護国寺(東寺)末
由緒・沿革
(一)人皇三十代欽明天皇御宇壬甲三月、高田山長福寺新造立(略)「寺院明細帳」
(二)往昔行基、当峯ヲ霊場ナリト見テ篭リ給フニ、生身ノ観音示現シテ、是ヨリ北ニ当リ浦アリ。其ニ竜宮ヨリ来リシ嘉樹アリ。之ヲ以テ我カ像ヲ刻ンデ仏閣ヲ建テ安置セヨ(中略)行基彼ノ浦ニ至リ見レバ流木アリ。之ヲ執リテ、千手・十一面ノ二仏ヲ刻ンデ千手ヲ当寺ノ本尊トシ十一面ハ別府飯田寺ニ安置。尚此ノ流木ノ残部ヲ以テ或ル修行者枕トシテ出雲枕木ニ至リケルニ、枕木ノ観音ノ御膝ニ穴アリ、修行者ノ枕ヲ合セタレバ符号セル由
「美田村来歴」を引いて由緒としているが、行基が隠岐に渡った証はなく、また行基建立と伝える寺院は畿内に四九ヶ寺程あるが行基作の仏像は一体もない(最近、奈良大教授井上正氏によって「霊木化現代への道」として行基作仏の研究を発表しておられる)これは古さをいう為のこじつけであろう。
ところが「出雲枕木山縁起書」万治二年(一六五九)に「当山草創ハ智元上人ナリ。初メ美田ノ源太ト号ス。王氏ヨリ遠カラズ。曽テ故有ツテ隠岐国ニ放逐セラレ云々(略)枕木山ニ安置ノ三尊ノ内薬師仏ノ左膝ガ折レテ安定シナイノデ源太ガ童児ノ時カラ老ニ至ルマデ肌身離サズ持ツテイタ枕ヲ当テテオイタ処、コノ枕化シテ膝トナル」(原書は漢文体)それより枕木山と称するようになったとある。前記美田村来歴では「行基」となっているが、美田源太こと、智元上人と関係があるのでないか。時代は明らかでないが、智元上人が長福寺草創と関係があるかも知れない。枕木山は天台宗の寺院(今は禅宗寺院)であったことからすると長福寺も草創時は天台寺院であったかも知れない。
復興
明治二年廃寺となっていたが、明治十二年に再興された。隠岐国で真言宗寺院が一番早く復興をみたのは天野快道(大山産)大野明演(海士宇受賀産)の両師(いづれも真言宗の僧侶)いち早く帰郷、御尽力された事による。そして復興初代の住職は大野師である。
本寺は元小向ヌクイ(高田山麓)に在ったが、寺地も現在の大津の元小山寺のあった処に移転建立した。旧本堂(現在海士、保々見清水寺本堂)は方形造で島前の寺院にはこの様式の寺は一寺もない。詳細は不明であるが、廃寺の折り、こぼして保管していたものを再建したのではなかろうか。旧本堂は合天井で法輪紋が画かれており(十方拝礼の祭笠の絵と同じ)須弥檀等も古いものの様であるので、明治の再建の折り、新築したものとは思われない。現在の本堂は昭和三十一年に新築された。
常福寺 山号大原山 浦郷
本尊 阿弥陀如来
脇士 不動明王・毘沙門天
宗派 真言宗東寺派
本寺 教王護国寺(東寺)末
由緒・沿革
大原山常福寺・真言宗・寺領二斗五升
当寺は人皇五十二代嵯峨天皇御宇、弘法大師、諸国修行の時、当国へ御渡海ありければ、この寺を建て給うとかや。其の後長門守修復を加ふるといふ「隠岐国往古旧記」を引用して由緒としているが、弘法大師渡海の証もなく、古さをいう為のこじつけであろう。ただし、日吉社(旧山王権現)に奉納されている「大般若経巻六百」の奥書に正応二年(一二八九)九月供養了。願主沙弥西蓮
奉込隠岐国美多庄浦方山王御宝前
応永十三年(一四八六)五月 権律師
奉込隠岐国美多庄浦方山王御宝前
栄吽
との資料がある。日吉社の祭礼には同社建立の当初より「庭ノ舞」の奉納と共に「大般若経」の転読が行われており、これはおそらく常福寺住僧の奉仕したものであろう。さすれば正応年中には常福寺のあった事がわかる。「隠州視聴合紀」にも「山の半に城福寺(この時代には常福寺でない)というふあり」とあるように人家より八丁あまり登った勇義山の中腹の眺望のよい地にあった。大体真言宗寺院は古いほど山腹にあるのが多い。
海士の「安国寺」知夫「松養寺」などもその例である。
復興
明治二年に廃寺となっていたが同十二年に再興の許可を受けた。ただし無住で住職は長福寺の大野明演師が兼務していた。
「同歳(十二年)六月許可相成候得共、十二年間有名無実、同二十四年七月中院工事落成、古来の過去簿記も不分明により二十六年の今日を以て新調。
明治二十六年巳年七月中院
真言宗大原山中興開山河村大忍
と寺記にあるので、明治二十年代に西村師が入山されて本格的な復興と教化に努められた。
現在常福寺奥ノ院と称している処に小堂(一間半・二間)があったというからこれは西村師の復興されたものであろう。
次いで、大塚欽龍師が入山、同師の手によって明治三十八年、現在の地に新築をみた。(昭和四十七年現住口村慈光師によって再建築)この大塚師は大正九年に入寂されたが、随分事績を残した人らしく、前長福寺住職照海明龍師(油井姓)の書信に「常福寺住職大塚欽龍上人の如きも、誠に僧侶らしい人であったと人がいいました。彼の浦郷で八十八カ所を設け、それより船越以下七ヶ里人間感じて三十三カ所(註 八十八カ所の間違いか?)の霊場を設け、次いて別府、物井の者ども八十八カ所をこしらへ、海士北分、崎に至るまで設けられる様になりしは、皆欽龍上人一人の力でありました云々」。明治四十四年には授戒を行い、これに要した仏具を備え、八祖大師掛絵、両界曼陀羅なども今に残されている。口村慈光師入山後、常福寺旧寺を奥ノ院と称して段々と整備し、昭和三十五年には西ノ島町役場の旧建物を購入して(五間・六間)一層の整備をみた。また山内に経蔵を設け、旧山王社に奉納された大般若経を収納保存された。この奥ノ院には本尊銅像阿弥陀如来座像(高二〇センチ)・銅像菩薩形座像(三四センチ)の二体の朝鮮仏(李朝時代)も祀られている。沿革とは関係ないが付記しておく。
専念寺 山号平野山 浦郷
本尊 阿弥陀如来
脇士 勢至菩薩・観世音菩薩
宗派 浄土宗
本寺 知恩院 末
由緒・沿革
本寺は往古橋村にありしという。開山狭蓮社善誉上人哲道大和尚、人皇後陽成天皇御宇慶長十一年(一六〇六)の頃という。人皇東山天皇(一六八七ー一七〇九)の御宇浦郷村蛸崎に移転(寺院明細帳)とあるが、「浄土宗大年表」には「正親町天皇天正七年(一五七九)四月、隠岐に専念寺を起立す」とあるように開山の年は天正七年である。「慶長十一年開山哲道上人寂す壽七十八」と同年表にある。
また橋村より移転の年時は東山天皇の御代(一六八六ー一七〇九)とあるが、隠州視聴合紀の浦郷村の項に「里の左岸に臨み松老いて風興ある処専念寺あり」とあるところからすると、哲道上人の最晩年に寺地を移転。寺院も整備したのではないか。(註 本寺往古橋村にとあるが、これは今の波止でなく、今焼却炉の設けられている処に五輪塔群があり地名もネイジ(尼寺か?)というから、あるいは専念寺の寺跡かも知れない)
復興
明治十三年二月隠岐島浄土宗寺院の復興の為に本山よりの命を受けて沖永恵隆師が渡島。次いで醍醐須忍師が十月渡島。この仁は主として島前の浄土宗寺院の復興にあたられたようである。醍醐師は浦郷に留まり本寺の住職となって、先ず仮説教所を設置。村民の協力を得て堂宇を建設。明治二十一年九月に再興の許可を受けた。これについては『浦郷町史』『隠岐寺院史』に詳述されているので略記するに留めた。寺号については平野山一心院と称したこともあるようである。
所讃寺 (山号なし) 別府
本尊 阿弥陀如来
宗派 浄土宗
本寺 知恩院 末
別府には元、飯田寺(浄土宗)の寺院があったが、「隠岐古記集」等に近年大破と記されている。この寺跡に「地福寺」という寺があったが、明治初年に廃寺となった。真言宗長福寺・常福寺等は再興の時に旧寺号に復したが、本寺の場合、どうした訳か再興に当たり、出雲大社の境内地にあったという寺院が住僧の愚により廃寺同様になっていたのを本尊共に移転して再興された。ただしこれは本尊のみをお迎えし、建物は新築したと思われる。檀徒としては寺号などは問題でなく、古くからあった寺院を復興したと思っていたであろう。その後、別府安藤家が主となって寺院も整備されていたが、昭和二十八年に本堂床下よりの出火によって、本尊等すべてが焼却した。そこで早速仮堂を設けて、その年の十夜法要を営み、仏前において再建を誓ったがなかなか再建が進まぬまま十年が過ぎた。もはやこれ以上の引き延ばしも許されぬので檀信徒一致協力して再建を見たのは昭和四十年の十月であった。この時本尊並びに脇士の三尊は京都の仏師松久氏の謹製になるものをお迎えして現在にいたっている。
福万寺 (山号なし) 赤之江
本尊 阿弥陀如来
宗派 浄土真宗本願寺派
本寺 西本願寺 末
由緒・沿革
往古は赤尾山福満寺といって、赤尾山寺床にあった由であるが、元禄七年(一六九四)の赤之江堂との関係は確証を得ない。再興福満寺の棟札は安永四年(一七七五)のものが寺に保存されており、享保元年(一七一六)再建の棟札も荒尾井の堂に残っているが、寺床にあったという福満寺は廃仏前既になくなっていて赤之江の堂に変わっていたようである。同寺は浄土宗の寺院であった。
復興
廃寺後、西本願寺の開教師香川黙識等の布教によって真宗本願寺派の寺院に変わって復活した。それは赤之江の海辺に堂といわれて残っていたが、現在は廃仏前の堂屋敷に寺を新築し、昭和二十二年住職神原師により寺号復活の許可をうけた。
誓願寺 (山号なし) 物井
本尊 阿弥陀如来
宗派 浄土真宗本願寺派
本寺 西本願寺 末
由緒・沿革
「増補隠州記」貞享五年(一六八八)、「隠岐古記集」文政六年(一八二二)のいづれにも「願成寺 真言」とあり、これが明治初年の廃仏までこの地にあった寺であった。これについては詳かにしない。明治十年代になってから島前の寺院も復興することになったが恐らく物井の人々にとっては、この寺の再興のつもりであったろう。
真言宗の寺院の復興に明治十三年に、当時真言宗の僧侶であった天野快道師(大山産)・大野明演師(海士・宇受賀産)がいち早く帰島されて再興につとめられたが、何故か本寺の再興には関わっていない。
幕末まであった島前の寺院は前記の「隠岐古記集」によると知夫村四ヶ寺 西ノ島町十一ヶ寺 海士町二十ヶ寺 計三十五ヶ寺であるが、その中に真言宗寺院は二十三ヶ寺もある。
当然、天野・大野の両氏も知っているはずであるが、この総てが再興したわけでもなく、又再興時に宗派の変わった寺院もできた。
復興
『隠岐寺院史』には「明治十年西本願寺開教師、香川黙識師、管龍貫師の開教によって開山の基礎を得たものと思われるのであって本尊阿弥陀如来は廃仏前海士村菱浦にあった同宗本願寺より迎えたものと言う」とあるが、隠岐には「西本願寺」の寺院は一寺もないが、各宗共競って本山の僧侶が渡島するので西本願寺もこの機をのがさじと渡島したものと思われる。
思うに香川・管の両師は初め島後に渡り、次いで島前に来てまだ再興のなっていない物井の願成寺に目をつけ、ここにあった庫裏の建物に本拠をおいて「出張所」として再興につとめたのでないだろうか(この出張所は本山の直営として名義も大谷光尊上人であった由)。年次を追って物井の信者もその気になって、当時、区の資産家の真野家が転退し、土地家屋の売却の話があったので区の有志等相談の上これを購入した。前記の菱浦の廃寺清楽寺(菱浦には本願寺という寺はないが、本尊は浄土でも真宗でも同じ)の本尊阿弥陀如来を迎えて寺の型をととのえたものであろう。以下「隠岐寺院史」にその後のことも記されているが、手元に資料もないので確認もできず略す。いづれの宗旨であろうがあまりこだわらないのが日本人の仏教に対する考え方が普通であるから、早く再興しないと死者などが出た時など葬儀もできないので、信徒には切実な問題である。物井の寺は願成寺(真言)であったが、復興に関わったのが浄土真宗の僧侶であったので復興時の宗派は浄土真宗となった。戦後法人手続きをして昭和二十九年三月誓願寺の寺号も許可された。願成寺でよいわけだがそれでは宗派と異なるので新たに寺号をつけたものであろう。現寺院は昭和二十九年に新建立した。
地福寺 山号月照山 三度
本尊 阿弥陀如来
宗派 浄土宗
本寺 知恩院 末
由緒・沿革
隠州島前三十三巡礼札所 元禄七年(一六九四)の中に三度村堂とあるが、天保御年貢帳によると廃仏前までは「地福寺」と唱えていたようである。ここには、阿弥陀仏外二体の仏像(未見)も祀られているが、元は七体あるいは十一体あったともいい、平家の残党が持ってきたものという伝えもある。間瀬、万田両家がその後裔とも言われている。
復興
廃仏の時も三度までは、その手が入らなかったらしく、旧のまま存続していた。昭和二十三年四月区民協議の上、時の住職宮本猛雄師によって宗教法人法の手続きをし、寺院としての許可を得た。この時「月照山、地福寺」の寺号も公認された。
福王寺 珍崎
本尊 阿弥陀如来
脇士 観音菩薩
勢至菩薩
宗派 浄土宗(本寺なし)
由緒・沿革
島前三十三カ所巡礼札所(元禄七年(一六九四))の中に「珍崎堂」とあり。またここに保管されている双盤の銘に「享保二十乙卯四月吉日(一七三五)、珍崎村福王寺什物、施主平兵衛」とある事からすると、この時代既に「福王寺」と称していたようである。
このように寺号はあるが、無住のいわゆる堂は美田地区の堂も同じである。寺号があっても「寺」と認められていないのである。ところが明治初年の「廃仏」の時、区の有志によって仏体は隠されて難を逃れていた。明治五年の学制が布かれてから、この建物は学校として使用されていた。明治三十四年にいたり、「宮の前」に新しく学校が建築されたので学校との同居は終わった。
大正五年に堂が新築されたが、年を経て老朽化もはなはだしく、平成元年に再び解体新築され現在に至っている。ただし寺号もありながら寺院としての手続きはしておらず、今もなおなされていない。これは他の区も同じである。以上真野享男氏の調査によって記述した。
参考文献
「隠州視聴合紀」
『隠岐寺院史』
「隠岐国寺院明細書」
「増補隠州記」
「隠岐古記集」
「美田村来歴」
古代より祀られていた神々
いわゆる古墳時代(三〇〇~五〇〇)には、現在の集落がほどんど出来ていたといわれているが、西ノ島の場合でも大体そう考えてよいかろう。神社の原初は社殿はなく、祭をする場所が決まっていて、そこに神をお迎えする仮屋を祭の度毎に設けたのが後に恒常の建物としたのが神社であった。当町の場合、平成二年に発掘した「兵庫遺跡」から祭祀に使われた土器が数多く出土しており、古墳時代に祭りが行われていたという事はわかるが、それに最も近い「大山神社」との関係は明らかでない。
大化の改新後、神事優先を国家的理念として揚げ、律令神祇制度が確立し、「大宝律令」の施行によって全国的規模に拡大する。平安前期に登録された官社の数は「延喜式」によると二八六一社(祭神数三千百三十二座)であるが隠岐では十五社(十六座)があげられている。そのうち西ノ島にある神社 由良比女神社・大山神社・海神社(二座)・真気命神社・比奈麻治姫命神社の五社である。
これらの神社に対しては国よりの幣帛が献られているが、この中で由良比女神社は、官幣の大社で他の神社は国幣の小社となっている。
さて、資料に見える神社は、前記の通りであるが、この時代に西ノ島には神社は五社のみであったとは考えにくい。出雲国の例からすると「出雲国風土記」に神社三百九十九所。内百八十四所(神祇官に在す)二百十五所(神祇官に在さず)とある。少なくとも式内社の倍以上の神社が存していた事からしても、西ノ島の場合も少なくとも十社くらいは存在していたのでないかと思われる。また延喜式には所載されていなくとも古い社はある。「焼火神社」の場合は平安末期の『栄華物語』に「たくひ神」とあり、既に都に知られていたのである。
中世期に祀られていた神社
島後の玉若酢神社に「隠岐国神名帳」という資料がある。これは玉若酢神社の祭礼に総社として隠岐国内の神々を勧請する祝詞の中で申し上げたものであるが、これを一本にまとめて「国内神名帳」として隠岐国の神社百十六社が記されている。この資料成立年代は詳かにしないが、記載内容からして中世期のものと考えられる。その中に西ノ島には
千波郡 十神
従一位 天佐自彦大明神(知夫村ニアリ)
○従三位上 海原明神
○従三位上 真気明神
従四位上 安宕彦明神(知夫村ニアリ)
従四位上 国彦明神
○従三位 柴木彦明神(美田村小向ニアリ)
従四位上 奈取彦明神
従四位上 云海彦明神(知夫村ニアリ)
従四位上 都玉貴明神
○従四位上 和太酒明神(知夫村ニアリ)
美田院 九神(異本には千波郡の中に入れる)
○従一位 比奈麻治姫大明神
○従三位 大山大明神
○従三位上 由良比売大明神
従四位上 呼乗彦明神
○従五位上 伊勢明神
○従四位上 水祖明神
従四位上 熊岐姫明神
従四位上 豊加姫明神
正(従)四位上 奈酒彦明神
( )は筆者註
の十九神があるが、○印のものは現在わかっている神々(消滅したものもある)であるが、○印のないものは詳にしない。
由良比女神社の場合、「延喜式」によると「名神大社」であるがこの神名帳では比奈麻治姫神社の方が「従一位」と筆頭にあげられている。従三位上海原明神は、海神社と推定してみた。従四位上和太酒明神は、知夫村の渡津神社があり、大山の渡利神社のいづれかであると思われる。
この期になると、浦郷の日吉神社(山王権現)美田八幡宮等も資料があり、少なくとも中世期には存在している事は、はっきりしているが、この神名帳には、熊野権現、八幡宮等に神仏習合色のある神社はどういうわけか挙げられていない。
近世期に祀られている神社
この頃になると資料も多くなるが全体が記載されているものでは、「島前村々神名記」(元禄十六年)があるのでこれをあげるが、この時代になって初めて各神社に祀られている神々の御名が明らかになる。
知夫里郡之内
浦之郷村
由良姫大明神
式内案上 須勢利姫尊 隠岐一宮
山王大権現 大山咋命
大原大明神 天兒屋根命(春日同体)
住吉大明神
底筒男・中筒男・表筒男命
石神明神 伊和佐久命・根佐久命
蓬来亀神社 豊玉姫 (神代ニイヅル)
平野少宮
仁徳天皇 大鷦鷯命
乙訓明神 大山咋命 松尾同体
森大明神 天鈿女命
青根明神 青加志伎根命
待場明神
猿田彦大神
比志利権現 事代主命
辧財天神社二所 豊玉姫命
知屋御前
宇祢美大明神
美田院
大山大明神 式内案下 大山祇命
正八幡大神宮 御相伝秘法 應神天皇 誉田皇命
高田大明神
素戔嗚尊・伊弉諾尊 相殿ニ座ス
三保明神 美穂津姫命
弁財天 玉依姫命
荒神所々(波止・市部)
素戔嗚尊 眷属
焼火山大権現宮
手力雄命左陽 天照大日霊貴 離火社神霊是ナリ 萬幡姫命右
陰 三座同殿 伊勢大神宮同体ナリ
末社
辧財天社
豊玉姫命
五郎王子 素戔嗚尊ノ五男王子
御前 事代主命
山神 大山祇命
随神 御門神左右
豊石窓命・奇石窓命
金重郎神 宮アリ
最勝神 同(註大杉ニ座ストモアリ)
荒神 同
道祖神
同
水神
疱瘡守護神 宮アリ
船玉神
別府村
六社大明神 式内案下 海神二座 (志賀三社一座 住吉三社一座)
伊勢内宮太神 日神
山神社
大山祇命(耳浦)
稲荷明神 倉稲魂命
荒神社
黒木社 九十五代後醍醐天皇尊治皇命
宇賀村
須気尾大明神 式内案下 真気命(真鶴雄也)・稲田姫命・大巳貴命 三座
末社
熊野社 伊弉諾尊
愛宕神社
火産霊神
八面荒神社 家伝記 素戔嗚尊眷属
済大明神 式内案下 比奈麻治比女命・活玉依姫命ノ別号
星加美嶋明神 鹿賀瀬雄命
渡須神社 龍神 和多積命
日御前
日神鏡 天照ト不可云
弁才天社 豊玉姫命
天満天神社 菅丞相 菅原朝臣道真
御崎 二社 事代主命・八束水臣津命
以上見られるごとく、村氏神の社も、祠に祀られている神と同列に記載されているが、祭神名が明らかになっている。これは元からの姿でなく、この期に吉田神道が全国の神社の神主に免許証を出したり、又神社調査を行ったりしているので、この時に、当時この社の神主、宮守等が古事記・日本書紀等に出ている神名を付会して付けたものがその大半であると考えられる。
その一例をあげると焼火大権現は「焼火ノ神」でよいのであるが、これは古典にない神名であるので「ヒ」のつく神で神格の高い天照大神の別号である「大日霊貴」に付会してある。又、由良比女神社の場合も延喜式には「由良比女神」「元名和多須神」とあるのにこれも古典にない神名であるので、大国主命の御后である「須勢理姫命」と付会している。
縁起について
中世以降、殊に近世に入ってから「縁起書」が作られる様になる。西ノ島では、「焼火山縁起」「由良大明神縁起」(縁起草案写)と一社でまとまったものと、「美田村神社之縁起集」(正長二年選・寛延四年写)の様に数社をまとめたものもある。これには「××大明神御相伝秘法」とあるがごとく御祭神の解説が主となっているが、その中に古くからの伝承と思われるものも一部含まれている。ここにある社名をあげると
大山大明神、山神一座、高田大明神、八王子大明神、八幡大神宮、美保大明神、地主大権現、木元大明神、渡利神社、焼火山大権現、高崎御社、天神御社、辧財天社
と記載があり、これが当時の美田村の主なる神社(祠)であったようである。
祭を主催する者
祭を主催する者(現代でいう神主)は古くは、その村の長となっている者、又は特に選ばれた者が何日間か心身共に清浄にし、いわゆる潔斎をして祭を主催したものであるが、それが後世には専門職の神主が主催する様になるのである。これは近世の例であるが、「両嶋神社書上帳」(宝暦七年)によると
浦郷村
由良姫大明神
神主真野丹波
森大明神 神主秋月右近
山王権現 宮守助四郎
美田村
焼火大権現 別当雲上寺
高田大明神
神主宇野河内
八幡宮 宮守八郎左衛門
大山大明神 宮守八郎左衛門
別府村
六社大明神 神主宇野石見
伊勢宮
神主宇野石見
宇賀村
杉尾大明神 神主宇野大和
済大明神
宮守十太夫
とある。
元禄度の「神名記」によると約四十社を数えるが、宝暦度の書上帳によると十一社には、現在でいう神主がいて祭祀を行っていた。
ただ江戸期と現在と異なるのは、どんな小さな祠でも少なくとも年に一度の祭を執行している点である。この例は海士町豊田には、氏神社の外に祠が四祠もあるが本社の祭礼の折りは必ず各社で祭祀を行っている。これが古い姿である。
現在の氏神神社と崇敬の社
焼火神社 (旧社格県社)
通称 焼火さん・隠岐の権現さん
交通 波止より車で七分、徒歩一五分。旧参道は波止より徒歩一時間
鎮座地
焼火山中腹
主祭神 大日霊貴尊(焼火大神)
境内社
山神・弁天・船玉・東照宮・五郎王子・金重郎・道祖神・雲上宮(明治までの本地仏である地蔵尊を祀ったもので、昭和三六年創建)
神紋
三ツ火紋
祭日
例大祭七月二三日、二四日・月次祭毎月二四日・歳旦祭一月一日・龍灯祭旧暦大晦日・春詣祭旧暦一月五日から一カ月・端午祭旧暦五月五日
本殿
権現造 木造銅板葺 二坪
幣殿 木造銅板葺 三坪
拝殿 木造銅板葺 一三坪
付属施設 社務所・客殿
境内地
四四七六坪
由緒・沿革
「焼火山」は元「大山」と称し知夫郡美田郷(和名抄)の最高峯で、古くより美田郷の中心地区の先住者によって神奈備山として信仰されていた。(大山神社の項参照)ところが、平安末より中世にかけて、修験者によって、山頂岩穴に社殿を営み、焼火権現と称えて祀られたと考えられるが、一方縁起書(万治二年・一六五九)によると一條天皇の御宇、焼火山の南海岸、曲浦の海中より神火が示現、山中に飛入ったのを里人がこれを奇として追って山中に入ると現在の社殿背後の奇岩を発見、これを神の鎮まります処として、大山権現、又は石尊権現と称して崇奉ると記されている。「たくひ」という神名は、承久の変により隠岐に御遷幸遊ばされた後鳥羽上皇が渡海の途中夜に入り方向がわからなくなった折り、船人が祈願を込めると神火が示現し、とどこおりなく着船、奉賽の為社参。それまで大山と称していたのを「たくひ」にする様にとの仰せによってそれ以降「焼火」と称する様になったと記されている。しかし、、栄華物語(巻三六)の中に「たくひの神のしるしばかりに」という歌の出ている事からすると少なくとも平安末期には既に「たくひ」という神名が中央の顕紳の間にも喧伝されていた事がわかる。右の如く焼火神は海上生活者が難船に及ぶ時祈願を込める事によって神火を現すという奇瑞によって中世以降ますますその信仰は盛んになった。殊に近世、日本海海路の開発と共に信仰圏はより広く、日本海は言うに及ばず、東北の太平洋岸の船人達まで信仰されたのである。かくして焼火神の船神としての性格は顕著になった。ところが明治以降日本海海路の衰退と共に情況は変わり現在は隠岐島前地区が信仰の中心となっている。なお、祭神、大日霊貴尊と呼ぶのは元禄一六年(一七〇三)以降であり、「焼火神」と称するのが本来のものである。平成四年には本殿・拝殿共国指定の有形文化財(建造物)になる。
黒木神社 (旧社格 無格社)
通称 黒木さん
交通 別府港より徒歩五分
鎮座地 別府
主祭神 後醍醐天皇
神紋
くろぎづた輪に菊紋
祭日 例大祭九月二七日
本殿 春日造 木造銅板葺 一坪
拝殿 木造銅板葺 七坪
付属施設
資料館(碧風館)
由緒・沿革
元弘二年(一三三二)後醍醐天皇が元弘の変によって隠岐に御遷幸され、約一年間御滞在遊ばれしという「黒木御所」の跡に神社を創建。記録としては「島前村々神名記」(元禄一六年・一七〇三)に「黒木社」とあるのが最も古い。しかし創祀の時代は天竜寺、安国寺創建(延元四年・一三三九)からそう遠くない時代に創建されたものと思われる。(「島前の文化財」六号参照)明治四〇年(一九〇七)大正天皇、大正六年(一九一七)昭和天皇、昭和四一年(一九六六)今上陛下、昭和六一年(一九八六)現皇太子。いづれも皇太子の折りに参拝せられた。
大山神社 (旧社格村社)
通称 大山さん
交通 大津より徒歩五分
鎮座地 大津
主祭神 大山祇命
境内社
山神外二座(一祠)
神紋 左三ツ巴
祭日
例大祭七月一三日(隔年七月一二日、一三日神幸祭)・春祭三月一三日・秋祭一一月一三日
本殿 春日造変態 木造銅板葺 二坪
幣殿
木造銅板葺 四坪
拝殿 木造銅板葺 二三坪
境内地 一一〇六坪
由緒・沿革
創立は定かではない。しかしこの地区は知夫郡美田郷(和名抄)の中心地区に位置し、西ノ島の最高峰焼火山(古くは大山といった)を仰ぐ西北麓に鎮座(伝えによると、古くは現社地の奥「宮谷」に鎮座されていたという)。山麓に社の建立されたのは平安初期の頃と思われる。「延喜式」知夫郡七座の内小社。大津・市部の氏神として崇敬されている。
境内社
高田神社 (旧社格村社)
通称 高田さん
交通 小向より徒歩二〇分、船越より徒歩三〇分
鎮座地
高田山中腹
主祭神 伊邪那岐命・素戔嗚尊
境内社 八王子(五男三女神を祭る)
神紋 三つ柏
祭日
例大祭七月一八日(隔年七月一八日、一九日には神幸祭が行われる)、春祭三月一八日・秋祭一一月一八日
本殿 春日造変態 木造銅板葺
二坪
拝殿 拝殿 木造銅板葺 一四坪
付属施設 神饌所・御輿庫
境内地 二九八坪
由緒・沿革
小向・船越の氏神として崇敬されている。社伝によると「天平神護元年隠岐次郎右衛門の息女小花姫に神託あり、高田山頂なる岩窟に祀り高田明神と崇め云々」とあるが、これは隠岐郡都万村高田神社の縁起と全く同じであり、これは中世末時宗の僧が島後より島前に進出して、都万村高田神社と相似した山頂岩窟に祀ったものと思われる。隣接する寺ノ峯には経塚があり、これも時宗の僧によって作られたものと思われる。旧美田村が一部方・二部方と分かれ、この二部方の中心となったのがこの社と思われる。棟札の古いものは元和二年(一六一六)である。
美田八幡宮 (旧社格村社)
通称 八幡さん
交通 別府港より五分
鎮座地 美田尻
主祭神
誉田皇命(応神天皇・八幡大神)・足仲彦命(仲哀天皇)・息長足媛命(神功皇后)
神紋 左三つ巴
祭日
例大祭九月一五日(隔年に十方拝礼と相撲が奉納される)・春祭三月一
五日・秋祭一一月一五日
本殿 流造 木造銅板葺 四坪
拝殿
木造銅板葺 二三坪
付属施設 土俵(履屋付)・御輿庫
境内地 一三七坪
由緒・沿革
社伝によると「延喜元年(九〇一)山城国男山より勧請」とある。もともと鎮座地美田尻の氏神として祭られてきたものが、中世以降、武家に信仰の厚い、八幡神を勧請して国中の総社として祭礼も守護職が主催して賑々しく行われたものであるが、(八幡宮祭礼式書ー文化一〇年・一八一三)現在は美田尻・大山両区の氏神として崇められている。しかし隔年に奉納される田楽(十方拝礼)は旧美田村七郷の奉仕によって行われている。「美田村神社縁起集」正長二年(一四二九)撰(寛延四年写一七五一)によると、後醍醐天皇が黒木御所より御脱出の折り、八幡神が「翁と現じて天皇を守り、美田小向ノ津まで案内云々」とあり又「天下一統の上正八幡大神宮と拝し奉る旨御倫旨被下云々」ともある。近世に入っても隣接別府の地に代官所が置かれたが、為政者の崇敬も篤かったといわれる。
神事・芸能
十方拝礼は平成四年に国指定の重要無形民俗文化財になる。
海神社または(わたの) (旧社格村社)
通称 六社さん
交通 別府港より徒歩一〇分
鎮座地 別府
主祭神
海神二座
境内社 伊勢社・稲荷社
神紋 三つ巴
祭日
例大祭七月二一日(隔年毎七月二一日、二二日。神幸祭 船御旅)・春祭三月二一日・秋祭一〇月二一日
本殿 春日造変態 木造銅板葺
二坪
幣殿 木造銅板葺 四坪
拝殿 木造銅板葺 七坪
付属施設 御輿庫
境内地 九六〇坪
由緒・沿革
創立不詳。延喜式内社、隠岐国知夫郡七座の内の小社。近世は六社大明神と称え、祭神、住吉三座、志賀三社と付会しているが、延喜式にあるごとく海神二座が古来からの祭神であった。この地に先住の海人族の祀りしものと思われる。現在は鎮座地別府の氏神として崇められている。棟札の古いところは元禄二年(一六八九)のものがある。本殿背後に古墳もあり、古くからの社地と思われる。
耳浦山神社
鎮座地
別府耳浦
「神名記」に山神社 大山祇命とある。
これは氏神ではなく元は個人(別府近藤家 屋号オカタ)の祀ったものであったが、今は区で祭祀を行っている。
祭日
春旧暦二月初巳(旧記には初午)、秋十月二十八日(旧九月二十八日)
祭儀
公会堂の一室に祭壇を設け、御神号を掛け御幣(三本)神供(五台)を献り、祝詞。それが終了すると神主従者と共に本社へ出向(神主御幣を奉持、従者米並びに水汲具を持つ)。この時出立(デヤンナヨーデヤンナヨー)を区民に知らせる(これは祭りに携わる神主に出会うと罰が当たるといって家居している)。本社着、先ず従者、酒石壷の酒を汲み、神主神前に献じる。従者は旧酒を汲み捨て、持参の米を石壷に入れ、蓋をする(酒造神事)。神主はその上に糀(こうじ)を置き祓う。次祝詞、拝礼、退下。帰って直会。
一般的には「でやんな祭」と呼ばれるこの祭では、公会堂を出立する時から、帰って来るまで神主と従者は無言でいなければならない。
この小祠に祀られた神に鄭重な祭を執行するのは、「酒造神事」をする特殊の神祭りであるので古例によって現在まで続いている。これは特別ではあるが、このように小祠においても年一回は祭を行ったもの、赤之江秋月神主の場合は小祠の祭りでも必ず神楽の巫女舞を奉納していた。祭の方式は大小色々でも必ず祭儀を行っていた。
真気命神社 (旧社格村社)
通称 素気雄さん
交通 物井港から七分
鎮座地 物井
主祭神 真気命
祭日
例大祭七月一九日(隔年毎に七月一九日、二〇日に神幸祭)春祭一月一九日、秋祭一一月一九日
本殿 春日造変態 木造銅板葺 三坪
拝殿
木造瓦葺 一〇坪
付属施設 参篭所
境内地 三五三坪
由緒・沿革
創立不詳。延喜式式内社であり、知夫郡七座の内の小社。国内神名帳に従三位とある。近世は素気雄大明神と称え、祭神も素戔嗚尊・稲田姫命・大巳貴命と付会している「島前村々神名記」。しかし隠岐国の式内社はいずれも神名が社名となっているものが大多数で、当社は「真気命」とすることの方が古来からのものである。なお、素気雄は社地の地名である。現在は物井の氏神として崇敬されている。
比奈麻治比売命神社 (旧社格村社)
通称 済さん
交通 宇賀港から徒歩十分・倉ノ谷港から徒歩十五分
鎮座地 宇賀
主祭神
比奈麻治比売命
祭日 例大祭七月二十八日・歳旦祭一月一日
本殿 隠岐造 木造銅板葺 四坪
拝殿 木造瓦葺
一六坪
付属施設 参篭所
境内地 八七六坪
由緒・沿革
創立不詳。延暦一八年(七九九)渤海使内蔵宿祢賀茂麻呂等が帰国の途中神助け受けた事によって官社に預かる(日本後記)とあり。次いで承和五年(八三八)従五位下(続日本後記)。貞観一三年(八七一)正五位下・元慶二年(八七八)正五位上(三代実録)と神階も上昇し、霊験の著しい事が中央に知られている。延喜式では知夫郡七座の内の小社。国内神名帳では従一位。右のごとく古代においては地方における霊験神として崇敬されたが、時代が下がるに従って信仰は薄れた。近世では鎮座地宇賀・倉ノ谷両区の氏神として崇敬されている。旧社地は宇賀を隔てる事、約四キロの所にある為、参拝の不便より安政二年(一八五五)に峠越という処に移転したが、氏子の中に種々災いが起こったという理由により、旧社地に返した。昭和三年(一九二八)に至って現地に再移転し現在に至っている。なお、旧社地には神社跡の石碑が建てられている。
橋乃里神社 (旧社格無格社)
交通 波止港より徒歩五分
鎮座地 波止
主祭神 素戔嗚尊
境内社 金刀比羅社
祭日
例大祭七月二三日・歳旦祭一月一日・春祭三月二八日・秋祭一一月二八日
本殿 流造 木造銅板葺 一坪
拝殿 木造瓦葺 四坪
境内地
一〇一坪
由緒・沿革
創立不詳。鎮座地波止の氏神として崇敬されている。島前村々神名記に荒神社三宝荒神、素戔嗚尊眷属とある。いわゆる区で祀った荒神である。旧来祭礼は二八日であったが、明治以降例大祭日を前記の様に変更して現在に至っている。
なお、春秋祭には区公会堂において前夜は日待祭(おひまち)を行い、祭当日は区民全員、公会堂において直会を行う。これが古い「氏神祭」の姿である。
渡利神社
通称 渡神さん
交通 大山港より徒歩五分
鎮座地 大山
主祭神 綿津見神
祭日
例大祭四月二三日
本殿 春日造変態(明神造とも) 木造銅板葺 一坪
拝殿 木造瓦葺 四坪
境内地 三四〇坪
由緒・沿革
創立不詳。大山区の氏神として崇敬されている。
境外社 荒神祠(荒神、山神、清正公)。祭日は七月一七日
由良比女神社 (旧社格郷社)
通称 由良さん
交通 浦郷港より徒歩一〇分
鎮座地 浦郷
主祭神 由良比女命
境内社
伊勢之宮(天照大神)・恵比須社(事代主神)・豊受宮(豊受神)出雲社(大国主命)
神紋 丸に並び矢
祭日
例大祭七月二八日(隔年毎に七月二八日、二九日には神幸祭・船渡御がある)・春祭三月一三日・秋祭一一月二九日・神帰祭(烏賊寄せ祭り)一一月二九日
本殿
大社造変態(明神造とも)桧皮葺 七坪
幣殿 木造銅板葺 一〇坪
拝殿 入母屋造木造銅板葺 一五坪
付属施設
社務所・神器庫・土俵(履屋付)
境内地 五七一二坪
由緒・沿革
承和九年(八四二)に官社に預る。延喜式神名帳には名神大。元の名は和多須の神とあり、国内神名帳には従三位上由良比女大明神とある。「袖中抄」にもその名が見え、それには仁明天皇が承和一五年(八四八)、陽成天皇が元慶元年(八七七)に鄭重なる祈願をしたとある。平安末期には隠岐国一の宮と定められた。安永二年(一七七三)には島前一統の祭とする事になった。
特殊信仰並びに神事
一一月二九日夜に行われている神帰祭。神事之時供物次第
安永七年(一七七八)によると「九月末日 神送り神事 御供 赤飯。十月末日 神迎神事 御供 赤飯」とある。右は由良比女神が出雲の神在祭に出られるのが神送りと伝えられ、それによって現在は帰神といわれる十一月二十九日に祭儀を執行する。由良比女神は烏賊に乗りお帰りとの伝があり、この夜は必ず由良の浜に烏賊の群が寄るといわれ、氏子はこれを「烏賊寄せ祭」と称している。
日吉神社または(ひえ) (旧社格村社)
通称 ひよしさん・山王権現
交通 浦郷港より徒歩十分
鎮座地 浦郷
主祭神
大山咋命
境内社 八王子社(市杵島姫命外七柱)・東照宮(徳川家康)・金刀比羅社(大国主命)恵比須社(事代主命)
神紋
丸に巴藤
祭日 例大祭旧九月九日・春祭三月九日・秋祭十一月二十八日
本殿 日吉造 木造銅板造 一坪
幣殿 木造銅板葺造
六坪
拝殿 木造銅板葺造 十二坪
付属施設 参篭所
境内地 六百二十八坪
由緒・沿革
社伝によると近江国滋賀郡真野庄に祀られていたのを、後白河法皇の時代領主真野宗源が兵乱を避けて隠岐に逃れた際、この社に仕える吉田某と共に氏神たる山王社・八王子社も共に奉遷し現在の社地に鎮座したという。吉田家蔵の大般若経の奥書に「正応二(一二八九)巳丑九月 供養了 願主沙門西蓮 奉込隠岐国美田庄浦方山王御宝殿」とあるところからすると大体伝承の通りが事実であると思う。こうして鎮座当時は「真野家」が中心となって祭礼を行ったであろうが、後には浦郷区の区民の信仰によって由良比女と共に両氏神と称して崇敬されている。明治五年十月に社名を山王権現から日吉神社に改称した。
神事・芸能
「庭の舞」・「十方拝礼」は平成四年に国指定の重要無形文化財として「隠岐の田楽と庭の舞」と命名され、美田八幡の十方拝礼と共に指定された。
茂理神社 (旧社格村社)
交通 赤之江港より徒歩五分
鎮座地 赤之江
主祭神
茂理大神(句々廼馳命・軻遇突知命・金山彦命・埴山姫命・草野姫・罔象女命)
境内(飛地)社 青根神社
神紋 五・七の桐
祭日
例大祭七月二六日(隔年毎に七月二六日・二七日に神幸祭あり)・春祭三月一二日・秋祭一一月二三日
本殿 木造銅板葺 一坪
拝殿
木造銅板葺 一二坪
付属施設 御輿庫
境内地 二二一坪
由緒・沿革
島前村々神名記(元禄十六年)には、森大明神とあり、祭神天鈿女命となっているが、諸書いづれも「句々廼馳命」外五柱が記されている。創立年代は不詳。鎮座地の赤之江区の氏神として崇敬されている。棟札の古いところでは元亀三年(一五七二)のものがある。
待場神社 (旧社格村社)
通称 待場さん
交通 三度港より五分
鎮座地 三度
主祭神 猿田彦大神
配祭神
天鈿女命・大日霊貴命・千箭御前・峯見神
境内社 稲荷社・大山社・出雲社
祭日
例大祭七月一三日・春祭三月一五日・秋祭一一月二四日
本殿 木造カラートタン造 一坪
拝殿 コンクリートブロック造
一二坪
境内地 三二一坪
由緒・沿革
猿田彦大神が三度この里に現れしにより地名を三度という。創立不詳。隠岐島前村々神名記(元禄一六年・一七〇三)に待場明神とあり。三度区の氏神として崇敬される。明治三年(一八七〇)の神社調べにあたって古い棟札に松尾神社とあって、それ以降松尾神社と称したが、この棟札は漁民が海中から拾い出したのを寄進した事が判明し、昭和一九年(一九四四)に社号を旧に復して待場神社とした。
伝説
天照大神の降臨
神代の昔、天鈿女命を従えた天照大神は三度の「鯛の鼻」の北にある「大神」という海の「立島」に降臨された。この島は細く天を突くような岩があたかも亀の背に乗っているような島である。ここにはこの時の「お腰掛けの石」もあるが、やがて天照大神は三度湾に船を入れて南の「長尾鼻」にある「生石島」に上陸された。最初この場所から少し東の海岸に目をやると、人影が見えた。神は「人のいそうもない海岸に、不思議なことだ」と言って、そこへ行ってみたが、誰も居なかった。そこで「生石島」に引き返して振り返るとやはり人影が見えた。もう一度返って捜したが誰も居なかった。・・三度目には意を決してその先の集落まで行ったので、ここを「三度」というようになった。人影と見えたのは、実はこの場所に何回かお迎えに出ていた猿田彦命の姿であった。常に人影が見えたので、ここには「常人」という地名がついた。またこの湾の「生石島」にも天照大神が腰を掛けたところから、地区の人は「お石様」と名付けて崇敬している。それに途中では水のある処を越したのでそこには「越水」という地名がついた。三度の集落に入ってからは、中谷正宅の裏にある石の上で休息された。それでこれを「お腰掛けの岩」と言っているが、近年までこの石に注連縄を張って祭っていた。ところで、天鈿女命は近くの山に登って「天照大神の鎮まります地はどこがよいか」と辺りの峯々を見回した。そこでこの山を「峯見山」と呼ぶようになった。峯見山から南東に見えたひときわ高い山に天照大神をお連れして、しばらく鎮まっていただいた。この山は珍崎の南にあって、あくまでも仮の場所なので「仮床」という地名をつけた。一説に、この山で狩りををしたので「狩床」になったともいう。さて、天照大神はここで七谷七尾根ある場所を捜した。その時「この山には谷が一つ足りない」と言って持っていた筆に硯の水をひたして一滴落とした。するとたちまち小さな谷が一つできて、これを「硯水」といった。また、その筆で手紙を書いて大空に投げ上げたところ、この山の頂から二羽の烏が飛んできて口にくわえた。そしてはるか東方に見える焼火山を目指して飛んでいった。烏の飛びだした場所には「烏床」という地名がついた。焼火山の神様は、この手紙を受け取って神勅とおぼしめし、早速聖なる大宮所を選定して報告した。それを受けて猿田彦命と天鈿女命は天照大神を焼火山の大宮所にお連れした。こうして焼火神社は天照大神をまつることになった。それに手紙をくわえて飛んだ二羽の烏は後に焼火山内に棲みつき、いつもこの神社の境内に来て遊んだ。参拝者があると、境内の木の上から鳴き、神殿の上から騒いで神社の人に知らせた。子供が生まれると、その役目を譲って親烏二羽はいなくなるという。その後、猿田彦命と天鈿女命は三度の海岸の「奈那」という所で雌雄二つの石を産み、神光を発しながら亡くなった。村人はこの二つの石を亡くなられた二柱の神の霊魂の寄代として崇め神社を建てて祭った。その場所は猿田彦命が天照大神を待っていた所であったので「待場」と命名し社名も「待場神社」とした。一方、焼火山の神様は別名を「千箭の神」といった。これは神功皇后が三韓に出兵するとき、弓矢を携えて出現なされ、待場・峯美の二柱の神を引率して従軍されたからである。千の矢を放った場所は三度崎の「追矢床」であり、その矢が韓の国まで走っていったので「矢走」という地名もついた。軍馬を出された所は「御馬谷」といった。
聖神社 (旧社格村社)
交通 珍崎港より徒歩五分
鎮座地 珍崎
主祭神 聖大神(事代主命)
神紋
亀甲型に三の字
祭日 例大祭七月二二日・春祭二月二七日・秋祭一一月二五日
本殿 流造唐破風向拝付銅板葺 一坪
幣殿 木造瓦葺造
二坪
拝殿 木造瓦葺造 五坪
境内地 八一三坪
由緒・沿革
創立年代不詳。珍崎区の氏神として崇敬される。古文書、棟札は焼失して古記録は不明。『隠岐島の伝説』より「神代の昔日本の国に比志利の神という方がおられた。この神は外国へ出かけてその帰り道に隠岐島近海で暴風雨に遭われた。けれども勇敢なこの神は西ノ島のフイドシ(フィドレともいう)の鼻に船をつけた。しかし、そこはそそり立った絶壁ばかりで一歩誤れば墜落するところである。比志利の神はそれでも岩角をつかんで、とうとうその断崖の頂上まで登りつめた。そしてそこからは山続きのハヤマに行って住むこと数年、ついにここでなくなられた。村人は悲しんで、この岩屋をそのまま比志利の神の墓所と定め名前も「比志利が岩屋」と呼ぶことにした。フイドシの鼻の絶壁には、この神の手の跡が数カ所あり、頂上には「お腰掛けの岩」も残っている。後に村人はこの神の神徳を慕って珍崎の里に神社を建てたが、今の場所に移るときにも比志利の神は途中珍崎の奥山の椎の木に仮の宿をされたと伝えられている。
以上十四社であるが、江戸期に祀られていた小祠も現在ほとんど現存しており、消滅したと思われるものは極わずかである。ただしそれ以降に祀られた神々もあるから神々の数は江戸期とあまり変わらない。殊に、恵美須神、弁財天は各区に祀られている。
氏神神社の祭神について
氏神とは、本来はその氏族の祖先を祀ったもので、その御名のわかっているものは「××命」などとなっている。それが後には、その地域に住み着いて開発した祖先(不特定多数)を祀ったもので固有の名はわからない。その例が最も多い。また、変じて、主として漁を生業とする人々が多い処は、海神を守神として祀ったり、農を主としている処では農神を祀っているが、これらを総べて「氏神」と呼ぶようになった。西ノ島での例を挙げると、別府海神社は「海神二座」とあるが、それを近世になると固有の神名を挙げる事になって、古典に出る住吉神社に祀られている「表筒男神・中筒男神・底筒男神、海人族の祀る志賀海神社の祭神である表和多積神・中和多積神・底和多積神」の神名をあげ「六社大明神」という風に申し上げた。この事からすると別府の先住者は海上を主たる生活の場とした者が多かったものと思われる。
由良比女神社の祭神は「由良姫命」と名付けているが、これは「由良」という地名のある海辺に祀ったからで、これも「元名和多須神」とあるので海の守神であることがわかる。
大体江戸期には神社名でなく「××大明神」と神名になっている例がほとんどである。
高田神社の場合は「高田大明神」と山の名を冠している(ただし、この山名は高田神を祀る山であるから後に付けたとも考えられる)
それが近世期になると神名を挙げる場合は、無理に古典に出る神名に付会してしまうのである。それは、その方が格の高い神と考えたからであろう。参考までに各区に祀る氏神の祭神について考察してみた。
比奈麻治比女命社
これは「ヒメ命」と固有の御名がわかっていて延喜式(平安期)の時代から、この名で呼ばれている。これは縁起からして「火の霊威」を称した御名であろう。
真気命社
これも「××命」と固有の神名である。前記の「延喜式」の中にも選ばれた神社で、平安期からの名称である「ケ」というのは、「食」という字を「ケ」と読むように食物と関係のある言葉で、「穀霊」を祀ったものであろう。ところがこの神名も古典にないところからして「真気命=真鶴雄神・稲田姫命・大巳貴命の三神を祀るようになった。この物井地区には古墳も数多く残っており、古代には今よりももっと多くの人々が住んでおり、それが今の倉ノ谷、宇賀、別府の方へも広がっていったのではないか。物井の先住者は古代には漁でなく農を主とした方が多かったのではないか。
海神社
これは「海神 二座」とあるように別府の先住者は海人たちであったろう。 近世期の祭神は初めに例として挙げておいたので省略する。
美田八幡宮
この地区は美田村の中に含まれているところであるが、隣接の別府は、中世から近世にかけて為政者(武家)が島前の中心的地域からか居を構えるようになってから、美田尻の氏神であった神社に武家の信仰の厚い「八幡神」を勧請して合わせ祀り、島前の総社的神社として祭礼も賑々しく執り行なわれた。
そのような沿革からして、ここに元から祀られていた神は自然に氏子等の心から消滅してしまったのでないか。「八幡神」は九州の宇佐八幡・京都の石清水八幡が名高く、縁起には「延喜元(九〇一)山城男山より勧請云々」とあるが、美田尻の先住者からすると異質の神であろうから、こんな時代にわざわざ武家の信仰する「八幡神」を勧請するわけはない。「八幡神」を氏神としたのは中世期以降のことであろう。祭神名は前記の神社に祀ってある誉田皇命(応神天皇)・足仲彦命(仲哀天皇)・息長足媛命(神功皇后)となっている。ついでに応神天皇を何故「八幡大神」と称えたかについては、色々の説はあるが結局、応神天皇は宇佐の八幡(やはた)という処でお生まれになったので、そのように称えるようになったというのが妥当に思われる。これからすると「ヤハタ」とするのが本来の呼び方のはずだが、音読して「ハチマン」と称する神社がほとんどである。
渡利神社
「神名記」には和多積神、また玉依姫命とある。「神名記」もあるが、いずれも海神として祀られる神で古くは海を生活の場とした人々が住んでいたであろう。あるいは別府の海人等が移住したかも知れない。近世に入ってからは、北前船の風待港でもあったので海神を祀る条件はあった。
大山神社
この神社も「延喜式」にある神社で平安期から祭神も「大山神」である。ただしこの地区は美田の中でも田畑の一番多い所であるから「山神」でなくてもよいように思われるが、古い祭場は森のある処が多く、また近くに高山があれば、その山を神の鎮まります処として、山を仰ぐ山麓に祭場とする例は多い。「大山祇命」は山神として古典にある神名である。古代には「田ノ神」も農作の頃には、山から天降って来て稲作を守ってくださるという信仰もあり、また祖先霊も山に鎮まっているという信仰もあるところからすると、お祀りした神も古代と変わっていないと思う。我々の祖先も遅くとも弥生時代(前二〇〇)頃には住んでいたのである。
高田神社
「縁起書」によると「天平神護元年(七六五)「隠岐次郎左衛門息女小花姫」に神託があり、頂上の鳴沢池より示現された神を高田山頂なる岩窟にお祀りし「高田明神」と崇め・・」と記されているが、これは、島後都万村高田神社の縁起と同じで、島後では至徳二年(一三八五)の事としている。そして小花姫に神託のあった神は「国常立尊」となっている。この「高田神」は「時宗」の僧と関係があった。
思うに時宗の僧が島前に進出した時に島後の「高田神」を勧請しお祀りしたのではないだろうか。さすれば神名は「国常立尊」と申し上げるべきではあるが、島前では「伊邪那岐命・素戔嗚尊」と申し上げたのではないか。いずれにしろ小花姫の神託によって顕わされた神であるので、古くからの「氏神」としての性格はない。
現在の美田四区の先住者たちは、「大山神社」を氏神としていたものと考えられるが、この「高田神」を祀るようになってから以降、船越・小向の人々はこれを「氏神」とするようになったのではないだろうか。
橋乃里神社
これは「荒神」であるが神名を挙げるようになると古典にある素戔嗚尊が八岐大蛇を退治したというように荒々しく強い神名になっている。荒神は各集落に祀っているが、石体が多く、氏神として社殿のあるのは西ノ島では波止・市部のみである。荒神を各区で祀っているのは、里内に入る悪神を防ぐ神として、それが里の守神として祀ったものであろう。
由良比女神社
これは再三例としてあげたように、元は海神であるが、後世に須勢理姫とした時代もあった。今は古きに返して「由良比女命」となっている。祭神の事と離れるが、江戸時代には「隠州視聴合紀」に「薄子浦あり。その山を出でたる処に由良明神と号する小社あり。極めて小さく古りはてて亡きが如し。里人も知る者なし」と記されている。ところが、「神名記」には日吉社の外に大原明神・住吉明神・石神明神・蓬莱亀社・平野宮・乙訓明神と数多くの神々が祀られているにもかかわらず、名神大社である由良比女社が前記のようであったのは何故であろうか。思うにこの頃は今のように氏神社を村の中心的神社とする考え方は少なく、前記のように小祠を個々に祀っていると同じ程度に考えている者の方が多かったのではないか。その後、社殿も段々と整備し安永二年(一七七三)には、島前の村々より青銅三貫文、浦郷村からも同額の三貫文が祭礼料として奉納され、これによって三年一度(隔年)の船渡御の祭を賑々しく行うことになった。これは庄屋・村役人が中心となって、名社である由良比女社に重点をおくような指導をし、又それに要する経費の捻出方も考えたのでないか。神社は祭礼を盛んにする事によって信仰心も増し、またこれに合わせて社殿等も整備されていくのである。
日吉神社
この社は祀った時期も、祀った人もわかっており、浦郷の古くから住んでいた人等が氏神として祀ったものではない。これは真野氏一族の氏神である。真野氏が隠岐に逃れてきた時、相当多くの人々も移住したであろうから、隠岐に来てからも自分たちの氏神を祀ったのである。したがって初めは真野一族の者によって祭礼を行っていたと思うが、それが後には浦郷の人等も参加して祭礼を行うようになり、江戸期には浦郷の氏神としても違和感のないものとなったであろう。
日吉山王本社の祭神は「大山咋命」である。この時、「八王子神」も共に移したようで、今も境内の小祠として祀られている。この外に金刀比羅社・恵比須社もあるが、これは浦郷の漁業者の人々が祀ったものであろう。
茂理神社
元禄の神名記によると「森大明神・天鈿女命」となっているが、いつの頃からか現在の「ククノチ命(木ノ神)・カグツチ命(火ノ神)・ミズハノメ命(水ノ神)・カナヤマヒコ命(金ノ神)・ハニヤマヒメ命(土ノ神)・カヤノヒメ命(野ノ神)となっている。「木火土金水」の神としたのは陰陽道によったものであろう。陰陽五行及びその実践としての陰陽道が奈良時代に日本に入ってから、国家組織の中に組み込まれ一貫して朝廷を中心に祭政・占術・諸年中行事・医学・農業等の基礎原理となって日本人の中に定着した。
陰陽五行とは、地上では陰陽の二元気の交合の結果、木火土金水の五元素、或いは五気が生じたと説く。それを日本の神話にある神々にあてはめると前記の神々となる。それに「野ノ神」を合わせ祀ったのである。
もともと「森大明神」と称えて神名としたが、これは恐らく祭を行った場所が近くの森であった処からの命名であったかと思われる。それを江戸期になって「木ノ神」外の四柱の神と、それに牧畑地のところが野原であるから「土ノ神」もあるが、特に「野ノ神」も入れたのではないだろうか。このような神々にしたのは赤之江の社家である秋月氏が考えた祭神かと思う。天鈿女命は自然に消えていった。
待場神社
西ノ島の神社で神降臨の伝承があるのは、この社と珍崎の二社のみである(神社別の項参照)。主祭神を猿田彦命とし、それに合わせて天照大神をはじめ関係のある神々も合せ祀っている。
いつの時代に氏神として祀つるようになったかは不詳であるが、これは三度の先住者が、いつここに住むようになったかが問題で、「みたべ」という地名から美田地区の先住民の一部が移住したのでないかという説もある。この地区には今のところ古墳等の遺跡も発見されておらず、美田地区から移住したとしても歴史時代に入ってからであろうか。ここでは天照大神が焼火山に鎮まり給うたとの伝承であるが、焼火神社で天照大神(大日霊貴命)を祭神としたのは江戸期に入ってからで、古いところでは「たくひ神」である。
聖神社
「神名記」には事代主命の神名をあげている。「聖神」は古事記(須佐之男命の子、大年神。大年神と伊怒姫の間に五神が生まれているが、その一神に聖神がある)にでている神であるが、(同名異神であるかもしれない)この神の事績は何も記されていない。右のようなことなので、漁神として一般に知られている「事代主命」としたのでないだろうか。
焼火神社
「島前村々神名記」の原本は松浦家に保存の資料であるが、これによると祭神は大日霊貴尊・萬幡姫(萬栲幡千幡姫とも)・手力雄命の三神をお祀りした事になっているが、これは伊勢神宮においても本宮に相殿神二座として祀っているので、これに習ったものであろう。
黒木神社
後醍醐天皇。これは申し上げるまでもなく奉祀の当初からはっきりしているが、社名を「黒木社」としたのは元禄の「神名記」が古い。ただし、これは一般的にあまり呼ばれなかったらしく、明治五年になって「後醍醐天皇御社、或いは黒木御所と称し奉りしを黒木神社と改称」とある。
(註) 「神名記」は「島前村々神名記」(元禄十六年)の略。神名記は異本も数種あるが、いづれも奥書がない
古典は「古事記」「日本書紀」、神名は古事記による
神社がその集落の中の一社に重点を置き祭祀を行うようになるのは、明治の神社制度確立以降のことで、それまでは氏神社も、その周辺に祀られていた小祠も同列にあつかったものである。そうであればこそ、江戸期に在った祠も明治まで変わらずに存続したのである。祭の大小はあっても、どんな小祠でも必ず祭を行っていたのであるが、明治国家の神社に対する考え方は、小祠に祀られていた神々は、出来得ればそれを村氏神に合祀または廃止するという方針であった。村人達は氏神の社に合祀してしまうと形がなくなるので、氏神社の境内に集めて小祠を造った。これが今境内にある小祠(末社)である。
ただし、この小祠に祀ったものも、その集落の人々の信仰の厚い神々は元の社地に返して祭を行っている例も多い。一例として市部の「荒神」社と大山の「渡利社」について記す。
市部には「地主権現」というのがあって「荒神」よりも重く祀られていたが、これは明治の神社制度が改正された折り、大山神社に合祀された。荒神は各区に祀られているが祠を造って祀っていたのは市部と波止のみであった。
ところが、市部区民は残されていた「荒神」の祠を新たに区内に社地を設け、また社殿も銅板葺の立派なお宮にして、祭りも旧時より賑々しく、また祭りの後の直会も区民全員参加して行うようにしたのである。
市部と大津の氏神は大山神社であるが、いわば、市部だけの「氏神」として荒神を独立させよう、という意識が芽生えた結果ではなかろうか。
次に大山の「渡利社」であるが、これは初めから氏神として祀られていたが、どうした手違いからか明治の神社制度改正の折り、「無格社」としての扱いも受けず、大山の里人は「美田八幡宮」の氏子の中に組み込まれてしまった。このような経過を経て、戦後の神社制度の改変を機に「法人登記」の手続きをして区の氏神として独立した。また「社格」という神社の格付けも決められ、それには少なくとも本殿・拝殿・参篭所等の設備のある処は「村社」という格を与えられ、本殿のみのものは「無格社」という格付けがなされた。「黒木社」「橋乃里社」が、その例である。
さて「渡利社」であるが、ここは本殿と参篭所のみで拝殿はなかった。ところが平成三年の台風によって建物の全てが倒壊してしまった。この社は小型ではあるが、大根島の宮大工豊島万蔵の作(松江の名工荒川亀斎の系列に入る宮大工で、焼火社の明治期の造営の折りの棟梁。由良比女社の建立をした三度の角谷氏とは相弟子であった)。文化財建築としても価値のあるものであったが、幸い浦郷の篠木幸壱氏の手によって立派に復原された。それを期に拝殿も新築され、小さいながらも社殿の整備をみた。
神社は祭祀を斎行する場ではあるが、それには社殿の整備も大切である。これも偏に氏子の氏神に対する篤い思い入れと、自ら意識するしないにかかわらず信仰心なくしては神社の永続はあり得ない。これは前記の社のみでなく各氏神社の場合も全く同じである。やはり日本人は時代がいかに変わろうとも神を祀る民族である。
都市部における団地などにもそこに数年間定着すると、誰が発起人するかは知らないが、「神社」を造るという例も出来ている。そしてそこが「ふるさと」になって行くのであろう。
主なる参考文献
『神國島根』(神社誌)
『島根の神々』
『式内社調査報告書』(山陰編)
『島前村々神名記』
『国内神名帳』
『美田村神社之縁起集』
「神社御由緒調査書」(旧黒木村)
「隠州風土記」
「隠岐国神社秘録」
波止(はし)
旧所属
美田村橋里、黒木村波止、西ノ島町波止
地勢
西ノ島町の中央に位置する焼火山の西麓にある集落であり、焼火神社の参道の一つがここから始まっている。集落の中央には水量豊富な波止川が流れ、昭和四五年には砂防ダムも建設され、もしかしたら西ノ島全体の水量を賄う事になったかも知れない程のものであった。海に面しては、中央に赤灘・少し右には珍崎が見える。港湾は漁港であり、三トン未満の小型漁船が十隻ほど停泊している。集落内の地域的区分は五組あり、東小路・西小路という区分もある。
交通機関
別府から約七キロ、浦郷から八キロ、車でおよそ一五分の距離にある波止は、西ノ島町で唯一バス交通機関の無い集落である。島前内航船(いそかぜ)が現在は一日に三便あり(浦郷へ一○分・知へ一夫へ一○分)浦郷行き三本、知夫行きが三本。自然と日常の交通はタクシー・自家用車に頼ることが多い。
就業概観
江戸時代においては、北前船の風待港であった事に影響を受けてか、ここの住民は船乗りが多かった。以前は自分で船を所有して海運業を営んだ家も少なからずあったが、現在はほとんどが外国航路に勤め定年になってから波止に帰ってくる場合が多い。そういう傾向は波止と大山には特に頻繁であった。
区内施設
波止集会所
波止集会所に現在の昭和五五年に旧来と同じ場所に新築。旧来は二階もあったが現在は平屋
ダー(老人集会所)
寺号としては地福寺と呼び、現在の建物は大正四年のもので、一部修復され区の集会所と隣り合わ所と隣せで使用されている。
日蓮さん
波止から焼火山に登る旧道脇に日蓮宗の堂があり、これを波止では「お堂」と呼び区の堂は「ダー」と呼んで区別している。
橋乃里神社
素盞鳴雄命(すさのおのみこと)
波止分校の横にある波止の氏神
波止分校
松浦斌の塾。明治七年美田村第百六十四番小学校支校として正式に誕生。この時は松浦家居宅を使用。明治八年に波止里の堂(地福寺)を校舎にあてる。明治二○年には簡易小学校として独立、明治二四年には尋常小学校として三六年まで続く。明治三七年からは仮校舎として四一年まであり、四一年から大正五年までは美田小学校に通い、大正五年からは新たに美田小学校波止分教場としてあり、昭和一六年には国民学校分校となった。以後昭和四六年の廃校にいたるまで波止住民はことごとくこの校舎を卒業していた。現在は、西ノ島町民俗資料室の倉庫として使用されている。
遺跡
波止遺跡
現在の弁天鼻「船隠し」と呼ばれる場所から、須恵器が発見された。
ニジ古墳
現在の西ノ島町ゴミ埋め立て場付近から土師器が発見された。
店数
亀屋商店。旧来は小林商店、升屋商店、俵屋(塩と煙草のみ)の四軒があったが、現在は亀屋(松浦)商店が一軒のみとなった。
トピック
焼火神社
大日霊貴尊(おおひるめむちのみこと)
旧暦十二月三十一日の夜、海上から火が三つ浮かび上がり、その火が現在社殿のある巌に入ったのが焼火権現の縁起とされ、現在でもその日には龍灯祭という神事が行われている。以前はその時に隠岐島全体から集って神社の社務所に篭り、火を拝む風習があった。現在は旧正月の五日から島前の各集落が各々日を選んでお参りする「はつまいり」が伝承されている。例大祭は七月二三日・二四日の二日間、昔は島前中から集って神輿をかってついだが、昭和三○年の遷宮を最後に廃止された。江戸時代には北前船の入港によって、海上安全の神と崇められ日本各地に焼火権現の末社が点在している。安藤広重・葛飾北斎等の版画「諸国百景」では隠岐国の名所として焼火権現が描かれている。
社殿は享保一七年(一七三二)に改築されたものであり、現在隠岐島の社殿では最も古い建築とされている。当時としては画期的な建築方法で、大阪で作成され地元で組み立てられた(今でいえばプレハブ建築のはしりとでもいおうか)。平成四年には国指定の重要文化財に指定された。城を偲ばせるほど広大な石垣の上に建設された社務所では、旧正月の篭りの時に千人ほどの参詣人が火を待ちながらたむろしたり、また、江戸時代には巡見使が四○○人以上の家来を率いて参拝した折りの記録も残っているが、現在は朽ちて客殿という場所にしかその名残をとどめてはいない。
山頂付近は焼火山神域植物群として保存され平成五年には神社から大山から神社まで遊歩道も整備された。一○年以上かけて開通した焼火林道は市部から始まって大山へ至り、平成五年には波止から焼火参道までは舗装整備されるまでになり波止からは車で一○分、そこから徒歩で一○分で神社まで到着可能となった。
文覚窟
文覚上人(もんがくしょうにん)。『平家物語』『源平盛衰記』などに登場する僧侶で、数回にわたって配流され、最後にはここで全うされた。一回目の配流(遠島・島流し)は伊豆諸島であり、そこで源頼朝と知り合いになり、平家討伐の切っ掛けを作ったとされる人物である。頼朝が鎌倉幕府を開幕してからは、大勢力をほこったが、頼朝の死去にいたって、中央から排除され、最後に隠岐島に配流れたと伝えられている。文覚窟は、波止と大山の中間の海辺にあり、現在は交通手段がない。
北前船
江戸時代初期から始まった千石船による海上交通は、次第に隠岐島を風待港として利用することになり、それによって西ノ島の経済・文化は多大な影響を受けるに至った。上方を出発して北海道に向かうのを「下り間」と称して大山に、逆に北海道から上方に向かうのを「上り間」といって波止に停泊したといわれる。
「上がり間」が波止に停泊したのは元禄時代くらいまでで、後には浦郷に変わっていく。
ユースホステル
昭和三七年に波止にある松浦家で「たくひユースホステル」が発足し、観光時代の先掛をになった。隠岐島が昭和三八年に大山隠岐国立公園として指定されたが、観光客が来ても宿泊施設は充分でなく、波止の住宅と焼火山の社務所のを両方使用して、多い時には一日に一五○名以上宿泊した時もある。ユースホステルに泊まるのは大学生が中心で四○戸くらいの集落に毎日五・六○人の若者を見るのは村人にとって珍しくもあり、楽しみでもあった。盆踊りになると地元の住民とユースホステルの宿泊客が一緒になって百人以上の踊の輪が作られた時が一○年以上も続いた。
弁天鼻周辺
昔は芋山、後にはトライアル練習場、現在は子供の公園、ログ・ハウス、キャンプ場、フィッシングデッキ、ホテル予定地など、にわかに波止集落の入口の峠は賑やかになってきた。
市部(いちぶ)
旧所属
旧美田村の本郷、黒木村市部、西ノ島町市部
地勢
現在は美田湾に面した集落を一般的に「美田」と称しており、旧来の美田村(美田尻・大山・波止をも含めたもの)とは若干区画を縮小した地域を指す。その美田湾に向かって一番右端の集落を市部(いちぶ)という。他集落の人から見れば、大津との境界が一瞥できないほどに住宅は接近しているが、現在は原商店までが市部とされている。最近はシーサイドホテルから波止に向かって住宅も拡がっており西ノ島町中では珍しく拡大している地域である。現在、区内の組は四組ある。
交通機関
大津から歩いて五○メートル。特にバスも無く、島前内航船も発着しないが、最寄りのバス停留所としては大津と同じ。
市部遺跡
現在のシーサイドホテル先から弥生土器が発見された。
区内施設
会場
昭和二一年建設
堂
寺号は成仏寺。現建物は大正一○年建設
荒神
店数
以前は板屋と原商店があったが、現在はない。
トピック
一分方
中世から江戸時代まで一貫して美田村の庄屋(公文)職をつとめた笠置家がここであった関係上、美田村では市部が本郷であった。その記述は、「隠州視聴合記」の地名を説明する時は必ず「・・本郷より何町」という言い回しに現れていることからも推測できる。それは集落内の旧庄屋の屋敷の前が「いちぶのまえ」という字名である事からも判別できる。
竹田家
明治から戦前にかけての資産家であり、大正一一年には竹田家からは県会議員も出たくらいである。
寺院
長福寺の末寺、円蔵寺は市部荒神から、波止に向かって左に曲がる左の山手にあったが、廃仏毀釈の影響で終わりをつげた。十方拝礼ではこの寺が中門口の役をする事になっていた。
田崎真珠跡
昭和四○年ごろ真珠を栽培していた場所がある。
一銭渡し
シーサイドホテルの先から灯台付近まで一銭で船を使用して人を運搬していた。
運動公園
総合グランド・総合体育館
シーサイドホテル
荒神から先に初めて家が建ったのが、このホテルであった。
町営住宅
市部荒神の先に昭和五四年に四戸の町営住宅が建設された。
大津(おおつ)
旧所属
美田村大津、黒木村大津、西ノ島町大津
地勢
(八組)美田湾の中央に位置するこの集落は、海から向かって左側に美田川をひかえ、この川を挟んで小向と対し、右側は市部に隣接している。
交通機関
別府と浦郷の間に位置し、別府へ三キロ・浦郷へ四キロの場所にある。バスもあり、定期船もここに駅を持っている。
区内施設
お堂
彌勒堂
大山神社
市部と大津の氏神であり、祭神は大山祇命(おおやまずみのみこと)
延喜式神明帳(約一千年前の書物)に早くも登場する古い神社で、大津と市部の氏神としてある。以前は現社地よりもさらに宮谷の奥にあったとされている。
遺跡
兵庫遺跡
美田ダム取り付け道路の入口から昭和五二年に発掘された遺跡。平成四年からも再度発掘されている。ここからは5~6世紀にかけての夥しい遺物が発見されており、住居遺跡とも祭祀遺跡ともいわれている。平成四年五月からの発掘では、ビーズや魚の歯なども出土しており西ノ島では最大の遺跡といえよう。
小円山古墳
現在長福寺のある丘から土師器が発見された。
立石古墳
現国道四八五号線の大山神社先の田の中から明治末と、大正八年に出土した西ノ島の代表的な古墳である。明治末年の古墳は既に消滅しており、遺物があるのみ。大正八年に発掘した遺物(金銅装飾太刀・槍・鉄斧・玉)は現在は東京国立博物館に保存されている。
宮ノ前遺跡
現在大山神社の境内から和鏡が発見された。
美田遺跡
現在、大橋川の大津側の田から石斧が発見された。
店数
山ノ内・岡田・岩井
トピック
長福寺
真言宗東寺派
縁起 「往昔行基当峯(高田山)を霊場なりと見て篭給うに、生身の観音示現して、是より北に当たりて浦あり。其に竜宮より来りし嘉樹あり之を以て我が像を刻んで仏閣を建て安置せよと夢裏分明なれば、行基彼の浦に至りて見れば流木あり。之を執りて千手、十一面の二仏を彫刻して、千手を当寺の本尊として十一面は同郡別府の飯田寺に安置。尚此の流木の残部を以て或修行者枕として、出雲枕木に至りけるに枕木の観音の御膝に穴疵あり、修行者の枕を合わせたれば符号せる由。(美田村来歴)」
明治二年に廃仏毀釈によって一時は廃寺となったが、明治十二年六月二日にようやく復興の許可がおり、復興することになった。復興に際しては地元出身の天野快道・大野明演たちに死にものぐるいの努力によることが多い。
伝承の寺院
「龍択寺がわ」「ダージコージ」と呼ばれている古井戸がある。十方拝礼に縁の深い寺院(龍択寺=道場寺・薬師寺、小山寺)
美田川
西ノ島随一の水量を擁する河川であり、美田ダムによって町のほとんどの水源をまかなっている。
美田保育所
昭和三十年建設、三十一年保育開始。平成七年新築
老人福祉センター 昭和四十九年建設
小向(こむかい)
旧所属 美田村小向、黒木村小向、西ノ島町小向
地勢
大津と同じく美田湾の中央に位置するこの集落は、海から向かって右側に美田川をひかえ、この川を挟んで大津と対し、左側は船越に隣接している。
六組(ヌクイ・コンケ・ミヤザキ)
交通機関
別府と浦郷の間に位置し、別府へ三キロ・浦郷へ四キロの場所にある。
区内施設
高田神社
小向と船越の氏神であり、祭神は伊邪那岐命(いざなぎのみこと)・素盞鳴雄命(すさのおのみこと)
お堂
遺跡
小向遺跡
加木氏宅の裏崖部よりおびただしい黒曜石・石器・土器などが発見された。
山根畑古墳
現在、大津と小向の分れ道付近から遺物が発見された。
寺ノ峯経塚
高田山の峰の並びにある「寺の峰」の頂上から「経塚」(きょうづか)と思われる遺跡が発見された。「経塚」とは、寺院の裏山に壷を埋め、その中に納経した場所をいう。これは主に平安後期のものであり、出土品は青白磁・銅銭・鏡などである。
長福寺跡
高田山の峰の並びにある「寺の峰」の中腹に元長福寺跡がある。ここは明治の廃仏毀釈によって廃寺となり、その後、現在の大津の場所に復興された。
店数
高梨・松浦
トピック
田園地帯
小向と大津の間にある西ノ島では最も広い田園地帯がここにある。これは平野があるというだけでは無く、真ん中に豊かな水流をかかえているという意味でも田園地帯である。「美田」という地名もここから生まれたものではなかろうか。御腰掛けの岩
後醍醐天皇が黒木御所を御脱出になる途中、美田を通りかかり、小向の面屋(木村家)が耕作していて天皇の難渋を見かねて、背負って自宅に御案内申しあげ、庭内にある大石でしばらく御休憩になられた。それから船を仕立てて赤之江の赤崎に停泊していた伯耆の船まで御送り申上げたと伝承されている。その石を「御腰掛けの岩」として今にある。その時の礼として天皇から愛染明王像と鳳乳石とを賜り、木村家に伝えている。
美田小学校
現在波止・市部・大津・小向・船越を学区とする美田小学校の校舎は大正一四年に建築され、島根県最古の木造校舎といわれるほど頑健な建物である。雨の日には「かけっこ」の練習をするほどの広い廊下があり、室内は親子孫三代が同じ風景が見られる現在では珍しい校舎である。
B&G財団西ノ島海洋センター
昭和六○年五月一○日竣功。ヨット・カヌー・ウィンドサーフィン・ジェットスキーなど青少年の海洋スポーツセンターである。
美田児童会館
昭和五十二年完成
町営住宅 昭和六十二年と平成元年に建設
船越(ふなごし)
旧所属 美田村船越、黒木村船越、西ノ島町船越
地勢
美田湾の最も奥、向かって最も左に位置する船越は、右に小向を接し左は浦郷との境界を持っている。湾の奥は船引運河につながり、その運河は内海と外海を結んで外浜海岸に出て行く。そこからは国賀海岸が始まり、西ノ島に来島する観光客は必ずやこの集落を通り抜けて行くことになる。また湾の最も奥に位置するせいか、津波の時に必ず被害が出るのもここである。外海に近い勢か百二十戸ほどの集落には割合に船が多く、漁業を営むことも多い。
現在、一二組
交通機関
区内施設
公会堂
昭和一○年建設
お堂(万福寺)
高田神社
小向と船越の氏神。祭神は伊邪那岐命(いざなぎのみこと)・素盞鳴雄命(すさのおのみこと)
浦郷漁協美田出張所(旧美田漁協)
昭和四七年に浦郷漁協に合併されるまでは、美田漁協として美田の漁獲物を一手に引き受けていた。
遺跡
来居横穴群
朝山事務所から浦郷に向かって一○○メートル程先の崖から八つの横穴古墳が発見された。この古墳からは須恵器・鉄釘・鉄斧・直刀・土師器・金環等の遺物が出土された。この横穴古墳は物井の初座横穴古墳と同じく、穴の内部が屋根型にくり抜かれているのが特徴であり、島前教育委員会の指定文化財になっている。
ニタキ横穴
浦郷と船越の間にある赤灯台近くの穴から須恵器が発見された。
犬遺跡
朝山事務所から山手に向かって少し入った場所から黒曜石片が発見された。
西ノ島中学校敷地内遺跡
現在西ノ島中学校が建っている場所から土師器が発見された。
店数
トピック
安達家(味噌屋)
島前の近世・近代漁業をリードしていた安達家は、越前国より元禄時代頃から船越に来て鯖網漁業を営んでいたらしい(家譜)。以後仁太夫の代になり、正式には享保二〇年(一七三五)に船越に定着している。この鯖網(四ツ張網)が隠岐での最初の四ツ張網と言われる。
シャーラ船
西ノ島の盆の風物誌であるシャーラ船は、元々今の様に大型では無かったが、明治三○年ごろ能儀郡から来た坂口某という船越の堂の住職がこれを公案し、集落共同で大型の藁と小麦藁で仏を送るのが発端であるとされている。それ以前は集落の各戸が供物を一斉に海に流したので、海岸が不衛生であり、これが原因で疫病が蔓延したという。この方式は波止・市部・大津・小向・浦郷・珍崎・三度にも伝播し今に至っている。
露人墓
日露戦争の日本海海戦の折り、敗北したロシア人が流れ着いたので、その墓がこの集落の墓所に祀ってある。
船引(ふなひき)運河
大正四年に美田湾と外海を結ぶ運河が建設され、西ノ島の漁船はこれによって効率のよい漁業を行える様になった。それ以前には船を引っ張って移動したのであり、地名も船引。そこから「船引(ふなひき)運河」と命名されることになる。船越という地名も元々は、これに由来するものと云われている。
外浜
美田湾から船引運河を外海にぬけると、隠岐島では珍しい三○○メートルくらいの砂浜の海岸があり、そこを「外浜」と呼んで夏には海水浴客で賑わう。
西ノ島中学校
元の黒木中学校と浦郷中学校は、昭和四五年に竣功した西ノ島中学校に統合され、船越の運河の近くに建設された。
町営住宅
昭和五一年には六戸、五四年には県営住宅(後に町営に移管された) 一六戸建ての住宅が建設され船越の戸数は一五四戸から一八○戸へ、人口は五二三人から五四四人に増大した。
- 観光前史
- 西ノ島観光のはじまり
- ピークの四十年代
- 変わる観光形態
- 観光地一覧
観光前史
いつから、西ノ島が観光の地として意識される様になったのかは定かではないが、以前は観光というのは名所・旧跡巡りを主とした地方巡り、という意味合いが強かったともの思われる。古記録においても、国賀などを記してはいるが、ここに何々がある云々という具合に、淡々と地名の記録に止めている程度である。(隠州視聴合紀・隠州視聴記・増補隠州記・隠岐記等)
旧来、名所と呼ばれたのは黒木御所・焼火権現・文覚窟など、神社仏閣・史跡が中心であった。このような社寺仏閣・史跡巡りの観光は、少なくとも明治二十五年までは続いている。明治二十五年に隠岐島を訪れた小泉八雲の旅程スケジュールには、国賀は入っていなかったし、彼がここを訪ねるガイドブックとして使用した「島根県管内隠岐国地誌略」(明治十二年発行)にも国賀は記述されてはいなかった。
自然景観の様に由緒を伴わなくとも、それだけで鑑賞に値する、景勝地としての「観光」の兆しは案外に新しく、西ノ島では明治四十二年が最初ではなかろうか。「知夫郡浦郷村情況調査書」には国賀を次のように紹介している。「・・又、本村字本郷より離るること三十町あまりにして、字国佳(国賀)と称する海浜勝地なり海岸、及び所々に点在せる島嶼はすべて奇岩怪石よりなり、風景絶景なり、もし天朗にして波静なる日一葉の小舟に棹して此地に遊べば俗塵を離れて壮快の気、自から禁ずるにあたはず、故に当地に遊ぶ者は必ず足を此地に入れざる者なく、本村における名勝地として挙ぐるに足るべき勝地なり。」
昭和初期には隠岐汽船社長であった安達和太郎は、当時としては型破りと思われるくらいに観光を強く意識した船として隠岐丸を建造している。船に対する注文の第一は、壱等室、貴賓室、喫烟室等の施設の重要性、次に客室の窓を四角く大きくした。(当時は普通の船は小さく丸い窓であった)、また第二隠岐丸は客室を広くするためディーゼルエンジン(当時、小型船のディーゼルエンジンは少なかった)にした。実際に処女航海の段になると大阪毎日新聞主催の観光団体を招いて乗船させ、隠岐島の観光宣伝にこれ努めている。
しかし、一般的に本土の人に知られるきっかけになったのは、昭和七年(一九三二)島根県観光協会から委嘱を受けて、河東碧梧桐(かわひがしへきごとう俳人)が、視察の任に当ってからである。彼は、その視察スケジュールに隠岐が入って無かったのを不思議がり、急遽、隠岐島を視察地に入れた。河東碧梧桐は、この事を東京に返り中央公論に発表した。それから文化人が隠岐に詰めかける事になる。当時ここを訪れた理博士・脇水鐵五郎は「明暮の岩屋」「摩天崖」という地名を命名した。昭和一三(一九三八)年には国指定名勝天然記念物指定地に指定された。
浦郷では、昭和二十年に町営旅館を開設したが、これは沢野岩太郎氏が役場庁舎に寄付するため菱浦から購入した建物で、町は氏の承諾を得て旅館に改築し運営を崎津繁男氏に委託した〈現在の鶴陽旅館〉。昭和二十二年、桜井伊勢太郎氏が率先して観光協会(浦郷町観光協会か)を設立し、自ら事務所を自宅に置いて国賀の宣伝・案内に努めた。
西ノ島観光のはじまり
昭和三〇年代初期には観光客は徐々に隠岐に入ってくるようになったが、その数は今ほどではなく、まだまだのんびりとしたものであった。観光の客は増えてもそれを運ぶ隠岐汽船は夜航海で、夜中に境港を出発し、早朝に島前へ到着。船も岸壁に着岸できないので、沖に停泊している処へハシケで輸送した。船への乗り降りは暗い時間に限られていた。船が着くと暗い港で客の案内や宿の手配をし、また、夜中に船に乗り込ませる。観光の係りは寝る暇もなく応対に追われた。 当時の観光客は全体的に若い世代で、特に学生たちは足にはキャラバンをはき、背中にはリュックを背負って、歩くのは当然という出で立ち。そういう意味では、島民の「よそ行き」の格好とは正反対だったのが当時の若者の旅行姿であった。
昭和三八年に大山隠岐国立公園に指定されると、観光客は急増した。当時の状況を振り返って坂本勲氏はこう回想している「この年から隠岐を訪れる観光客のイメージは一変し、相当年配のお年寄りは勿論のこと、ハイヒール姿のモダン女性、又は和服姿の中年女性、そして男性のほとんどは背広(スーツ)姿といった、全く予想もしなかったお客さんのスタイルに、ただ驚くばかりでした・・」 この年には、おきじ丸も就航し、ようやく昼航海もはじまったが、夜と併存していたので受け入れる側にとっては忙しさも倍加した。隠岐での観光時季は夏に限られ、そこに集中して客が来島するものだから、いつも混み合った。
昭和三九年には国民宿舎国賀荘も完成したが、それでもすべてすべてを補えるものではなかった。短時間で多くの場所を見物し、しかも安いコストであげる旅行が多かった。こうした客に応えるために、民宿・ユースホステルという手軽な受け入れ施設が、民間の力によって徐々に充実されていった。西ノ島に来て国賀と海水浴だけでなく、民謡をもって歓迎しようと地元の有志が集まって「キャラバン隊」が結成されたのもこの年であった。
ピークの四〇年代
昭和四〇年大浜町長が姿勢方針演説で「漁業・観光・牧畜」を西ノ島の三本柱とすると発表。この年に島後では隠岐空港が開設され、西ノ島では春に第一回目の「国賀びらき」が開催された。翌々年には観光宣伝として西ノ島町を国賀町に変名するという話題が議会で検討され、町は観光で一色に染まった。国賀巡りの観光船は多数をきわめて、隠岐観光株式会社が設立されたり、皇太子殿下、同妃殿下(現天皇)が国賀や黒木御所を訪れたのもこの年であった。
昭和四三年から四七年にかけて、国賀レストハウス、鬼舞スカイライン、国賀港完成、別府港に観光センター建設、初のフェリーボート「くにが」就航など矢継ぎ早に観光施設が整って行き、ついに四八年にはピークの一七万人の観光客が西ノ島に訪れた。当時は国鉄のキャンペーン「ディスカバージャパン」が全国に浸透しており、都会から田舎に旅するのは若者のファッションでさえあった。
変わる観光形態
昭和五十年代に入ると、隠岐汽船はフェリー「くにが」に次いで「おき」「おきじ」を建造し、五十八年には高速船「マリンスター」が就航して、船の大型化と高速化が図られたが、観光客数は減少した。
この頃から日本の観光は海外に目を向け、若者は海外に行く傾向が顕著になってきた。一方、国内旅行は旅行業者によって中高年を主体とした団体旅行が組まれ、国内の観光地は老人で賑わっているのが一般的な光景であった。隠岐はある意味では中央に知られ、横溝正史原作の「悪霊島」のロケ地として西ノ島が使われた。
ピーク時には個人もしくは少人数の旅行が多かったが、段々と旅行業者を中心として団体旅行が大きい割合を占め、客層も若者から中高年へと変わっていった。
六十年代になると、ただ景色を眺めるだけでなく、若者を対象とした観光が意図され、「参加する観光」が企画された。昭和六十年、初の体験学習を中心とした修学旅行が誘致され、東大阪市の生徒が二七二人訪れた。この年には西ノ島海洋センター(B&G)が開設、ファミリーマラソンも開催された。以後、オキ・アイランド・トライアル、耳浦キャンプ場、マリンパーク弁天の開始など、イベント参加型観光企画が展開されていった。
観光地一覧
国賀(くにが)
船引運河をぬけて、左側の海岸沿いに三度(みたべ)まで進む行程を国賀海岸という。国賀という地名は、一六○○年代にも、記録されてはいるが、いわゆる景勝地としての国賀では無い。単なる字名である。古くから「浦郷村と美田村の海の境界争いの時にどこそこの松が、その境線である。」といった具合に・・・。即ち、国賀の、海は漁場であり、陸は牧畑であった。当時の国賀の風景は、陸には、秋になれば麦がたわわに稔ったり、その後を牛が草を喰む姿も見えたし、海にはカナギや漁船が浮かんでいたであろう。
ゴルフ場の様な今の風景は、昭和三八年の離島草地開発事業に端を発している。国賀が「緑の草原」というイメージは、そこから始まったといっていいだろう。それまでは、牧畑なので、大麦・小麦等々の穀物を生産しながら牛馬を放牧する牧場であった。(牧畑参照)
観光地としての国賀は、昭和初期から一部には知られていたが、産業を成り立たせるほどの脚光をあびるには昭和三八年の国立公園化を待たねばならない。それまでの日本の観光は、名所・旧跡・史跡(神社・仏閣)が主であって、単なる自然景観のすばらしさだけでは観光の対象とならなかった。魔天崖(マテンガイ)はトノヅ。通天橋(ツウテンキョウ)はマドジマ。鬼ヶ城(オニガジョウ)はオンガツメと地元民に呼ばれ、漁場の目印、もしくは単なる字名であった。 昭和三八年以降、夏場にはひっきりなしに観光船が往き来するに至って、元々の字名よりも、国賀の名所としてのいわゆる観光名の方が、一般に知られるようになる。国賀という名前に至っては、旅館名・観光船名・隠岐汽船の船名、最後には町名変更の話題にまで発展することになった。
国賀観光の遊覧船は、昭和二四年、重谷乙郎氏によって開始された。次に三四年西ノ島町観光協会が設立され、三六年には、国賀のキャンペーン民謡「国賀ドント節」がレコード発売、大山隠岐国立公園指定の三八年には浦郷から国賀に道路が開通し、陸上からも観光可能になった(この道路が西ノ島町初のアスファルト道路となる)。本格的に観光客が訪れたり船が頻繁に往来するするのは、昭和三八年の国立公園指定頃からで、この年には、隠岐汽船も「おきじ丸」を造船。次の年からは、国民宿舎「国賀荘」、隠岐民謡観光キャラバン隊結成など、この町は観光に向けて一斉に走りだした。今日の隠岐島観光の代名詞として国賀はある。
黒木御所(くろぎごしょ)
別府湾に位置する小高い丘の頂上にあり、後醍醐(ごだいご)天皇が配流されて、約1年お住まいになられた場所であり、昭和三三年には県指定の史跡に指定されている。平成三年からNHKの「太平記」が始まり、脚光をあびるにいたった。関連の史跡としては、三位の局館跡・判官屋敷跡・千福寺跡・御腰掛けの岩・赤崎がある。(写真挿入)
局屋敷
三位局(さんみのつぼね)(本名は藤原廉子)は、天皇につき従ってこられた女性の一人であり、その御方の屋敷跡と目され、別府の坪ノ内(つぼのうち)という場所にある。
(写真挿入)
判官屋敷跡(はんがん)
貞永元年(一二三二)・島前三島を管轄する役所のあった場所。
御脱出の折りの隠岐の守護
大名は佐々木清高であった。その屋敷跡とされるのが、別府のニシノイエという場所にある。
(写真挿入)
千福寺御座所跡(せんぷくじござしょ)
別府の道場ノ前(どうじょうのまえ)という場所にあった、後醍醐天皇の行在所に充てられ、天皇の御守本尊毘沙門天絵像を奉安して、ご冥福を祈ったと伝えのある寺院である。
(写真挿入)
御腰掛けの石
小向の木村氏(面屋)の敷地内にあり、天皇御脱出の折り、乗船までのしばらくの間、御休憩されたと伝えられている。その時に拝領したという「愛染明王懸仏」を今も伝えている。
(写真挿入)
赤崎(あかさき)
赤之江から珍崎に向かって少し行ったところに、後醍醐天皇が船に乗って脱出されたと云われる場所である。ここに伯耆国(今の鳥取県)の船が天皇をお待ち申上げ、無事に知夫港に御到着になった。
(写真挿入)
浦郷町史から抜粋(島根県口碑伝説集から)
赤崎の伝説
佐々木隠岐判官のこと元弘の昔、後醍醐天皇隠岐に遷幸あり。別府村黒木御所に行在中、北条高時の下知により、浦郷村字城山と云ふ塞を構え、佐々木隠岐判官之に在城し、又同村字番屋と云ふ所に番所を設け、遠見番を置く等防備頗る厳重であった。されど判官の心中には、如何にしても密かに、内地に送り奉らんと思って居る。時恰も浦郷港字赤崎という所に伯州船が碇泊していた。是れ正しく天幸なりと。二人の密使を選んで御所に忍ばせ、元弘二年壬申八月一日、天皇を密かに送り奉る。美田字宮崎と云ふ所までは、陸路を背負ひ奉り、それより御船に召され、浦郷港碇泊の伯州船へ遷し奉り、御船は密かに漕ぎ出でた。皇船の港を離るること、凡そ十余里の沖合に出でさせ玉ふ由を番所より注進に及び、判官は大いに驚いた面持ちで、片時も早く追船を漕出せよと船夫等に命令し、数隻の船を揃えさせ追い掛けたけれど、順風に真帆を上げたこととて、皇船は走ること矢の如く、影も見えずなって、追っ手の船は空しく引き返した。(島根県口碑伝説集)
赤之江の地名伝説
元弘の昔、後醍醐天皇小向の里から小舟に召されて、今の入江を赤崎の岬に急がせられる際、過って笏を海中に取り落とされた。それから此処を笏の江と称えたので、後世赤崎の赤を入れて赤之江と訛したものである。当時の御製として、
幾度か思い定めてありながら
夢やすろはぬ赤崎の宿(夢さすからぬともあり)
朝な夕な民やすかれといふだすき
かけて祈らん茂理の社に
など古老の口に語られている。この第二に「朝な夕な」の歌は松浦静麿氏の説によると、西郷町の流人となって在住した樋口功康作の歌であるとの事である。
焼火神社(たくひ)
焼火山の中腹にあり、明治以前は焼火山・雲上寺であった。一般的には焼火権現として知られる。縁起は、十二月三十一日の夜中に海中から三つの灯が上り、それが現在社殿のある、巌(いわや)に入ったことから焼火権現が始まったとされる。平安時代から全国に海上安全の神として知られ、安藤広重・安藤広重二代目・葛飾北斎も諸国百図で焼火権現を描いている。現在でも旧暦の正月中には、ハツマイリといって島前の島人がこの神社にお参りする風習が続いている。
(写真挿入)(版画挿入)
〈隠岐・焚火ノ社 北斎漫画〉
国指定重要文化財 焼火神社本殿・通殿・拝殿
国指定重要民俗資料 ともど舟
県指定有形文化財 銅鐘
県指定天然記念物 焼火神社神域植物群
町村指定(史跡) 焼火神社社務所石垣
町村指定(有古) 紙本墨書・焼火神社縁起書
町村指定(有古) 紙本墨書・沙門良源勧進帖
町村指定(天記) カラスバト繁殖地
町村指定(天記) カゴの木
文覚上人(もんがくしょうにん)
「平家物語」「源平盛衰記」などに登場する僧侶で、数回にわたって配流され、最後にはここで全うされた。一回目の配流(遠島・島流し)は伊豆諸島であり、そこで源頼朝と知り合いになり、平家討伐の切っ掛けを作ったとされる人物である。頼朝が鎌倉幕府を開幕してからは、大勢力をほこったが、頼朝の死去にいたって、中央から排除され、最後に隠岐島に配流れたと伝えられている。文覚窟は、波止と大山の中間の海辺にあり、現在は交通手段がない。(写真挿入)
外浜海水浴場(そとはま)
西ノ島を結果的に二分する、船引(ふなひき)運河をぬけると右手には隠岐島では珍しい砂浜、外浜海水浴場があり、ここは国賀海岸の入口でもある。ここの砂は、貝の小粒が寄り集って出来た砂浜といえる。(写真挿入)
鬼舞(おにまい)赤尾(あかお)スカイライン
鬼舞=昭和四四年・赤尾=昭和四八年完成。 西ノ島町の西側の山頂を通過する鬼舞・赤尾スカイラインは、外海と内海 を同時に見渡せる山頂道路で、まだ3分1は、舗装されてはいないが、 オキ・アイランド・トライアルなどの出場者にはそれが、荒らされていない 印として好評がある。(写真挿入)
西ノ島海洋センター(B&G)
B&G(ブルー・アンド・グリーン財団の略語)は、本来は地元の子供にとっての施設であったが、ヨット・ウィンドサーフィン・ジェットスキーなど、マリンスポーツに欠かせない施設があるため、体験学習生徒・一般観光客にも開放されるようになった。
観光イベント
ファミリーマラソン
昭和六○年(三月三一日)・六一年(四月二九日)家族も一緒に参加する形式のマラソンが、この年から西ノ島町で開催され、浦郷・別府間がそのコースとなった。町おこしイベントで、島外者を多く想定していたが、案外に町民参加者が多数参加して、賑わった。
(写真挿入)
オキ・アイランド・トライアル
昭和五九年五月四日開始されたオートバイの全国大会。トライアルとは、傷害物のある一定区間をオートバイで通過し、いかに足をつかないかという競技である。
西ノ島町制三十周年記念事業の一環として、西ノ島町・商工青年部・観光協会・青年団・トライアルクラブひぐま、の五者が主催となり、北は新潟・南は熊本から一三二人の参加者を集めて開催され現在に至る。
(写真挿入)
修学旅行誘致
昭和六○年に関西地方を中心に体験学習と称して隠岐島特に西ノ島 に都会から修学旅行生が訪れるようになった。東大阪の高校生二七二人
(写真挿入)
観光客数推移
観光の統計によると昭和三七年(一九六二)には、約九,○○○人、 昭和四八年(一九七三)には、ピークの一六五,○○○人に達し、そこからは 序々に下降線を辿って、今(平成二年)は昭和四五年(一九七○)と同様一○万人に至っている。(黒棒は西ノ島、白棒は隠岐島)昭和三、四○年代は若者が多く、五○年代に入ると壮年・老年主体の観光地となっている。
参考文献
「島根県管内隠岐国地誌略」
「知夫郡浦郷村情況調査書」
「知夫郡黒木村情況調査書」
『浦郷町史』
『黒木村誌』
「島根県口碑伝説集」
「隠岐の文化財」
『観光の事始め』
黒木御所ー後醍醐天皇行在所はどこかー
一、序
日本が国として統一され、国郡制も定まり、法(律令制)をしいて国の行政機関がととのった。その頂点にあるのが天皇家であった。
この体制は奈良から山城(京都)へと都が移ったいわゆる「平安時代」まで続いた。この時代までの武家は、身分は低くそれぞれの本拠地の地方から召し出されて、都の治安に当たるのがその任であったが、武家の平氏は本拠地を都に構え、徐々に力をのばして官職も藤原氏にとって代わるまでになっていった。
これに対して同じ武家である源氏は、内々に皇家の命を受けて平氏を滅ぼした(文治元年 一一八五)。これで平安時代の体制になると思われたが、源氏の頭領であった頼朝は、本拠地を関東の鎌倉に置いて幕府を開いた。
ところが武家の棟梁である、源頼朝は鎌倉に本拠を置いて幕府を開いた。
それまでは武家でも天皇から官位をいただき任命されていたが、幕府が出来てからは、各国々を治めるために「守護・地頭」を設け、天皇の任命による「国司」があるにもかかわらず、幕府が権力によって勝手に任命するようになった。いわば国を治める為の権力が二重構造になったわけである。(武家法の制定)
そこで後鳥羽天皇は国の統治を以前の姿に返すためには、幕府を武力を以て滅ぼさなければならないと決断してこれを決行した。いわゆる「承久の変」(一二二一)であるがこれは失敗に終わった。
それから約百年後、後醍醐天皇が再び倒幕を決行したがこれも成功せず両度とも幕府(武家)によって天皇は隠岐国に遷される事になった。しかし、これによって天皇家を無くそうというわけではなかった。武家方の考え方は、自分等は何も天皇家を滅ぼす為に武力を用いるのではない。天皇の方から武力を以て我々を滅ぼそうとした。(武家方は天皇御謀反と呼んでいる)だからそれに対して武力を以て立ち向かったわけである。いわば武家にとっては死活問題であるから当然であるというわけである。戦いは武家方の勝利によって終結した。そして、その戦後処理として両天皇は「隠岐国へ御配流」させられた。
二、問題の発端
後鳥羽・後醍醐両帝は何故「隠岐国」へ御配流と決まったのか。それは武家が権力を持っても法治国である事に変わりは無いから「律令制」の規定によって執行したのである。その規定の中で死刑の次に重い刑に「配流刑」があり、遠流の国として「隠岐国」外五カ国が定まっている。後醍醐帝の時は、後鳥羽院の前例があるので、これに準じて執行されたのである。ところが「隠岐国」と規定されていても配流地の中の何処にするかという事までは規定されていないから、その決定にあたっては、おそらくその地の守護の意見を聞いて決定され、その監視の責任は守護にまかされたのである。
したがって当時の幕府の記録には場所もはっきりしているはずであるが、配流先は「隠岐国」とのみあって大体の記録からでは詳細な場所を特定することはむずかしい。それは、その地の遺跡と伝承による外はない。
後鳥羽院の場合でも記録で地名の出るのは「吾妻鏡 巻二十三」に
「八月五日丙辰上皇遂著御平隠岐国阿摩郡刈田郷」とのみあって「源福寺」という事は出ていない。後醍醐帝の場合も中央の記録に出るのは「増鏡」に「海づらより少し入りたる国分寺という寺をよろしきさまにとりしひておわします所に云々」と「太平記」に「府ノ島トイフ所ニ黒木御所ヲ作リ皇居トス」と出ているのみである。
これを書いたのは隠岐の地理を詳しく知らない者の記録であり、又これを読む者も「国分寺」も「黒木御所」も同じ場所にあるくらいにしか考えなかったであろう。
ところが後世になって、この事を研究するために現地に来てみると「国分寺」は島後にあり「黒木御所」は島前・別府の地にあることがわかり、それではどちらが本当であるかという事が問題となるのである。
これを問題としたのは中央の歴史学者である吉田東伍博士である。明治三十五年に発行された『歴史地理』への発表が、この問題の初まりである。次いで明治四十年代に県史編さん者の野津佐馬之介氏が県史によって国分寺説を発表した。 これに対して、島外では後藤蔵四郎氏、島内では松浦静麿氏、藤田一枝氏等が研究を発表して国分寺説に対抗した。現在のところ藤田氏の論考より研究は進んでいないのでこれを要約して紹介し、それに私見を加えて述べることにする。
三、島の伝承と内地の記録
先ず初めに「国分寺説」の根拠になった史料は(一)増鏡
(二)送進鰐渕寺文書等目録の二点である。
国分寺説を説く研究者は右を根拠にして、それに江戸期の文書も入れて論ずるのであるが、ただここで一番問題になるのは「国分寺」にはこれに関する伝承のないことである。
これに関して藤田氏は『行在所問題に於ける伝説の占める比重について』の一項を設けて「池田の国分寺がその昔天皇の行在所であったとしたならば、一カ年近くもの間、天皇行在所であったと言う、その寺、その土地に何故そうした言い伝えが残らなかっただろうか(中略)」「それは今日や昨日に無くなったのではなく寛文七年(天皇御脱出後三百三十四年)には既になく、更に遡って永正四年(一五〇七)(天皇御脱出後百七十四年)に既になかったと信ずべき理由がある。歴史家という科学者は「伝説」を軽視する。そして「書き物」を過信する。 隠岐に於いて六百年前の古文書を持ち続け得ない事は島の経済力の貧しさによる。
しかし一世を転倒した日本史の大事件のしかもその主役である天皇が約一年にわたる間住まわれたという寺、しかもただぼんやりと余生を送られたと言うのでなく、心中深く回天の構想を練って、苦悶の日々を送られたというその土地に、しかも万人の予想を裏切って「脱出」という大ドラマを演出されたその発足の地に、百七十四年後に既に伝説も何も消えてしまうという事があり得ようか。事、天皇に関する限りただ一時の腰の疲れを癒されたと言う「腰掛の石」一つさえ注連縄を張り廻らし言い伝えられて来た時代に、一年の御生活は民衆の語り草となって物語が残されるほどのものではないか(中略)」
「隠岐国のどこにもないにもかかわらず、何故黒木にのみ行在所とその御脱出にまつわる伝説が数百年にわたって豊富に語りつがれ、又、それに関連する遺物が種々伝来したのであろうか。しかも北朝の天皇が皇統を伝えた時代に「現世利益」に何の効もない後醍醐天皇を神社に祀り、崇敬の祭祀を維持し来った。数百年の史的事実を如何に解釈すべきであるか。島後の「国分寺」を行在所とするならば右の如き歴史的事実に対して心有る者は先ず首を傾けざるを得ない。
問題は「黒木か国分寺か」ではない。「隠岐にある伝説」と「内地の記録」の矛盾とをどう調整するかの問題である。
同じ問題に関して「黒木」と「国分寺」両方に数百年来持ち続けた伝説があって、その何れが本当であるかを比定する場合に、海の彼方の史料によって、その一方が真実である事を立証する事は可能である。真相はそうではない。隠岐における伝説は唯一つである。他には何もない。そして、それに対立する資料は内地において、内地の人が書いた文献である。古文書偏重の史学っ[古文書に書かれた記事は一言一句真実である。古文書の支証がなければ総て否定すべきであるとする態度は、地方史を研究する場合には考えねばならぬ態度である。(中略)」
その記事が島の現地を実地踏査した者が書いたかどうかが問題である。現代においてさえ、島に現に来た学者の中には内地へ帰って隠岐の事を書いた文章の中で地名錯誤を冒している例がいくらでもある。』これも数百年後の者がみた場合にはそのままに事実として使うのである。
四、島後に伝承のないわけ
「後醍醐天皇が「国分寺」においでになったのを我等の祖先が忘れて、あるいは間違えて「黒木の御所」においでになったと言い伝えて数百年信じて来た。それを今また内地の人に教えられて思い出したなど、およそナンセンスではないか(下略)」
まったくその通りであるが、しかし研究には文献があれば先ずそれにより、「黒木の伝説」の存在する当然の理由、また国分寺に伝承のない事の当然の理由に対する例証を挙げるのが順序である。
後鳥羽院が隠岐に御配流になって行在されたのは当時刈田郷にあった「源福寺」であった。行在所が国分寺であるなら、当時「国分寺」が立派な建物として実在していなければならない。そこで藤田氏は「国分寺の衰退」の資料を挙げて証明しておられる。その資料として国分寺復興のことにつとめられた権少僧都憲舜が書き残した「国分寺再興置文之事」を挙げている。、今はその原本はなく、写本が残っている。
これを全部引用すると煩瑣になるので、その内容を要約すると、「国分寺は
(一)推古天皇の建立
(二)聖武天皇の御再興
(三)安徳天皇の地蔵堂御祈願のこと
(四)後鳥羽院の三重塔婆の御祈願等々
と述べたすぐ後に「爰(ここ)ニ本堂久シク大破ニ及ビテ棟梁柱根皆以テ朽損シテ更ニ修造ノ便ト成ス可キ様ナシ」と国分寺本堂大破の模様を書き列ね、再興にあたって思い切って遺構に大改変を断行。「本堂ノ屋根ヲ塔之下ニ引下シ、本堂之跡ニ地蔵堂ヲ立テ、始メテ本堂ノ屋敷ヲ引ク」とある。
天皇に関する由緒を書き並べながら
(一)後醍醐天皇に関する事が一つも書かれていない
(二)現在国分寺の創建の本堂跡として保存されている礎石の配置は、奈良時代の国分寺創建の遺跡でなく、憲舜が改造した時の礎石の配置である。」
以上のように、後醍醐帝の時代には衰退の極にあったと思う。右のようであれば既設の「国分寺」を行在所にするわけはない。
五、伝承の記録
地方(じかた)文書で、後醍醐天皇の事にふれている最も古いのは、「隠州視聴合紀」(寛文七年 一六六七)である。著者斎藤勘助は、寛文七年秋より八年の秋まで「郡代」として隠岐に赴任・在住した。彼は赴任早々に島前・島後と隈無く歩いて詳しくその見聞を書き残した。
今「国分寺」の項と「別府」の項をあげると
国分寺
「国分寺村は東山の間、平村に対せり。寺は昔伽藍にして当国の第一なり、西の翠微を禅尾と言ふ。故に寺を禅尾山と号す。本堂に入る所に二王門あり。堂前は高原にして四顧空闊なり、老樹処々に在りて野草芳微たり。院は東の山下にして、左右松杉日を蓋ひ青苔自ら塵なし、山旁々に囲み、渓水湲々と流来る。籬を遶りて三径微なり。院は漸く古りて香煙靡くばかりなり。寺僧伝へて曰く、賊徒乱入の時、経書に縁起を交へ奪去って絶へけらし。昔より只伝へて真言の法を修す。又昔の勧進帳あり。其略に曰く、本堂は聖武天皇の時に造立す。西の側の地蔵堂は安徳天皇の時に営す。三重の塔婆は後鳥羽院の時に作るとなり。又永正四年の頃、阿闍梨権少僧都憲舜という僧、此寺の廃破を哀しみ、時の県主新五郎宗清に請ふて近国に奉加を勧む。其奉行は宝定寺若狭守重高、村上信濃守清景とぞ、然るときは其美なる知るべし。禅尾を隔て一村あり。南山を登れば有木村に至る左の岡に尼寺あり。西に出づれば大道あり、所謂山道筋なり。」
別府
「府より北の山崎を黒木という。伝に曰く。昔後醍醐天皇しばらく狩し玉へる所なり。故に今に到りて黒木皇居と云ふ。北の方海に随ひて東が崎と云ふ所を過ぐれば、北の山を香鴨といふ、寺ありて香鴨寺と号す、其崎を廻り行けば、十四町ばかりにして宇賀村に至る。」
さらに詳細な「隠州記」(貞享五年 一六八八)の国分寺の項をあげる。
「禅尾山国分寺 真言宗 寺領五石 釈迦薬師 弥陀三如来 是ハ人王三十代欽明天皇御祈願所ト言伝也。四天王寺有、仁王門在、其他寺家六坊在(中略)三重塔、鐘楼堂ハ絶テ今礎石バカリ残ル。此寺ハ五年ニ一度蓮華ノ祭トテ本堂ノ前ニ舞台ヲ設テ笛、太鼓ヲ奏シ児童再三出テ舞曲ヲ成ス、寺僧数人出テ色々ノ舞有リ。獅子舞、田楽有リ(下略)「山王権現、熊野権現、池畦大明神、八幡宮、清滝権現」
右の記事によっても、国分寺内に後醍醐天皇に関する何の伝説もうかがうことが出来ない。現在国分寺境内にある後醍醐天皇の祀堂といわれているものは後人の付会であって、ここにある山王権現か、明治二年当時にあった東照宮の祠であろう。(「島後神社巡察日記」)
後醍醐天皇の行在所のことは二書いづれも「別府」の項に記されている。
煩瑣になるので以下資料の主なるものをあげておく。「隠州視聴記」「隠岐往古以来諸色年代略記」「隠岐古記集」「一宮巡啓記」等のいづれも島前の別府にあると記されている。松浦静麿の「黒木御所史料輯録」に掲げた資料の外に、藤田氏の発見になる「宇野家家譜」(宇賀、宇野家蔵)の中に行在所の位置についての記述があるので掲げる。これも江戸期の写本であるがこの文書の内容からして書かれた原本の年代は暦応元年(延元三年 一三三八)からあまり遠からざる年代であろうと藤田氏は考察しておられる。
「正慶元年壬申三月二十三日、字中原申エ御遷幸有、之処ニ農三軒、與次郎、房次郎、清九郎、同夜與次郎屋ニテ一宿(中略)同二十四日勝丸ノ宿ニ御光遷被遊、中ノ原ヨリ二町東。
同二年酉ノ春二月十八日朝美田ノ津ヨリ御帰有(中略)暦応元年寅七月守護楠正行送リノ御号地名與次郎処ヲ御壷ノ内中場ト申処ヲ王城と申外黒木御唱(下略)」とある。
六、国分寺説の根拠
島前黒木説の資料はこれくらいにして国分寺説の決め手となった資料をあげ、検討することにする。これは藤田氏の考究である。
これは詳しく資料の全文をあげるのが本意であるが、長くなるので要点のみをあげることにした。
元弘二年(正慶元年)八月十九日後醍醐天皇は隠岐行在所より出雲国鰐淵寺南院に対して左の願文を送られた。
発願事(書き下し)
「右心中の所願疾に成就せしめば、根本薬師堂の造営急速に其功を終へ顕密の興隆を致すべき之状件の如し
元弘二年八月十九日(花押)」
天皇は「心中の祈願成就」のために鰐淵寺のみならず隠岐島内の諸社寺へも祈願のあった事は島後都万「天健金草神社」の縁起にも記載されており、その一端をうかがうことができるが、今こうした「御願文」は島内各社寺には残っていない。
さすが出雲の名刹鰐淵寺である、天皇の「御願文」を今に伝えている。これを受けた僧頼源は、貞治五年(一三四九)三月二十一日の時点において老衰のため余命いくばくもない状況下に自ら拝受し保管中の文書数十通を浄達上人にゆずり永く後生に残さんことを期した。その譲渡文書の目録の中の注釈的記述が「国分寺説」の支証として取り上げられたものである。
送進鰐淵寺文書等目録事
(張紙)鰐淵寺々務井福院衛門督律師執行自筆法橋筑兼ハ律師御房祇候
後醍醐皇帝
一通 先朝御願書
元弘二年八月十九日於隠岐国分寺御所被下之、上卿千種宰相中将忠顕卿
一通 吉野帝御願書
興国二年八月二十八日於大和国吉野御所被下之、上卿洞院右大将実世卿
一通 同重御願書
正平六年九月八日於同国賀名布御所被下之、上卿四條大納言隆資卿
巳上三通御震筆也頼源賜之
(以下略)(全部で二十二通)
貞治五年午丙三月二十一日
権少都頼源(花押)
浄達上人御房
右のように頼源の花押があるので頼源自筆と考えられていたが、前記のように張紙によって筆者井福院衛門督律師が書き、法橋筑兼が律師のそばに立ち会っていたというのである。
初めてこの文書を発見したのは野津左馬之介氏(旧県史編さん員)だが、野津氏はなぜか張紙のことには触れず、「於隠岐国分寺御所被下之」とあるからには頼源は隠岐の御所にうかがって直接御願文を受けているので「国分寺」が行在所であることは間違いないというのである。「国分寺御所に於て」と解したのである。藤田・松浦氏等は「於て」を「国分寺御所於り(より)」と解して、頼源は隠岐には渡っていないとの見解をとっている。
藤田氏は頼源自筆の「目安状案文」なる資料によって、これには「(上略)先朝、自(より)隠岐御所、去る元弘二年八月、忝くも震筆の御願書を当寺根本薬師堂に篭めらる、依て朝敵滅亡の御祈念を致せらる、程無く翌年元弘三年先代悉く誅伐され畢んぬ(下略)」
右にあるように頼源自筆の文書には「自(より)隠岐御所」と書いてあって「国分寺」と書いてない。
考えるに、監視のきびしい行在所に頼源が伺候して受けるということが実際にはできることであろうかと疑われる。「国分寺説」の決め手となった文書であるので要点のみを挙げて藤田氏の考究された点をあげた。
七、守護職の在住した役宅はどこにあったか
平安時代までは「国司」の役宅である「国衙」は島後にあった。ただしこれが中世期になると主たる役宅は島前の別府に移ったのではないかと思われる。
注置
都万院堺事
四至
東限保土畠 柄峯 西限神船岸 片着石窪
南限座着 神島 北限未路二本椙 焼杉
(上略)那具先頭刑部尉重基父子共彼堺之事致諍令訴訟之時、去貞永元年八月之比常当守護宇賀郷入部時、那具地頭代公文百姓列参之時無異論之由申切畢(下略)
寛元四年丙午九月朔
右の文書は都万院の境界についてのもの(旧島根県史)であるが、その中に「貞永元年」(一二三二)に守護が島後から島前宇賀郷に移ったことが書かれている。何故にこの時代に守護の住居を移さなければならなかっただろうか。それは恐らく承久二年(一二二〇)に隠岐に配流させられた後鳥羽院の監視という事が第一の理由はでなかったかと思われる。であれば海士に移ればよさそうであるが、以前から島前では今の別府の地に国衙の出先の役人の居宅が設けられていたのかも知れない。(後世には郡代は島後におり代官役宅は島前、島後の両方にあった)後醍醐天皇の時代になってもそのまま主たる役所は島前ではなかったろうか。この時代、近江の佐々木氏は出雲・隠岐を兼帯していた。
八、天皇の御脱出
次に天皇御脱出についてもふれておく。「太平記」には御脱出の港は「千波湊」とあり、これは今の知夫港である。
島後国分寺からの御脱出であれば、何故島前の知夫湊を経由して御脱出せねばならないのか。風の方向も本土への場合と島前の場合は方向が異なる。ところが島前の伝承では知夫湊には伝承が無く、西ノ島の赤之江からの御脱出が言われている。これについては松浦静麿は後醍醐天皇一行の御脱出と三位局一行の御脱出の二回があったのではないか。別府から小向(美田湾)に出られたのは同じでも、天皇の御脱出は闇夜に決行され、三位局の御脱出は昼間の出来事であったので、この二回が混同されて伝えられたのではなかろうかと考察している。この御脱出には別府近藤家、美田尻近藤家をはじめ島人等の供奉協力があったと伝えられてる。後醍醐天皇、三位局は同じ場所に場所におられたことは間違いないのでいづれも島前からの御脱出であったわけである。
九、遺物について
後醍醐天皇にまつわる伝承をともなった遺物が西ノ島に残されている。一つは焼火神社に伝わる「後醍醐天皇御勅筆色紙 一幅」というのが寄付帳に記録されてある。寄付主は「別府 近藤十郎の娘 於金」元禄十一年(一六九八)とある。この色紙は「於金」が焼火山快順に嫁した時、引き出物として持参したものを寄進したものである。最近になりこの遺物を古筆学研究所(神崎充晴氏)に鑑定してもらったところ「新浜木綿和歌集」の写本の一部であることが判明した。「新浜木綿和歌集」の歌切は現在七葉発見されており、西ノ島に残されたものは八葉目になるわけである。
「新浜木綿和歌集」の成立は嘉暦二年(一三二七)九月下旬であり、写本である八葉の歌切は、現在の研究結果では同時代のものと鑑定されている。さて、この「新浜木綿和歌集」歌切の筆跡であるが、これは江戸時代の鑑定によると西ノ島にあるもの以外の七葉全て後醍醐天皇筆とされていた。しかし現在では江戸時代の鑑定が正確ものとは認められず、後醍醐天皇の筆跡である事には否定的な判断がくだされている。
「後醍醐天皇御勅筆色紙」というのは近藤家の伝承であり、必ずしも天皇の御自筆ではないのかも知れないが、少なくとも同時代の物には間違いなく、天皇から賜ったとの伝えであるので代々家宝として大切に保存されていたものであろう。
次に小向の木村家蔵の「懸仏」(かけぼとけ)も後醍醐天皇から賜った物として伝承されている。これは南北朝時代に盛んに信仰された「愛染明王」の「香木の懸仏」である。この遺物は未だ鑑定に出されてはいないが、その結果によっては伝承を裏付ける証拠となる可能性が高いものと思われる。
その他三位局屋敷跡、御休憩になられたとされる「御腰掛石」等々、西ノ島には色々な伝承が残されている。
むすび
以上、あらゆる観点からしても島前の別府の「黒木御所跡」が行在所であったのが真相と思われる。ただ、現在、国の史跡としては「国分寺」となっているため「国分寺」が本当であるかのように考えがちだが、研究としては不十分であるとしか言いようがない。国が昭和九年「建武中興六百年」を期に全国の関係地を急遽、史跡として指定した(黒木御所は仮指定)。その頃は専ら「文献史学」絶対の時代であったから、「文献」による研究によって結論を出すのが学者としての在り方で、「伝承」は研究の対象として重視されなかった。
最後に天皇の御詠をあげる。それは天皇家を含め貴族等は自らの心を歌に託する伝統があるからである。この時代の天皇では後醍醐天皇が一番多く歌を残されている。
こころざす かたを問はばや 波の上に
浮きて ただよふ あまのつり舟
(あまは海と海士(中の島)の掛詞)
この御詠は「増鏡」に出ているものであるが、「国分寺」からの景観とは相容れないもので「黒木御所」からの嘱目の御歌として見れば、そのまま現代に生き返り、六百余年の星霜を忘しめるものである。
主な参考文献
「後醍醐天皇隠岐行在所考」 後藤蔵四郎
「黒木御所史料集録」 松浦静麿
「黒木御所について」 松浦静麿
「後醍醐天皇の行在所について」 藤田一枝
(以上は「波の荒磯」に収録)
「島根県史」 野津左馬之介
「帝王後醍醐」 村松剛
「古筆学大成」
「中世歌壇史の研究」 井上宗雄
方言は常に人間関係を内と外を分ける最も解りやすい目印として働いている。地元では隠岐以外の言葉を「よそ言葉・よそ声」と称して区分けし、また島毎に「島後(どうご)弁」「知夫里(ちぶり)弁」ともいわれる。西ノ島内でもさらに浦郷、美田、別府など、最後には一つの集落毎にまで行き着くかと思われるほどに繊細な識別感覚さえある。我々が西ノ島に住んでいる限りは気にならないが、一旦外に移住すると言葉の違いが気を重くさせて他人との会話が巧く運べない経験を持つ事が多かった。しかし、島外に住む郷土仲間にとって、方言はかけがえのない精神安定剤ともなったのである。
ここに生まれ育つと会話は家庭と友達の影響下にあった。学校での言語教育は基本的に文字を書くことと読むことであり、そこではしゃべる事は切り離されていた。
ここ一〇年ほどで特に顕著になってきたのが子供の会話の感覚である。保育所で八〇才の老婆を講師にして西ノ島の昔話を聞かせたところ、園児は地元の方言が理解できずポカンと口を開けていたが、周りで見ていた保母さんや父兄には大盛況であったことが印象深かった。極端な場合、地元の会話にも世代の断絶があらわれてきたと感じた。
この様な変化は突然あらわれたのではなく、その前段階としてマスメディアの浸透と島外人との交流が引き金となって累積され現在に至っていると思われる。
聞く耳の環境
ラジオ放送は日本では大正十四年に開始され、松江の放送局は昭和七年に開局され六十年の歴史を持っている。西ノ島では昭和三十二年に黒木村・浦郷町共に約三十%の普及率であり、テレビが普及するまでの四十年代までは家電製品のトップを飾っていた。当時の全国平均の六十%と比べると約半分であったが、これはただ普及が遅れたというのではなく、それを許さない島の電力事情が背景にあった。電力の増大にともなり、他の家電製品と共に西ノ島ではラジオ・テレビは急激に増大していった。昭和四十年代に入りラジオの聴取料金も廃止になる頃になると、テレビも普及し、ラジオはより小型化・低価格化して個人専用になるまで普及するにいたった。
さて、ラジオの言葉、特にアナウンサーは松江・大阪局といえども方言を使用した訳ではない。番組のなかでの会話は別としても、アナウンサーの言葉は東京弁(下町ではなく山の手の言葉)を中心としたものであった。千キロ以上も離れた隠岐島においてもラジオから流れてくる言葉は常に東京弁であり、現場は知らなくとも、自分でスピーチできなくとも、言葉だけは親しいものとして東京はあった。
生まれてから死ぬまでこの島を出た経験が無くとも、ラジオの普及まで全く他方言を聞いた事がないという島民もおそらく数少ないと思われる。ラジオの普及よりも千年以上昔から他国との人的交流は始まっていた。神亀元年(七二四)隠岐島は配流の地と定められるに至って、以後本土からは流人がこの地に移住する事になる。近世になり、定期的に百人以上の流人が隠岐島に流されることになると、もはや他国の人が珍しいという状況ではない。
近世から近代にかけて流人だけではなく、それ以上大量の北前船が入港した。記録によるとピーク時には隠岐島全体で年間に四千隻以上の船の出入りが数えられている。そうなると、本土の山村などでは想像できないほど多くの方言のサンプルが日常風景としてに島ではみかけられたと思われる。
会話の修練
江戸時代から少しずつこの島の出稼ぎは始まってはいたが、本格的には明治の解放を待って大量の出稼ぎ時代は到来した。北前船の影響かどうか、出稼ぎ先は関門方面から大阪がほとんどを占めた。出稼ぎではなくても徴兵、進学など否が応でも島を出なければならない機会が増え、しかも地元の方言が通用しない場所で暮らすことがことのほか多かった。そういう経験者が少なくても家族の中に一人はいたのである。
戦前には隠岐の子供が大阪などに就職した場合、自転車に乗れなかったことと、会話が思い通りに出来ないことから電話の受け答えができず、職場では能力の低い子供と思われたが、年がたつと徐々に会話ができ、まじめに何でもできるので重宝がられたという。
現在では義務教育から高校を経て島を出る割合は九割を上回り、一時的にもせよほとんどが本土で暮らす経験を持った。西ノ島からは関西へ出ることが多いという状況から、スピーチの修練場は関西が中心になる。テレビ・ラジオから流れる言葉が関西弁ではなくとも、流人、北前船との交流により聞くだけなら全く目新しい言葉ではなかったと思われるが、自分が他方言を使うのは初めてであった。昭和五十年頃からは徐々に関東方面への出郷もはじまり、この方面の言葉はテレビ・ラジオと同じなので理解はしやすかったであろうが、やはり会話にはそれなりの苦労がいった。
方言の変容
地元の内側で起こっている会話のギャップは、ひとつには世代の間に生じている。極端な例では保育所での昔話の様に半分も聞き取れないという事態まで起こってくるが、現在西ノ島の児童が決して方言を使ってないというのではない。方言の度合いが明治生まれの世代と昭和の末に生まれた者では明らかに違うのである。この傾向は核家族化にもともなって、さらに拍車を掛ける結果となろう。
また家族の一員、特に母親が隠岐以外の地域から入ってきた場合は、他方言の無意識なる教師となって働き、家庭内では「よそ言葉」と隠岐弁の二カ国語が飛び交うこともさほど珍しい光景ではなくなってきた。
島から外に出て暮らすときは否応なく言葉が矯正されたとしても、ここではむしろ島外とは立場を変えて「よそ言葉」が少数派であり、隠岐弁が多数派になる。
見る見るうちに方言が変わっていくというものでもなかろうが、十年二十年単位で切ってみるとかなりの様変わりをしていようが、現実に使用している会話が資料化されたことはなく、「隠岐方言」として少しばかりの単語が抽出されているのみである。
具体的に少し聞いただけで方言と解るのは訛(イントネーションやアクセント)であり、この部分がなかなか変容しにくい要素でもある。例え総ての単語が東京のものであっても、隠岐弁の訛で語れば隠岐弁らしくなる。現実には少しずつその様に変わりつつある。そして、少しずつ方言の単語や言い回しは忘れられ、生粋の方言を耳にすることは地元でも希になってきた。
二十代の方言と七十代の方言が明らかに異なる部分は、丁寧語・尊敬語の部分である。二〇代が「いらっしゃいました」というところを七十代は「ござらした」という風に・・。逆に変りにくい部分は仲間・目下の関係で使用する方言である。いづれにせよ、方言は実験室の中で純粋培養されることはなく、常に変化の中にある。
最後に西ノ島の特徴的な方言の一部を列挙しておく。
方言用語例
- 家屋
- ヘヤ
- オモテ
- ナカイ
- ガワグミ 棟上げ・建前
- カド 庭
- オモテグチ 正式な玄関(普通の家には無かった)
- オモ
- ツンをカウ 鍵・錠をかける
- オトシ 鍵の一種
- 食事
- チャノコ 間食
- コジャ 間食
- イモ 薩摩芋
- バラズシ チラシ寿司
- マキ サルトリイバラの葉で包んだ粽
- ヒラ 膳の内で煮染めなどを入れてある物
- ツボ 膳の内でケンチン汁などを入れてある物
- アマガイ 甘酒
- チャクンジャワン 湯呑み
- ハンド 台所にある日常の水が入れてある瓶
- 家族
- オジ 弟
- アッポ 赤ん坊
- ンマゴ 孫
- 共同
- ジゲ 集落・区
- ブラク 集落・区
- ダー お堂
- ジゲシゴト 集落全体の共同作業
- ブ 集落の中の一部の共同作業
- ヤド 会場の提供
- カアロク
- ヤテド
- スをタテる 採集物の解禁日・場所
- カワ 井戸
- 農業
- マキハタ 牧畑(畑と牧場を同一場所で交互に行なう農業方法)
- クナヤマ
- アワヤマ
- アキヤマ
- ホンマキ
- ネンネンバタ 畑
- ナダラ 稲を掛ける段
- ハデ 稲を掛ける段
- イモグラ 芋を貯蔵する壁に掘った穴
- キド 牧の境界の通過戸
- モクジ 牧畑の総合管理人
- ヤマ 畑
- ツカリ 篭のショイコ
- カルイ ショイコ
- クヨシ 山・畑を焼く事
- サンヤマ 畑
- サンダラ 俵の両端の丸い部分
- シカセ 牛小屋に敷く藁
- ダゴエ 牛の糞(肥料に使用)
- 漁業
- カナギ 採集漁業の一種で、網漁・釣り漁以外の磯漁
- ヤス モリ
- カンコ てんま舟
- トモド カナギ専用のてんま舟
- カガミ カナギに使用する水中眼鏡(舟の上からのぞく)
- アバ 網の重り
- ノリツミ 海苔をとる事
- フナオロシ 進水式
- マンガイイ 運がいい
- ゴンガラ 烏賊釣りの漁具(放射状の針がついている)
- カシキ 船のコック
- クロクソ 烏賊の墨
- ケンガラ 海苔をとる道具
- スンコム 海に潜る
- ソブ ウロコ
- ジークチ 烏賊の口
- シゴ 処理
- 行事
- ヒモオトシ 数えの四才の時の、祝い
- シジュウニ 数えの四二才の時の、祝い
- ロクジュウイチ 数えの六一才の時の、祝い
- オクリ 死者を見送る
- ノバタ 墓に立てる旗(盆と葬式の時)
- スヤ 石塔を作るまでの、木造の小屋型の墓
- シャーラブネ 盆の一六日に仏を送る集落共同の精霊船
- トシトコサン 正月に迎える神様
- トンド 正月一五日に飾りを燃やして、正月を送る行事
- セチ
- ナノカボン 七月七日の盆始まり
- ボンバナ
- オジガンサン 氏神様
- コモッシャ 氏神の横にある、篭もる為の建物
- ハツマイリ 旧正月に焼火神社に集落単位で詣る事
- デヤンナマツリ
- ジヌッサン 地主神
- コウ 講
- オヒマチ
- ヨイサカ 赤之江の盆行事
- チョーヤッサ 御輿をかつぐ時のかけ声
- 名詞
- アマコ・カマコ ゴキブリ
- オドロ たきぎ
- ガガマ アカンベー
- カタリ イガ
- カンギ 髪の毛
- キッキョ ジャンケン
- キンマ 木材を運ぶソリ
- ボタ ボロ布
- クロキ 雑木
- ケントーサク あて推量
- ヤワキ 噂・密告・告げ口・陰口
- コーコ タクアン
- ダー 堂
- コーヘ・コゴーヘ こまっしゃくれた・生意気に理屈を言う
- ゴンゾ=ゴンタ いたづら
- タマダレ どうしようもない悪者
- サデマ 熊手
- サラピン 新品
- ヨッタリ 四人
- センジョーコンゴー しつこく繰り返して言う事
- ジカタ 本土
- シコリ 宴会・酒を飲む事
- ダ 俺
- ショレ・ショダテ いい格好をつける・よそ行きの姿をする
- イネ 帰れ
- カバチ 面(つら)・講釈をいう
- クンジ お堅い
- タビ 集落から出る事
- ヨソ 本土へ行く
- シャベクレ 無茶苦茶
- シャー 精
- セーロク お節介
- ジャーシキ 無理な注文
- センド 前回
- ダメヅメ 理屈で最後まで決着をつける
- ソテ つまはじき
- ショシャ 様子・姿
- 形容詞
- クサジ すごい
- ガッチャイ すごい
- シチコテ 生意気
- シッタイシッタイ 偉い偉い(幼児に対して使う言葉)
- 動詞
- セケル 嫉妬する
- マギル 曲がる
- シャーカタル 反抗する
- クル 行く
- アレセン 無い
- ハシル 痛い
- ジグロウ 痛くてころげまわる
- 副詞
- ダンダン ありがとう
- ツッツラ ツンとして(まったく知らない顔をしている事)
- スッパリ 全部
- センギセンギ ギッシリ
- その他
- ペサーマ あらま?
- ペャー あらま?
- シャー へっ
- ~サラ ~だよ
隠岐島の昆虫(淀江賢一郎)
蝶●隠岐島の昆虫研究略史
日本海に浮かぶ離島・隠岐の昆虫相については古くから多数の記録が残されている。それらはさまざまな雑誌に公表されているため全貌を把握するのは容易でない。ここでは代表的なものを年代順に紹介し、隠岐の昆虫研究略史とする。各論文は、発表年、タイトル名、著者名、雑誌名(単行書は出版社名)の順とした。江崎悌三、安江安宣、白水隆、日浦勇、大野正男、藤岡知夫、鈴木邦雄などわが国昆虫界の重鎮で、生物地理学に深い造詣をもつ学者が次々登場されていることがよくわかる。また、隠岐在住の木村康信氏や県職員だった門脇久志氏の活躍も大きい。
ところで、三宅(一九〇七)による鱗翅類目録、神谷ら(一九三四)による甲虫類目録は、いずれも当時の島根県農事試験場八田分場(島後・西郷町)に所蔵されていた昆虫標本をとりまとめたものである。この厖大な標本は場長・田中房太郎が作成したものであり、田中こそが隠岐の昆虫研究の草分けといっていいだろう。この標本は誠に惜しいことに、その後の保管が悪くすべて消滅した。なお、田中の蔵書一万五千冊余は現在島根大学図書館に保管されている。
(表挿入)
●隠岐のチョウ研究と木村康信
隠岐博物学の生き字引とも称すべき木村康信先生は、チョウ類についても一九三二年の初報告から六〇年以上にわたって研究を続けられてきた。この息の長さは全国的にみてもまったく例がなく、丹精こめて採集された貴重な標本を惜しみなく中央の学者にゆずられるなど、その功績は極めて大きなものがある。
木村先生は論文「隠岐の蝶」(一九七五)の序で次のように思い出を語っておられる。
『隠岐の昆虫採集には時代が時代だけに色々と複雑な思い出があるが、昭和七年から美田小学校勤務となって児童達と野外で捕虫網を振って昆虫を追いまわした十一年間が面白くて主力を尽くした時代であった。……その後も一種一種と数を増やすのがうれしくてよく野外に出た。……』
この一文には毎年の少しづつの積み重ねこそが「博物学」の基本かつ醍醐味であることがよく表現されている。先生が著された論文を振り返り、研究の跡をたどってみることにしたい。これはそのまま、隠岐のチョウ研究小史となる。
○一九三二年
島前に於ける動植物分布(概観島前地誌、隠岐地理学会)
アゲハチョウ、キアゲハ、クロアゲハ、カラスアゲハ、ヲナガアゲハ、ジャコウアゲハ、アヲスジアゲハ、モンシロチョウ、モンキチョウ、キチョウ、ツマキチョウ、ルリタテハ、ヒオドシチョウ、アカタテハ、ヒメアカタテハ、ヘフモンチョウ、ウラギンヒョウモン、オホウラギンヒョウモン、ウラギンスジヒョウモン、ミスヂチョウ、コムラサキ、ジャノメチョウ、コヂャノメ、ヒメヂャノメ、クモガタヒョウモン、ミドリヒョウモン、ヒメウラナミジャノメ、シジミチョウ、イチモンジセセリ、ダイミョウセセリ、ベニシジミ、ルリシジミ、ヤマトシジミ、ツバメシジミ、ウラギンシジミ。計三五種。
○一九三六年
島前に於ける動植物分布(観島前地誌増補改訂版、隠岐地理学会)
モンキアゲハ、メスグロヒョウモン、スジグロシロチョウ、ゴマダラチョウ、ホシミスジ、サカハチチョウ、コミスジ、アサギマダラ、テングチョウ、ウラキンシジミ、ゴマシジミ、ムラサキシジミ、ウラナミシジミ、キマダラセセリを追加、四四種となる。
○一九三六年
私の見た隠岐の蝶亜目(隠岐教育四号、隠岐教育会)
前報に同じ。
○一九三八年
隠岐の昆虫(隠岐教育一〇号、隠岐教育会)
キタテハを追加、四五種になる。
○一九三九年
隠岐黒木村ニ分布セル動物植物目録(謄写自刊)
ミヤマカラスアゲハ、ウラゴマダラシジミ、トラフシジミを追加、四八種。
この目録は隠岐生物研究の金字塔ともいうべき貴重な文献であるが、ガリ版刷で今では容易にみることができない。幸いなことに一九七七年発行の「美田の学舎百年」(美田小学校百周年記念史)に再録された。編者の見識に敬意を表したい。
○一九四二年
隠岐の動物(隠岐教育一八号、隠岐教育会)
ルーミスシジミ、ツマグロヒョウモンを追加、五〇種となる。
○一九六三年
隠岐の生物(隠岐郷土研究六号、隠岐郷土研究会)
代表的昆虫の解説。
○一九六九年
隠岐の自然(隠岐の旅情、隠岐観光協会)
チョウ五七種。
○一九七五年
隠岐の蝶(島前の文化財五号、隠岐島前教育委員会)
エゾスジグロシロチョウ、イチモンジチョウ、ヒカゲチョウなどを追加、六〇種をリストアップする。
隠岐を代表する珍蝶・ルーミスシジミ発見のいきさつが語られ興味深い。
○一九九一年
隠岐でも繁殖亜熱帯の蝶(山陰中央新報、一九九一年一〇月一三日付)
ウスイロコノマチョウを複数発見。八〇才を超えての現役!
一九九一年
隠岐・西ノ島で多数のウスイロコノマ(すかしば、三六号)
ウスイロコノマチョウの正式な採集報告。六一種目。
○一九九二年
またウスイロコノマチョウを西ノ島で採集(すかしば、三七~三八
号)
南方系の迷蝶・ウスイロコノマチョウを二年連続美田で発見。モニタリング調査としても貴重なもの。
○一九九二年
隠岐・西ノ島でナガサキアゲハを採集する(すかしば、三七~三八
号)
ナガサキアゲハは江戸時代シーボルトが発見命名した南方系のチョウである。
隠岐で二頭目、西ノ島では初記録。これで合計六二種を発見されたことになる。
ところで、木村先生の採集された多数の昆虫標本は美田小学校へ寄贈保管されていた。しかし、有能な後継者に恵まれず、手入れがなされなかったようである。そのためウラキンシジミ、クチキコオロギ、ヨコヅナトモエなどわが国唯一の貴重な標本さえ虫害にあって現存しない。
マルバウマノスズクサを食草とするジャコウアゲハも一九七五年頃までは美田川の川原に多かったというが、ダム建設により、本土との地理的変異(対馬や朝鮮半島産との関連比較)も未検討のまま、絶滅してしまった。今残るのは木村先生採集の三匹の標本だけである。オランダの博物館にはシーボルトが採集した一二〇
年前のナガサキアゲハ標本がいまでも残されているのである。
一時的なブームにのった宣伝よりも、こうした郷土のもっとも基礎的な仕事に価値を認める施策(自然館建設など)を求めたいものである。
●西ノ島のトンボ
日本に産するトンボはおよそ二〇〇
種、島根県本土で八八種、隠岐全体で五一種が報告されている。西ノ島は、川や池沼に乏しく、水系に依存するトンボ類はあまり多くない。 手頃な観察地は由良比女神社境内にある小池で、青緑色に輝く複眼をもつヤブヤンマが集まってくる(最近発行された「山陰のトンボ」という本には由良比女神社で撮影したヤブヤンマのカラー写真が出ている)。 ところで七月中旬の梅雨前線が停滞する頃、国賀は深い濃霧につつまれるが、よく見るとその中を無数といっていいほどの“アカトンボ”が飛び交っている。その正体はすべて「ネキトンボ」で、西ノ島にはこれだけの量を発生させる池がないことから、どこからか集団で飛来してくるものと考えられている。次に目録をあげておく。
キイトトンボ、アオモンイトトンボ、クロイトトンボ、オオイトトンボ、モノサシトンボ、ハグロトンボ、ヤブヤンマ、オニヤンマ、シオカラトンボ、シオヤトンボ、オオシオカラトンボ、ナツアカネ、アキアカネ、マユタテアカネ、ヒメアカネ、コノシメトンボ、ネキトンボ、コシアキトンボ、ショウジョウトンボ、ウスバキトンボの二一種。
島後と比べて欠落が目立つのは、山地渓流性の種(オオカワトンボ、オジロサナエ、ダビドサナエ、ムカシトンボなど)や湿地性の種(エゾトンボ、サラサヤンマなど)である。
●西ノ島のチョウ
チョウは多くの人に親しまれ比較的よく調べられているグループである。わが国では二六〇 種、島根県本土で一三三
種、隠岐全体では七九種が知られている。西ノ島からは、木村康信先生、門脇久志氏、筆者らの調査により現在までに五八種が発見されている(別表リスト参照)。あと一〇種程度の新発見が見込まれる。
島後に生息しておらず、西ノ島だけしか記録のないチョウにはムラサキシジミ・ジャコウアゲハがある。ムラサキシジミは、隠岐を代表する珍蝶・ルーミスシジミに似るがやや大型で翅表の紫色も濃い。本土では普通、西ノ島では焼火山のみで採集されている。ジャコウアゲハはマルバウマノスズクサを食草とする。
美田川に多かったが、ダム建設と河川改修のため絶滅してしまった。
逆に、島後には生息していて、西ノ島にいないチョウには、前出ルーミスシジミや、キリシマミドリシジミ、オナガシジミなど照葉樹林帯や深い渓谷を生息地とする種が多い。しかし、イチモンジチョウ、ミヤマチャバネセセリなどのように島後の低山地に普通に見られる種が、西ノ島に生息しない理由はいまのところ説明がつかない。
また、国賀や鬼舞などの放牧地にはオオウラギンヒョウモン・クロシジミが生息していたが、近年著しく減少している。両種とも環境庁が一九九〇年に作成した「日本の絶滅の恐れのある野生生物」(レッドデータブック)にそれぞれ絶滅危惧種、希少種としてとりあげられているチョウである。
隠岐・西ノ島/チョウ類目録(五八種)
セセリチョウ科
ダイミョウセセリ
ホソバセセリ
キマダラセセリ
チャバネセセリ
イチモンジセセリ
アゲハチョウ科
アオスジアゲハ
ジャコウアゲハ
キアゲハ
アゲハ
オナガアゲハ
クロアゲハ
モンキアゲハ
ナガサキアゲハ
カラスアゲハ
ミヤマカラスアゲハ
シロチョウ科
キチョウ
モンキチョウ
ツマキチョウ
モンシロチョウ
エゾスジグロシロチョウ
スジグロシロチョウ
シジミチョウ科
ムラサキシジミ
ウラゴマダラシジミ
ウラキンシジミ
カラスシジミ
トラフシジミ
ベニシジミ
クロシジミ
ウラナミシジミ
ヤマトシジミ
シルビアシジミ
ルリシジミ
ツバメシジミ
ウラギンシジミ
テングチョウ科
テングチョウ
マダラチョウ科
アサギマダラ
タテハチョウ科
ウラギンスジヒョウモン
ミドリヒョウモン
クモガタヒョウモン
メスグロヒョウモン
ウラギンヒョウモン
オオウラギンヒョウモン
ツマグロヒョウモン
コミスジ
ホシミスジ
サカハチチョウ
キタテハ
ルリタテハ
ヒメアカタテハ
アカタテハ
ヒオドシチョウ
イシガケチョウ
ゴマダラチョウ
ジャノメチョウ科
ヒメウラナミジャノメ
ジャノメチョウ
ヒメジャノメ
コジャノメ
ウスイロコノマチョウ
●西ノ島の食糞性コガネムシ
ファーブル昆虫記第一巻に出てくるスカラベ(タマオシコガネ)がこの仲間で、古代エジプトでは聖なる虫として有名。動物の糞をいち早く食べて掃除するため、自然生態系のなかで欠かせない昆虫である。西ノ島では、国賀の放牧地で調査されたことがあり(塚本珪一、一九五八)、次の五種が確認されている。
エンマコガネ属:カドマルエンマコガネ
マグソコガネ属:フチケマグソコガネ、キバネマグソコガネ、エゾマグソコガネ、オビグソコガネ
なお、隣の知夫里島でも牧畑が盛んで、牛馬の糞にはカドマルエンマコガネ・マグソコガネが多く、また、タヌキの糞ではコブマルエンマコガネ・クロマルエンマコガネが見つかっている。
●西ノ島の歩行虫(オサムシ)
鞘翅目ゴミムシ科昆虫の一群。後翅が退化しているため飛ぶことが出来ず、地上を徘徊するため歩行虫と呼ぶ。漫画家の手塚治虫が学生時代研究しており、ペンネームを治虫(おさむし)としたことは有名。移動力が弱いため地理的変異が著しく、種分化が激しい。食肉性で、夜間歩き回りカタツムリやミミズを襲う。
西ノ島ではオキオサムシ、マイマイカブリの二種が生息。島後の普通のヤコンオサムシは分布していないようである。オキオサムシはダイセンオサムシの隠岐亜種で、本土産と比べ翅の色彩が銅色を帯びる。マイマイカブリも後翅末端部の尖りが弱いなどの地理的変異が見られる。
●島後と島前の昆虫相の違い
一九〇八年(明治四一年)三宅恒方(東大講師)は、『……今や島前島後の昆虫相を比較せんに、二島僅々九里の海峡によって隔てられるも其相の遥かに同じからざるを見るは予想外なりとす。たとえば、かのモンキアゲハの如き島後にては極めて普通にして何処に至るも出会いせざるなきも島前にあっては一頭をも発見せざること之れなり。………』と学会誌に報告して、島前と島後の昆虫相の異なることを指摘している。
その理由としては、島の大きさ、山の高さ、植生の違い、牧畑などの人為開発を上げているが、現在でもこれに付け加えるものはない至言である。
しかし、八〇年以上経た今もって比較標本の蓄積は十分でなく、“具体的な”違いはよく調べられていない。
調査のすすんでいるチョウ類については、ウラゴマダラシジミ、カラスシジミなどで島前・島後間に地理的変異のあることが判明している。他の種類についても比較検討が望まれる。
●昆虫の地理的変異
隠岐島の昆虫には本土のものと同種類でありながら、比べてみれば、斑紋、色彩、形態の異なるものがいる。ホシミスジ、サカハチチョウ、ウラゴマダラシジミ、ヒメコブヤハズカミキリ、ダイセンオサムシなどがその代表である。
二万年前、隠岐が本土から隔離され、移動力の弱い昆虫たちが互いに交配できなくなった結果であるが、それではなぜ隔離されると「地理的変異」を生ずるのであろうか。
生物集団の遺伝子は交配を重ねる毎にその構成比率が変化し、何世代も経ると初めとは異なる遺伝子構成をもった集団ができる。その変化を生ずる割合は集団が小さければ小さいほど大きい。これが「遺伝子浮動」で、自然淘汰とは無関係な偶然の結果として遺伝子構成が変化していく現象である。もし、その集団の中に突然変異が生じたりするとその変異が集団に固定され、独特の変異をもつようになっていく。隠岐島のような狭い離島ではその効果を目のあたりに見ることができるわけである。
●オオウラギンヒョウモンの衰亡
オオウラギンヒョウモンは翅の開張七〇~八〇mm
ほどの中型のチョウの一種。
翅の地色は橙色、表面に豹紋状の黒斑がある。草原性の種で、戦前は全国各地に広く分布していたが戦後まもなく減少を始め、現在生息しているのは全国で数ケ所(山口県秋吉台、長崎県大野原、宮崎県えびの高原、隠岐島)を数えるほどの珍蝶となった。一九九〇年環境庁が公表した「日本の絶滅の恐れのある野生生物」(レッドデータブック)では「絶滅危惧種」とされている。
隠岐・西ノ島でも昔は広範囲に分布していたことが木村康信先生によって明らかにされている。その後、一九七二年まで国賀の放牧地に生息していたが、以降確認されておらず、絶滅が心配されている。お隣り知夫里島には一九八七年までは多産していたが、その後始まった松枯れ対策の殺虫剤空中散布のために激減した。
なお、ロシア共和国沿海州にも生息するが、ここでも絶滅危惧種に認定され、その生息地リヤザノフカ周辺は手厚く保護されている。
●マツバノタマバエと生物的防除
昭和二〇年代隠岐島では、マツの衰弱に関係なくマツ林が茶褐色になって枯れていく被害が大発生したことがある。島根大学の三浦正先生は、原因が、マツ葉の基部に寄生するマツバノタマバエという小さな昆虫であることを明らかにされた。
当時の防除対策はBHCやDDTなどの農薬に頼るしかなかったが、全く効果がなく被害林は広がるばかりであった。先生は研究の結果、タマバエの寄生バチ(プラチガスター・マツタマ、体長一~一、五mm
)を発見され、天敵を利用する画期的な生物的防除方法を実用化、やがて被害はおさまった。このことは、現在の松枯れとマツノマダラカミキリに対する農薬一辺倒の対策への教訓と受け止めるべきであろう。
その後、韓国でもタマバエ被害が続出したが、三浦先生が調査され、この寄生バチが分布するところでは被害が抑制されていることがわかった。
●西ノ島のセミ
セミがウンカやカメムシの仲間と言っても、誰も信じないだろう。しかし、ウンカとセミを並べて観察すれば、大きさこそ違うものの口器や翅の形状などそっくりであることがよくわかる。
隠岐島には六種が分布するが、その代表は島後の山地に住むエゾゼミである。
その名のとおり北方系の昆虫で木村康信先生の発見による。残念ながら西ノ島にはエゾゼミは生息しないようだ。ただ、上田常一先生の「隠岐の動物」を読むと“ハルゼミ”のことが出ており、もしかしたらハルゼミは生息しているのかも知れない。
西ノ島にいる五種のセミと方言を紹介する。
セミ=ジージ、ジンジ。ヒグラシ=カネカネ、ツケツケ、カナカナ。アブラゼミ=オホジンジ。ミンミンゼミ=メンメー。ツクツクホウシ=ツクツクイス、ホイスチョコチョコ、ニイニイゼミ(岡部武夫、隠岐雑俎より)。
●西ノ島のホタル
蛍は「日本書紀」にも出てくる如く古くからよく知られた昆虫で、語源は「火垂る」、「星垂る」などの説がある。ホタルの仲間は全世界に四千種余知られ、その内発光するものが約半数だという。わが国では約四〇種が分布するが、発光するものは少ない。西ノ島では既に一九三七年、木村先生により発光ホタル三種が調べられている。
ゲンジボタル、ヘイケボタルは水生で、幼虫はカワニナやモノアラガイを食べる。地域によって発光パターンの異なることが最近判明しており、増殖するため別の産地のものを養殖・放流することは遺伝子を攪乱するので禁物である。そこにホタルを定着させるだけで自然が回復したと考えるのは誤りで「ホタルの家畜化」に過ぎない。
あと一種ヒメボタルは陸生で陸産貝類(オカチョウジガイなど)を餌とする。
大きさは
六~七mmほどと小型だが、光は黄金色で強い。メスは後翅が退化し飛翔できない。マツ林を生息地とするため、農薬の空中散布の影響を直接に受け激減したが、空中散布をしてない美田ダム近くのマツ山にはまだ多産する。
一九九一年に大場信義博士(横須賀市立自然史博物館)が現地視察され、「日本一の生息地」とのお墨付きを与えられた。美田では松山ボタルとか竹山ボタルと呼ばれている。
●松枯れとマツノマダラカミキリ 本土側では一九七〇年代、隠岐島では一九八〇年代に入って、急激な松枯れが目立っている。 林野庁ではその原因を「マツノザイセンチュウ」によるものと考え、センチュウを伝播する「マツノマダラカミキリ」を退治すれば松枯れはおさまると、大規模な殺虫剤の空中散布を開始した。当初の説明では三年で根絶ということだったが、空中散布が始まって二〇年たつにもかかわらず、松枯れが収束したところは全国に一ケ所もない。その理由として林野庁は、空散しない地域からカミキリが侵入してくるためと言っているが、隠岐島のように周囲から隔離された離島でさえも収束できない状況は、今までの対策が根本的に誤っているとも考えられる。
最近では、(一)酸性雨や大気汚染などの環境悪化と、(二)松林の放置による遷移の進行が主原因であると主張する学者が多い。農薬に頼る対症療法ではなく、自然の生態系を大切にする抜本的な対策が一日も早く望まれる。
●ホシミスジ
隠岐島を代表するチョウといえば誰もが島後のルーミスシジミをあげるのに異存はないだろう。されば西ノ島を代表するチョウといえば、第一候補としてホシミスジをあげたい。黒地に筋条の白帯がはしる中型のとても上品なチョウで、裏面にある粒状の黒斑が特徴である。六~七月ごろに、山道をゆるやかに飛びシモツケ、ウツギ、クローバーなど種々の花に集まるのが観察される。食草は、海岸の岩場や露岩地などに見られる隠岐特産ミツバイワガサで、幼虫は葉を筒状に巻いてその中で冬を越す。
島根県本土では、大田市三瓶山、出雲市立久恵峡、浜田市三階山の三ケ所しか生息地がなく個体数も少ない。隠岐産と本土産とは白斑紋の形状に顕著な差異が見られ、近く別亜種として記載される予定である。
●カラスシジミ
初夏に山を彩る樹の花といえば、真っ白な花を咲かせるウツギだろう。近づいてよく見るとウツギには実に多くの昆虫が集まってきている。その中に小さな黒っぽいチョウが混じって吸蜜していたらそれがカラスシジミだ。日中は不活発だが、夕刻には食樹アキニレの樹上高く活発に飛び回る。
島根県本土では大田市三瓶山、横田町船通山のような山地に稀なチョウだが、隠岐島では平地に近いところに生息している。西ノ島産は、メス前翅裏面の白い点線状の列がくの字型になっており、島後産と比べて異なるのが興味深い。
●ウラゴマダラシジミ
数年前、日本鱗翅学会(チョウとガを研究する学会)では、各県別に「県のチョウ」を選定する準備をしたことがある。四七都道府県で重複しないように選ぶと、島根県からは本種「ウラゴマダラシジミ」が候補にあがった。北海道から九州まで分布は広いが、隠岐のものがもっとも特化しているからである。隠岐産は本土産と比べて翅表の薄紫色が暗化しており、しかも西ノ島産は島後産よりさらにその変化が著しく、研究者の間で注目を浴びている。
食草はイボタで、赤い円盤状の卵を小枝の分岐点に生み付ける。卵で冬を越し、翌春イボタの芽吹きとともに孵化し若葉を食べて成長、六月にチョウになり林縁を輝きながら飛び舞う。
なお、「県のチョウ」が行政レベルで認定されているのは、いまのところ埼玉県制定のミドリシジミだけである。
●隠岐島の昆虫の系統
○西部中国系の昆虫
昆虫の系統はさまざまあるが、最も古い形質をもったグループは、西部中国(雲南省~ヒマラヤ)に起源をもつものである。隠岐島には数十万年間前に侵入定着、現在では遺存的に分布し、いわゆる珍しい昆虫といわれるものが多い。代表的なものを紹介する。 ルーミスシジミ、キリシマミドリシジミ、オナガシジミ、オオウラギンヒョウモン、ホシミスジ、ムカシトンボ、○北方系の昆虫
隠岐島は、南方系・北方系両系統の生物が混在して、生物地理学上興味深い地域であるといわれている。一般には南方系(学問的に言うと東洋区系)要素の色彩が強調されがちだが、北方系要素の存在にももっと注目すべきだろう。北方系の代表的な昆虫を紹介する。
エゾゼミ、マルグンバイ、キボシミズギワカメムシ、ツノアオカメムシ、トホシカメムシ、モイワサナエ、ダビドサナエ、エゾトンボ、エゾスジグロシロチョウ、センノキカミキリ、ヤツボシハナカミキリ、ルリボシカミキリ、ハンノオオルリカミキリ○南方系の昆虫
隠岐島は緯度が高いわりに対馬海流の影響で気候温暖であり、南方系の昆虫が侵入してきている。代表的な南方系の昆虫を紹介する。
シルビアシジミ、イシガケチョウ、ナガサキアゲハ、オキナワルリチラシ、ベーツヒラタカミキリ、フタオビミドリトラカミキリ、クツワムシ、オオゴキブリ、クチキコオロギ、オオアシナガサシガメ、オオキンカメムシ、ウシカメムシ、ウスイロヒメヒラタナガカメムシ、ハネビロトンボ、ムスジイトトンボ○環日本海系の昆虫
朝鮮半島~沿海州~日本列島と、日本海を取り囲むような分布圏をもつ昆虫がいる。。昨年訪れたロシア沿海州の海岸部は、隠岐の海岸と似た景観が見られ、ウラジロミドリシジミ、ホシミスジ、オオウラギンヒョウモンなど隠岐では少なくなりつつあるチョウが繁栄していた。代表的な種類を紹介する。
ウラゴマダラシジミ、クロシジミ、ウラジロミドリシジミ、エゾミドリシジミ、ミヤマカラスアゲハ、アカスジキンカメムシ、コバネアオイトトンボ、アオヤンマ、ヒメコブヤハズカミキリ
●西ノ島の双翅目
双翅目とは読んで字のごとく翅が二枚しかない昆虫で、蚊、ハエ、アブ、ユスリカなどの総称である。この仲間は衛生害虫が多く医学上の必要性から調査がすすんでいる。蚊類については鳥取大学医学部の長浜操教授らがフィラリア症の調査のさい、ニッポンホソカ、トウゴウヤブカ、コガタアカイエカ、シナハマダラカなど八種類。ブユ類については京都府立大学の吉田幸雄教授らが、アオキツメトゲブユ、ヒメアシマダラブユ、ウチダツノマユブユなどを報告している。
また、家庭内で生ゴミを放置しておくとすぐ繁殖するのがショウジョウバエである。一般には“コバエ”といい、遺伝の実験にもよく使用される。島根大学の若浜健一教授の調査で隠岐から四六種類が記録されている。
山道を歩くと、目の回りをうるさくまとわりつく小さな虫がいる。「クロメトマイ」というショウジョウバエの仲間である。西南日本に広く分布し、オオワラジカイガラムシに寄生して育つ。石見地方では“メツツキ”と呼んでいる。
●隠岐民謡しげさ節に出てくる昆虫。
古くから伝承される民謡“しげさ節”にはいくつかの昆虫たちが詠みこまれており、美しいチョウや鳴く虫が人々の生活の中に定着していたことを思わせる。
登場する昆虫たちを紹介してみよう。
○ちょう
鱗翅目異脈亜目の一科。翅表には色素のたまった鱗粉がのり美しい。蛾類との分類学的な区別は困難で、外国にはガチョウ科というグループがあるほどである。フランスでは昼の鱗翅目をチョウ、夜の鱗翅目を蛾という。
○とんぼ
蜻蛉目昆虫の総称。語源は「飛ぶ棒」「田んぼ」説などがある。大きな複眼と頑丈な羽など、飛ぶための機能が発達している。幼虫(ヤゴ)は水生。
○きりぎりす
直翅目キリギリス科の一種。触角は鞭状で細く長い。体長四〇mm前後で、体色には二型あり緑色または褐色。かなり強い肉食性がある。日当たりの良いススキなど丈の高い草むらでチョンギース(またはギース)と鳴く。六~九月。
○すずむし
直翅目コオロギ科の一種。体長一五mm、産卵管は一二mm。黒色。林の中の暗い湿った草むら下に住み、鳴き声はリーン・リーンと大きい。かめの中で産卵させて繁殖させることも容易である。八~一〇月。
○まつむし
直翅目コオロギ科の一種。体長は一七mm、産卵管は長くて一七mmのきり状。体色は淡褐色。雑木林の縁のススキなど乾いた草原に多く、夜間チン・チロリン(あるいはチッ・チロリッ)と鳴く。八~十一月に発生。
○くつわむし
直翅目キリギリス科の一種。体長二五~三六mm
、羽は広く木の葉状をしている。体色は緑色または褐色。灌木やヤブ中に住みガチャガチャガチャとやかましく高い声で鳴く。八~十月。
●西ノ島にやってきた南方系の迷蝶
地球温暖化を証明するかのように、ここ数年来、九州以南の暖帯でしか記録のなかったチョウが隠岐島で見つかるようになった。その土地に土着はしておらず、風にのって飛来してきたチョウを迷蝶といい、その代表がイシガケチョウ、ナガサキアゲハ、ウスイロコノマチョウである。
○イシガケチョウは一九八八年頃から島根県本土の海岸線沿いに分布を北に拡げていたが、一九九〇年に島後(都万村那久)で木村晴男氏によって初めて発見され、一九九一年には西ノ島別府と知夫里島でも発見された。本種の食草はイヌビワで豊富にあることから今後とも土着する可能性が高い。
○ウスイロコノマチョウは奄美以南に生息する熱帯性のチョウだが強い移動力をもち、今までもしばしば島根本土・隠岐で採集されてきていた。しかし、一九九一~一九九二年にかけて西ノ島美田では、木村康信先生により複数の個体群が見だされ、南方から飛来後二次的に産卵・発生を繰り返しているものと考えられている。
○ナガサキアゲハは九州以南に分布していた南方系のチョウ。一九五〇年代に島根県に侵入した。島後で一九八五年に一頭が発見され、一九九一年に木村康信先生が美田でも発見された。
●西ノ島の直翅型昆虫
直翅型昆虫とは聞きなれないが、キリギリス、バッタ、コオロギ、カマキリなどの仲間のことである。戦前、古川晴男博士が木村康信先生の採集標本を材料に、ヒメカマキリ・ヒナカマキリ・ツノオホゴキブリ(オオゴキブリ)・コバネオホヅコホロギ(クチキコオロギ)の四種の南方系の種類について報告している(一九四一年、動物学雑誌)。そのほか、クサヒバリ、カネタタキ、マツムシ、スズムシ、ケラ、ナナフシ、クツワムシ、キリギリス、カマドウマ、ショウリョウバッタなど四五種が知られており(木村、一九三九)、西ノ島の直翅型昆虫は面積の割に豊富である。
キリギリスやコオロギ類を“鳴く虫”と呼ぶことがある。これらのオスは、左右の前翅を震わせて互いにこすり合わせて音を出す。なぜ鳴くのかはよくわかっておらず、(一)メスを呼ぶため、(二)縄張り宣言、(三)仲間どおしが分散してしまわないため、などの説がある。一般にコオロギ類の声が優雅で、キリギリス類の声は粗野である。
●西ノ島のカミキリムシ
天牛と書いてカミキリムシという。触角が長く牛の角に見立て、天とはよく飛来するので合わせて“天牛”となった。成虫・幼虫とも食植性で、伐採木などに集まる。
木村康信、藤村俊彦(元島根県農業試験場技師)、門脇久志(現島根県環境保健部次長)、福井修二(現島根県林業技術センター技師)らによって調査がすすんだ。
島根本土から二三四
種、隠岐全体で一二七
種、西ノ島からは次の四五種が発見されている。 ウスイロトラ、クハ、ビロウド、ヤハヅ、キスヂトラ、ミヤマ、ホソ、クロ、ゴマフ、キイロトラ、クロトラ、ミドリ、トラフ、ゴマダラ、キボシ、センノキ、ベニ、キマダラ、ノコギリ、アヲスジ、ハイイロヤハズ、ヘリグロベニ、シラホシ、キクスヒ、ホタル、クビアカトラ、シロスジ、ヒメスギ、アトジロサビ、ゴマダラモモブト、ヤツメ、ネジロ、ナガゴマフ、メスアカハナ。ウスバ、キバネニセハムシハナ、フタオビノミハナ、チャイロヒメハナ、セスジヒメハナ、ヤツボシハナ、ヅマルトラ、フタオビミドリトラ、ホタル、ゴマフ、キクスイモドキ。
なお、一九五八年に島後・西郷町大満寺山で発見されたスネケブカヒロコバネカミキリ(臑毛深広小翅天牛)は隠岐を代表する珍虫の一つでネムノキの立ち枯れに発生する。最近、中ノ島でも発見されたので西ノ島にも生息しているものと考えられる。
●“オキ oki”の名がつく昆虫たち
一 オキツヤヒサゴゴミムシダマシ Misolampidius okiensis
Nakane
二 オキオサムシ Carabus daisen okianus Nakane
三 オキチビハネカクシ
Micropeplus okiensis Watanabe
四 オキノアサカミキリ Thyestilla gebleri
kadowakii Fujimura
五 ヘリグロベニカミキリ Purpuricenus spectabilis ab.okiensis
Fujimura
六 クビアカトラカミキリ Xylotrechus rufilius ab.kadowakii
Nakane
七 オキノミハムシ Parazipangia okiana Ohno
八 オキチャイロコガネ Sericania
kadowakii Nakane
九 (オキイワトビケラ) Plectrocnemia okiensis
Kobayashi
十 オキノホシミスジ(未記載種) Neptis preyei ssp.Fujioka
十一 オキヤコンオサムシ
Carabus yaconinos okii Ishikawa
十二 オキウエダニンフジョウカイ Podabrus uedai
hisashi Nakane
十三 オキナガゴミムシ Pterostichus okiensis
Nakane
学名または和名に“オキ”の名が付けらている昆虫をあげてみた。学名というのは二三〇
年程前にスェーデンのリンネが提唱したものである。世界共通の名前であり、ラテン語で書かれる。細かい規約があるが、基本的には、属名、種名、命名者名の三つの単語で構成される。
(七)のオキノミハムシを例にとれば、“Parazipangia”が属名、ノミハムシというグループ名で人でいえば家族の名字にあたる。“okiana”は種名で人でいえば家族の名前、“Ohno”は命名者で、大野正男博士のこと、人でいえば名付け親である。
一般に種名は、産地あるいは発見者の功績をたたえて献名されることが多い。
これから見ても、隠岐昆虫研究における門脇久志氏の活躍が目立っている。
西ノ島町誌に使用した文献データベース(CSVファイル, Shift-JIS)です。項目は、1巻号・2ページ数・3行数・4内容・5西暦年・6月日・7元号・8出典・9干支となっております。エクセル・データベースに読み込んでご利用ください。
文献データベース文献資料
一、木の葉比等。隠岐の国に初めて住み着いた人間は木の葉比等であった。後の世に木の葉爺・木の葉婆・箕爺・箕婆などといった人も、この木の葉比等の族であった。この人は下に獣皮の着物を着て、上に木の葉を塩水に漬けたものを乾かして着て、木や川柳の皮で綴ったものを着ていたから出来た名前である。髪を切らないし、髪も延びたままで、目だけくるくるして恐ろしい姿でったが人柄は良かった。一番初めに来たのは、伊後の西の浦へ着いて、海岸沿いに重栖の松野・後・北潟(分の北方)に来て定住した男女二人で、火を作る道具や、釣をする道具を持っていた。次に来たのは男女二組で、長尾田についたので、重栖の煙を見て来住したが、今一隻が男一人・女二人南の島へ着いたというので、晴天の日、南の島へ渡って探したが、わからないので、一番高い山の上で火を焚いたところ、火がなくなって困っていた男女三人が登ってきた。当時、火は一番大切であったし、目標になるので、この山頂の火は、男女二人が絶やさぬようにして子孫に伝えた。この山が焚火山で、この三人が着いたのは、今の船越であった。その後年々島の各地に同種の人間が漂着して定住したが、先に来たものが生活が楽であったために、重栖と船越に集合したが、後には全島に分散居住した。この人々は甘い団子を作ったが、この団子は後々まで、役道の邑にて作られ、杵取歌・餅まき歌・子守歌とて伝えられるも杵取・餅まき歌は歌意難解、邑長家のみ伝わる。子守歌は難解のまま一般に今も歌わる。
「島のモクノシセイボン熟れた、ハイベンタイベンソウベン拾うた(牟羅にてはハイベンタイペイソウペイは拾うたという)、ハレパメこめてのもみプリホクに、ムリトントガヂャドすべも焼いた(牟羅はトガトンという)、モリクシソメをサンにして、クドのシリキがヨンギあげりゃ(牟羅にてはシキリをセイロといいヨンキはモヤという)杵翁やっとこ臼婆は、やっとこはいや やっとこはい、たらいしとぎのつきはじめ、あーらめでたやめでたやな。餅まき歌 臼婆は杵爺にこづかれだんつくだん、だんつくだんだん子が出来た、出来たその子がそれだんご、サンヤク苺タイマママイ苺、椎栗団子にたらいぞえ、トキカリひろげてキダリショウ。子守歌 アチメ露分けて枝折になり暮れりゃ、ネエリチョンナリタアトさん、木の葉団子を貰うて、チャーシャーアドリに負うはして枝折のサンコクケンチヤーナねんねの子よ団子の子、ほえりや杵翁がひげの中、ドングリズニを光らせて、白い歯出して笑うぞえ、ダンマテねんねせいよ、この子はよい子だねんねせ」
これら木の葉比等は、西方千里加羅斯呂 から来たというが、また韓之除羅国から来たともいう。
二、海人(阿麻と云う)。顔から全身入れ墨した物凄い風体で、この人間が、木の葉比等に次いで来た時、木の葉比等は大いに驚き恐れて、部落人が集合して彼らに立ち向かったが、海人も甚だ温和で、漁が上手であったので、遂に雑居するようになったが、年月と共に出雲から相次いで来住し、後には木の葉比等とは海人がつけた名称だという。海人の於佐神は於母島の東後、奈岐の浦にいた。この頃隠岐は小之凝呂島と称えた。それは小さな島の集まりであったからである。この大島を於母の島、南の小島三島を三つ子の島、東の島を奈賀の島、南の島を知夫里島、西の島、船越の南を麗又の名宇留、北を比奈又の名を火地と称えた。海人が来航して間もない頃になって出雲の大山祇の神様の一族が来航したが、数は少なかった。その後海人の於佐の神が海賊に殺された。
三、山祇。海神の於佐之神が死して、出雲の鞍山祇之大神の御子沖津久斯山祇神が小之凝呂島の神として来航、於母の島の東の大津の宮居して長い年月平穏であったが、出雲の国が於漏知に奪われてから、此島へも於漏知が来航して財主を奪い、乱暴するので、三つ子の島の民は於母の島へ逃げ、於母の島の東大津も又於漏知に襲われるようになったので、宇都須山祇山祇神の代に至り、神は於母島の西の大津松野という地、後の主栖津、北潟に移して、海防に努めたが、後三つ子の島は全く於漏知に奪われ、民は於母の島に避難し、神は於母の島民を結集し、老若男女すべてに武事を教えて対抗、於母の島と三つ子の島は長い間闘争したが、三つ子の島の力は年月と共に強力になった。於漏知は踏鞴を踏んで金を作り、鎧・兜・盾・剣を作るので、それを用いたので、人数は少なくても戦いは強かった。然して於母の島も於漏知の度重なる来襲に耐え難くなり、流宮の加須屋の大神祇大神の援助を受けるため使いをやった。小之凝呂島に米を作った。始まりはこの山祇神の代であったので、後の世まで島の各地の護神として山祇神が祀られた。又流宮の大海祇神もこの島の海人共によって各地に祀られた。沖津久須山祇其女神比奈真乳姫神其御子比奈真岐神は共に三つ子の島比奈の地に祀る。
四、大人様。流宮加須屋大海祇大神は宇都須山祇神の願により、軍兵を小之凝呂島へ遣す準備を整、御子奈賀の大人様に多数の兵戦に多くの軍兵を乗せ武器・衣料・農工具・種子類まで持たせて流宮を出発せしめ、大人様は於母の島の松野に着船、全島征服の準備をされた「(以下阿部老の昔話)大人様は一足先に出雲に来り、大山祇神の姫をめとり、脇板(?)んで、只一足で小之凝呂島の於母の島にわたり、松野につき、右足を主栖に左足を都万に大満寺に腰掛け焚火の火で一服された。その時、吸殻を落すために煙管で知夫里島をゴツンと打ったところ三つ子島の於漏知共が驚いて、十尺許り飛び上がった。その時に西の島と知夫里島の間が雁首の跡で瀬戸になって、吸殻が海へ落ちてチンと言ったので、珍崎という名が生じたという昔話がある由」大人様は、とりあえず、於母島の於漏知を討伐したが、於漏知は相次いで渡来するので、油断ができず、その上於漏知は強力で、遂にその子孫五代にわたり空しく松野に相継ぎ、年月が流れていった。六代目の出雲大山祇神の姫をめとり、その援助を得て、於母の島全体を征服し、今度は三子の島の征服の計を立てたが、三子の島では尚於漏知の数も多く容易でないので、先ず本拠を松野から於母の島の東の大津に移して宮居を作りこの宮地を公処(くむだ)と称えた。これが後の宮田である。公処のある地を大人様の祖先の発祥地名を取って奄可と称した。又大人様の土地の長職の意味から地公の命・又の名奈岐の命と称え、この津一帯を奈岐の浦と称え、命は又奈岐の浦命とも称した。この命は津戸を三子の島征服の拠点として密かに渡船の機を待ち、奈賀の島の豊田に上陸した。この地方は於母の島から最も早く着く里であったので、地方名を早着里、又は佐作と呼んだ。而して三子島全島を服し、比奈の船越し美処・又の名美田に三子の島の公として、主栖の山祇の神を駐し、奈賀の島の南の瀬戸を左道と呼び左道守の神を屯せしむ。この神を左路彦命という。又奈賀島の北の瀬戸を右道と呼び、その守神として海人比等邦公を充てたのであるが、この子孫は天平の頃まで栄えたという。後奈岐の浦命の子孫は全島海部大神として栄えた。
五、美豆別之主之命。又の名小之凝呂別命・水別酢命・瑞別主命、これの命天津神の御子にて数多の久米部・綾部・工部・玉造部の民を率いて来島、小之凝呂島を奈岐命より譲りうけ、その娘をめとりて宮居を奈岐の浦中の鼻に立て、城を築き、目の城と称し、浦に注ぐ大川に添える地を開きて農耕をすすむ。この地を新野という。この川は八谷り尾の合流なれば八尾川という。於母の島西岸の防衛を前線とし、島の南北を貫ける山を境として後線とし、これに城を作り、久米部をもって城邑をなさしめて防備の傍ら開墾に従事せしむ。この城のありし地、今もその地の名に城を附して残る。宇津城・阿羅城・江津城・増城・阿武城・宇陀城・焚泊城(今歌木)これなり。城の東を周城と称す。西は民少なく、主として久米部の駐屯せるによりて役道又の名を伊未自という。周吉は加茂・新野・奄賀三郷なり。役道は布施・飯尾・元屋・中村・湊・西村の大浦・今は牟羅という。主栖は昔、主の住みけるによる。役道の南端を津麻という。端の意なり。これ役道三郷なり。比等那公を以て治せしむ。三子の島にありては、主栖の沖津久期山祇神を小期凝呂山祇首として比奈・麗・知夫里を兼治せしむ。那賀の地は奈岐浦命を小之凝呂島海部首として兼治せしむ。この後、阿曇首という。かくて全島平穏に帰し、於漏知も温和となり、高志・丹波・竹野・出雲との交通もひらけ、重栖はこれらの地と韓との交通上、往航最後の待機港、復航最初の給食給水の穏息港となったので、後に穏息または穏座と記して於母須と訓した事もあった。主栖の地は三子の島から於漏知に追われて来住した山祇人が栄えたので、その遺跡が特に多くあるが、海人のもある。斯くして小之凝呂別命に依って治められたこの島も、その後出雲に大きな戦いが起こって因縁の深かった大山祇大神の勢力が落ちてきたために、新たに出雲から奈賀の命が来航、この島の治神となり、小之凝呂別命は免じられて、全島の久米の首として久米部の主力を率いて主栖に移住される事となった。その本拠は後の国府路の垣の内という地であった。別之主命の祖神は別の祖の神として久米部の祖神としてこの地に祇られた。
六、奈賀命(后中言命という)。阿遅鍬高彦根命の御子にて丹波の須津姫をめとり、来島。新野川辺に宮居を建てて住みたまうという。後この地を蔵見という。この神大いに農耕をすすめ各地に開墾・溜池を作り道路を新設し、漁船の建造をすすめたまえるによりて島民の生活は大いに向上してきた。又妻神須都姫命は丹波の長自羽麻緒姫と共に織女を迎えて各邑に織布を教え、丹波の須津より薬師を招きて薬草の栽培をすすめ、医師を迎えて病者の治療に努めた。その後主栖に珠城宮天皇の皇子誉津部、又の名保地部という御名代部を定め給う。この後の名代田、又の名苗代田植之内にて、その田は後の保地なり。更に日代宮天皇の御代にいたり、新野と主栖に田部屯倉を定められ、そこを田部垣の内という。奈賀命は田部首を兼ねたまう。この時美豆別主命は別の酢の神を奉じて久米部を率いて久味に移駐し返防の事にあたり、開墾・農耕をはげました。息長足姫皇後、三韓を討ちたまうみぎり、皇后は多遅摩出石にいたり、美豆別主命又の名伴の首に兵船の事を命じたまう。命は小之凝呂の久米部を数多く率いて皇后の軍に従いたれば、韓国より得たる数多くの財宝をば皇后より賜る。この時の剣は後美豆別酢神社に残った。竹内宿弥は都万の地に祖神紀之健名草三神を祀りて武運長久を祈り神地神戸に定む。更に神功皇后の兵船が役道の主栖に来れる時久米首の祖伊未自姫は十挨命の妻となり十男子あり、後に姫死して男子は大和美和の父命の許に送られしという。美豆別主命の後は大伴部首という。その後若桜宮の朝に至りて久味の地に伊勢部を定められ、この命は美豆別主命の神璽を奉じ、伴部の民をつれて役郷に移住し、各地の久米部を持ち、奈賀命についで力があり。役郷は久米部の郷の意なり。伊勢国造の御子健伊曾戸命は、その祖天日別命又の名大伊勢命の神璽を奉じ、伊勢部の民を率いて久味に来住した。宇津志奈賀命は後国造の来島により於母の島の田部首となりて一族を具して、その祖奈賀命の神璽を奉じ主栖に移住し、役道を兼治したが、後に三子の島の田部をも領した。徳が高く、その子孫阿曇首は後出雲大阿曇造に属し長白羽姫の子孫、服部首家と共に栄えた。七、国造。誉田天皇御間都比古伊呂止命五世の孫十挨族命を隠岐国造に定め給えるに及び大津部伊勢部海部山部服部の五首は国造に協力し功あり。この頃異国人の来襲盛んなり。国造は沿岸の防備を益々堅固にし田部名代部を督して開墾を励め道路を開き、島民に衣を与え、医師・薬師を各邑に見舞わしめ、兵船を数多く作り、民心を和し、賞罰を明かにし、各部の氏神に領地を配し、敬神の志を厚らかしめ、孕婦の労力を禁じ、幼少老人病人に食衣を給し、密察使を置いて民情を糺し、漂着者に(以下略)。
【田中註】
本書は五月二十七日、池田国分寺にて開かれた第六会隠岐郷土研究会の席上、北方金坂亮氏の発表せる伊未自由来記を筆写せるものである。伊未自由来記について金坂氏は次の如き説明をした。「この原本は六十枚程あり、表紙には伊未自由来記、永享三年持福寺一閑、古木所有と記されていた。この他に隠座抜記・隠岐国風土記といったものもあった。」
明治四十三年ごろ、金坂氏が北方郵便局に在職の時、那久の阿部廉一翁が上記のものを持参し、金坂氏に口約しつつ説明したので、金坂氏が四三・一〇・三〇の消印のある電報受信紙の裏に筆記したものである。隠座抜記や隠岐国風土記は今どこにあるか不明だが、伊未自由来記の内容から見て、その原本とも思われるので、その発見が望まれている現状である。
「日本庶民生活史料集成」第二十巻
隠州視聴合紀 巻四
嶋前記
知夫郡・同別府
島前は地脈三つに断たれて三島たり。海部郡一つ、知夫郡二つ、皆峻高にして原野あらず、故に嘉蔬少なくして、菽麦多し、其草は惟れ短く其木は惟稀なり、其山は峻にして其村落は皆山を後にし海を前にす、此故に網引漁釣を事とし、此を山税海租とす。海部は坤より艮に長く、知夫は其西南より北方に曲りてケンサンたるカイ山なり、其半面東の内浜に向ふ所、則ち別府なり。古島後より一小吏を遣わし、島前の事を知らしむ、故に此を別府という、北の小岡に昔の館所あり、今の駅亭は其下なり、代官の家此にあり。民家左右に分かれ、猶地勢高くして遠きを見る。河の南に見付島と云うあり。蓋崎邑より入来る船の、先ず此島を見るによりて名づく。其南の山崎に松樹多く生出す此より美田郷の境なり、即ち美田尻といふ、上に八幡宮あり、別府の古吏の氏神といふ。府より西は山にして半腹に飯田寺といふあり、越えて西に下れば高崎といふ、高岸千丈雑樹多し。海に立島といふあり、此を白島といふ、釣魚の宜地なりとぞ。府より北の山崎を黒木と云ふ。伝に曰く、昔後醍醐天皇姑く狩し玉へる所なり、故に今に到りて黒木皇居と云ふ、北の方海に随ひて東が崎と云ふ所を過ぐれば、北の山を香鴨といふ、寺ありて香鴨寺と号す、其崎を廻り行けば、十四町ばかりにして宇賀村に至る。
宇賀村
宇賀村は内海の岸辺、地形別府に似て狭し、後の山間に田園ありて往来崎嶇を経、十町ばかりを西北に越ゆれば外海に出ず、此処を鹿浦と云ふ。是より南別府山に次ぎて、耳が浦といふあり、皆人家なくて岩間にて漁釣をなす。村より左は倉谷といふ。海岸を北へ回りて山下を行くこと十九町にして、大宇賀小宇賀といふ蜒家あり、十町ばかり丑寅に廻り行きて海に冠島二股島あり、北へ行く事三十町にして、沖の方に星神といふ嶼あり、雨を祈り風を祈る、高さ五十間廻り百六十間此より北は海漫々として天を窮む。別府に帰りて八幡の前より西の方小坂を越えて美田に行く、左右は皆翠微にして或は少しく田園あり。
美田郷
(或は美田院と云ふ)
美田郷に東より入り小坂を下れば又田園あり、左に古き神祠あり、西に向かふ高平の地に旧石塔の大なるあり、一国の中物の是に似たるなし、想ふ故あらん、然れども銘摩滅して證す可らず。此より下れば入海の渚に出づ、南に去る事三十町ばかりにして海に出ちる小島あり、此を小山と云ふ、松根波に濯はれ、岸高き上に旧坊あり、此より右に行く山の腰に長福寺あり、岩径斜にして松竹柴門を蓋へり。其麓は田圃ありて、温居市部大津小迎船越なんど云ふ村店あり、皆入海の岸に臨み、山に随つて住居せり。其船越といふ村より外海に出づること甚だ近し、東西の山勢尽きて、陸地十八九間ばかり海に出づる径亦此の如し。往年多力の賊夫あり、入海の岸より船を負ひて外海に出でて終日釣漁し、又負うて入海に帰る、故に此村を船越と号す。 克く船を遣ることあり、況んや近き海辺をや、萬言にあらざるべし。此辺の小村は皆美田の境内にして、税賦も亦同じ。彼小山より寺前を左へ行けば、美田本郷に至る。三方は山にして、未申に向かいては入海の岸上なり、茂樹繁竹の間山路縦横なり、板屋茅屋軒を接へ、田俊船叟群居す、此も亦昔は院の御料とて美田院といふ訝し、何故かあらん。或人曰く造蔵院のある所を院といふとぞ。南に松山あり海の西へ指出たり、越ゆれば遠く波止村につづけり、其間樵路多くして近隣の者薪柴を探り、背の山の東麓より内海を伝行けば美田までは三十一町、其間を大山脇と云ふ。
「按神名帳知夫郡有大山神社此山焼火之神歟、謂之脇則斯山可為大山者可知牟、脇者其麓根之義歟、」
大山脇より南に去る事海路十六町にして、山南に大巌の峨々たるあり、高き事五尋あまり、上に穴二つあり、一口は未申に向ひ、一口は巳に向ふ、内の広さ丈余ばかり、此を文覚が岩窟と云ふ、昔文覚投荒せらるる時、此に居て修練す、小松側に生じ苔蘚石を彩れり、岩下浪翻り怒潮音誼し、遡回して従はんと欲すれば、崖岨て且つ高し、船中より見るのみなり、一島の出たる処の右に廻れば鉢が浦と云ふ。是より西方直に北に行く其山址を波止といふ、先の美田の松山につづけり、此は彼の後鳥羽院の官船を寄せ給ひし処とぞ。谷際に小堂あり、茅屋が軒端の月も見しと製吟ありし堂なり波止村より焼火山に登る村の間、谷水流れ傍ら椿多し。此より山上に至る其路二十町許り、険難九折にしてまた赤土あり、強半を過ぎて少しく平かなる尾上あり、遠望絶景なり、門前に至る処又谷深く径窄にして石肩高く出でたり、波止村より船に乗じ美田に帰ること三十四町、入海を斜に渡りて西に行けば浦郷に至る、其船路二十町あまり。
浦郷
浦郷は東南に向ひ入海の浜なり、西に神祠あり、山の半に城福寺といふあり。里の左の岸に臨み、松老いて風興ある処に専念寺といふあり。人家多く連なり、北の方山に次いで小径あり、越えて下れば外海なり、北山長く列なり、彼船越村を極む。郷の右につづきて薄子浦あり、其山の出でたる処に、由良明神と号する小社あり、極めて小さく古りはてて亡きが如し、里人も知る者なし。「按神明帳知夫郡有由良比女神、乃可為斯社也、恨土人知城福寺之為仏、不知斯社之為神、神在而如亡、呼哀哉。」出たる山崎を右に行くこと遥かにして、荒生城奈尺居形崎なんど云ふ小村、入海の岸に連なり、処々に住居せり。形崎の南の山端より、郷に帰る道一里十二町、山より西の外海に廻り、美田居の崖鯛か崎国が浦賊が崎と云ふ処あり、其間に美田郡と云ふ蜒家あり、餘は皆岩間の釣漁の地なり、又彼形崎山指出て、知夫山の北赤灘山に対し立って海門となり。又東に出て葛島あり、五町ばかりを行渡れば、乃ち知夫山なり。漁翁の曰く斯間勢不恒、或其形如岳嶽、其奮如雷電、膨騰奔激使人見之、則雖丈夫凋顔牟。其湍怒何以到之乎、南有赤灘山、北有形崎山、崖爽勢迫湧而溝高、逆西風当東山沸、湧キョウ無可退消之地如彼浙浙江海門、故数十間島中第一之急灘也、或風微潮平則有。一葦者渡。
知夫湊
並山
赤灘より知夫の本郷なり。故に惣て知夫山と云ふ。赤灘の左に小島あり。棹し囘れば二十餘町にして宇類見と云ふ民村あり。山南の絶頂を卯辰に行く道あり。二十二町を経て二部里といふ。山の趾に巨石多し。みな牙の如し。村老告げて日く。昔此に蘭舎あり。即ち宇類美坊といふ。又南に在るをば二部里坊といふ。此両寺昔は殊に美盡せり。後醍醐天皇の皇居なりといふ。其地の躰も然らんと見ゆ。
按、別府黒木謂之皇居。此地又號天皇行在。蓋先在黒木。後遷于此歟。不然則経営黒木之間姑在於此、終不果而潜幸歟。彼鶏人眠而出於寝所、半夜歩而到干知夫浦。可交見也。若在黒木則何得歩行渡珍崎・赤灘乎。是其一一按也。
二部里より山崎を廻る事三町にして、沖に雁島あり。高きこと三十間。此を廻れば二町四十間。東に去つて麻島あり。高きこと八間。此を廻れば四町三十間。又、二部里より山路の曲折なるも次げり。南より海の入りける所即ち知夫津口なり。左を大居といひ、右を郡といふ。人家分れ、岸に随ひ、津を挾んで列なり、田俊両所にあり。山路を宇類美の菖跡に行けば、山上に願成寺あり。郡の北に松養寺あり。一宮又此に祭れり。凡そ此津は隠州の南岸、雲州に近き浦なれぱ、往來の船多く泊れり。又、東西の旅舟も晴を量り、風を占ふ時は、多く此に集まるとぞ。津を出づれば西の方に多澤村あり。棹し出づれば左に渡島あり。長きこと六町二十間。横は三町ばかり石田あり。西の崎に渡明紳と號する社あり。或人疑ひて日く。此紳は和太酒の社なるべしと云ふ。然れども其よる所を知らず。惟だ言の近きのみなり。南の島崎を大頭と云ふ。此より郡・大居までは十九町。渡島と山岸との間を舟にて行けば、又、海の入りたるあり。西の岸に宇菅といふ小村あり。先の多澤より山を傳ひて來る道あり。六町三十間ばかり。宇菅より二町ばかりにして崎野といふ人家あり。其南の山下を東に廻り西に廻る處、皆嵬※たる岩壁にして、大舶を宿らしむることなし。岸を離れて五町ばかり南の沖に墓島あり。廻り十町ばかり、其上に竹を産す。故に竹島ともいふ。西風激しく潮煙常に潅ぎかかる。此故に竹の色班々として節高からず、葉もまた短し。好事の者此を求むる事多し。然れども四面絶壁にして、而も林中蛇多し。若し此島に至らんと欲する者は、風浪の穏かなるを窺ひ、孤舟に乗りて岸に至り、乃ち舟を岸間に引き上げ、杖を以て地を撃ち、蛇をして蟄居せしめて、而る後竹を伐り、舟を下し、相喚んで帰る。凡そ此知夫山は東西一里二十八町。南北二十一町。山傀儡として木少なく。谷深窄にして田園分る。小径多くわかれ、人家隔て住めり。麦・黍惟税、釣漁惟業なり。東北の海中に小竹島あり。此より海部の崎村に渡ること海路一里五町。
海部郡
崎村
海部郡の西南に指出たる山崎を木槽崎と云ふ。岸聳え山蒼々たり。此より南に廻り、三町餘を渡り行けば、山間三十間ばかり、海の入ること五十間にして崎村に至る。村は岸上の山腹三面に人家あり。松老いて偃する間に神社あり。此を崎村の氏神と號す。其故あるべき處なり。後ろの山に建興寺といふあり。當國の山伏先達の居所なり。海岸を左に行けば大井といふ小村あり。専ら釣網の蜑家なり。又、山を越え、戌亥に下れば、文畳が岩窟に向ひて塘と云ふ海岸あり。村老傳に曰く。此は彼鼠嵩と號する名区なり。俗訓鼓を塘と云ふ。又随ひて字を作ると云ふ。山径を一里ばかりにして布施村に至る。
布施村
布施村は東海西山にして、廣さ十五町ばかり。田園少しく左右にあり。右の山を越えて今浦と云ふあり。左の岸を北に傳ひ行けば、四町ばかりにして臺浦に至る。
臺浦
臺浦は布施に似たる境地にして、海の濱山の下なり。西に廻れば日須賀といふ小村あり。又、内海の西岸にして、殊に陋しき處なり。左に松山あり。此より別府に渡る内海の船路二十町、又、臺より山頭より傳ひ行く事十三町にして知々井浦に至る。其山間に櫻本と云ふ小寺あり。知々井浦
知々井浦は海の入ること遙にして、山崎に松林あり。左殊に指出たり。此を知々井御崎と云ふ。克く東北の風を防ぐ故に旅泊の輻輳する所なり。老人の曰く。昔より傳ひて此地を中の湊と云ふ。此も亦名場なり。島前東南の諸津の半に在るによれりとぞ。山を西北に下れば、又、海濱を保々美と云ふ。浦人の小村あり。其田嶋を西に行く山の尾上に雑樹あり。門の前に巨石出で、活水湧いて冷々たり。石菖蒲茂生ひて岸上は滑かなり。門に入れぱ一堂あり。観音を安置し、清水寺と題す。堂の左に坊あり。樹蓋ひ、苔生じて自ら塵無し。又、山に登り下れば、東分と云ふ小村あり。森郷の内なり。
森郷
海部部の地故国人皆海部と云ふ
森郷は東分より行く。経山を越えて半腹に安國寺あり。岩径斜に登れば遠望懐を伸べ、山容粛條として佛壇高く、窓前松老いて象緯迫れり。人跡稀にして烏雀階除に馴れ、藤蘿木々に掛れども、西渓は晴れたり。願念の便無きにしもあらず。西の山下に西と云ふ小村あり。十八町を過行けば本郷に至る。後は小岡にして松竹陰繁く、人家南に列りて尾上長く指出たり。昔賊徒乱入の時、近隣の諸民此地を要害とし、柵を設けて防き戦ふ。賊軍常に敗続して一人を虜とせず、一處を犯さず、終に奔り帰る。其捷を島後に献ず。時の國守佐々木氏、此事を功として手から書を賜ふ。共状今に至つて此郷の長某が所にあり。郷に入る左の丘に一宇の草堂あり。桑門多く集まり居て、念佛不断の行を修す。其麓の渚に一社あり。諏訪明榊と號す。又、長某が門前を直に行けば田園多し。畦路を分過ぐれば三町ばかりにして山下に源福寺あり。是を葛田山といふ。後鳥羽上皇の御陵なり。門に二王門あり。側に華鯨を懸けたり。此二王は君手づから刻み玉ふと言傳へたり。此より四十間ばかり石※を山に上る。半過きて左に入る。左右松竹凄々として緑薙雛に蔓り、又一小門あり。鞠躬して入れば拝處の前に至る。御廟其後に高し。欄干を設けて階上に登る。四方は皆喬木にして竹籍を引團む。其間は小石隣々たり。遊客も來ること希に、落葉も勤めて掃はず。見るに涙落ち、感慨自ら生ず。小門の前より直に登れば堂前に至る。前庭は廣くして背には樹多し。本堂は胡麻(護摩)を修する地とて五大尊を置けり。煙に薫じて佛も黒し。阿※棚に菊楓折乱せり。堂の左に坊あり。※を隔て空庭あり。其内に方池あり。嶼に孤松の※するあり。此を葛田の池といふ。老僧語りて日く。昔王御遊の夕べ、蛙鳴いて松風吹く。折に遇へば是もさすかに哀なるにや。
蛙鳴く葛田の池の夕疊み聞かましものは松風の音
と詠ぜさせ給へり。是より蛙鳴くことなく、今に到りて然り。門を出で、三五歩だも過きざるに、其鳴くこと常の如し。
元之大徳年中、仁宗在潜邸曰。駐※於懐孟。特苦群蛙亂喧。終夕無寝。翌旦太后傳旨諭之曰。吾母子慣々、蛙忍悩人耶。自後母再鳴。其後雖有蛙而不作聲。後越四年。仁宗登大賓。古人論曰。元后者天命※帰。行在之所雖未践詐、而山川鬼神以陰來相之。不然則蟲魚微物耳。又能聴令者乎。仁宗後登祥。後鳥羽逐崩干茲矣。彼後爲天子。此初爲至尊。雖如有小異。命所以行小蟲者一也。天王之令嚴矣哉。按其令如此。何以王師敗績遂狩遠境乎。夫天壌之内唯理而已。王者継天而爲之子。得其理於心行之。故普天之下無不王土。四海之物不得逆其理。雖小蟲所以聴命也。若行違其理、而王之不王則敗六軍之衆、棄萬乗之位。爲獨夫死邊地。然則天理豈不大哉。戦※可持、王者如此。況其下者乎。
寛永年中に法皇より命ありて、群臣に歌奉らしめて、御舊跡を御弔あり。勅使は水無瀬中納言氏家卿とぞ。其和歌の一巻併に氏家の記行あり。此を寺の賓物とす。寺前を帰りて、諏訪の鳥居の前より田径小岡を経て六町許り、又轉じて西の山下に行く事二十町餘にして、北分を過きて福井村に至る。
福井村
福居村は西山の下、左右に荒田あり。初め此村を福頼と云ふ。比屋貧骨に徹す。一老祝あり。名を改めて福井と云ふ。是よりやゝ住付けり。後の山の一峯の高きを阿堂と云ふ。人常に登らず。登る時は必ず怪ありと云ふ。山の麓を北に越ゆれば菱といふ小村あり。並ぴて菱野といへる處あり。此より内海を舟に乗じて別府に渡る。其間三十二町。字賀村に渡ること十五町。福井より北に出たる山岡を二十町許り行盡せば、又森の郷の境なり。左は内海、右は入海、此口は二町許にして宇津賀村に至る。
宇津賀村
宇津賀村は小山の間、人家分れて住めり。後ろに宇津賀明神の社あり。松山蒼々として風興あり。前に花表を立て瑞離長し。按神名帳、海部有宇受加命社。可爲斯神也。北の山崎を離れて三島あり。三郎島といふ。其沖に小守島あり。島の後津戸の大守に対してしか云ふ。又北に二胯島に併ぴて大岩の出たるあり。此を新島と云ふ。二胯は宇賀の海中なり。昔は此を一村とせしとぞ。村より岡邊を斜に下れば豊田湊に至る
豊田湊
豊田湊は海部の北境、島後に渡る津口なり。左右高く出て右を御崎と號す。沖に向ひて高岸の立ちたるに佛像を刻付けたるあり。一里許り沖に出て松島あり。廻れぱ一里一町。制ありて妄りに入られず。左の岸上に昔小野篁が住みし菖跡あり。潮勢來没※石。廻欄越入二柴扉。故に崎崕の樹根は露れ出でゝ、芽※の前常に船を繋ぎ、天晴れて島後の遠山を見る。
島前
男 二千二百八十八人
女 二千二百九十一人
僧 五十人
合計四千六百二十九人
知夫郡焼火山縁起
神之在焼火山號雲上寺。隠州之南知夫郡之山枕美田縣。立海角秀諸峯。地脈相連数百里。高嶺幽澗幾千仞。麓根曰波止村。自是入山中、松杉交柯、蔭九折之岩路。絶壁石峙、攀葛※之支蔓。具嘗其嶮難則僕痛馬病。然而干春夏干秋冬。干陰晴風雨。有往者、有遊者。有來上而経宿者。其地往來無有虚日。惟神之所有験也。於人事見焉。※有巨岩。其高八十尋。半腹有穴。低頭※瞰不能見底。古來傳云。窟斜去徹山頂也。乃神之所在焼火之夫也。攀欄干到穴前。玉堂蓋美臨深谷。畫棟絆石根之雲。珠簾映海門之月。横峯倒嶺蒼色連、古木奇石天籟島地之殊勝不可敢談矣。伏窺松栢之間則墓嶼・葛嶋・珍崎・赤灘皆目下之壮観。遠眺海煙之上則雲州・伯州之山。或淡難見、或晴可指。朝之晩之時而変化。西方又無彊。海漫々何爲大哉。其記曰。昔一條院之御宇、海中有光数夜。一夕飛而入此山。村人尾之蹐跼而登。忽見一岩濁立其形如薩陀者。各拝稽首而退。仍営一宇以崇之。祷則有験云々。承久年中後鳥羽院狩干斯也。日既暮矣。暴風起波瀾立。乃詠曰。「朕古曾波新島守與隠岐海荒幾浪風心志而吹」。於是風波漸収。然而夜間月没。官船不知所之、漂-泊於中流。風波又欲起。王心念天時、遙火在雲間。其餘光照海。黄郎得便邑從奉賀也。王奇之詠曰。「灘奈羅波藻鹽屋久野土思邊志何遠焼藻乃煙奈類覧」。而後到其津。有漁翁。蹲磯上。勅曰。是何浦。翁封曰。隠州知夫波止村也。王有歌名。今夜海上之製何爲然乎。王勃然問其故。翁曰。焼藻則又何疑。只言焼火則可也。王奇之問其姓名。翁封曰。臣在斯者尚矣。誓護海船言終不見。王爲立祠祭之。以空海法師所刻之藥師佛按茲。號山於焼火。扁寺於雲上。蓋焼火在雲上之義也。上有一壷。神銭湧出。人得其銭則免水難、避疾病。受其銭之例、投二銭受一銭。故日々覃数千倍。雖然無敢溢。又雖祠人・社僧不得私一銭。有用則借以償之不得不納焉。山中有雙鴉。不見其外。常遊堂前。巣山樹。欲客來則啼屋上。噪庭柯。於是社僧.祠人豫知之、出神前以待之。産兒則反哺而去又如恒。高楼有鐘。其傳云。伯州米子里有鋳冶甚左衛門者。常有信心。一日昧爽闕戸。有老僧而立。容貌太嚴也。告曰。隠州焼火山鯨音久断。今年新命雲州能義郡宇波善兵衛者鋳之。到則可以致隠州、其船五艘可在海岸。就中新造船可也。所券之償等云々。而甚左衛門奇之、不妄発。黙以待之。到其日有一人。來日。焼火山之洪鐘鋳成以迭之。問其名則善兵衛者也。曰。曾有僧、來約之。故致之。齋償而帰。甚左衛門走見海濱、有五艘之解纜。中有新舸。問之則知夫郡之賈客也。乃載迭之。社僧驚曰。我自初春到勢州、遊若州、未有此事。正知是神之所爲也。則一造樓、以懸筍虚。遠発宸霜之響、長破旅船之夢。清音無絶而到今也。時元和四年春三月。又伯耆國之大賈村川民自宮賜朱印、致大舶於磯竹島。遇颶風、落高勾麗。日暮不知津。船隻念焼火山。怱有漁火、得入其津。帰帆之後盆尊崇焉。聞者驚懼。此挙其一隅而已。凡如此之類、司柁者、算潮者、運於市船者、爲常談。予亦聞之熟。或問曰。吾聞之、念斯神則必使挙火而識其處、惟爲神歟。似怪請明辮之。答曰。惟神也。非怪矣。夫神之充塞於天地也、古來常理矣。念之必有験也。一心之應者神之感也。村燈漁火自然出。而使之知其處者神之徳也。雖然有應與不應。此亦依一心之誠非神之不爲神。彼胡越同舟倶恐其欲覆、而無有彼此之分也。於是知之。人當急迫之地不入譌於其間。夫恐覆也急。故其念神也實、夫念神之實。故其應之忽。雖異域無不験者是也。其誰不思而敬乎。按。明人称天妃神、而游海者崇信之。是又此神之類歟。可合思也。鳴呼吾曾遊焉。春日渡海黄※遷喬。朝霞一抹、谷風習々。夏雲出則疑前峯。秋葉飛則憶紅錦。槽聲遙入漁村之煙。雪色却映夕日之春。翠眉含雨則爲文君之顰。海面晴來則挙西施之粧。千変萬化非言之所及。惟山容之朝暮余之所眼見也。如其奇談怪説社僧以傳焉。
貞享五年(一六八八)
小物成
浦郷村
竃役銀 銀八二匁
漁請役 銀二○○目
鰯七五俵役 銀一一二匁
とび魚七五束役 銀一五○目
大鯛七五枚役 銀一五匁
和布一○束役 銀一匁
核苧二貫四六○目役 銀六匁五分
牛皮二四枚役 丁銀四八匁
舟数 八二隻 手安舟 一三隻
艫戸舟 七○隻
美田村
竃役銀 銀六○目
漁請役 銀七○目
鰯五五俵役 銀八二匁五分
とび魚五五束役 銀一二○匁
大鯛六枚役 銀一匁二分
和布六束役 銀六分
鯣六連役 銀一匁五分
椎実五升役 銀一匁
柄油九斗六升役 銀一九匁一分
削除 山手塩一二○俵役 銀七二匁
核苧一貫八○○目役 銀四匁分
牛皮一二枚役 丁銀二四匁
海苔五升役 銀五分
舟数 五九隻 手安舟 八隻
艫戸舟 五○隻
小渡海舟 一隻
別府村
漁請役 銀一六匁
鰯五五俵役 銀八二匁五分
とび魚二束役 銀四匁
大鯛七枚役 銀一匁四分
串海鼠八串役 米五升三合
柄油四斗八升役 銀九匁六分
串鮑八串役 米一斗七升八合
核苧三三○目役 銀九分
牛皮二枚役 丁銀四匁
海苔八升役 銀八分
舟数 一七隻 手安舟 二隻
艫戸舟 一三隻
大舟 三隻
宇賀村
竃役銀 銀五一匁
漁請役 銀三七匁
とび魚二束役 銀四匁
和布二束役 銀三分
串海鼠八串役 米五升三合
柄油二升役 銀四分
串鮑五串役 米一斗一升一合
核苧一貫五○○目役
銀三匁九分五厘
牛皮七枚役 丁銀一四匁
海苔一斗三升役 銀一匁五分
舟数 三八隻 手安舟 五隻
艫戸舟 三一隻
大舟 二隻
「焼火山雲上寺・真言宗・寺領十石・神主吉田岩見
知夫郡焼火山縁起
当山は本郷より巳ほ方へ壱里三町也、端村よりは一四町鳥居よりは九町、大山明よりは五〇町在、其路何れも険難九折を経ていたる、嶺に巨岩在り、其半腹に穴あり、是に宮殿を作れり、拝殿より長廊を造り続けり、鐘楼在り、宝蔵有、山上へ行道在て到れば神銭涌出る一壷在り、人壱銭を得る時は水難をまぬがれ疫病をさける、一銭を受けて二銭をなしける故に、日々数十倍に及、しかれどもあえてあふるる事なし、西の方に僧房在、昼夜参拝の客無絶、貴賎を不分饗応をなす、古樹立並て茂れり、山中に双鴉在り、常に堂前に遊ぶ、山樹に巣ふ、客来とする時者庭樹噪ぎ屋上に啼く、是によって社僧祠人は之を知る、神前に出て以待之、子が産れた時は反哺して去る。縁起有、神徳を記して説くにいとまあらず、神火を施して闇夜の漂船を助け給う、凡そ秋津州は言うに及ばず、高麗に到っても神火を請う時は出ずと云事なし、承久の昔し後鳥羽上皇御来島の時波瀾暴風強く、御船中御製在て神火の出事は海士村勝田山に記す、其時より焼火山雲上寺と号すとかや、是上皇の賜所の号なり、晴に望時は雲州伯州の山を見る、曇る時は墓島、赤灘、葛島等も雲霧に阻てらる、気景に勝れたる地なり、他国にも有かねる山なり、所々より多宝物を捧奉る也、宝蔵、ただ神徳の致す処にあらず、寛永之始、水無瀬中納言、勅に依て勝田の御廟へ来りし時、上皇の御取立被成山なれば、昔の跡を慕い御参詣在て、所々巡礼せられしに、彼御寄進の薬師仏も僧房に在とかや、其時之詠歌とて・・千早振神の光を今も世にけたて焼火のしるしみすらん・・短冊に書て在り氏成卿自筆と見へけり」
『新修島根県史ー資料編ー近世(上)』「増補隠州記」一八八頁より
『忠敬先生日記』文化三年(一八〇六)
(是より隠州測量を主とし我等雲州松江城下未次逗留療治ヲ加書す)
七月三日 晴天未明順風ニ相成候ニ付三穂関出帆、
翌四日 昼時隠岐國知夫里郡知夫里嶋江着、旅宿知夫里村枝郷字大江庄屋徳左衛門、着後出候者元方岸八重八・点検役原田祖重・同見習須田定市・大庄屋官蔵・同雇福井村庄屋十右衛門・海士村庄屋愛四郎、後刻(雲州候より)岸八重八ヲ以左之通贈物有之、金百疋宛 高橋善助・坂部貞兵衛下河辺政五郎、銀三両宛 宛内弟子六人、銀弐両宛 僕四人、右之通進物有之侯ニ付受納いたし置侯得共、先預ケ置、追而江戸表江帰府之上伺済ニ而受取可申旨相断、右八重八江預ケ遣ス
七月五日 晴天、一番下河辺・佐藤・栄次 勘嶋 浅嶋神津嶋 波鹿嶋右四嶋各一周、小波鹿嶋ヲゴケ嶋 遠測、二番高橋・稲生・門倉・惣兵衛知夫里村大江旅宿下より右旋、同枝郷宮谷 郡 太澤 薄下 先野を過而字竹浜迄測ル、三番坂部・小坂・吉平知夫里村大江旅宿下より左旋、同枝郷仁夫里ヲ過而字ハナレ迄測ル、右終而各大江へ戻り再宿、尾形・、永澤・角次不快ニ付大江ニ逗留
七月六日 晴天、二番坂部・小坂・吉平知夫里嶋字竹濱より始メ右旋、来居 古海ヲ過而字ハナレ〔埼〕ニ至り知夫里嶋一周ヲ結ブ、俵嶋 弁才嶋 腕嶋 離嶋 各遠測、右畢而西之嶋 浦ノ郷村持大桂嶋江渡り一周、一番門倉佐藤・栄次西ノ嶋江移り、知夫里郡浦ノ郷村之内字赤灘鼻より始メ左旋字国川迄測ル、高橋・下河辺・稲生・尾形昨夜木星交食測量ニ付今日休ミ午中ヲ測ル、右畢而各浦ノ郷村江移り泊ル、旅宿浦ノ郷村庄屋幸十郎、永澤瘧疾ト成ル
七月七日 晴天、一番下河辺・門倉・栄次浦ノ郷村字国川より始メ左旋、美田村之内字ニグ迄測ル、ニ番坂辺・小坂・佐藤・吉平 字赤灘鼻より始メ右旋、浦之郷枝郷赤之江 生名 荒生 臼子より浦ノ郷村泊り下ヲ過而美田村堺迄測ル、三番高橋・稲生・惣兵衛浦ノ郷美田村境より始メ美田村枝郷 船越 小向 大津 市部 ヲ過而橋浦人家下迄測ル、夫より焼火山江登り山々測量、旅宿美田村枝郷市部庄屋栄次郎
七月八日 晴天、二番下河辺・門倉・栄次美田村枝郷橋浦人家下より始メ、焼火山麓通り別府村堺迄測ル、一番高橋・佐藤・惣兵衛美田、別府村堺より始メ、宇賀村枝郷蔵ノ谷大宇賀ヲ過而字済ノ浦ニ至り、三番手卜合測、三番坂部・稲生・小坂・吉平実田村之内字二グより始メ左旋、別府村ヲ過而宇賀村之内字済ノ浦ニ至り一番手卜合測、星神嶋遠測、右終而各宇賀村泊り、旅宿宇賀村之内物井庄屋勘十郎
七月九日 朝曇天雨昼後晴天、一番下河辺・稲生・門倉・栄次海士郡中ノ嶋布施 福井村堺より始メ右旋・布施村之内ヒスカヲ過而崎村松屋岬ニ至り打止メ、崎村泊り、尾形痛ニ付物井より直ニ崎村江行、永澤瘧疾ニ付昨八日市部ニ逗留いたし、今日市部より直ニ崎村江行、
旅宿海士郡崎村渡辺半次郎、ニ番高橋・佐藤・惣兵布施 福井村境より始メ左旋福井村枝郷菱村ヲ過而・同村之内字ツラハゲニ至り三番手卜合測、三番坂部・小坂・吉平海士郡海士村字ニタ子より始メ右旋、同村枝郷多田北分海士村本郷を過而福井村字ツラ禿ニ至り二番手卜合測、右両手泊り、海士村庄屋愛四郎
七月十日
晴天、三番坂部・小坂・吉平海士村字二タ子より始メ、宇津賀村 豊田村ヲ過而、又海士村地内ヲ通り知々井村枝郷保々美人家下迄測ル、二股嶋遠測、一番下河辺・稲生・門倉・栄次崎村松尾岬より始メ、布施村 太井村ヲ過而知々井村人家下迄測ル、二番高橋・佐藤・惣兵 豊田村持松崎 知々村持苜苜小嶋各一周、右各測量畢而泊り、知々井村旅宿 百姓弁之助・入亭主年寄 忠次郎
七月十一日 薄曇、嶋前より嶋後江移ル、小坂・佐藤・吉平海士郡知々井村泊り下より始メ、右旋御崎ヲ廻リ同村枝郷保々美迄測り、中之嶋一周ヲ結ブ、高橋・坂部・下河辺・稻生・尾形・門倉昨夜太陰木星ニ近く、依而夜中測量ニ相掛り候ニ付、今日知々井村より直ニ嶋後江行、
縁起
神代の昔、天鈿女命を従えた天照大神は三度の「鯛の鼻」の北にある「大神(おおがみ)」という海の「立島(たてじま)」に降臨された。この島は細く天を突くような岩があたかも亀の背に乗っているような島である。ここにはこの時の「お腰掛けの石」もあるが、やがて天照大神は三度湾に船を入れて南の「長尾鼻(ながおばな)」にある「生石島(おいしじま)」に上陸された。最初この場所から少し東の海岸に目をやると、人影が見えた。神は「人のいそうもない海岸に、不思議なことだ」と言って、そこへ行ってみたが、誰も居なかった。そこで「生石島」に引き返して振り返るとやはり人影が見えた。もう一度返って捜したが誰も居なかった。・・三度目には意を決してその先の集落まで行ったので、ここを「三度」というようになった。人影と見えたのは、実はこの場所に何回かお迎えに出ていた猿田彦命の姿であった。常に人影が見えたので、ここには「常人(じょうひと)」という地名がついた。またこの湾の「生石島」にも天照大神が腰を掛けたところから、地区の人は「お石様」と名付けて崇敬している。それに途中では水のある処を越したのでそこには「越水(こしみず)」という地名がついた。三度の集落に入ってからは、中谷正宅の裏にある石の上で休息された。それでこれを「お腰掛けの岩」と言っているが、近年までこの石に注連縄を張って祭っていた。ところで、天鈿女命は近くの山に登って「天照大神の鎮まります地はどこがよいか」と辺りの峯々を見回した。そこでこの山を「峯見山(みねみやま)」と呼ぶようになった。峯見山から南東に見えたひときわ高い山に天照大神をお連れして、しばらく鎮まっていただいた。この山は珍崎の南にあって、あくまでも仮の場所なので「仮床(かりどこ)」という地名をつけた。一説に、この山で狩りををしたので「狩床」になったともいう。さて、天照大神はここで七谷七尾根ある場所を捜した。その時「この山には谷が一つ足りない」と言って持っていた筆に硯の水をひたして一滴落とした。するとたちまち小さな谷が一つできて、これを「硯水」といった。また、その筆で手紙を書いて大空に投げ上げたところ、この山の頂から二羽の烏が飛んできて口にくわえた。そしてはるか東方に見える焼火山を目指して飛んでいった。烏の飛びだした場所には「烏床」という地名がついた。焼火山の神様は、この手紙を受け取って神勅とおぼしめし、早速聖なる大宮所を選定して報告した。それを受けて猿田彦命と天鈿女命は天照大神を焼火山の大宮所にお連れした。こうして焼火神社は天照大神をまつることになった。それに手紙をくわえて飛んだ二羽の烏は後に焼火山内に棲みつき、いつもこの神社の境内に来て遊んだ。参拝者があると、境内の木の上から鳴き、神殿の上から騒いで神社の人に知らせた。子供が生まれると、その役目を譲って親烏二羽はいなくなるという。その後、猿田彦命と天鈿女命は三度の海岸の「奈那」という所で雌雄二つの石を産み、神光を発しながら亡くなった。村人はこの二つの石を亡くなられた二柱の神の霊魂の寄代として崇め神社を建てて祭った。その場所は猿田彦命が天照大神を待っていた所であったので「待場(まちば)」と命名し社名も「待場神社」とした。一方、焼火山の神様は別名を「千箭(せんや)の神」といった。これは神功皇后が三韓に出兵するとき、弓矢を携えて出現なされ、待場・峯美の二柱の神を引率して従軍されたからである。千の矢を放った場所は三度崎の「追矢床(おいやどこ)」であり、その矢が韓の国まで走っていったので「矢走(やばしり)」という地名もついた。軍馬を出された所は「御馬谷(みまだに)」といった。
『隠岐島の伝説』より
一条天皇の昔、西ノ島の海上に、夜になると明々と燃え盛る火があった。それは数日続いた後に、飛行して西ノ島町の最高峰焼火山上に入った。驚いた村人がこれを追って登ってみると、山頂近くに高さ数十メートルの岩壁がそそり立ち、それがあたかも仏像のように見えた。そこで村人はこれを拝み、その場所に一宇の堂を建てて祀ったのが「焼火山雲上寺」の始まりである。この寺は別に大山権現・焼火権現などといわれた。また、明治五年には焼火神社と改称されたが、この神社のある焼火山には、今でも大晦日(旧暦)の夜になると、南の海から火の玉が昇って行く。それは、知夫村古海の俵島を通過して、山頂近くの「灯明杉」にかかり、やがて本殿内の常夜燈に移って燃え盛る。里の人はこれを海神が焼火神社の神様に神燈を捧げるからだといってこの夜参拝するが、漁師や船乗りはこの火をことのほか篤く崇敬している。そしてこの神燈が盛んに燃えた次の年は必ず豊漁であると信じられている。一説に、俵島を通過した火の玉は、一つは焼火山上に上がり、もう一つは島後の大満寺山に昇り、最後の一つは出雲の国の枕木山華蔵寺に入るともいう。また、焼火神社の神様は、暗夜に漂流する船を救助するという。時化に遭って、海上で万策尽きたとき、焼火の神様に祈願すると、三筋の光が現れてくれる。その中央の光に船を向けると必ず安全な港に入ることが出来ると伝えたれている。
『隠岐島の伝説』より
むかし一条天皇の御宇、このあたりの海中に光り輝くものが現れた。住民がふしぎがっていると、やがてある晩、その光が飛んでこの山に入った。住民が登って見ると、そのに薩陀のような石が立っていた。人々は恐れつつしんでそこに一宇の御堂を建てた。時代は下がって承久年のこととなった。倒幕の企てに失敗された後鳥羽上皇は、都からはるばるこの隠岐島に流されて来られた。ところが日暮れて波高く、御座船は今にも沈みそうになった。上皇は一心に念じ、一首の歌を詠まれた。「われこそは新島守よ沖の海の荒き波風心して吹け」。すると波はおだやかになった。しかし暗夜のこととて方向がさっぱりわからない。そのうち風雨がまた起こり、御船はまたゆれ出した。上皇は必死になって祈念された。するとはるか彼方の空に一点の光が現れ、それが海上を照らした。そこで上皇は、「灘ならば藻塩焼くやと思うべし何を焼く藻の煙なるべし」と詠まれた。こうして上皇はとある港に着かれた。するとそこに一人の老翁がうずくまっていた。上皇が、ここはどこかとたずねられると、老翁は、隠州知夫の波止というところでございます、と答えた。そしてまた、今夜海上で歌をお詠みになりましたが、なぜあのようにお詠みになりましたか、と問う。上皇が何のことかと聞き返されると、あの「何を焼く藻の」というところが少しおかしいと思います。「何を焼く火の」といえばよいではございませぬか、という。上皇が驚いて、お前は何者か、と問われたが、老翁はただこのあたりのものでございます、というだけで、深くは答えない。そして誓って海船をお守りいたしましょうといったと思うと、急に姿が見えなくなってしまった。上皇はのちにこの山上に祠を建て、弘法大師が刻むところの薬師仏を安置し、焼火山雲上寺とされた。これが焼火山の起こりである。この山上に一つの壷があり、そこから神銭がわき出す。これが水難よけのお守りになるとして、方々から受けに来るものが多いが、そのときには必ず二銭を投じて一銭を受けるというふうにするので、その数はふえる一方である。山中に二羽のカラスがいる。常に二羽いてそれ以上にはふえない。参拝者があるとこれがさわいで社人に知らせると・・
『出雲隠岐の伝説』「隠州視聴合紀」より
「焼火山雲上寺・真言宗・寺領十石・神主吉田岩見当山は本郷より巳ほ方へ壱里三町也、端村よりは一四町鳥居よりは九町、大山明よりは五〇町在、其路何れも険難九折を経ていたる、嶺に巨岩在り、其半腹に穴あり、是に宮殿を作れり、拝殿より長廊を造り続けり、鐘楼在り、宝蔵有、山上へ行道在て到れば神銭涌出る一壷在り、人壱銭を得る時は水難をまぬがれ疫病をさける、一銭を受けて二銭をなしける故に、日々数十倍に及、しかれどもあえてあふるる事なし、西の方に僧房在、昼夜参拝の客無絶、貴賎を不分饗応をなす、古樹立並て茂れり、山中に双鴉在り、常に堂前に遊ぶ、山樹に巣ふ、客来とする時者庭樹噪ぎ屋上に啼く、是によって社僧祠人は之を知る、神前に出て以待之、子が産れた時は反哺して去る。縁起有、神徳を記して説くにいとまあらず、神火を施して闇夜の漂船を助け給う、凡そ秋津州は言うに及ばず、高麗に到っても神火を請う時は出ずと云事なし、承久の昔し後鳥羽上皇御来島の時波瀾暴風強く、御船中御製在て神火の出事は海士村勝田山に記す、其時より焼火山雲上寺と号すとかや、是上皇の賜所の号なり、晴に望時は雲州伯州の山を見る、曇る時は墓島、赤灘、葛島等も雲霧に阻てらる、気景に勝れたる地なり、他国にも有かねる山なり、所々より多宝物を捧奉る也、宝蔵、ただ神徳の致す処にあらず、寛永之始、水無瀬中納言、勅に依て勝田の御廟へ来りし時、上皇の御取立被成山なれば、昔の跡を慕い御参詣在て、所々巡礼せられしに、彼御寄進の薬師仏も僧房に在とかや、其時之詠歌とて・・千早振神の光を今も世にけたて焼火のしるしみすらん・・短冊に書て在り氏成卿自筆と見へけり」
『新修島根県史ー資料編ー近世(上)』「増補隠州記」一八八頁より
<書跡>紙本墨書、焼火山縁起書一巻。所在地、隠岐郡西ノ島町焼火神社。所有者、焼火神社(宮司、松浦康麿)。指定事由、焼火山縁起の近世に於ける集大成であり、奥書は万治二年秋八月とあり。作者は松江藩士で寛文年間隠岐郡代を勤め「隠州視聴合紀」を著した斎藤勘助豊宣で斎藤家の二代目である。この仁は隠州視聴合紀を著わすほどの人であるので、郡代勤務中たまたま焼火山へ登拝し、当時の別当より色々と縁起につて聞き、それをまとめたのが本縁起であろう。豊宣は「焼火山縁起」のみでなく、「文覚論」も書いており、そのいずれも視聴合紀の巻末に載せている。また、この外に「焼火山由緒記」もあり、この中には当時の龍灯祭の事に就いて記している。奥書、干時萬治二年秋八月。雲陽散儀生藤、弗纈緩子誌。とあるが弗緩子は豊宣の号である。現存のものは、「延宝九年」松江藩士静宇木子の筆になるもの。これは前期豊宣書のものが相当破損したので上書して巻子に仕立てたものである。島内にも縁起書の残った神社も数社あるが、半紙綴のものが多く、これらの代表として本縁起を指定した。(松浦記)
『隠岐(島前)の文化財一五号』
伝承
神仏に心願成就を祈念する時、その礼物をあらかじめ神仏に約束してから立願する方法がある。その御礼奉賽に参ることを「願開き」というその献納物はいろいろであるが、焼火神社に於けるものは、
千本幟の願
これは島前どこの神社でもある方法である。五寸位の長さの割竹をけづり、それに巾一寸五分位の紙を幟形に巻いたもの千本。鳥居から拝殿までの参道の両側に立てる。これは戦後も続いていたが、現在は殆ど見られなくなった。
金(かね)の鳥居の願
金の鳥居というと聞こえはよいが、鉄板又はブリキで高さ巾共五・六寸位の鳥居を献納する。神をあざむくもはなはだしいと思うが、ただし当人は初めから右様の物を考えているから神をだましたという意志はないはず。これは今でも時々ある。
ジンメの願
「ジンメ」は恐らく神馬であったと思うが、その方法は馬と関係ないのではっきりは言えぬ。おれは心中にジンメの願を掛け、願成就の時には参詣してその旨を申出て最小一日から長い者は一週間位神社の雑役奉仕を願出た。今流にいえば勤労奉仕、天理教でいう「ヒノキシン」と同じ考え方である。仕事の内容は境内の掃除、祭礼時の荷上げ、春詣りの賄手伝等々が主であったという。変わった処では裁縫をさせてくれと申出た者もあった。これは大正の中頃まであった。
流し木の願
これは岡山県和気地方で行われている方法である。この地方では「隠岐の焼火の権現は一生に一度は必ず命を助けて頂く事の出来る神様」といわれており小願は一週間、大願は二十一日間自宅に於て祈念をする。そして満願の時は奉賽の為に「流し木」をする。木の大きさは人それぞれに異なるが、一間から三間位までの丸太を近くの吉井川に流すとそれが焼火権現に届くと伝えられている。(岡山県和気郡佐伯町用賀藤原栄氏開願の為に参拝、談)
木を植える願
これは開願の時神社に参って境内に献木植樹するもの。鳥取県八頭郡智頭町方面で行われているもの。この地方には別に人の目につかぬ奥山に入って「焼火権現の方に向かって人火を焚く」という方法もあるという。最近あったのは昨年三月智頭町戸板定雄氏が檜苗五本を持って参拝した。
蚊帳に入らぬ願
私の少年の頃まで、夏になると蚊帳に入らぬ願をしていたからといって、夕方に参拝して客殿でお篭りをして帰ったものである。蚊の多い処で蚊帳に入らぬというならわかるが、私の山の家はあまり蚊がいないので、蚊帳は一帖もない。この開願などはユーモラスがあって面白い。以上が焼火神社に対する「開願」の方法である。庶民信仰として面白いと思い記してみた。
『隠岐(島前)の文化財六号』
船越の奥に高崎山という山があり、そこには古い寺跡がある。昔、この寺の住職良賢和尚は焼火山雲上寺をも掛け持ちで務めていた。生まれは九州薩摩の人であり、愉快なのは魔法飯綱を駆使したことだ。たとえば焼火山に客が来ると「高崎山に茶を忘れてきた」などとつぶやいて書院に入り天狗に命令してすぐに持ってこさせたという。また、高崎山の弥山(みせん)という所には「白滝」という場所があって、そばに一本周囲四メートルの大杉があった。これは天狗集合の目印の杉であったという。寺跡から東に一キロばかり行くと「傾城が床(けいせいがとこ)」という場所がある。この寺は女人禁制の霊場だったので傾城が床には大きな家を建てて、そこに遊女を数人置いていた。そして、寺に参詣人があると良賢和尚は寺内の男達と共に参詣人を連れて傾城が床に出かけて酒を飲み遊興の限りを尽くした。それで「傾城が床」という地名がついた。そこから南西に七〇〇メートルばかり下ると「魚切」という所がある。ここは「傾城が床」で必要な料理を作った場所である。後に美田の長福寺の僧侶で覚文坊という男が高崎山にこもって飯綱の法を修得しようとした。ところが、どうしたわけか、この山の天狗に嫌われてうまくいかなかった。その上、この山に七年いたが七年とも不思議に台風が吹いたので、ついに里人の願いによって覚文坊は山を下ろされた。そのときから、高崎山の寺は次第に衰え、本尊の薬師如来は別府の千福寺に移されてしまった。今はその千福寺も失われてしまった。
『隠岐島の伝説』より
焼火神社の特殊の御守に「銭守(ぜにまもり)」がある。これを江戸末期頃まで、江戸に於て頒布していた記録がある。「御尋申上候一札之事。松平出羽守様御屋舗深造院内不動尊脇へ焼火山之写ヲ拵へ御相殿ニ被為成、是江戸隠州方ヨリ神銭御望ノ儀申来候節、其ヨリ仰聞候ニ付差出運送(中畧)同所ニ於テ御取扱ナサレ候由ノ処、以来ハ右神銭深造院へ請込ミ諸方望ノ仁へ相伝候様ニ相成候テモ差障ノ儀ハ無之ヤノ旨御尋ナサレ候処、右両様共差障ノ儀御座ナク候此段御請申上候以上。隠州焼火山別当、雲上寺(印)弘化二年八月。御役所。」また、弘化三年「御尋ニ付申上候演説之覚」の一札もある。この内容は神銭の授与料についてであり、一二銅で授与しているが、その内六銅は今まで通り深造院の方で取り六銅を当方に送る。また「神銭壱万銅位宛御望ノ儀申来候ニモ差支ノ儀無之」云云とあるところからすると年間江戸で一万体以上の神銭を授与していたようである。この神銭については当社の縁起書にも書かれており、それによると「山上ニ壱壷アリ神銭涌出ス」云々「二銭ヲ投シ一銭ヲ得」とあるように二銭をあげて一銭を頂いて御守としたようである。霊験の方は「水難ヲノガレ疾ヲ避ク」とあるが、江戸の翫銭好事家の記録「板児録」には「火難、盗難除の守」となっている。当方に「天保三年、年中御札守員数」という資料があり、年間の集計が個所をあげると、一神銭七九〇〇銅、御供一二四〇、疱瘡守一七一六〇枚、牛壬一五〇〇余、大御影一六〇〇余、小御影三九〇〇とある。右の神銭の数は江戸に送ったものも含まれているかどうかはわからない。右によってその時代の振興の内容も伺われて興味深い。疱疱守一七〇〇〇余は驚きである。今は殆どみなくなったが、旧字には正月に疱瘡神を祀るヒモロギ様の小さい台があったのを覚えている。神銭守は今でも神社で出しているが往昔のように受ける人は数える程しかいない。こちらでは、錠が海底にかかって取れない時とか網が掛って取れない時、おもしろいのは猫にばかにされた時神銭(一文銭)の穴からのぞくとよいなどといわれている。神銭が通貨であるのも特徴である。(松浦記)。
『隠岐(島前)の文化財一七』
隠岐の北前船
「御拝借米」という米を島民が借り受けて銀納で返す制度は元禄期には慣例化していた。逆にいえば、銀納の方が可能性があったという事かも知れない。つまり穀物以外に貨幣化可能な生産物があったという事ではなかろうか。即ち、島前の年貢は銀納の方向にしか可能性は見出せなかったのである。
島後では寛文9年(1669)には江戸に木材を送っており(寛文8年の江戸の大火の為か)「増補隠州記の記載から」
1672(寛文12年)美保関港制札写では隠岐国からの荷物が薪・材木・魚・海藻となっている。 北前船 西廻航路の開発
寛文12年(1672)河村瑞賢が西廻航路の開発。北前船は近江・加賀・越前・能登・大阪等の廻船問屋が大阪に根拠を定め、大阪と松前間の貨物の運搬に使用していた千石船である。旧正月あけに大阪で「囲い」を解いて縄・砂糖・菓子・その他の物資を積んで出発し尾道、馬関海峡を経て旧六月、七月ごろ隠岐に寄港する。これは下りの船であって主に大山に寄港することになっていた。これは二百十日付近の荒日を避け風を待つためであった。そこで一ヵ月ほど停泊してハエの風の吹くのを待って出帆し順風に送られた十日前後にして松前に達し、鰊・昆布などの海産物を積んで今度は八・九月頃には再び隠岐に寄港する。これは上がりの船で、この時は浦郷に寄港した。 これが一般的には隠岐の流通経済の先掛になったと言われているが、西廻航路が開発されてから、すぐに隠岐島が風待港になったわけでもない。北前船の沖乗り(港から港の距離が、沖を通るとこによって長距離になり、短時間になる)が可能になって初めて風待港として繁栄するのである。
北前船の外観
千石船とは千石積みの船で大体二四反くらいの帆を上げたものである。一枚の帆を益すと千百石、二枚帆を益すと千二百石積みという具合いで数えられたという。(後にこれは大和船と呼ばれ、西洋船と区別される事になる)
小渡海船は、千石船には充たないが80石未満の貨物船をいい、幕末からはこれが隠岐島地元の主力運搬船を多く占めることになる。
西洋型船(帆前船)とは、西洋型のマストを立てた船(大和船よりも帆が前にあるのでこう呼ばれたのではなかろうか)。船の大きさもトン数に変わってくる。明治20年代に隠岐島に初めて入港する。
機帆船は、機械動力を伴ったエンジンを備えつけた帆船をいう。 北前船入港推移表
表のサンプルは大山の元問屋の資料であり、これは10年毎をまとめたものであるので年間の入港量は平均10で割らなければならない。例えば、天保10年に大山の元問屋に入った船数は60隻と最高であるが、この時には西郷は630隻と約30倍である。即ち、このデータは西ノ島(旧美田村の大山)の一問屋のみの資料なので、隠岐全体となると年間に4千5百隻くらいは入港していたのではなかろうか。
北前船の船籍
隠岐に入った北前船の船籍は加賀1325・越中917・越後470。この3地区の合計(2712)は全体の6割を占めている。だから全体は4520隻くらいではなかったであろうか。
船数推移表
上記で見られる様に、隠岐の地元ではあまり千石船は多くなく、次第に小型廻船が増えてきている。すなわち隠岐の産物は小型廻船によって主に輸送していたと思われる。
船の運送料金 「船方賃銭之覚」 『近世隠岐島史の研究』245。
天保9(1838)・安政5(1858)。単位は銭が文
| 行先 | 天保9 | 安政5 |
|---|---|---|
| 能代 | 10,500 | ? |
| 秋田 | 10,100 | 10,100? |
| 庄内 | 8,500 | 8,500 |
| 新潟 | 8,000 | 8,000 |
| 三国 | 3,000 | 4,200 |
| 敦賀 | 2,600 | 3,400 |
| 小浜 | 2,500 | 3,200 |
| 丹後 | 2,300 | 3,000 |
| 但馬 | 2,200 | 2,600 |
| 因幡・出雲 | 2,000 | 2,300 |
| 江崎・須佐 | 2,300 | 3,000 |
| 萩 | 2,500 | 3,200 |
| 瀬崎 | 2,600 | 3,300 |
| 油谷 | 2,700 | 3,600 |
| 下関 | 3,000 | 4,000 |
| 長崎 | 6,000 | 8,000 |
| 讃岐・備中 | 6,500 | ? |
| 大坂 | 8,000 | 10,000 |
北前船の船員
船頭一人・オモテ一人・ワキオモテ三人・マカナヒ一人・隠居一人・船子二四、五人である。船頭は普通の船頭と異なり金の番をする者であった。オモテが船の指揮にあたり、ワキオモテ三人はそれを補助する。マカナヒは会計をやり、隠居は船所帯の世話をした。船子は帆一枚に一人の割合であったようだ。船子の出身地は各船主の国の者が比較的多かったが、島前でも浦郷だけで一四・五人くらいが船子になっていたそうである。船頭は給料の他に定石以上(千石船なら千石)に荷物を積んだ場合、その余分は自分の収入となった。このことをハセニと言う。そうしたハセニの部分は船子達にも臨時の収入責任となっていた様だ。逆に定額に充たない時は「カンガキタ」といって足りない部分だけ船頭以下の船員の責任となったのである。
北前船寄港中の様子
風待港として繁盛したのは大山と浦郷であり、そこには問屋と附舟屋(つけふねや)があり、惣嫁(「ソウカ」と読む。売春も兼ねた、船員の酒の付き合いをしたり、芸もしたりする酌婦)も沢山いたようだ。問屋は船頭やチクが泊まる処で、浦郷には古くは渡辺という家が一軒しかなかったが、明治二○年頃に寅屋という宿に代わったそうである。附舟屋は小宿ともいい、船子達が船の着いた時か、寄港中とかに来て、そこで休んで問屋に出掛けて風呂に入ったり惣嫁と遊んだりする処で、浦郷には三・四軒あったという。大概の船は附舟屋も定まっているのが常であり、新たに寄港した船は最初港に入って来て、一番先に船綱を受けた船の附舟屋に行く事になっていた。派手な帆船時代の船員であるから一ヵ月くらいにわたる停泊中には相当な金を隠岐に落としていったものらしい。明治二○年から三○年にかけては一隻につき一日十円くらいの金を費やしたという。当時多い時には島前に五○隻から七○隻の千石船が入っていた。
北前船回顧
北前船が入港の際には、各船は相当の間隔をおいて入ってきた。港内にいくら船が多くても、帆を一杯に張ったままでどんどん入港し、錨を下ろすと同時に帆も一度にドッと下ろした。何故こんな危険をおかしたかと言えば、帆を一杯に張っていなければ、かえって舵が利かなかったからである。それ故肝の小さいオモテ師などはウロウロして船を当ててしまうこともあった。また帆を一気に下ろしたので帆の半分くらいを海中にたたき入れることも多かった。帆が下りると同時に赤褌のカシキがハヅナを口にくわえて海中に飛び込む。寒い時雨の時分にはこれが殊に勇ましく見えたものである。船が入ってくると附舟屋達は各自の小船をこぎだしてそれを迎える。そして入港しようとする千石船はその附舟屋の小船を目掛けて綱を投げ、その綱に早くとりついた船に客として行くことになっていた。四時頃夕飯を済ませると、船員一同が揃って伝馬船をおろし、二○人くらいの船方がが乗って裸で上陸する。ヤサホイ・ヤサホイ・エンヤラエーの掛け声で、櫂一六挺くらいをもって漕いだ。大櫂は会計方のチクサンが必ず取ることに定まっていて、大概皆んな居櫂(いがい)で漕いだが、中には伊達な船もあって立櫂(たてがい)で漕ぎ、櫓を押す時には一同立ちあがり、ひく時には一斉に後に倒れる。これは見ていると何とも見事なものであったという。こうして上陸した船員は附舟屋に行って多くの場合は席に並んでいる惣嫁を選んで泊まるのだが、その際宿や惣嫁に支払う金はいづれも金一封であったので、船が出てからでないといくら出したか判らなかったそうである。北前船は縁起をかつぐ。出船しようとしても上げかけた錨を惣嫁が再び海へ下ろすと出帆を延期し、その日は決して出船しなかったそうである。
「北前船は、ほとんど隠岐の産物の取引は無かったようである」(今崎半太郎談・昭和11年現在のインタビュー)(今崎氏の北前船とは、隠岐を風待港として利用した他国の千石船の謂いであろう。だから隠岐の船は同等の事業をしていても北前船とはいわない)しかし、航路の開発によって、隠岐島民の中から積極的に北前船に参加する者が増え、これが近世の隠岐の経済活動をになってきた。
情況調査書(明治42年) 黒木村(1909)
「船ノ数。日本型船二二隻(三八二○石)西洋型船五隻(二六九トン)、西洋型船」「船舶の出入り。一ヶ年概数一六○隻(定期船を除く)多くは他国商船にして一時仮泊するものなるが故に貨物の集散等の影響少し只真に本島の交通機関と見るべきものは前項に掲げん船舶と定航海の汽船なり。・・」
浦郷村(1909)
「日本型船一隻(一○四石)」「船舶の出入。一ヶ年概数三○隻(定期船を除く)にしてそれらは主として他国商船の風波を避くる為順次寄港する者なるが故貨物の集散等に何等影響なし・・」
海運と経済 「増補隠州記」から判る事
1688(貞享5年)「増補隠州記」特に島後では「材木・薪伐出シ商売ニ仕ル今ハ尽キタリ」とある所をみると、この時代には既に商品としての材木は尽きるほど移出されていたことになる。
鯖・鯵・烏賊・鯛・鰤・アゴ・シイラなどが採れていた。即ちこれらの流通範囲はすべて異なっていた。それに加えて税も課されていたのである。鯖網も一般的に普及していた。小物成(鰯・アゴ・ワカメ・鯛・スルメ・海苔・串鮑・串海鼠)
1744(延享元年)俵物集荷の実をあげる為、幕府は長崎商人八人と、その下に俵物手請負方を定め、さらにその下に指定問屋を設けてこれにあたった。
1725(享保十年)には鳥取藩は米子に自由市場方式をとったのでますます松江との格差が大きくなり、米子・境港への集荷が多くなって行く。
(天明五年以前1785)町人請負-地元船-民間問屋-隠岐との貿易をする-各地へ輸送-産物価格は自由変動 長崎会所直買制度
天明五年(1785)指定問屋-長崎商人・民間商人-地元船の運搬
(天明五年以後1785)「長崎会所直買制度」役所請負-御用船(地元船雇)-指定問屋-隠岐との貿易はせず-直接に下関へ輸送-長崎俵物価格は低安定
民間問屋と海運
村々にスルメ問屋ができる様になった。元々は御用問屋のみであったが、次第にスルメだけは需要が多かったので、民間でも問屋をして、それを商売スルメという様になり、この商売問屋が独自のネットワークを張り、次第に隆盛していった。(米子・境港方面に)
北前船以後 陸上交通関連事項
鉄道の発達により、船が鉄道よりも大量・安価な運賃を提出できないようになったため、次第に材木・海産物も移出コストが低くなっていったものと考えられる。
(明治18年)隠岐汽船株式会社発足
(明治33年)陰陽連絡鉄道(姫路・鳥取・米子・境間)工事着工
(明治35年)米子・境間鉄道開通
(明治44年)大阪商船の大阪・山陰線、下関・境を連絡地として国有鉄道と旅客、貨物の船車連絡開始
(明治45年) 一畑軽便鉄道株式会社創立
(大正2年)大阪商船、下関・境線を米子・安来・馬潟に延航(11月より隠岐浦郷・菱浦・西郷に変更)
(昭和3年)国鉄伯備線全通
(昭和6年)山陰線京都・下関間全通
(昭和12年)木次線全通し芸備線と接続、陰陽連絡
北前船が明治30年を境に激減したとしても、なお地元の船は産物・貨物の運搬として使用されていた。
隠岐の海運業の衰退は、移出物の激減と漁船の大型化による運搬船の不用によっている。 移入物は隠岐汽船程度で賄えたのである。
問屋(とんや)
西ノ島でよく耳にする屋号にトンヤというのがあるが、これは隠岐島の近世・近代において一世を風靡した、流通業の記念ともいえる名前である。 今でいう問屋とは一般的には卸売業のことであるが、近世においては必ずしもそれだけではなかった。特に幕府から指定された「問屋」は、卸売よりもそれをチェックする検査官の意味あいが強かった。自分で卸売業をするせよ、検査するにせよ、いずれにしても隠岐島の近世から近代にかけては、流通を抜きには語れない時代であった。その鍵を握るのが問屋である。 隠岐島で問屋が文献に度々出てくるようになるのは、北前船の入港が頻繁になってからであるが、問屋を必要とする流通経済はそれ以前に十分に発達していたと思われる節がある。 島後では寛文年間には既に江戸に木材を輸出し、美保関には薪・木材・魚・海藻などが頻繁に隠岐国から送られてきたと記録に残されている。また、寛文元年頃には年貢を物納ではなく貨幣で納める方法も考慮され、後にはそれが慣例化された程に貨幣経済は浸透していた。隠岐島では貨幣収入の道は、貿易を基盤にして拡大されていった。 寛文一二年(一六七二)河村瑞賢によって西廻航路が開発され、これが一般的には隠岐の流通経済の先掛になったと言われている。しかし隠岐の回船業は、少なくとも江戸初期から行われていた可能性が強い。しかも、西廻航路が開発されてから、すぐに隠岐島が風待港になったわけでもない。北前船の沖乗り(港から港の距離が、沖を通るとこによって長距離になり、短時間になる)が可能になって初めて風待港として繁栄するのである。 北前船の時代になると隠岐国の貿易業者は、山林が尽きるほど薪や木材を輸出したり、海産物である鯖・鯵・烏賊・鯛・鰤・アゴ・シイラなどを他国に売った。 また、享保十年(一七二五)には鳥取藩は米子に自由市場方式をとったので、米子・境港への集荷が多くなり、米子市場では隠岐からの入荷に関しては木材・竹材は無税、海産物には問屋に五分を支払う以外は何も制限が無かったので、隠岐以外に出雲浦の方面からも集荷されるほどであった。その頃、隠岐国の海運業を支える大船は、島前で七隻、島後では百十隻を数え、当時の流通経済の趨勢をうかがわせる。 この様な世情を反映してか、隠岐の代官所では小物成(鰯・アゴ・ワカメ・鯛・スルメ・海苔・串鮑・串海鼠に対する課税)と呼ばれる物品税の割合が年貢の半分近くも占めていた。 地元での民間を中心とした海運業は次第に拡大し、それにつれて他国船の往来手形を改めたり、駄別銀(だべつぎん)と称する荷物の点検手数料の徴収、北前船の宿をするなど、「問屋」と言わなくともその役割を果たす仕事の形態は既に整っていた。
官制問屋の役目は、他国船や他国商人のチェックと管理、俵物の集荷であった。具体的には、往来手形(旅券)・宿手形(宿泊人届)・往行御札(商売許可書)などをチェックして、代官所に提出・申請する役目を負っていたので、いきおい村役人の性格が強かった。積み荷の口銭(点検代金)として近世の場合は三分(三〇%)を徴収し、その内一分は村もしくは里に納め、二分は問屋に入る事になっていた。しかし、問屋は自分では売買せずに事務手続きのみと決められていた。 延享元年(一七四四)俵物集荷の実をあげる為、幕府は長崎商人八人と、その下に俵物手請負方を定め、さらにその下に指定問屋を設けてこれにあたった。宝暦三年(一七五三)の美田村の指定問屋は、喜兵衛(波止)・八兵衛(大津)・六兵衛(大山明)武左衛門(船越)であった。 隠岐の特産物である長崎俵物とは、天領地隠岐の代官所が長崎奉行管下の「長崎俵物役所」に対して出荷した物を指す。海産物であるスルメ・干しアワビ・キンコ(乾燥ナマコ)を産地から買い入れて俵につめたことから俵物(たわらもの)と呼ばれていた。 この時点での問屋は官制の売買をしないものと、自己資金で売買をする民間問屋の二種類が併存していた。 隠岐の長崎俵物は元来、幕府(松江)を通して長崎から中国向けに輸出されていたが、松江には「隠岐宿」と称して隠岐の海産物を一手に取り扱う俵物責任者が創設され、それが隠岐の御用問屋から海産物を集荷していた。しかし、その手数料は元々の買取が安い上、更に手数料を上乗せされるので、次第にここには集荷が少なくなってきた。そこで幕府は何回も他国への密売を禁止するが効果は無く、隠岐宿は廃止されることになる。 天明五年(一七八五)には「長崎会所直買制度」が制定され、積荷はコスト合理化のために長崎に直送されることとなった。旧来は、積荷責任者→俵物買集世話人(島前別府村庄屋)→俵物取締世話人(島前大庄屋)→俵物請負人(島前代官)→長崎俵物会所下関俵物方御買入所という流通経路をとっていたものが、俵物買集世話人(島前別府村庄屋)→長崎俵物会所下関俵物方御買入所となったのである。
官制の問屋は強制的に低く買い取り、競争を許されなかったので、次第に民間問屋が経済の中心になり、特に需要の多いスルメなどは自由競争できるスルメ問屋として独自のネットワークを全国に拡大していった。天保・弘化時代には浦郷では虎屋(山王丸)・尾張屋(日吉丸)・大前屋(金栄丸)・中原(明神丸)・万屋(八幡丸)などが自分で船を持ちながら同時に回船問屋を営んでいた。(表挿入) 島後では化政期にかけて廻船問屋・スルメ問屋・材木商人などが西郷周辺に増大して次第に勢力をのばし、隠岐島の近世の商業資本はこれらの民間問屋によってになわれていった。これら問屋は入銀と称して前以て金を貸し付け、海産物を集荷・確保し、しかも低く買い取る様に計らった。民間の自由貿易問屋は隠岐騒動の時には「出雲党」などと呼ばれて同志派・正義党と対立する事になる。 まとめると、最初に民間レベルで流通経済が発展し、それを幕府が利用する形で「問屋」制度として制定するが、産物の買い上げが民間問屋に比べてあまりにも低いので度々運営に支障をきたす結果になった。隠岐の特産品として人気の出てきたスルメなどは、特にスルメ問屋と言われるように独立分離して精力的に活動し、それが近世隠岐の流通経済を実質的にリードしてきたのである。
明治にいたり、幕府の制度としての問屋は廃止されたが、浦郷では漁師と魚商人との間に立つ一種の販売仲介業者として、単に水産物の卸売りのみならず農作物の卸売りにも介在した。問屋は選挙で選び、後には権利を入札で落とす様になった。その権利は一五〇円くらいであったという。任期は三年、仲介料金は三%であった。例えば漁師が釣った烏賊を各自で干して、これを商人に売るのだが、その前に問屋が一々魚家を巡り、烏賊の干し加減をみてまわる。これをハガキトリと称した。時期をみて、何時何時烏賊を入札するという案内を出す。すると商人はその時に集まってきて入札したり示談で値をきめて買う。その他の漁業の場合においても問屋はいちいち浜にでかけて魚の水揚げに立合い、商人の買い取った魚を帳面につけておいてその三分(三〇%)を口銭としてもらったのである。しかし、この制度も共同販売所の創立によって大正十四年に廃止された。宇賀では正月の二十日の総会で問屋を決め、この事を組合と言った。そしてこの問屋を組長と呼んでいた。赤之江の問屋は昭和十一年にはまだ、この問屋の風習が残っていたという。参考文献『隠岐』「増補隠州記」『隠岐島前漁村採訪記』「アチック・ミューゼアム・ノート第三号」『近世隠岐島史の研究』『黒木村誌』
はつまいり
黒木村の大津では正月十日から十七・八日までの内に初参りをする。まづ島前の各部落から焼火神社に詣で、それがすむと各村内の神々を巡拝する。この初参りには部落全体から必ず一人参加する。各里に奉願と呼ぶ役のもの二人づつあり、これが初参りの世話役となる。初参りの日が決定する、まずその事を奉願が焼火山に知らせに行く。すると焼火神社ではその奉願の到着順に各部落参詣人の昼飯を用意する。皆は参拝して後、この昼飯を御馳走になり、帰りに御供物語餞米を頂戴して帰る。奉願の役は廻り持ちで、この役に当たった人はその年の参詣費用を出さぬが、他の人々は一円くらい出している。奉願という役はこの初参りの時だけの役目である(大津の人)。知夫村古海では新春の焼火山初参りの途中にはオシクレゴとて船漕競争をする。その時小年寄りと若い者とが競争するので、この目印に浜辺に幟を立てる。なお、この日は各自の家では昔は白い麦酒を造り祝い、年寄、小年寄、若者の年齢別に船に乗って、焼火神社に赴いたものであった。『島前漁村採訪記』より
社務所全景

客殿南面
直会(なおらい)風景

旧幕時代の隠岐にも、巡見使は渡った。将軍の代替り毎に、幕府から諸国へ派遣され、土地の政情を査察する公儀役人のことである。はじめに土地の役人たちが、この中央から派遣される役人のために、いかに心をつかって、その送迎にあたったものであったかを和巻岩守手記によってうかがってみたい。-御巡見其他役人の巡回-旧幕時代に、高位高官の役人は勿論、下役のものでも、各村へ巡回する時は、先触れとて、何々役、何日、巡回につき送迎申、宿割人足割等、其メメ待方を通達する。各村に於ては二三日前より其準備に忙殺され、多くの費用を費やしたものである。御巡見とて、徳川幕府より、今の巡閲使を派遣し、諸国の状況を視察せしめたものだが、其御巡見使の入国するときは、数十日、前に前触を為し、上を下への大騒ぎで送迎の準備に手の尽くさるる限りを尽くしたもので、今から之を思えば、昔如何に役人が傲慢を極めたかが想像せられる。当家に正徳2年6年、享保2年、延享3年、享保元年、寛政元年、天保9年に巡見使が入国された時の書類がある。其最近の天保9年の巡見振りを紹介してみる。巡見、諏訪縫殿助、知行三千石、上下付添三十五人。同、竹中彦八郎、同二千石、同三十人。同、石川大膳、同一千五百石、同二十七人。勘定方、高橋繁之丞。支配勘定八木岡大蔵。御徒目付、山本庄右衛門。雲州御馳走方上下十三人。御医師上下十二人。御船方奉行、上下五人。御朱邦預、上下二人。御茶道、上下六人。御台所役人、上下十人。御料理人、十人。外ニ両島役所の役人二十五人。郡代、上下六人。代官、上下六人。御目付、上下二人。合計百八十一人。本巡見の巡見せられる区域は、山陰、山陽の両道である。一行を崎村庄屋新八郎松江表へ出迎し、一行は四月十日知夫村泊、十一日焼火山にて休憩別府泊、十二日海士村を巡見直に都万村へ渡海、矢尾村泊り、夫より美保関へ渡海之先触あり。一行前記の通り二百人近い多人数で、之を送迎して相当の礼遇を尽くさんとするのであるから、島前一帯は上を下への大騒ぎにて、その準備に苦心惨胆したものである。賄方では、フトン百二十枚、味噌八十五貫匁、醤油二石、干瓢四百匁、鰹魚五連、煙草三貫匁、烟管三十本、酢四斗、砂糖十斤、箸千膳、油六斗、半紙十束、下駄百足、草履百五十足、草靴二百足、唐紙三千枚、蝋燭八百匁、半切紙三百枚、杓子百丁、薪五百〆、其他数十点にして、布団は各村より借集めた。船と人夫は御召船の漕ぎ船四人乗八十四艘船人夫を百三十九人外に夘事人多数あり、乗馬二十四頭、巡見入国の前日より、各村から多人数出張り遠見番所より、船見ゆの相図あるや忽ち漕船出て漕寄せ、直ち上陸宿所へ案内し、島前の共同賄とする。翌十一日は別府村泊りにして夜具その他一切の物を持運びて知夫の如くに歓待し、翌日は海士村巡視村上助九郎邸に休息せられ、御召船以下八十余艘を従ひて都万村へ渡海せらる。その巡村の行列は実に盛んなるもので諏訪巡見使一人の夫を記してみれば陸行には直先に旗を押し立て、具足箱二人、長持二棹十二人、御用人足六人、御乗物一挺八人、御供篭二挺八人、御供馬七匹口取七人、夜具持四人、下駄草靴草履持二人、其他十一人計七十人にして、内二十三人宛小頭を付けらる。船行には御召船一隻、御供船一隻、漕船四人乗四艘(島後請)御用達船四人乗四艘、以上一巡見使の行列であるが、他の二巡見の夫れも多少の相違はあっても略之と同一である。其他郡代、代官、之に属する諸役人に要する人足、御用船夥しきものである。この惣人足三百三十九人、船数八十四隻舟夫三百三十六人、其料理人卯事人、給人、小使等多人数を徴発、各村の庄屋、年寄は勿論当時頭分惣出にて本陣(宿所)一切の世話から、荷物の取扱、賄方及人夫船の世話又夜具諸具の持廻り等落度なくしたものだ。今日から思えばその混雑の状想像も及ばぬ程である。以上、和巻岩守氏の手記によって、当時の隠岐の在地役人と、巡見使入国のすがたを想像していただきたいのであるが、焼火神社に記録された巡見使御社参記の完全記録を筆写させていただいて感じた、所見をのべて、巡見使のことを考えてみたい。隠岐に渡海し、その任務を遂行して去った何回かの巡見使は、例外無く焼火神社に参拝した。どの理由のすべては、はるかに渡る海上安全その制度の初期から享保ごろまでは政治視察の上で幕府にとっても効果をあげたといわれているが、寛文ごろからは殊に海辺浦々の巡見が重視されたという。焼火神社の御社参記録には、寛永十年の巡見以来の記録がその都度認められ、和巻手記にある先触れから知夫一泊翌日社参、一泊のこともあり、休息の後出発の場合もあった。ここには、その一つをあげて大体のことを知っていただく事にしたい。淳信院様御代替え翌年。延享三年寅六月御巡見御参詣之記。大巡見。小幡又十郎様、御知行千五百石。板橋民部様、同千七百石。伊奈兵庫様、同千石。延享三年寅四月二十八日雲州三保関より知夫里湊江夜五ツ時に御着船翌二十九日四ツ時橋浦より御登山、御迎住持宥賢伴僧清水寺、有光寺恵光、精進川土橋之前に而御待受申上、小幡又十郎様御用人関仲右衛門殿三張常助殿御先へ登山、直に神前へ御参詣済、寺へ御入り候而、又十郎様より住待へ御口上之趣並御初穂白木台ニ而御持参取次、同宿春山、次に又重郎様御乗物五丁程跡より参、伴僧壱人ツ、御案内路次門迄参り夫より御座敷江之御案内春山。次板橋民部様右同断、次伊奈兵庫様右同断。御座敷江御着座巳後、住持御目見御挨拶申上、次御引渡三宝、次御盃御吸物次御酒次御肴等。一、御行水之支度仕候得共、御行水は不被遊候。神前へ御参詣御案内春山、祖寛、拝殿に御待請ハ清水寺恵光、住持御殿之高蘭之内ニ着座、御三殿之膝付迄御登り御排相済、拝殿へ御帰座之上、御神酒御洗米差上寺へ御着座。一、御用人衆御家老衆六人屋舗、御家老衆四人上ケ炬燵ノ間、士衆二十四人客殿ニ而是迄御吸物本膳御上候同断、但客殿光之間へは二之膳出し不申候。一、家来衆七於余人是亦こたつ之間、囲爐裏間ニ而三しきりに膳部差出相済候。外ニ雲州より渡海之御船手等大勢入込杯之外膳部余計出し候、殊ニ御船手等勝手迄入込大混雑ニ御座候。一、雲州より御馳走方三人御料理方御茶道、是ハ新六畳之間。一、医師衆三人、是ハいろり之間上ニ着座此外、御供人数十人斗は隠居ニ客着座、是も二しきりに膳相済。一、雲州より之御船頭衆三人此外、中間等拾四五人は座敷無之ニ付直に橋へ下山。一、当島御郡代御代官目付元吟味方、是ハ朝五ツ半時知夫里より登山膳相済夫より西之蔵ニ着座、其外下役人衆勝手廻りニ被居候。一、当山ヲ九ツ半時御、下向橋浦へ、御下山夫より美田へ御通り御船ニ而、別府泊り御見送り住持、伴僧若党ニ而精進川土橋罷出候。一、先達而、雲州より両度之御巡見御渡海海上安全御祈祷被迎遣候、御初尾白銀一枚神献御座候。則前方を護摩キ行御巡見御登山之節座敷ニ而右雲州より御祈祷御頼ミ被露仕御礼差上申候。
一、翌晦日別府御本陣迄御影神銭等持参、昨日御社参之御礼ニ住持罷出候、伴僧長福寺春山、若党伊八、外ニ二人召連。一、同日海士村へ御渡海御泊。一、五月朔日島後都万村へ御渡海、同日西郷へ御越し二夜泊同月三日島後御出船三保関へ御着船。
夘月晦日之献立。御引渡、三宝、御吸物、御酒、御肴、三種。御本膳。生盛。夏大根、すまし、志ゃうが。御酢和会。きくらげ、御汁、小志いたけ、めうが竹、ふき、ゆず、山椒。御煮物。むかこ、水こんにゃく、御飯、路くぢやう、引而、香之物。二之膳。平皿。ちくわとうふ、くわい、竹の子、かんぴょう、つけ松たけ、御汁。とろろ、あおのり、包こしょう、猪口。こまとうがらし、うこぎ、すりわさび煮。御麩皿。麩。いり酒、生こんにゃく、指末、海そうめん、けん青梅、かんてん、れんこん、河たけ。
御地紙折。山のいもちりめん焼、あけこんぶ、やきしいたけ山枡みそ付。御酒、御肴。ふりけし、ひたし物。御肴御吸物。みそ、御吸もの、御肴。此方見合。後段。御茶、御菓子、御餅。すまし御吸物、へきいも、しいたけ、しほで。御酒御肴いろいろ。
御次之献立。皿、すあへ、夏大根、こんにゃく、青みちさ。汁、あられとうふ、ふき。煮物、香之物、おわり大根、むかご、氷こんにゃく。飯。平皿、引而、山いも、わらび、かんぴょう、あげとうふ、こんふ。指味、からしかけ酢、とさか、かんてん、ちさ。あへもの、ひじき、白あへ。酒、肴、いろいろ。
後段、茶。料理人、水野善兵衛。手伝、崎村観音寺。美田重左衛門。別府次郎左衛門。座敷給仕等配役覚。知々井春源、同宿恵光。同宿、春山。一、御座敷、規寛、小座敷、美田新九郎。同、伝之進。先炬燵之間、海士村建興寺。美田甚兵衛。客殿、有光寺。美田甚助。度した炬燵之間、大山教運。美田次郎右衛門。同儀右衛門。囲爐裏間、美田儀右ヱ門。同八之丞。はし伴助。新座敷、別府千福寺。同松之助。座敷惣見役、美田長福寺。勝手見繕、浦之郷。七兵衛。勝手繕場見繕、知夫里伊八郎。酒方、文太夫。四郎兵衛。行水場役、二人。勝手働、男女二十三人。料理方、四人。〆五拾四人。一、橋村より御登山之節床御小休所迄御茶持参役。新九郎、千太郎。松之助、作左衛門。此節毎度ニ遣候人足四拾参人、是ハ西鳥居より内道橋掃除等ニ遣候御社参当日人足遣候。右何レも橋村之者共。一、御札守役、宇野大和。是ハ護摩堂ニ而出ス御影六百枚程用意仕置、是ハ沢山也。神銭三千程拵置候得共七百、程不足ニ付翌日相成別府へ持参仕候、壱枚縁起等余程入用也。一、当寺之寺号山号並住持之名同宿之名迄書出候様被仰候ニ付則左之通書出候。覚。一、焼火山雲上寺住、兵部郷法邦宥賢。同宿、春山。恵光。視寛。一、当山境内並寺内間数書出候様。被仰出左之通書出候。覚。一、隠岐国嶋前知夫里郡美田村焼火山雲上寺。寺内間数梁行五間半桁行十五間。境内麓寄り絶頂迄拾丁余東西拾二三町。右当山之儀断崖絶壁樹木深欝故巨細ニ難斗候故大既書上申候。延享三年寅年四月二十九日別当兵部卿法印。宥賢印。如此三通相認別府(翌日御礼ニ罷出候節差出申候。御初穂之覚。一、金弐百匹、小幡又十郎様より。青銅三百文、銅御用人衆中より。一、同弐百匹、板橋民部様より。青銅三百文、同御用人衆中より。一、同弐百匹、伊奈兵庫様より。青銅三百文、同御用人衆中より。以上である
一回の御社参記は終っているが、大方の場合、この大一行は焼火山の苦心も大変なものであったことであったにちがいない。和巻手記の方では、島前村方の方の苦労がわかるが、焼火山が中心になって、当時の島前各寺々の僧を集めて、その応接にあたっていることがわかる。こんな大仕かけな仕事を仰遣わされ、それをみごろに果たしてきた当時の焼火山雲上寺の実力は想像以上であって、後年の焼火信仰の普及と経営に大きく作用したと考えられる。いまは、島民から忘れ去られているけれども、巡見使の来島と、焼火社参りの例外のなかった史実について、もっと考えてみたいと思うのである。それにしても巡見使が必ず最初に着岸し、そこで、一泊した知夫の地に、なぜその伝えがのこらなかったか不思議思はれる。筆者が島後の古文書で調べたところではその当時の知夫の宿割りの明記したものも残っているので、知夫には伝えだけでものこってよい筈である。何かわりきれない感じがする。
巡見使社参。
1、寛氷十年、大巡見、市橋伊豆守。村越七郎右衛門。拓植平右衛門。
2、寛文七年、大巡見、稲葉清左衛門。大巡見。市橋伊豆守・村越七郎右衛門・拓殖平右衛門。大巡見。稲葉清左衛門・市橋三四郎・徳永頼母市橋三四郎。徳永頼母。
3、延宝九年、大巡見、高木忠右衛門。服部久右衛門。佐橋甚兵衛。
4、元禄四年、御料巡見、秋田三郎左衛門。宝七郎左衛門。鈴木弥市郎。
5、宝氷7年、大巡見、黒川与兵衛。岩瀬吉左衛門。森川六左衛門。正徳二年、御料巡見、大巡見。高木忠右衛門・服部久右衛門・佐橋甚兵衛御料巡見。秋田三郎左衛門・宝七郎左衛門・鈴木弥市郎。大巡見。黒川与兵衛・岩瀬吉左衛門・森川六左衛門。森山勘四郎。三橋勘左衛門。湊五右衛門。
7、正徳六年、大巡見、鈴木藤助。小池岡右衛門。石川浅右衛門。
8、享保二年、大巡見、松平与左衛門。落合源右衛門。近藤源五郎。
9、延享三年、大巡見、小幡又十郎。伊奈兵庫。板橋民部。
10、延享三年、御料巡見、佐久間吉左衛門。野呂吉十郎。山田幸右衛門。
11、宝暦十一年、大巡見、阿部内記。弓気多源七郎。杉原七十郎。
12、同年、御料巡見、永田藤七郎。高野与一左衛門。児島平右衛門。
13、寛政元年、大巡見、石尾七兵衛。
御料巡見。佐久間吉左衛門・野呂吉十郎・山田幸右衛門大巡見。阿部内記・弓気多源七郎・杉原七十郎御料巡見。永田藤七郎・高野与一左衛門・児島平右衛門大巡見。石尾七兵衛・花房作五郎・小浜平太夫・花房作五郎。小浜平太夫。14、同年、御料巡見、清水利兵衛。池田八郎左衛門。村尾源左衛門。
15、天保九年、大巡見、諏訪縫殿助。竹中彦八郎。石川大膳。
16、同年、御料巡見、高橋。八木岡。山本。天保九年の大巡見は、松江藩人
数を入れ
御料巡見。清水利兵衛・池田八郎左衛門・村尾源左衛門
御料巡見。高橋・八木岡・山本
て総渡海人数は四百十三人といった大がかりのものであった。近世の焼火信仰。早くから航海安全の神として崇められていた焼火権現が、西廻航路の航程のなかに隠岐が入ってから航海業者や船乗りの参詣が多くなったこととあわせて、この数度ににわたる巡見使の参詣が慣例になって、地元の篤い信仰とともに、焼火信仰は全国に拡がり普及していったことはまちがいない事実である。補。知夫里村、大江、渡辺喜代一氏の所蔵古文書のなかに、(襖の下張にしたものをはぎとったもの)巡見使の人馬先触の断片があったので、それをかかげて参考に供したい。前文紙切れてなし。宝暦十一年巳三月十。但馬宿中。○人足弐人馬二疋従江戸播磨但馬備中備後美作石見丹後隠岐国迄上下並於彼御用中幾度も可出之、是者右国為巡見御用御徒目附児島平左衛間罷越ニ付而相渡之者也。宝暦十一年己三月、但馬宿中。○永田藤七郎、高野与一左衛門持参之巡見御用書物長持壱棹。従江戸丹後但馬石見隠岐播磨美作備中備後国々迄御用中幾度も急度可持候者也。巳三月、但馬宿中。覚。御朱印一、人足弐人。同断。一、馬三疋。内弐疋ハ人足四人ニ代ル。御リ文。一、御用長持壱棹持人足。永田藤七郎分。御証文。一、人足弐人。同断。一、馬三疋。沙汰文。一、人足弐人。一、馬一疋。これは、筆者が現在までに知夫で見た唯一の巡見使関係古文書である。
『隠岐(島前)の文化財一号』
隠岐焚火ノ社
初代広重
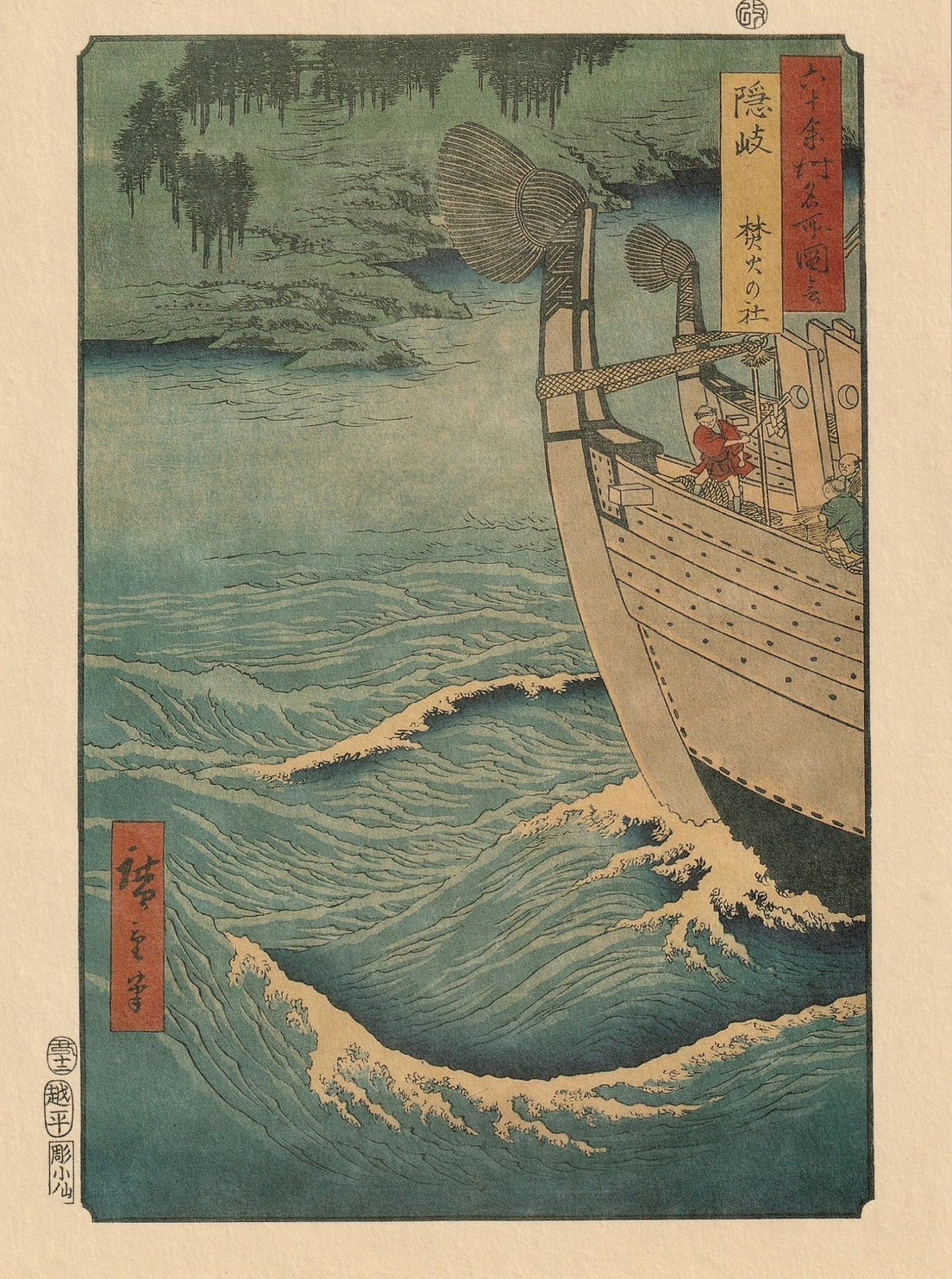
歌川(安藤)広重作。嘉永六年(一八五三)から安政三年(一八五六)にかけて作成された版画で「六十 余州名所図会」の中の「隠岐 焚火ノ社」です。この絵は嘉永六年十二月の印。(原寸三四・四×二二・八センチ) 焼火(焚火)という珍しい神の名は、平安期にすでに都に聞えたらしく『栄花物語』長元三年(一〇二九)に右近少将源経俊朝臣に「恨みわび干さぬ袖だにある物を恋に朽なん名こそ惜しけれ 下もゆる嘆きをだにも知らせばや焼火神(たくひのかみ)のしるしばかりに」と歌われております。焼火の神がことにその神威を発揮するのは中世になってからであり、船人が海難に遭ったときこの神に祈ると必ず神火が現れて、その方向へ船を進めると無事に港に着くと信じられておりました。 近世に入り、日本海の西廻り航路が開かれると隠岐はその寄港地として賑わい、焼火権現の名は日本海沿岸だけでなく、三陸海岸のまだ隠岐を見たこともない船人たちの間にまで霊験あらたかな船神として知られていました。西廻り航路の北前船が沖合で夜を迎えるとき安全を祈って火を海に投下する「献火」の作法がありました。その際に「お燈明 お燈明 お燈明 隠岐の国 焼火権現様にたむけます。よい風にあわせなはれ 千日の上日和」と唱えた伝承が岩手県にありました。 初代広重の絵は「献火行事」でなく舳で御幣を振っている図になっていますが、二代広重・葛飾北斎の絵では火を海中に投下している構図となっていますいずれにせよ北斎・広重共に 山陰を訪ねた証はないので恐らく江戸において「献火」の事を聞いて画題としたものと思われます。
二代広重
「焚火ノ社」の浮世絵は「北斎漫画」七編の中に出ているが、これは諸国名所 絵としては早い頃の作品であろう。北斎、広重は風景画の二大作家として有名 であるが、広重が「東海道五十三次」を発表してより以降は風景画の方は広重 の方が世にもてはやされるようになった。初代広重は諸国名所絵を何度も画い ているが、その一つである「諸国六十八景」は早い時期のもので、後に「六十 余州名所図絵」を画くが、そのいずれにも隠岐の代表ととして「焚火の社」を 選んでいる。本画は二代広重で「諸国名所百景」と題して初代広重に習って隠 岐では焚火社を画いた。焼火信仰の特色は「神火示現」の信仰でそれが為に航 海安全の神として船人等の強い信仰を受けていた。ここに画かれているのも北 前船に於ける海上安全を祈る「献灯」の行事である。ただし、北斎・広重共に 山陰を訪ねた証はないので恐らく江戸に於いて「献火」の事を聞いて画材とし たものであろう。二代広重も初代広重に習って構図をすこしかえて画いたと思 われる。 初代広重「焚火の社」 「焚火の社」は「六十余州名所図絵」のものでこの方は「献火行事」でなく舳 で御幣を振っている図になているが、このような行事があったかどうかは詳ら かでない。 (松浦記)『隠岐の文化財十三号』
隠岐・焚火ノ社(葛飾北斎)
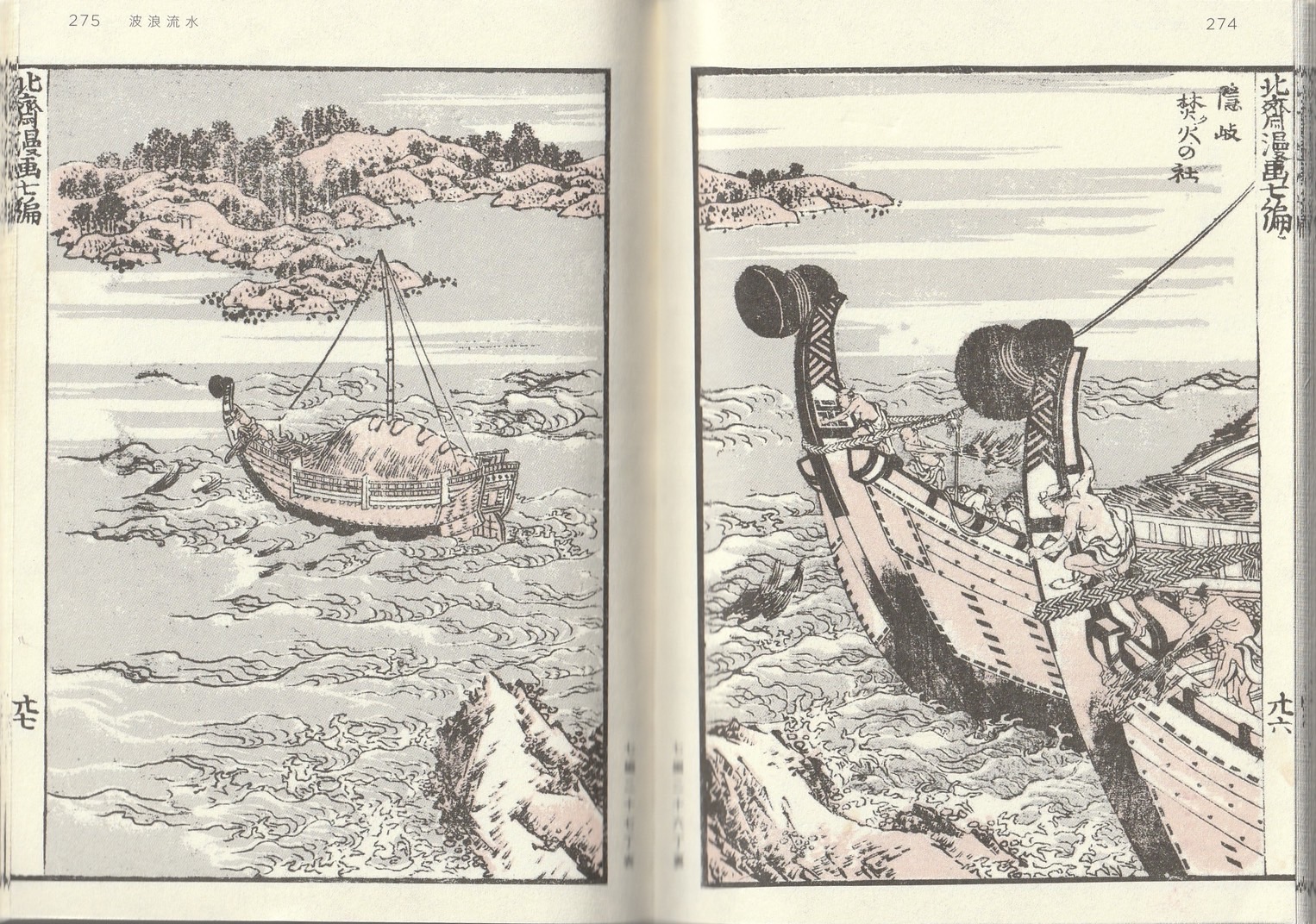
隠岐島前の焼火権現の信仰は島内のみでなく、日本海航路の開発と共にその信仰圏は、日本海沿岸から東北の太平洋岸にまで及んでいた。この船人の信仰を、北斎・広重共に画いている。本図は北斎漫画(文化十一年から刊行十五編ある)七編の中にある「諸国名所絵」の中に画かれているもの。焼火信仰の特色は神火示現の信仰で、航海安全の神として船人の間に強い尊崇を受けていた。ここに画かれている図柄も北前船における海上平穏を祈る献灯の行事を画いたもので、この作法は明治初年頃まで行なわれていたという。
葛飾北斎
(一七六〇~一八四九)江戸本所割下水に生れ、九〇歳の長寿を保ち、うまずたゆまず画作につとめた人であるから、各時期に応じて画格に変化がある。北斎は数多くのいわゆる「名所絵」を画いているが、すべて現地に往き写生して画いたわけではなく(北斎、広重共に山陰にきた事実はないという)、想像によって画かけたものも多い。この「焚火ノ社」も江戸に於て焼火社の信仰の話を聞いて想像して画いたものであろう。話はちょっとそれるが、焼火権現から今も出している「神銭守(ぜにまもり)」は江戸時代年間相当多くの数を江戸に送って頒布していたので記録もあるから隠岐を知らぬ江戸の庶民も「神銭守」を通じて焼火信仰の話を聞いたのであろう。神銭守の事は玩銭蒐集家の残した「板児録」という記録の中にも出ている。また、この神銭守の事は「焼火山縁起」の中にも一項を設けてのべられている。なお、現在は「焼火」と書くのが普通であるが、江戸期には焚火、託日とも書れ、ちょっと変っているのは離火とも書かれているが、いずれも焼火の事である。(松浦康麿記)『隠岐の文化財十五号』
焼火山扁額
扁額

焼火神社に保管されている扁額は、持明院権中納言基輔卿の二 男、京都東寺観智院僧正賢賀の筆になるもので、松平定信(楽翁)の編になる 「集古十種」の扁額の部に掲載されており、同僧正の筆になるものが当社のも のもふくめて三点入れられている。当社に原書並添翰が保存されているので併 せて紹介する。旧源福寺にも「隠岐院」の扁額が保存されているが、この書も 持明院基延筆(文政十年ー原書なし)で書法は全く同じである。持明院家には こうした扁額用デザイン文字の書法が代々伝えられていたのである。「添翰。 山陰道隠岐国島前焼火山雲上寺当住善純法印者予資也。観智院法未年歳既久。 有権現神祠礼拝成群華表在海辺也。法印来於京師、語曰神廟荘厳縡已周備、未 掲額字冀労師筆、為永世偉宝牟予謂累代勝縁何敢 黙尓向千八襄且羅微恙不得 肆力予別無一長可取、徒執筆成字非放以為正也。古人言観其書慕其人牟吾学額 字也。元禄年間志学之比、従祖父基時卿得此伝也。且野山西方院春深興使筆法 於千歳之下此等法皆在吾寺。不得止而筆之者垂四十餘国二百餘所、就中萬歳楽 之三字、一枚施薩州之僧、一枚献大守、一枚贈琉球国波上山三光院真言宗国祷 寺、鳴呼何幸加之方今子之懇請何復容辞。若待予之暇書則至来年、亦不可知船 便亦希、於是率應其需因勒蕪陋之詞以贈焉。宝暦十年龍集庚辰六月七日。真言 一宗惣本寺、東寺定額僧貫主、観智印僧正賢賀(書判)。(松浦康麿) 島前の文化財 6巻